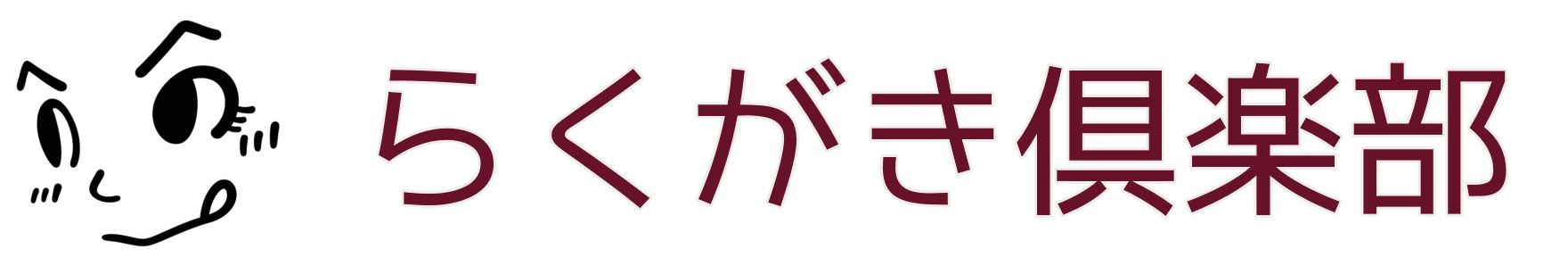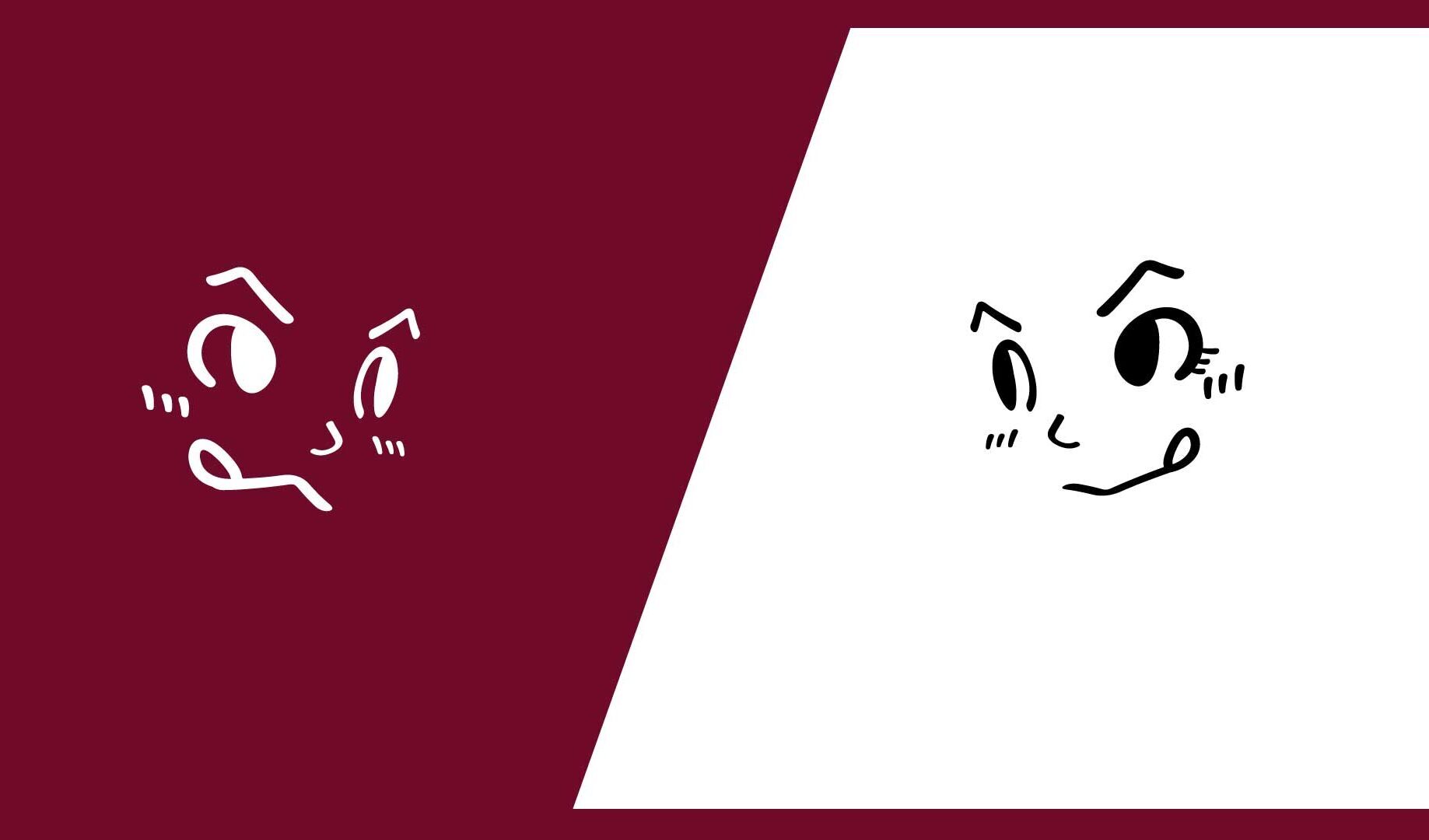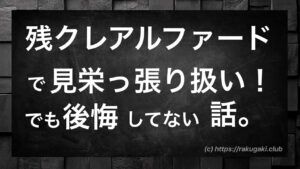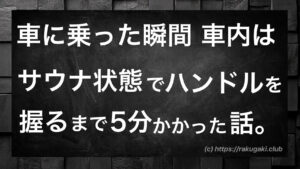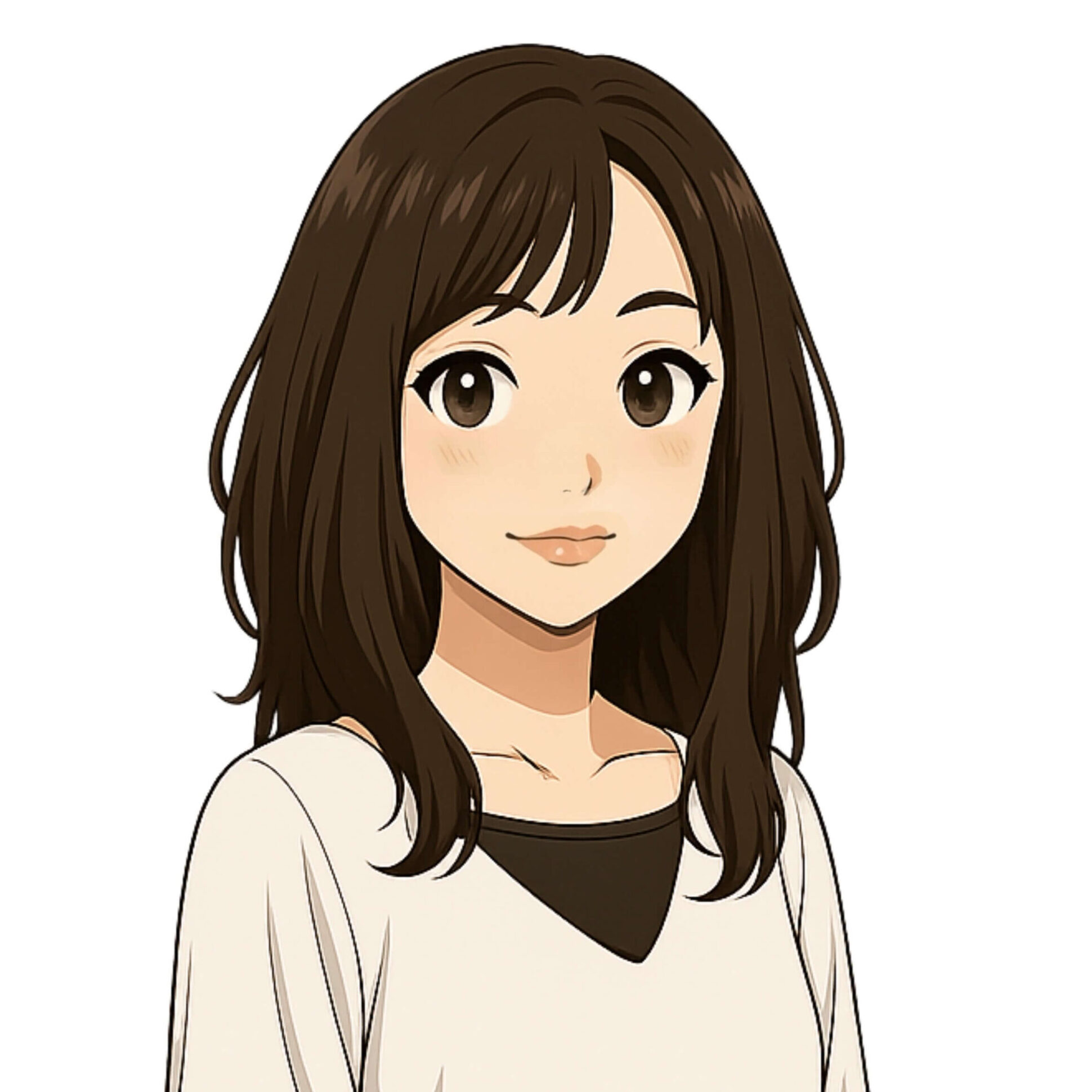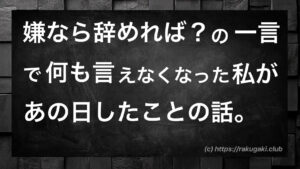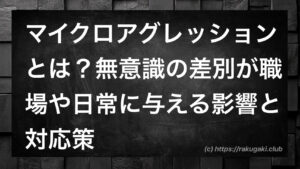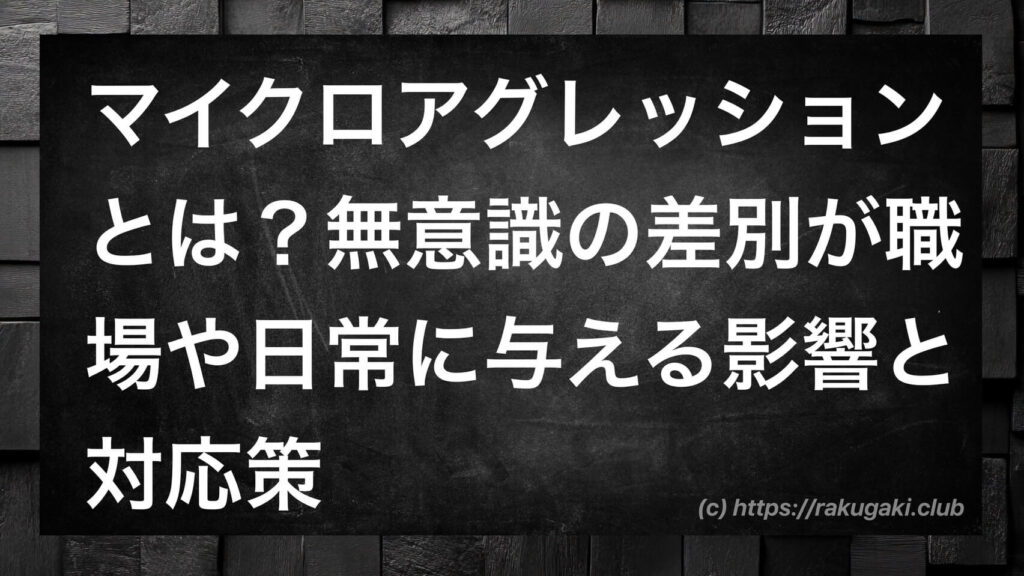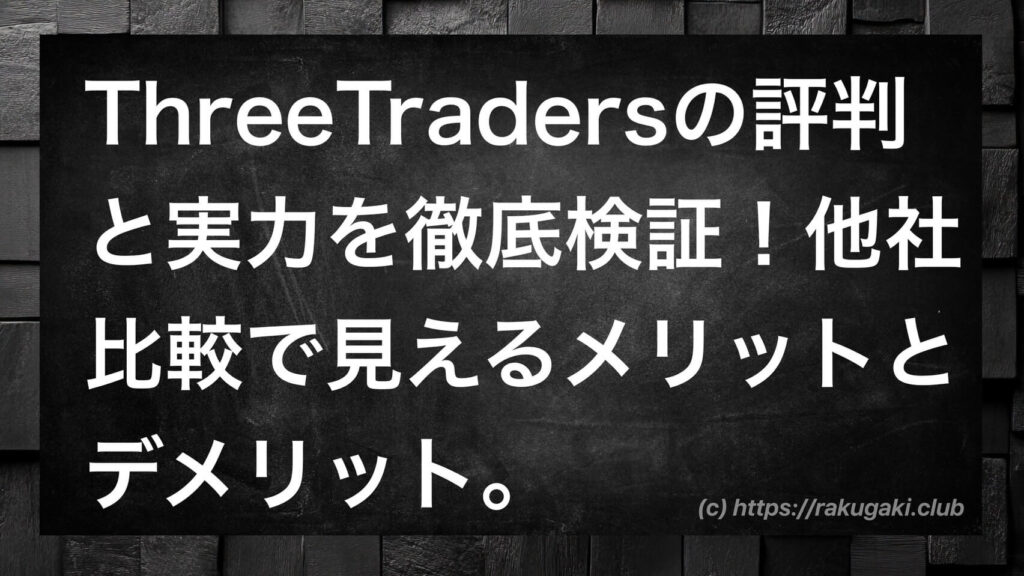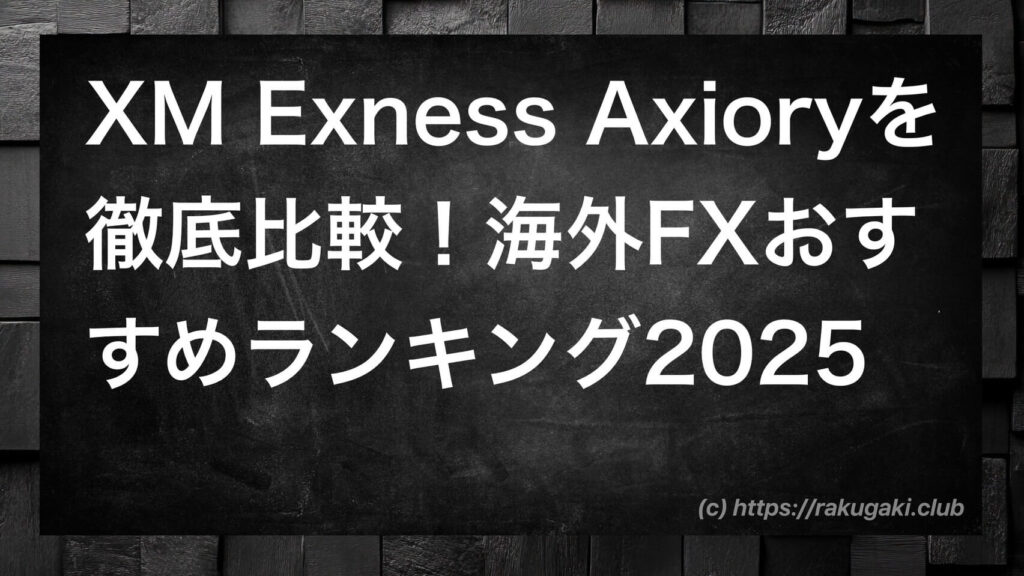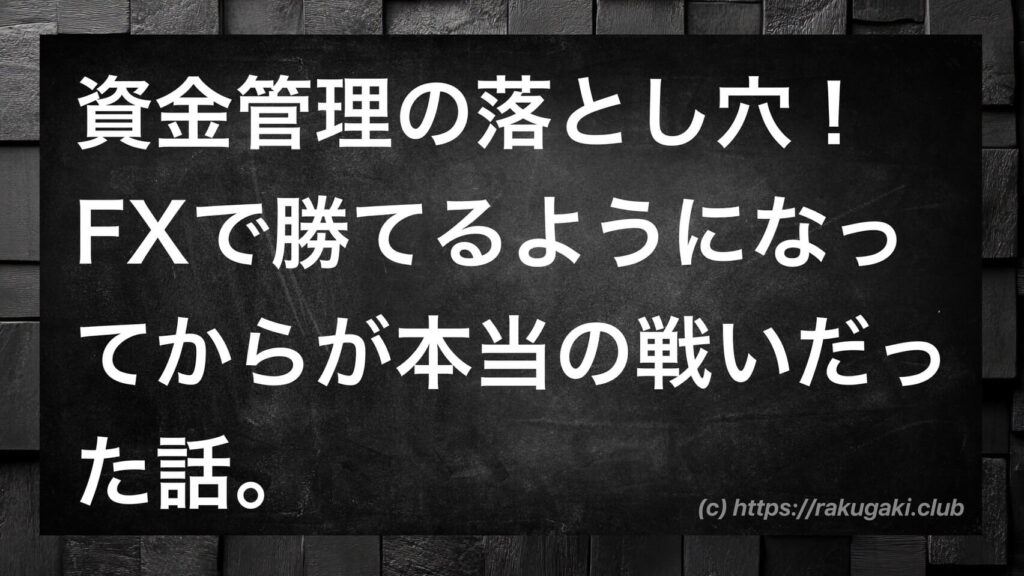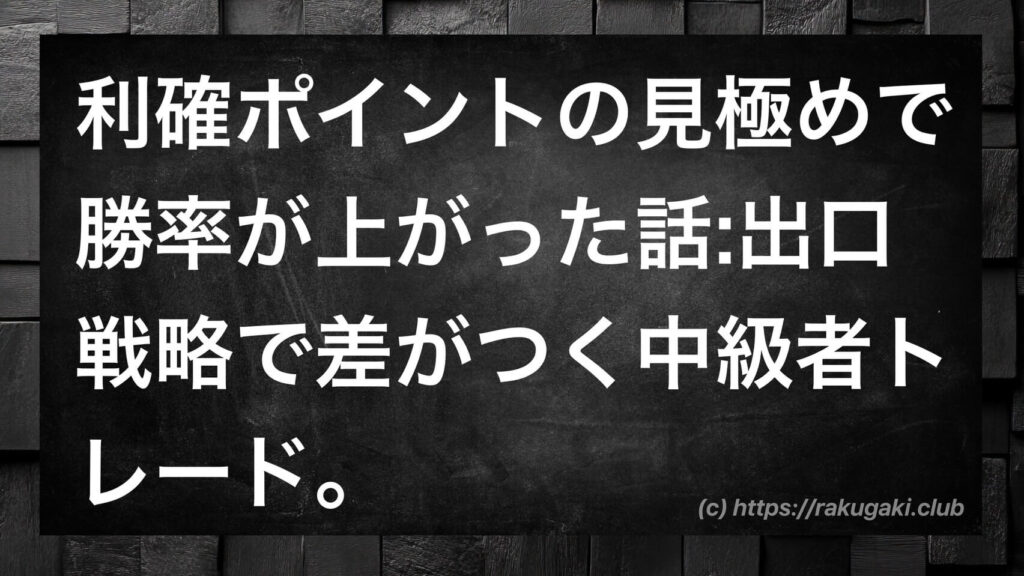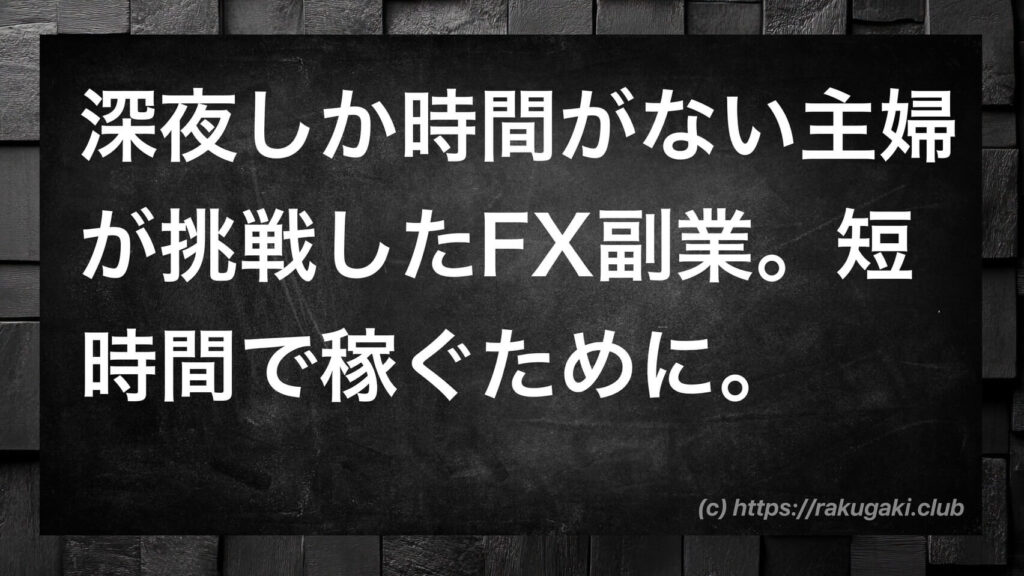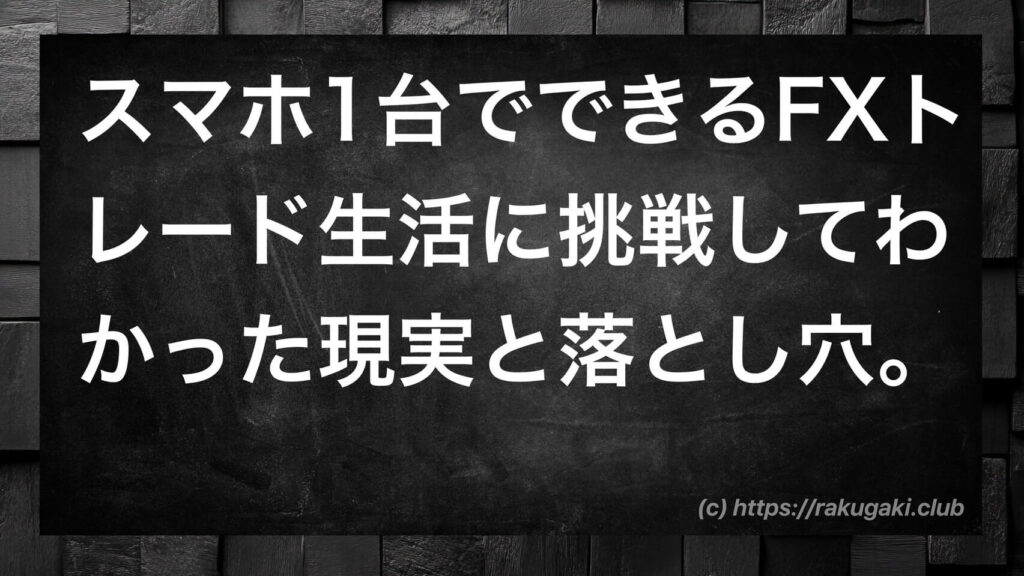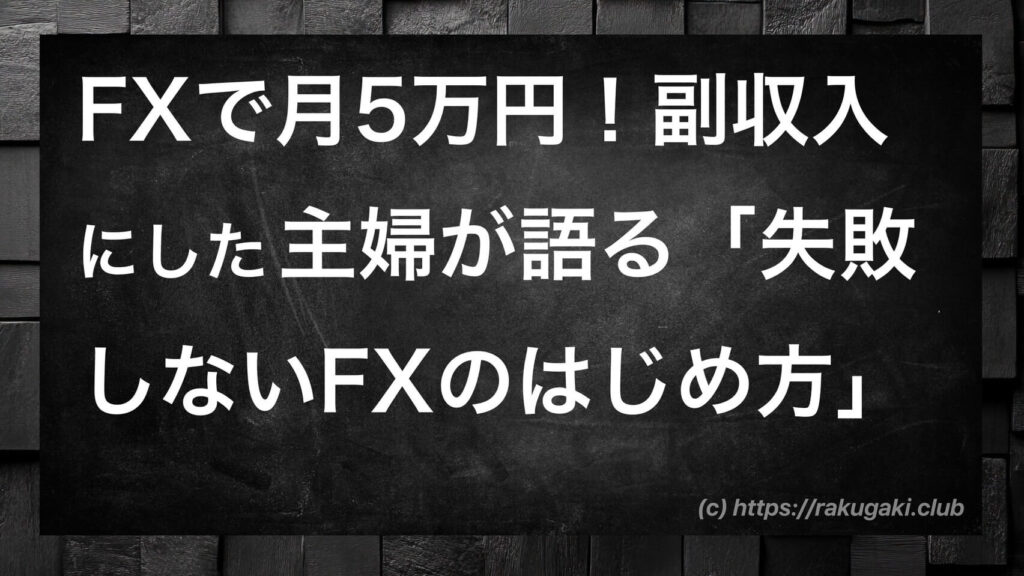フォロワー1,000人の壁にぶち当たった頃の話
「フォロワー1,000人から先が伸びないんですけど……」
そんな悩み、SNSをやっている人なら一度は経験があるんじゃないだろうか。
そして、その“壁”にぶち当たっていたのが、当時の俺――イッチくんだった。
自己紹介がてら、当時のスペックを
社会人6年目。メーカー勤務で営業職。仕事はまあまあ、家と会社の往復で平和な日々。
でもそんな平凡な日常の中、ちょっとした“趣味”と“自己表現”の場として、X(旧Twitter)をやっていた。
投稿内容はというと、いわゆる日常ネタ。
- 電車で見かけた面白い光景
- 昼ごはんのラーメンの写真に一言つける
- たまに仕事での愚痴や反省メモ
そんな“ゆるい雑記”が中心で、特にバズるわけでもないけど、フォロワーはポツポツと増えていってた。
多分、大学時代の友人とか、趣味アカの人たちが中心だったと思う。
ある日、フォロワーが「1,000人」に到達した
通知の数字を見たときは、正直ちょっと感動した。
「おお、ついに四桁か…!」
「“フォロワー1,000人”って、なんかそれっぽい響き…!」
「ついに俺も、“ちょっとSNSやってる人”になったか?」
でも、そのあとだった。
嬉しさの次に来たのは、思った以上の“停滞感”だった。
増えない。まったく増えない
そこから先が、驚くほど伸びなかった。
一日に1人増えては2人減る。
3日放置すると10人ぐらいごっそりいなくなる。
数字を追う気はなかった…はずだった。
けど、「1,000人」を超えてから、なぜかやたらとフォロワー数を意識するようになっていた。
SNSを“見る”側から、“やる”側に変わってしまった瞬間
もともと俺は、SNSを「見る専」寄りで楽しんでいた。
面白い投稿に反応したり、身内でワイワイやったり。
それが純粋に楽しかった。
でも「数字が増える喜び」を知ってしまったことで、
次第に「どんな投稿なら伸びるか」「何時に投稿すればいいか」なんてことを考えるようになってしまった。
そして気がつくと、**「戦略的にSNSを運用している人たち」**のノウハウに手を出し始めていた。
SNS運用系の発信者たちの“伸ばし方”を研究しはじめた
- 投稿は朝7時、昼12時、夜21時がゴールデンタイム
- ターゲットを明確にしてペルソナを意識
- 共感系ネタは3日に1回が効果的
- 結論→理由→具体例→再結論の構成でまとめる
- 「いいね→保存」されるような実用性を意識
いわゆる“SNS攻略本”みたいなことを、日々真面目にメモしては試していた。
そして、「これはイケる」と思った時期も、たしかにあった。
実際、ちょっとずつ数字は動き出した
この頃の俺の投稿は、もはや日常という名のネタ発信装置だった。
- 朝の満員電車で心が折れそうになった出来事を「構成4分割」でツイート
- カフェで見かけた微笑ましい親子連れに「共感&余韻」を込めて投稿
- Xのアルゴリズム変更の話題を“速報風”にアレンジして引用投稿
その結果、1投稿で200いいね、500いいね、たまに1,000いいね…と、
たしかに、**フォロワーが伸びる“波”**みたいなものが見えてきた。
だけど、なんか違う。楽しくない
「フォロワー増えてるのに、なぜかテンションが上がらない」
そんな日が増えていった。
SNSに“投稿すること”が日課になって、
スマホを見てる時間は明らかに増えて、
でも、その割に満たされていなかった。
いつしか、俺は“数字で自分の価値を測る”ようになっていた
たとえば、100いいねいかなかった投稿に対して、
- 「この時間に出したのが悪かったのか?」
- 「文末の絵文字がいけなかった?」
- 「俺って、もう飽きられてる…?」
こんなふうに、自分の価値がSNSの数字に左右されるようになっていた。
気づけば、日常の出来事を「ネタとして見てる」自分がいて、
笑いごとにして投稿できそうかどうか、心の中で自動判別していた。
あのときの自分に、ひとこと言いたい
「お前、それ楽しいか?」
って。
フォロワーを伸ばすって、
たしかに嬉しいことも多い。
でもその過程で、何かを置いてけぼりにしてたんじゃないか?
そんなモヤモヤを抱えたまま、次の転機を迎える。
“SNSコンサル”の人に絡まれて一気に冷めた瞬間
フォロワーはいつの間にか3,000人を超えていた。
日常ネタにちょっとした気づきを乗せた投稿が、安定して数百の「いいね」を稼ぐようになっていた。
「これはもう、運用がうまく回ってる状態」と言ってよかったと思う。
だけど、その分だけプレッシャーもあった。
「次はどんなネタが伸びるか」と常にアンテナを張って、
“日常を楽しむ”というより“ネタ探しする”日々になっていた。
そんなある日だった。
ある投稿が、バズの「当たり」を引いた。
そのポストは“実体験+ちょっとした共感”だった
内容は、会社帰りに見かけたファミレスの風景。
隣のテーブルにいた中学生カップルが、割り勘についてちょっとした言い合いをしていたんだけど、
最後には女の子が「でも私、〇〇くんといるだけで楽しいし」とか言ってて、
それを聞いた男の子が急にしおらしくなって「やっぱ俺が出すわ…」みたいな感じになったという話。
俺はその一部始終を、笑いを交えながら端的に描いた。
共感、青春、ちょっと笑える、ほんのり心があたたまる——
そういう“伸びる要素”がうまく重なったんだと思う。
投稿から3時間で5,000いいね。
インプレッションは10万を超え、フォロワーは一晩で1,000人以上増えた。
「これがバズか……!」
スマホの通知が鳴りっぱなしで、手応えはあった。
でも、ここからが地獄だった。
突然、リプ欄に現れた“SNSコンサル”の人
その人はアイコンに「SNSマーケター|実績○万人」みたいな肩書きをつけていて、
プロフィールには「バズの構造を分析・解説します!」と書いてある。
どうやら「バズってる人を分析してタグ付けし、自分の界隈に引っ張り込む」系のアカウントらしかった。
俺の投稿に、まるで“品評会”のようなコメントがついた。
「この構成、ちゃんとエモ系→共感→余韻の流れを押さえてますね。完璧です👏」
「こういう投稿、よくバズるんですが再現性がない人が多いんですよね」
「リライトするなら、最後のオチを2語で締めると更に強いです」
何だろう、この“教壇から評価してくる感”……。
たしかに、その人は実績のある人だった。
フォロワーも5万人超え。分析力もあるし、他の人にも同じように解説をつけては称賛したり、
逆にダメ出しをしたりして、界隈ではそこそこ有名っぽかった。
でも俺は、その人の一言一句を見ながら、
どこかで心が急速に冷めていくのを感じていた。
「いや、別に褒めてほしくて書いたんじゃないんだけどな…」
そう、俺はただ、
ちょっと笑える日常の一コマを共有したかっただけだった。
そこに“バズ戦略”とか“構成技法”みたいな視点を持ち込まれると、
なんだか自分の投稿が、誰かの教材にされてるような気がしてしまった。
リプ欄には「すごい!」「好き!」「わかる〜!」みたいな軽い共感コメントが並んでいたけど、
その人の長文コメントだけが、空気を変えていた。
そして、さらに最悪だったのが「引用RT」
そのコンサルの人は、俺の投稿を引用リツイートして、こう言った。
「これ、エンゲージメント伸びやすい事例。
①キャッチ(“〇〇で見かけた一幕”)
②ストーリー展開(登場人物2人、台詞形式)
③オチ(余韻系+ちょっと泣ける)
参考にしたい人は保存推奨!」
……。
なんだろう。
「自分の投稿が分解されて、誰かの“サンプル”にされてる」この感じ。
バズったはずなのに、
自分の中には、ちっとも嬉しさが残っていなかった。
いいね数が増えていくほど、心は静かに萎んでいった
数字はどんどん伸びた。
でも、スマホを見るたびにため息が出るようになっていた。
この頃からだ。
「投稿するのがちょっと怖くなる」感覚が出てきたのは。
誰かにまた“分析”されるんじゃないか。
「お前の投稿はこういう型だから伸びただけ」と言われるんじゃないか。
その恐れが、ちょっとずつ俺の投稿を“静かにしていく”方向に向かわせた。
もはや「人とつながるSNS」ではなくなっていた
“誰とつながるか”よりも、
“どんな人に評価されるか”ばかりを気にするようになった。
「炎上したらどうしよう」
「またあの人に見られてるかも」
「内容に“正解”がなかったら、どう思われるんだろう」
そんな思考がぐるぐるして、
気づけば投稿する前に10分以上「推敲」している自分がいた。
SNSって、なんだったっけ。
日常をつぶやく場所じゃなかったのか。
誰かと“共感でつながる”場所じゃなかったのか。
そのうち、俺はアカウントを数日放置するようになった。
投稿をやめて気づいた“数字の呪い”と静かな回復
「今日も投稿しないまま終わったな」
そう思いながら、スマホの画面を閉じる夜が続いた。
かつては朝イチで考えていた“ネタの構成”も、今では頭に浮かばない。
フォロワーは9,000人を超えていたけれど、それがむしろ重かった。
まるで、何千人もの前でスピーチを強要されているような感覚
「どうせなら面白いことを言わなきゃ」
「意味のあることを言わなきゃ」
「共感されることを書かなきゃ」
そんなプレッシャーが、静かにのしかかっていた。
SNSは自由な発信の場だったはずなのに、
いつの間にか、“義務感の牢屋”になっていた。
投稿しない日々が続くと、フォロワーは減っていった
100人減った。
その次の週には200人減った。
一気にじゃなくて、少しずつ、ゆっくりと、まるで時間差で効く毒みたいに。
画面の右上に表示される“フォロワー数”が、数字ではなく“評価”のように思えて、
何度もプロフィールページを開いては閉じた。
でもある日、ふと思った。
「この数字、別に“俺”を測ってるわけじゃないよな」
9,873人 → 9,714人 → 9,538人
数字が減っていくたびに、心がザワついていたけど、
そもそもこの数値、俺の価値でも、人格でもない。
たまたま「面白い」と思ってくれた人がいた。
たまたま「共感できた」と感じてくれた人がいた。
でもそれは、“その瞬間の投稿”に対してであって、“俺”に対してじゃない。
SNSの「いいね」は、“いい人だね”じゃなくて“いい投稿だね”なんだ。
そのシンプルな事実に、なんだか救われた。
数字の呪いが少しずつ溶けはじめた
そこからは、無理に“投稿を戻そう”とは思わなかった。
むしろ、しばらくSNSから距離を置くことにした。
スマホの通知はOFFにした。
アナリティクスも見ないようにした。
「ネタになりそうなこと」を探すクセもやめた。
すると、だんだんと、普通の生活が戻ってきた。
「笑うための時間」じゃなく「笑える時間」が増えた
友達とラーメンを食べに行ったとき、
ふざけて替え玉を6回も頼んだアイツの顔が面白くて、
スマホにメモしようとしたけどやめた。
そのまま笑って終わりにした。
「これ、ツイートすれば伸びそう」と思うこともあったけど、
それを“ネタにしない自由”を、初めて手に入れたような気がした。
SNSが“生活の中心”じゃなくなったとき、本当に気がラクになった
前までは、スマホを開くたびに緊張してた。
「通知が来てるかもしれない」
「誰かに批判されてるかもしれない」
「何か炎上してるかも」
でも、もうそんなことはどうでもよくなっていた。
代わりに、気づいたことがあった。
「俺、もともと“人の投稿を見るのが好き”だったな」
他の人が書いてる何気ないポストを見て笑ったり、
深夜の弱音にうっかり共感して涙が出たり、
見知らぬ誰かが焼いたパンケーキの写真を見て幸せになったり。
それが、SNSの一番好きなところだった。
「俺が発信しなきゃ」と力んでいた頃は、
“見る楽しさ”を完全に忘れていた。
ふと思いついたことを投稿してみた
そんなある夜。
なんとなく書きたくなったことを、そのまま投稿してみた。
“飲み会の帰りに、ポケットにからあげ入れて帰る同期がいて、
本人いわく『明日の朝用』らしい。
令和のハイエナかよ。”
いいねは30件くらいだった。
通知も鳴らなかった。
でも、その投稿はなんだか久しぶりに“自分の言葉”だった。
誰かに刺さらなくていい。
バズらなくていい。
ただ、面白かったことをちょっと書いただけ。
それが、めちゃくちゃ心地よかった。
何気ない投稿が再びバズってしまい、葛藤がぶり返した夜
“飲み会の帰りに、ポケットにからあげ入れて帰る同期がいて、
本人いわく『明日の朝用』らしい。
令和のハイエナかよ。”
その何気ない投稿は、深夜0時前に思いついて、ほぼ思考ゼロで投稿したものだった。
もうSNSは“戦略の場”じゃなくて“遊び場”に戻ったし、通知もオフだし、
「たぶん数十いいねつけば御の字だな」ぐらいの気持ちだった。
それが、まさか翌朝——
起きたら通知がバグっていた
目覚ましより先に、スマホのブルブルが止まらなくて目を覚ました。
「ん?なんだこの通知…」
ロック画面に表示された“X”のアイコンに、99+の数字が踊っていた。
寝ぼけながらアプリを開いた瞬間、
目が一気に覚めた。
インプレッション30万超、いいね1万超。
引用リツイート、リプライの嵐。
リプ欄には「朝から笑った」「唐揚げ同期かわいすぎる」「このセンス好き」みたいなコメントがぎっしり。
どうやら“バズ”の再来だった。
嬉しい…けど、また始まってしまった感覚
もちろん、嬉しかった。
でもそれと同時に、
「また、これが始まるのか」という小さなざわつきがあった。
数字が伸びれば、注目される。
注目されれば、分析される。
分析されれば、プレッシャーがついてくる。
「今回は偶然」
「たまたまタイミングが良かっただけ」
「いつも通りの“ノリ”の投稿だっただけ」
そう自分に言い聞かせながらも、
やっぱり“数字”が出てしまうと、気持ちは落ち着かなかった。
引用リツイートでまた“分析勢”が現れる
「これ、リズム感とラスト一行のギャップが絶妙」
「キャラ配置がうまい。唐揚げ男→冷静な語り手→落ち」
「一文目で読者を引き込む構成、見習いたい」
…ああ、またこれだ。
今回は直接絡まれることはなかったけど、
それでも「誰かの教材」として、また使われている感じがして、
心のどこかがザラついた。
そしてまた、「投稿が怖くなってきた」
気がつけば、次の投稿を“慎重に考え始めている”自分がいた。
「また同じように面白くなきゃダメ?」
「次はもっと笑わせなきゃダメ?」
「自分のノリって、これで合ってる?」
頭の中で“期待に応えなきゃ”という声がよみがえる。
前にあれほど距離を置いたはずの“数字の世界”に、
もう一歩、足を踏み入れてしまっていた。
でも、今回はちょっと違った
投稿を開いて、リプ欄をスクロールしていたとき、
ふと目に留まったひとことがあった。
「この人、前に“からあげじゃなくてポケットにプリン入れてた同期”の話もしてた人ですよね?地味に好きです」
……。
そんな話、したっけ?
過去ログをさかのぼってみると、
たしかに2か月前、飲み会帰りに「コンビニプリン買ってポケットに入れて爆発した同期」の話をしていた。
完全に忘れてた。
その投稿にはたしか、20いいねもついてなかった。
でも、覚えてくれてる人がいた。
たった一人の“読者”の存在に、救われた気がした
バズじゃなくてもいい。
数字にならなくてもいい。
それでも、自分の言葉を「覚えていてくれる人」がいる。
それがなんだか、とてつもなく嬉しかった。
このとき、ようやく腑に落ちた。
「俺、たぶん“数字が欲しい”んじゃなくて、“誰かにちゃんと届いてほしい”んだな」
SNSとの“本当の付き合い方”が、ようやく見えてきた
- 全部がバズる必要はない
- 毎日投稿しなくていい
- 何気ない言葉が、誰かのツボに入ることもある
それで十分じゃないか。
そして、何より——
“自分が楽しいと思える”投稿じゃなきゃ、続かない。
“欲”と戦わずに済む、自分ルールをつくった夜
再びバズった投稿を見つめながら、俺は自分に問いかけていた。
「このまま、この調子でフォロワーを増やしていくか?」
「それとも、また距離を置くか?」
「そもそも、俺は“何のために”SNSをやってるんだっけ?」
スマホを握ったまま、何度も考えた。
でも答えは出なかった。
だから、少しだけ“距離を測る工夫”をすることにした。
自分の中に「投稿ルール」を設けてみた
バズってからしばらくは、ずっと「誘惑」と戦っていた。
「この流れでもう一回バズらせたい」
「1万フォロワー、いけるんじゃないか?」
「ここで止めたら、もったいないかも…」
そんな“欲のささやき”が、頭の中をぐるぐるしていた。
でも、前みたいに押しつぶされるのはイヤだった。
だから、あえて“欲と戦わなくてもいい形”を作ろうと思った。
ルールその①:「投稿は週に2本まで」
思いついたらすぐ投稿、というやり方をやめた。
“発信すること”が義務みたいに感じてしまうから。
代わりに、週に2本だけ投稿すると決めた。
ペースを落とすことで、自分の中の「もっと出さなきゃ」モードを断ち切れる気がした。
ルールその②:「バズったら3日間は投稿しない」
これも自分なりの“鎮火期間”。
伸びてる数字を見続けると、それが「基準」になってしまう。
だから、バズったら投稿を休む。
代わりに、リプを見たり、引用RTを眺めたり、
たまに通知をオフにしたりして、冷却期間を過ごす。
不思議なことに、こうすると「もう一発当てたい!」という焦りが消える。
ルールその③:「“誰に向けて書くか”を決めてから投稿する」
これは特に大事にしている。
「とりあえずウケそうだから」とか、
「ネタになりそうだから」という理由で投稿すると、たいてい疲れる。
逆に「これは、あの同期に話すような感じで」とか
「この話、フォロワーの〇〇さんが好きそうだな」と思って書くと、心がざわつかない。
“具体的な誰か”に向けて書くと、SNSが「人とつながる場所」に戻る。
自分ルールができてから、SNSが“味方”になった
最初は、自分を縛るような感じがしていた。
でも今は、「守ってくれる柵」みたいに思っている。
それまでは、
「たくさんの人に届く」=「正解」
みたいな思い込みがあった。
だけど今は、
「誰かひとりにちゃんと届く」=「満足」
と、自然に思えるようになっている。
フォロワーは1万人を超えた
バズが続いたこともあって、フォロワー数はついに1万人を超えた。
前だったら、スクショ撮ってポストして、
「ありがとうございます!」って言ってたと思う。
でも、今回は静かに見守った。
通知も開かず、カウントの画面も見なかった。
1万人超えても、自分は何も変わらない。
それを知っていたからだ。
“SNSを使う自分”じゃなく“使われない自分”でいたい
数字やアルゴリズムに気を取られて、
心が削れるくらいなら、
無理して「続ける」必要はない。
SNSは、あくまで“道具”であって、
それに人生を乗っ取られちゃいけない。
そんな当たり前のことを、
一周回ってようやく理解した。
そしてもう一つ、大事なことに気づいた
SNSは、ひとりでもできるけど、
ひとりで“頑張りすぎる”と、どこかで壊れてしまう。
だから俺は、
身近な友人や昔からのフォロワー、
リプライをくれる人や引用RTしてくれる人たちを、
ちゃんと「大切にする人たち」として見るようになった。
相手も“アカウント”じゃなく“人間”なんだよな、と。
1万人よりも、たったひとりに届くほうがうれしいと思えた今
SNSを始めたころ、
「バズってみたいな」「フォロワー1万人いったら何が変わるんだろう」
そんなふうに、漠然と思っていた。
実際に戦略を練って、投稿を調整して、
フォロワー数は確かに増えていった。
でも、数が増えるほどに
“自分が見えなくなる感覚”も、同時に強くなっていた。
数字が増えたとき、心がすり減っていた
人に見られている緊張。
毎日の投稿プレッシャー。
過剰な分析や期待、そしてバズへの依存。
それらが積もり積もって、
SNSを開くことすら怖くなったこともあった。
フォロワーは増えたのに、
自分の投稿が“自分の言葉”に感じられなくなっていた。
投稿を休んで、ようやく気づけたことがあった
一度SNSから距離を置いたとき、
やっと本当のことに気づけた。
自分が欲しかったのは、「バズ」じゃなかった。
「認めてほしい」と思っていたのでもなかった。
本当に欲しかったのは、
“誰かが、笑ってくれる”とか、“覚えてくれている”とか、
ただそれだけだった。
ある日もらったDMに、思わず泣きそうになった
「いつも投稿見てます。今日のからあげの話、元気出ました。最近しんどかったんですけど、笑って、ちょっと救われました。」
画面の前で、しばらく動けなかった。
バズの数字とは比べものにならないほど、
その一通のメッセージが、胸に刺さった。
“ああ、俺、これだわ。”
SNSの本質は「人とつながること」だった
バズらせるためにやってた頃、
誰かとつながってる実感はほとんどなかった。
でも今は、
コメントやリプをくれる人の“言葉”をちゃんと読める。
相手が笑ってる顔を想像したり、
「この人にも日常があるんだよな」って、
当たり前のことを思えるようになった。
それって、すごく健全なSNSの使い方だと思う。
1万人よりも、「ひとり」に届けばいい
数字はもちろん、うれしい。
でも、それは「結果」であって「目的」じゃない。
いまの俺は、
「この話、誰かに伝えたい」っていう気持ちで、週2回だけ投稿してる。
バズらなくてもいい。
いいねが少なくてもいい。
その代わり、“届く相手”が誰かひとりでもいたら、それで十分。
最初の“戦略”も、今の“ゆるい投稿”も、どっちも俺
思えば、フォロワーを増やそうと試行錯誤していた日々も、
無駄じゃなかった。
そこで心が削れたからこそ、
いまの“距離感”が持てている。
バズりたくて頑張ったことも、
疲れて離れたことも、
全部ひっくるめて、俺のSNS体験なんだと思う。
SNSを「武器」にするんじゃなく「道具」にしたい
誰かを攻撃したり、
自分を守るために装ったりする場所じゃなくて、
ただ、日常をちょっと笑って、
誰かと「わかる!」を共有する場所。
そんなSNSが、一番気持ちいい。
そしてまた今日も、何気ない一言をポストする
“コンビニの袋を木に引っ掛けてる人、
この世で一番やさしい人種かもしれん。”
たぶんそんなに伸びないと思う。
でも、もし誰かが「ふふっ」て笑ってくれたなら、
それだけで、もう十分すぎる。
これからも俺は、SNSとちょうどいい距離感で付き合っていく。
そしてきっと、今日も、誰かのちょっとした日常に、
小さく混ざっていられたら——それでいい。