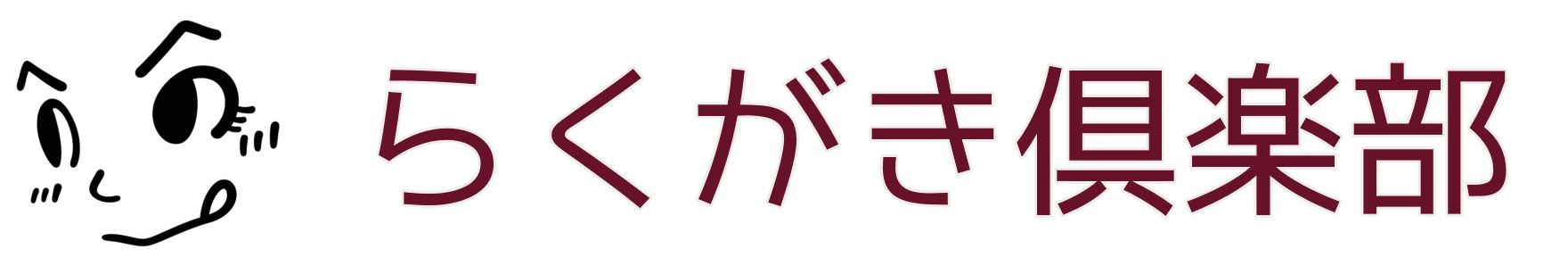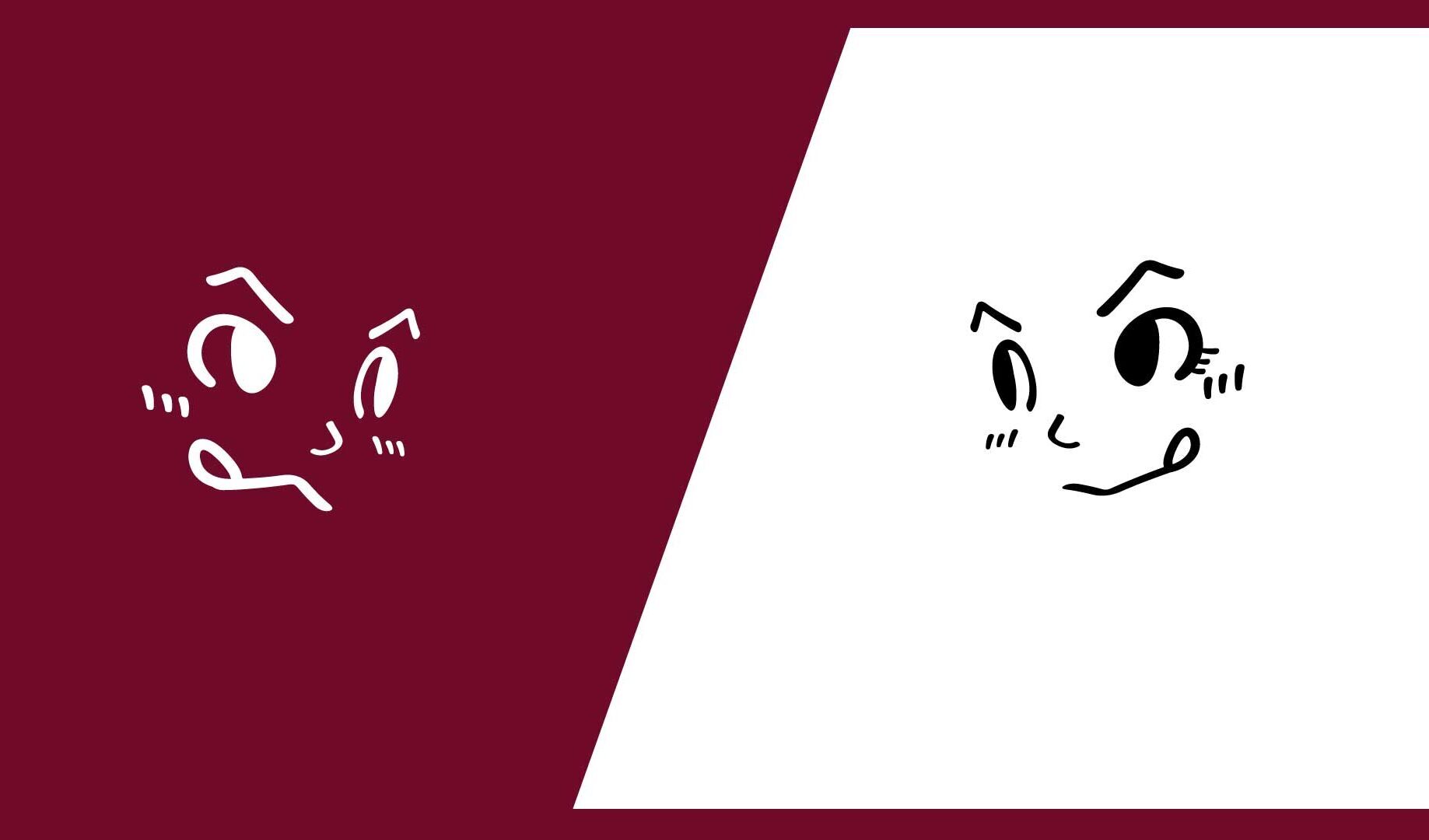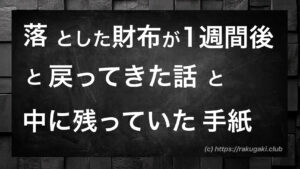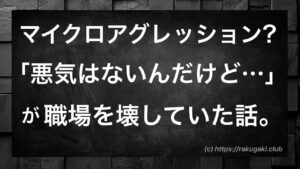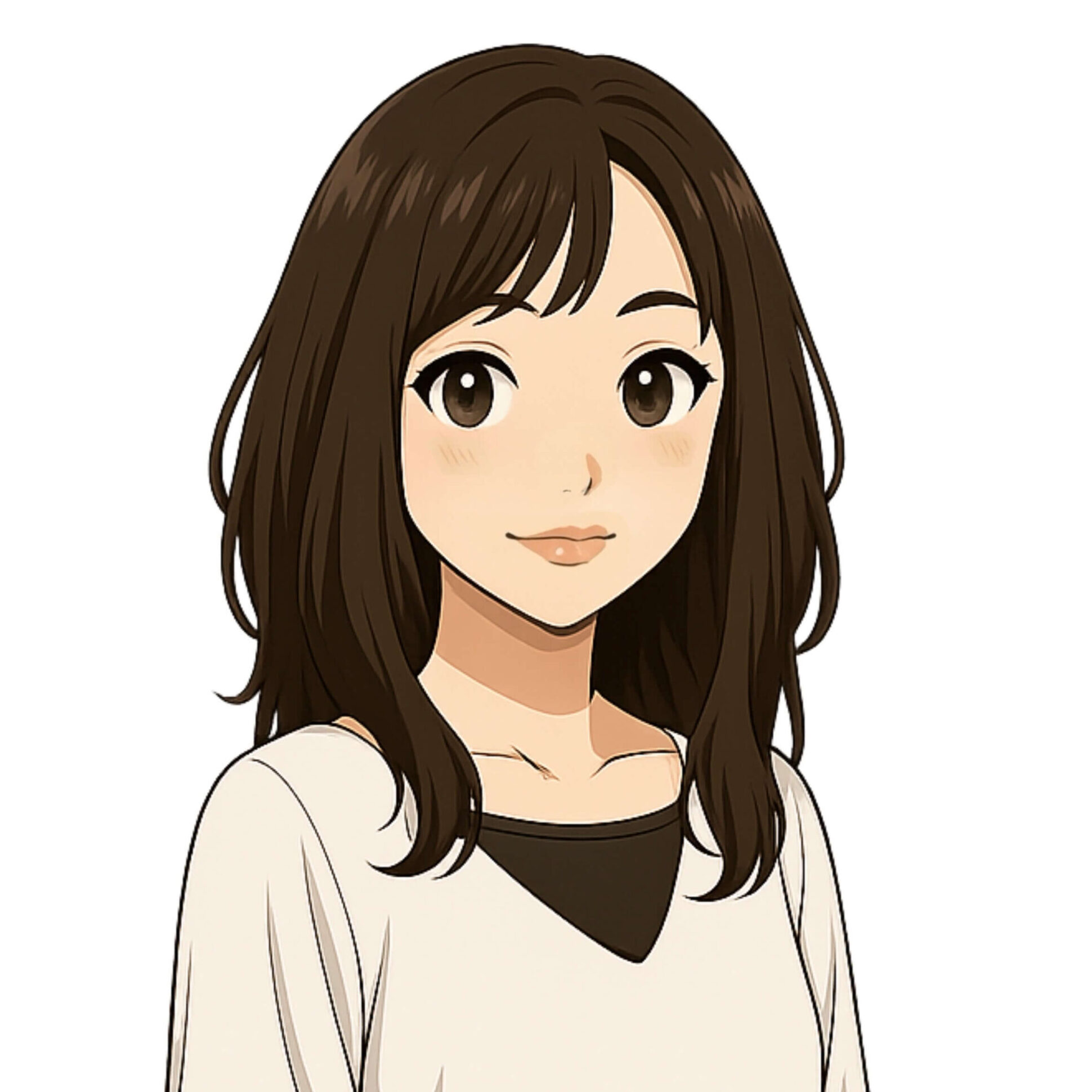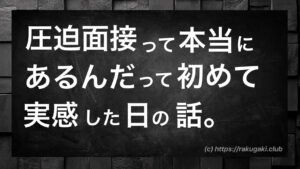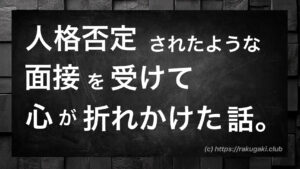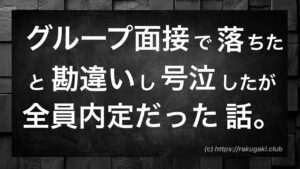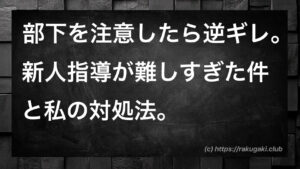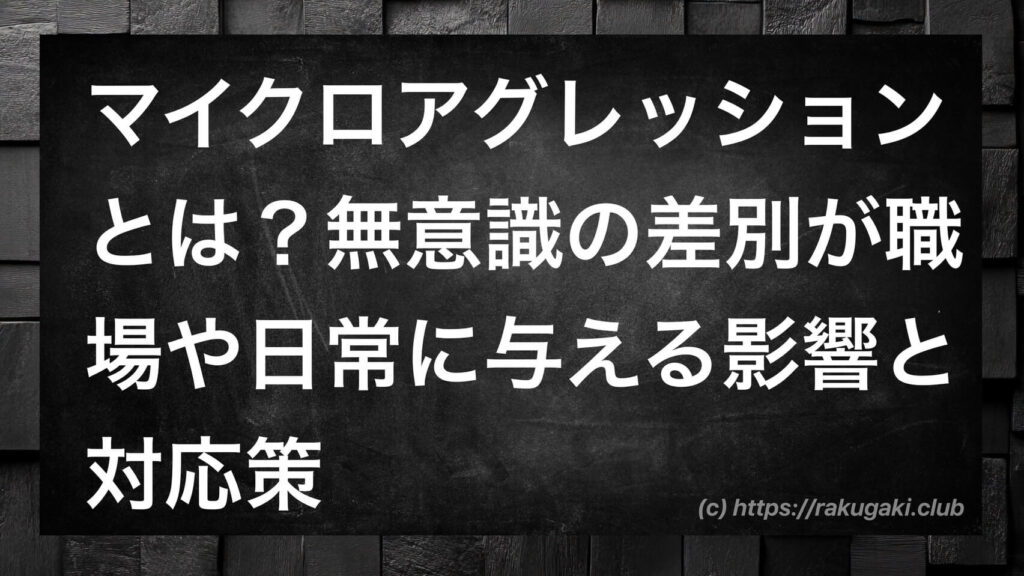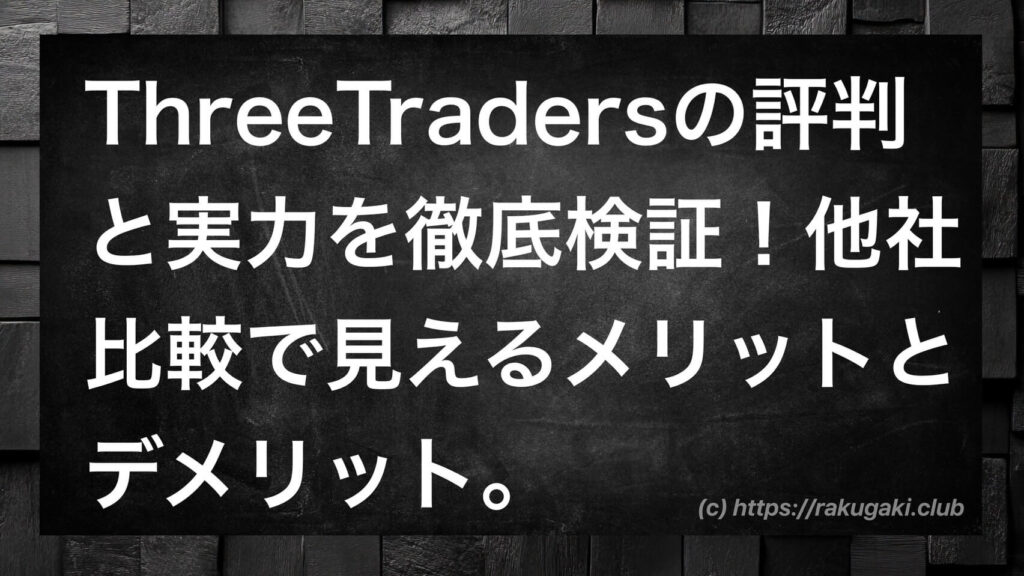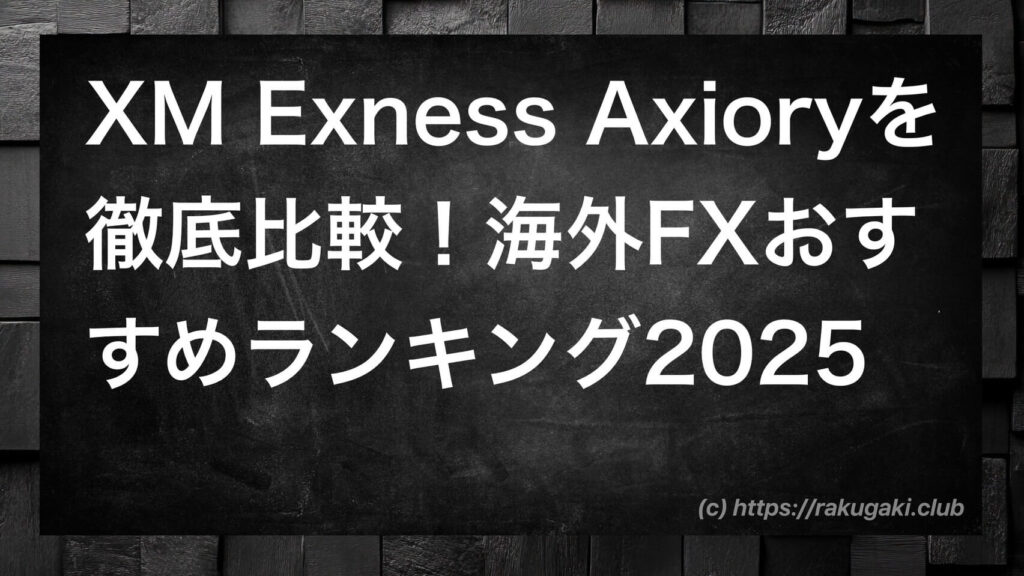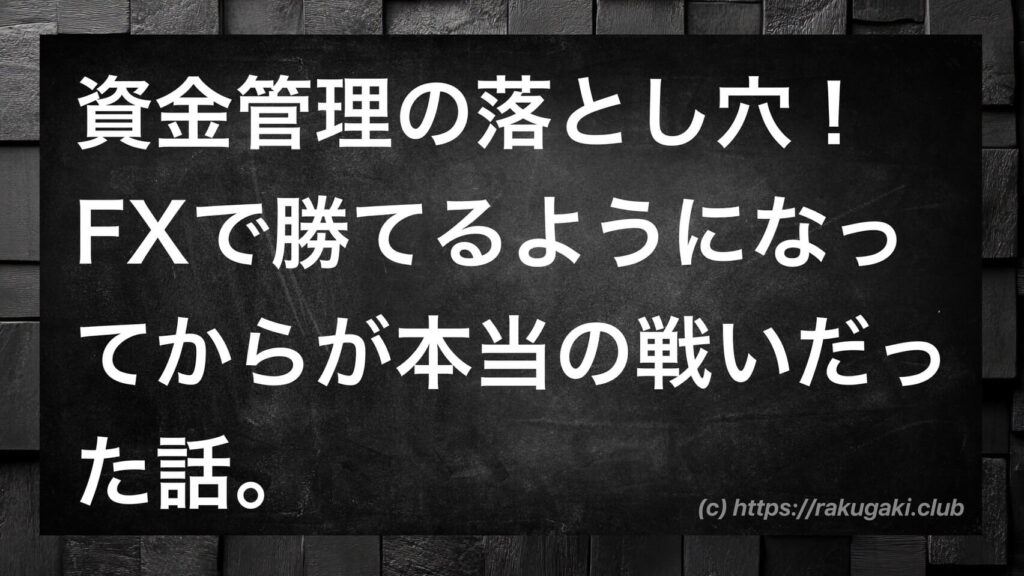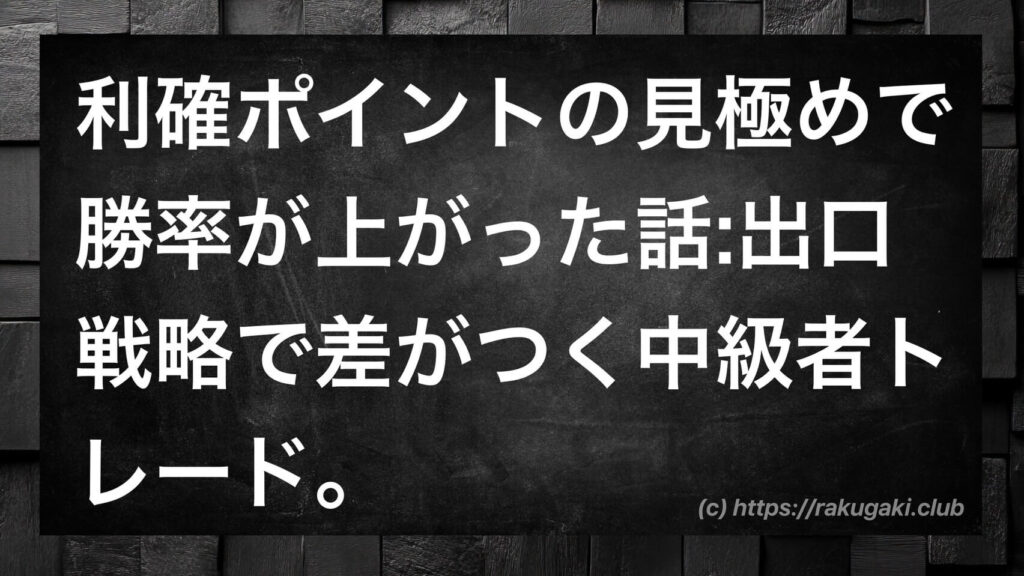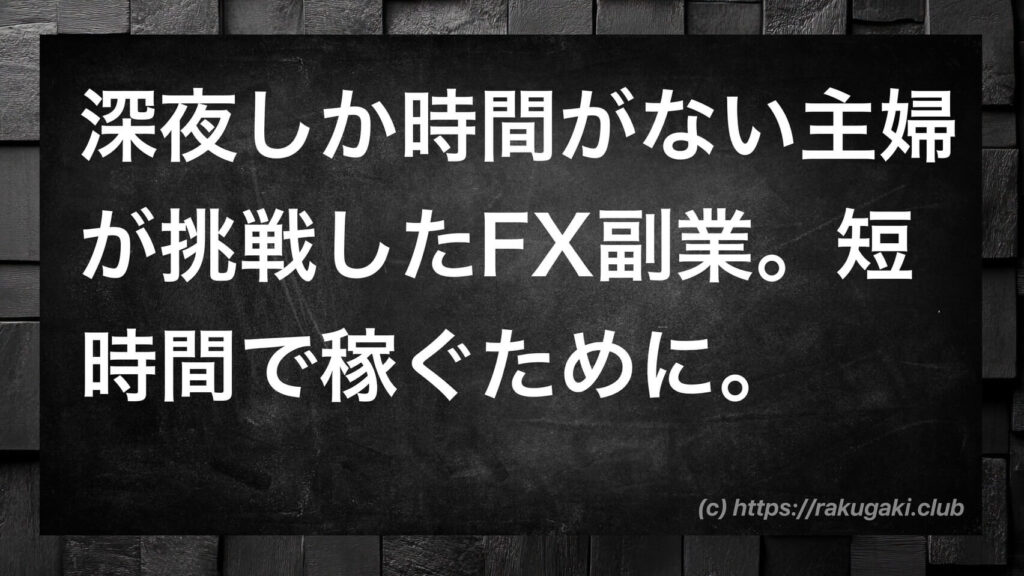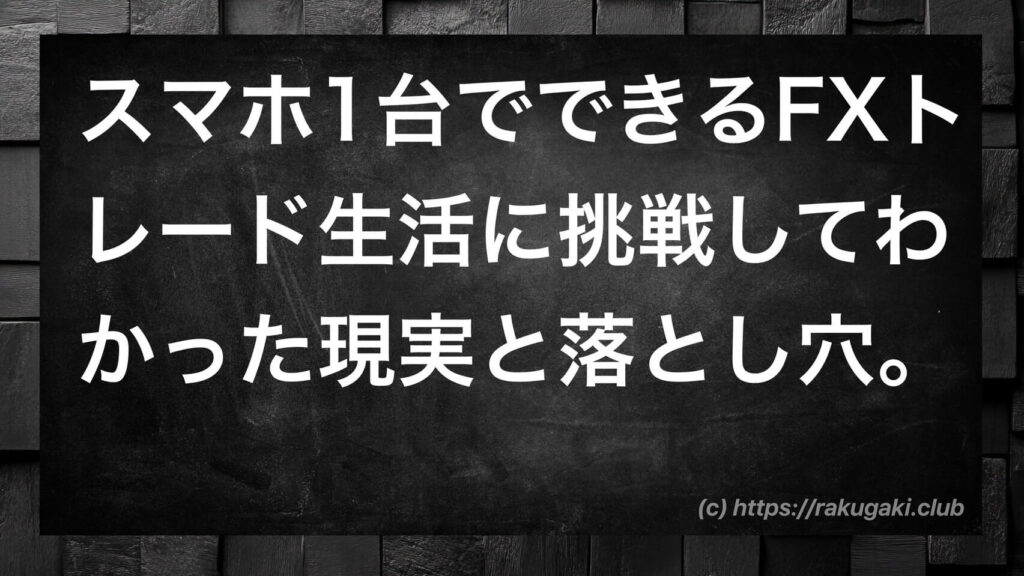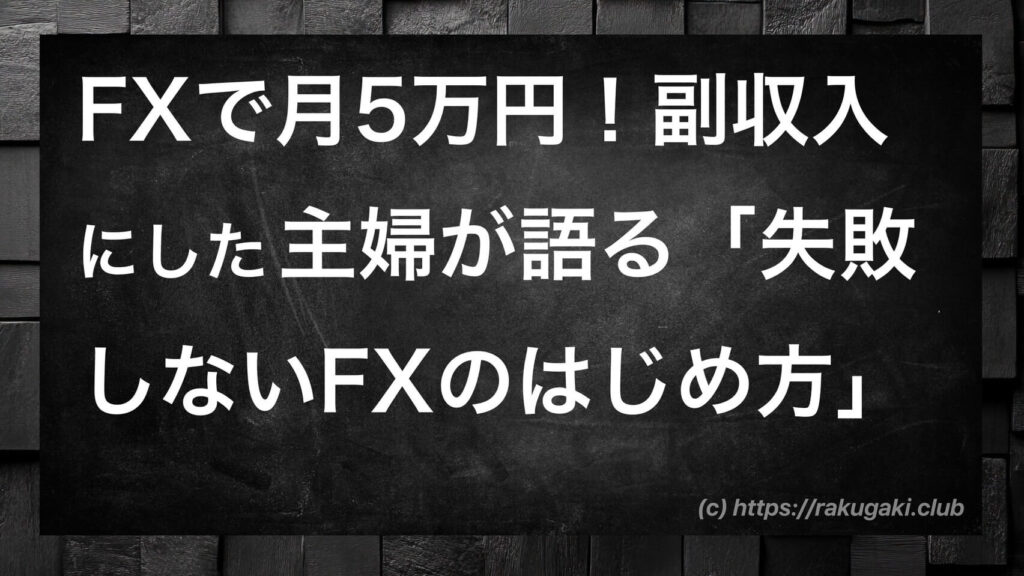セクハラと気づかれないセクハラ
「冗談でしょ」と笑い話で済まされる恐怖
私は、あるメーカー系の子会社で、総務課に配属されていた。
規模としては従業員120人ほど。男性社員が多く、女性は部署ごとに1〜2名いるかいないかといった環境だった。
最初に違和感を覚えたのは、新卒で入社して3ヶ月が経ったころ。
直属の上司であるA課長(50代・男性)が、私の容姿や私生活について、雑談の延長のような形で頻繁に口にするようになった。
「今日のスカート、攻めてるねえ」
「彼氏できた?俺が若かったらなあ」
「どうせ家帰っても誰もいないでしょ?」
――その場では、私自身も「苦笑い」しかできなかった。
なぜなら、まわりの男性社員たちがそれを笑い話として受け取っていたからだ。
むしろ、若手の男性社員が「課長、また言ってる!」「セクハラですよ〜!」と茶化しながら場を盛り上げる。
女性である私は、「真面目に受け取ったら空気を壊す側」になってしまう構図だった。
こういう時、「ああ、まだ私は若手なんだ」と思い知らされる。
冗談を冗談と受け取れない方が悪い。
空気が読めない奴と思われることの方が職場では致命的。
実際にその空気の中で、私は“黙って笑ってやり過ごす”選択肢しか持てなかった。
でも、心の中では何かがおかしいと感じていた。
「誰も止めない」環境の怖さ
ある日、A課長は私の髪を触ってきた。
「髪の毛サラサラだね〜!うちの娘よりキレイだよ」
それに対して私が一歩身を引いた瞬間、彼は言った。
「え?冗談だって。そんな顔しないでよ」
“冗談”。
この一言が、あらゆる責任を霧散させてしまう免罪符になっていた。
私は嫌だった。だけど言えなかった。
課長だけでなく、まわりが笑っているから。
私だけが“本気で受け取ってる側”になってしまうのが怖かった。
だんだん、社内でA課長と顔を合わせることに緊張を感じるようになった。
彼の姿を見ると、気づかないうちに背筋が固まる。
昼休憩中も、会話が聞こえてくると耳を塞ぎたくなる。
これって、もう普通の状態じゃない。
でも、会社で「これが異常」と言う人は誰もいなかった。
周囲に相談しても「そういう人だから」で済まされる現実
勇気を出して、先輩女性社員(別部署の事務職)に話してみたことがあった。
すると彼女は苦笑しながら言った。
「A課長ね……あの人、昔からそういうところあるのよ」
「悪気はないから、聞き流すしかないって感じ」
私は愕然とした。
「悪気はない」
この言葉も、“被害者が我慢して折れる理由”として使われてしまうのかと。
セクハラに「加害者側の意図」は関係ない。
受け手が嫌だと感じている時点で、すでに成立している。
そう教わった記憶がある。
でも、社会人になったら、それを“正論”のままぶつけられる環境はほとんどない。
心身の限界が近づいていた
それから数ヶ月、私は徐々に体調を崩していった。
出勤前にお腹が痛くなる。
デスクに座っても集中できない。
同期との雑談も減り、笑うことが減っていった。
セクハラ自体は軽口程度のものに見えたかもしれない。
だけど、それが継続的に繰り返されることで、私の精神はすり減っていった。
「自分が敏感すぎるのかも」
「こんなことで騒いでたら、やっていけないのかも」
「私が社会に出るには早すぎたのかも」
そんな風に、自分を責める言葉しか浮かばなくなっていった。
ある朝、出勤準備をしていた私は、ついに玄関で崩れ落ちた。
「行きたくない」
声に出して初めて、自分の限界を知った。
このとき私は、ようやく“何かを変えないといけない”と思い始めたのだった。
初めて「記録を残す」という行動に踏み出した日
体調が崩れ、職場に行くことすら辛くなっていたある日。
私は会社を休んで、自宅のベッドの上でぼんやりと天井を見つめていた。
何もしたくない。何も考えたくない。
だけど――「このままにしていてはいけない」という感覚だけが胸の奥に重たく残っていた。
会社の誰も止めてくれない。
直属の先輩に相談しても、まるで昔から決まっていた「処世術」を渡されるようなだけだった。
それなら、自分で自分を守るしかない。
その日の午後、私はスマホのメモアプリを開き、“言われたこと”を記録することから始めた。
記録しはじめて初めて見えた「頻度」と「パターン」
最初は曖昧だった。
「9月13日 朝の挨拶で “また色っぽくなった?” と言われた」
「9月14日 廊下ですれ違いざまに “今日は一段とミニだね” と笑われた」
書き留めてみて、初めて気づく。
A課長の発言は、もはや週1どころか、ほぼ毎日何かしらあるという現実に。
しかも、発言には“パターン”があった。
- 朝の挨拶に性的な冗談を混ぜる
- 雑談で彼氏の有無を聞く(それを課長自身の立場に結びつけてくる)
- 飲み会の予定があるときに露骨に服装に言及してくる
- 「若いっていいよね」と“相対的に自分を下げながら褒める”という構図で正当化する
そのすべてが、「冗談」「親しみ」「世代ギャップ」といった言葉で包まれていた。
行動に移すために、社内規程を読み直した
その後、私は社内ポータルサイトから就業規則とハラスメント防止規程を見直した。
実は、入社前の研修で「ハラスメント防止マニュアル」を一通り学んだ記憶があったが、正直そのときはピンと来ていなかった。
でもあらためて読んでみると、そこには明確にこう書かれていた。
『セクシュアルハラスメントとは、労働者の意に反する性的な言動によって就業環境を害することを指す』
私が今感じていること、抱えているストレスは、まさにこれだった。
意に反している。
でも誰も止めない。
結果的に、私の就業環境は確実に悪化している。
この時、私はようやく「これは私のわがままじゃない」と言語化できた気がした。
総務部への“相談”という選択肢の重さ
社内規程には、相談窓口として総務部の個別対応のメールアドレスが記載されていた。
「社内相談窓口までの連絡ルート」も簡易マニュアルで載っていた。
だけど、メールを打つ手が止まった。
「相談したって、揉み消されるんじゃないか」
「A課長とまた顔を合わせて仕事を続けられるの?」
「社内にいづらくなるのは自分じゃないか」
こんな思考がループした。
相談するには、何段階も“怖さ”を乗り越える必要があった。
匿名相談からはじめた
私はまず、社内ポータルにあった「匿名通報フォーム」に投稿することにした。
社内規程に則った通報チャネルで、投稿内容は人事本部が確認し、必要に応じて本人に面談希望を出す形式だった。
内容はこうだった。
「ある管理職から日常的に性的な冗談を言われており、困っています」
「部署の空気的に誰も止めてくれず、相談しづらいです」
「可能であれば、このような状況が全社的に見直される仕組みをつくってほしいです」
数日後、人事からの社内通達が掲示された。
「ハラスメント防止研修の再実施」
「全社員を対象にしたアンケートと匿名フィードバックの導入」
「直属の上司による定期ヒアリングの強化」
誰が動いたかは誰も知らない。
だけど、職場の空気が、ほんの少しだけ「凍った」。
あの温度変化を、私は忘れられない。
「あれ?最近、課長が静かじゃない?」
人事の通達から数日後、職場で小さな変化が起き始めた。
A課長が、妙に“静か”なのだ。
それまでなら、朝の挨拶で何かしら私に言葉をかけていた彼が、黙って会釈をするだけ。
「今日は大人しいですね」なんて他の社員に冗談交じりに言われても、「いや、最近ちょっとな」とごまかす程度。
最初は“たまたまかな”と思った。
でもそれが、1日、2日…1週間と続く。
あの空気を読まずに喋り倒していたA課長が、自分の言動にブレーキをかけているように見えた。
目に見えない「チェック」が働き始めた
後輩の男性社員がぽろっと言った。
「なんか最近、課長めっちゃ言葉選んでません?」
「ハラスメント研修のせいかも」
その言葉に、私は内心ギクリとした。
私の匿名通報は、もちろん誰にも知られていない。
でも、「誰かが声をあげた」ことは、確実に職場に伝わっていた。
それが抑止力になりはじめていたのだ。
社内にはアンケートや研修だけでなく、定期的に“管理職対象のフォローアップ面談”が導入されることになった。
その中でA課長にも何かしらの「指導」が入っているのだと、後に知ることになる。
私自身も「変化」を求められる側にいた
皮肉なことに、A課長が黙るようになってから、
一部の男性社員が私に対して微妙な距離をとるようになった。
「課長、最近元気ないね」
「セクハラとか、難しい時代だな」
「冗談も言いにくい空気だよなあ」
――まるで、**空気を壊したのは“被害者側”**であるかのような反応だった。
もちろん全員ではない。
むしろ何も言わず、普通に接してくれる人たちもいた。
けれど、微妙な距離感や視線を感じるたびに、
私は「これが正しかったのか?」と、自問する毎日を過ごしていた。
直属の女性管理職がかけてくれた言葉
そんなとき、別部署の女性係長が、私に話しかけてくれた。
数少ない女性の管理職で、いつも淡々とした人だったが、その日は違った。
「…あのね、私、あの通達が出てから気づいたのよ」
「自分も“何も言わない側”だったって」
その係長は、過去に自分もA課長に同じような言動を受けたことがあると言った。
でも、管理職としてスルーしてきた。
それが“当たり前”だった時代を生きてきたから、抵抗感すらなかったのだと。
「あなたが声をあげてくれてよかった。私も遅ればせながら、自分の責任を考えるようになった」
その言葉に、私はようやく“肩の荷”が少しだけ降りた気がした。
「言わなきゃわからない」は正しいが、簡単じゃない
この経験を通して痛感したのは、
セクハラの問題は、加害者と被害者だけで完結しないということだった。
- 黙認してしまう同僚
- 仕方ないとあきらめる先輩
- 冗談で場をつなぐ若手社員
- 「面倒くさい」と距離を取る一部の周囲
誰もが加害者にも傍観者にもなり得る。
声をあげる側には、孤独と代償がつきまとう。
でも、それでも動かなければ、何も変わらない。
「声をあげる」のではなく、「環境を整える」が本来あるべき姿だと、私はやっと実感し始めていた。
少しずつ変わっていった空気
半年が経った頃、A課長は他部署へ異動になった。
理由は社内では明かされていないが、
「部下との関係性の再構築が必要とされた」と噂されていた。
私は人事から呼ばれ、個別ヒアリングを受けた。
その中で、あの匿名通報の内容について詳しく聞かれた。
守秘義務のもと、私が書いた内容が確認されたという。
人事担当者の女性が、こう言った。
「行動に移してくれてありがとう。今後の社内教育の見直しにもつながります」
ようやく、**組織としての“意思”**が見えた気がした。
「自分のため」だったはずが、周囲の意識を変えていた
A課長が異動になり、あの重たい空気がようやく抜けていったころ。
私は自分の部署に戻り、ようやく“いつもの業務”に集中できるようになっていた。
でもその矢先――同じ部署の後輩、Kさん(新卒2年目の女性)が、私に声をかけてきた。
「先輩…あの…ちょっと相談いいですか?」
いつも明るくて快活なKさんが、めずらしく控えめなトーンだった。
応接スペースに移動して、ゆっくり話を聞いていくうちに、私は息を呑んだ。
あの空気が「自分だけじゃない」と気づくきっかけに
Kさんの話は、まさに“デジャヴ”だった。
内容こそ多少異なるが、
・業務に直接関係ない場で、年上男性社員に服装や髪型についてコメントされる
・恋愛事情や私生活を探られるような質問をされる
・断ると「冗談だよ〜」「怒らないでよ」とごまかされる
まさに、“昔の私と同じ状態”だったのだ。
でもKさんは、あの社内通達やハラスメント研修を見て、「こういうの、言っていいんだ」と感じてくれたという。
「たぶん、あれって…先輩が動いたやつ、ですよね?」
Kさんはそう言って、少しだけ笑った。
私は驚いた。
誰にも言っていないはずなのに、伝わっていたのだ。
被害の“連鎖”を断ち切るためにできること
Kさんには、私が過去に記録を残していた方法をそのまま伝えた。
- メモアプリに日付と発言の概要を残すこと
- 体調面の変化があれば記録すること
- できればスクショやメールなどの物証も残すこと
- 社内ポータルの匿名フォームの使い方
「それだけでも、ぜんぜん違うから」
自分の体験を、“誰かの対処手順”として残すことになるとは思っていなかった。
けれど、それがKさんにとっては救いだったらしい。
私の記録が「マニュアル」として活用され始めた
数ヶ月後、さらに驚く出来事が起きた。
人事部から社内広報が発行され、ハラスメント防止に関する“現場事例”として、匿名事例A・Bが共有された。
その“事例A”は、どう見ても私の件だった。
- 日常的な言動に対する記録の取り方
- 匿名通報と社内体制の連携方法
- 管理職へのフィードバックルートの運用フロー
つまり、私の行動が「公式化」されたのだ。
名前も部署も明かされていないが、
そのプロセスが社内で共有されたことには、大きな意味があった。
空気が変わることで、沈黙の人たちが動き出した
広報誌のあと、私のもとに何人かの女性社員が話しかけてくるようになった。
「実は、前から気になっていたことがあって…」
「これ、他部署の話なんだけど…」
「私も匿名で出してみようと思ってます」
私は専門家でも、正義感の塊でもなかった。
むしろ、当初はただ自分を守りたかっただけだ。
でも、その“小さな動き”が、
他の誰かの背中を押していたことをようやく実感した。
職場という“閉じた空間”だからこそ、可視化が必要だった
セクハラの問題は、直接的な暴言や暴力だけではない。
冗談という言い訳に隠れた、微妙な“揺さぶり”や“支配”が蔓延しやすい。
特に日本企業のような「空気を読む」文化の中では、
・はっきり言わないこと
・表沙汰にしないこと
が、美徳のように扱われがちだ。
だけどそれは、
加害者が“逃げやすい”構造を生み出すだけだ。
私たちは、“告発”をしなくてもいい。
でも、記録し、共有し、伝えることは、誰にでもできる第一歩だと私は思う。
そのひとつが、私だっただけ。
そう思うことで、ようやく自分の行動が肯定できるようになった。
「“動いた人”として見られるようになってしまった」
ある日、別部署の会議に参加したときのこと。
初対面の女性社員が名刺を渡しながら、こんなひと言を口にした。
「◯◯課の〇〇さんですよね?…あの件、ありがとうございました」
「え?」
一瞬、どう返していいか分からなかった。
“あの件”というのが、私が匿名で人事に通報した件であると、すぐに察した。
情報が漏れたわけではない。
でも、社内で広まっていた“誰かが声をあげた”事例と、私の行動が結びついていたのだ。
匿名のつもりだった。でも、匿名ではいられなかった
その後、何人もの女性社員が、私に個別に声をかけてくるようになった。
感謝の言葉もあれば、共感、そして「実は私も…」という新たな相談も。
私は、“社内の相談役”のような立ち位置になっていた。
けれど、それは決して楽な役割ではなかった。
対応を間違えれば、2次被害に繋がる。
「聞いてくれる人」として見られ続ける重圧もあった。
そして、時折、こんな陰口も耳に入ってきた。
「いちいち騒ぐのって、やっぱ女の人だよな」
「被害者ムーブって、あざとく見えるときあるよな」
それを言っていたのは、別の部署の男性たちだった。
一歩前に出るということは、二歩目を求められること
通報して終わり、ではなかった。
一歩前に出るということは、「次はどうする?」と周囲から問われる立場になることでもある。
私自身が正しく動けているか?
誰かを巻き込みすぎていないか?
制度や支援の限界も含めて、考えなければならなかった。
そうして悩んでいたある日、同じように人事に匿名通報をしたという社員と、偶然顔を合わせた。
お互い「もしかして」と思い、ランチの時間に少しだけ話した。
「私、正直もう少し静かに終わるかと思ってた」
「でも、動いた後の方がずっとしんどいんだね」
その言葉に、私は深くうなずいた。
社内で「対処フロー」が再設計されはじめた
半年後、社内の人事部が“新しいハラスメント相談体制”を公開した。
- 匿名相談に加え、希望者には第三者仲介の面談制度を導入
- ハラスメント発生時の管理職への即時通達ルール
- 「相談した人」へのアフターフォロー面談の導入
しかもこの新制度には、“社内ヒアリングの実例を参考にした”という注釈があった。
おそらく、私たち数人の行動が、直接的なトリガーになっていたのだ。
上層部のコメントに、こんな一文が添えられていた。
「“気づかないふり”を続けたこともまた、組織の責任であると考えています」
私の中に、何かがほどけていくのを感じた。
あのとき、1人で抱え込んでいた孤独感が、やっと報われたような気がした。
変わったのは、空気と制度だけではない
Kさんは今、社内の新人向け研修で「信頼できる相談窓口」として紹介されている。
私も“経験者”として、簡単なフィードバックを提供する側になっていた。
A課長のような人物がいなくなったわけではない。
けれど、「言っていい」ことと「言ってはいけない」ことの境界が、はっきりしてきた。
それだけでも、職場の安心感は大きく変わった。
そして私自身も、「誰かを守る」と同時に、「自分を守る術」を持てるようになった。
「見て見ぬふり」から「支える行動」へ
あの日、「冗談だろ」で笑って済まされたセクハラ発言。
もし私が黙っていたら――今もきっと、誰かが笑ってごまかし、誰かが黙って泣いていたと思う。
ハラスメント対策は、一人ではできない。
けれど、「一人の声」が、組織の“足を止めて考えさせる力”を持つことを、私は知った。
動いた人が、責められるのではなく、
支えられる存在になる職場へ。
その流れが、少しずつでも確かに広がっていく。
そう信じられる今が、ようやく少しだけ、誇らしい。
セクハラを「冗談」で流させない職場環境をつくるには
今回の私の体験は、特別な環境で起きたことではありません。
むしろ、どこにでもある中規模の企業で、日常の延長線上に存在していた“典型的な構造”でした。
だからこそ、**「気づき」「行動」「制度設計」**のどれか1つでも動けば、変化は生まれる――
そう実感できたことが、最大の収穫でした。
以下に、再現可能な実践手順と職場改善に必要な視点をまとめます。
1. まず「記録」を取る。感情よりも客観的事実を優先
- 日時・相手・発言内容をメモアプリなどに記録
- 可能であれば、周囲にいた人・状況・自身の体調変化も添える
- スクショやメールなどの証拠も保管する(無理に集めなくてもOK)
重要なのは、“後から振り返れるデータ”を持つことです。
人事や第三者に相談するときも、記録があるかどうかで対応の精度が変わります。
2. 内部制度を確認する。使えるルートを“選ぶ”
会社により相談ルートは異なりますが、一般的に以下の3つが存在します:
- 上司や先輩への直接相談(非公式ルート)
- 人事部・コンプライアンス窓口(準公式)
- 匿名通報制度・社外相談機関(公式)
自分の立場や安全性を踏まえて、“選べる手段”を知っておくことが重要です。
3. 相談後の“動き”を記録しておく(組織の対応の質も含めて)
相談を行った後、どのような対応があったかを記録しておきましょう。
- 放置された
- 異動になった
- 話し合いがあった
- 組織として方針が出た
この蓄積が、自身を守ると同時に、他の人の「選択肢」にもなりうるからです。
4. 被害者の声を「共有知」として活かすには
セクハラの“再発防止”には、個人の記録・体験が組織に届く必要があります。
- 相談を通じて制度設計に活かされる
- 匿名フィードバックが研修に反映される
- 誰かの記録が「相談マニュアル」になる
つまり、“声をあげる”というよりも、「見える化」することの積み重ねが組織を変えるのです。
5. 変わるのは制度だけではなく、「空気」である
ハラスメントの温床は、明確な加害者ではなく、黙認する空気そのものです。
「またあの人か」「冗談だろ」で済ませる文化を、
「それ、ちょっと不適切じゃない?」と言える文化に変える。
これは制度だけでは変わらない領域であり、
個人の働きかけ、つまり“空気を変える行動”が必須です。
◆まとめ:個人で始め、組織に接続する流れを意識する
| ステップ | 行動内容 | 目的 |
|---|---|---|
| Step1 | 記録する | 感情を事実に変換する |
| Step2 | 制度を確認 | 最も安全な経路を知る |
| Step3 | 相談後も記録 | 組織の対応を可視化する |
| Step4 | フィードバック | 組織改善の素材にする |
| Step5 | 周囲と共有 | 空気を“無言の味方”から変える |
セクハラ対策は、決して“声を上げた人”だけの仕事ではありません。
でも、その“ひとつの声”がなければ、組織が動くきっかけは生まれない。
だからこそ、まずは**「声を可視化する仕組み」を整えること**が、
これからの企業と社会に必要な視点だと考えます。
黙っていたら、何も変わらない。
でも、正しく記録し、正しい場所に届けることで、少しずつ未来は変わる――
それがこの体験からの、もっとも現実的で前向きな学びでした。