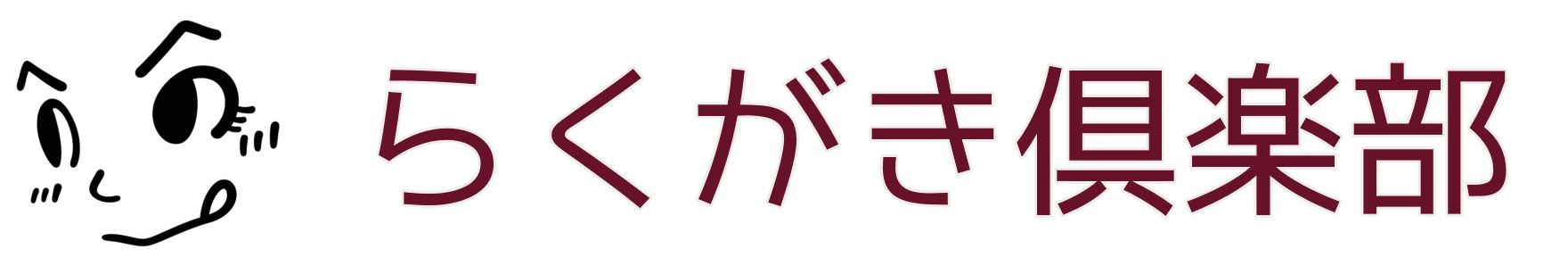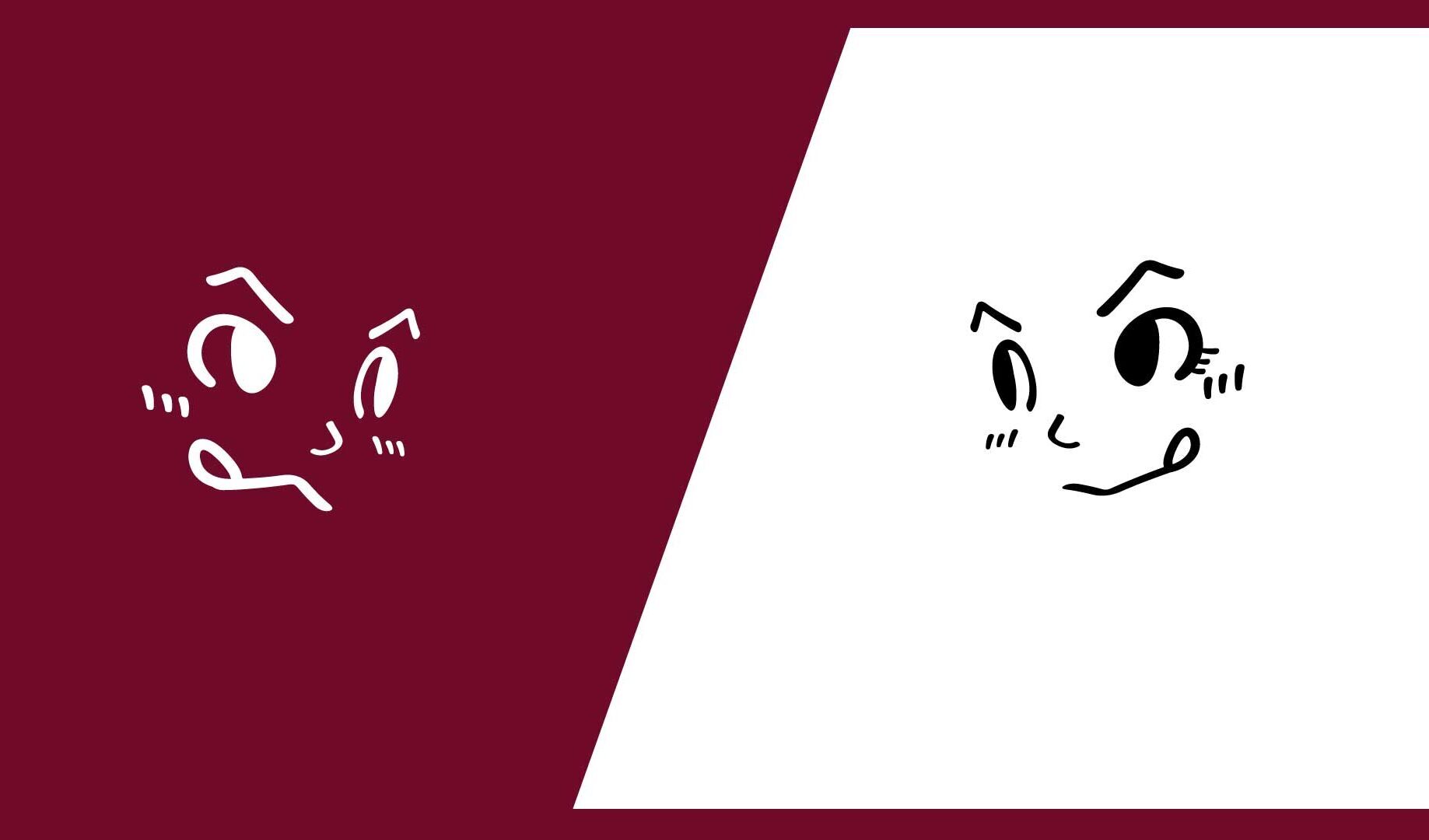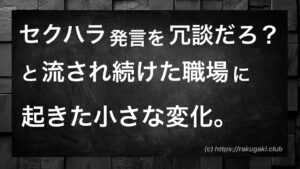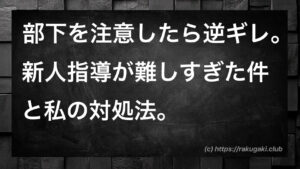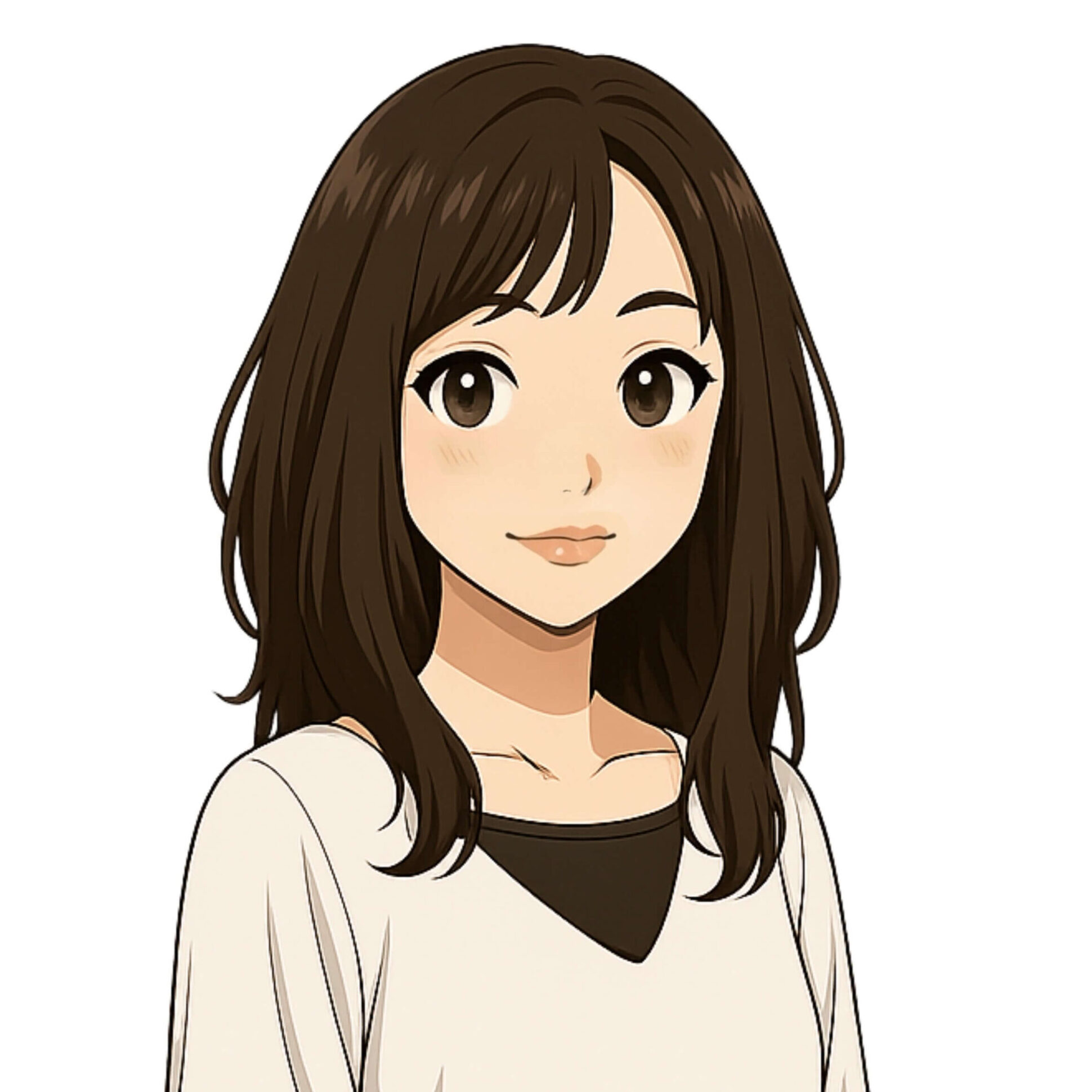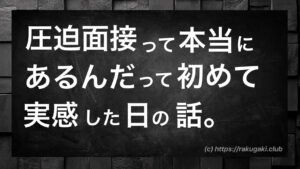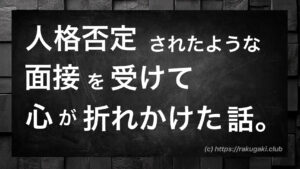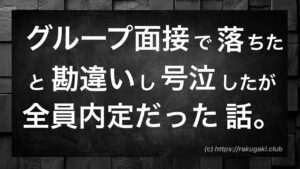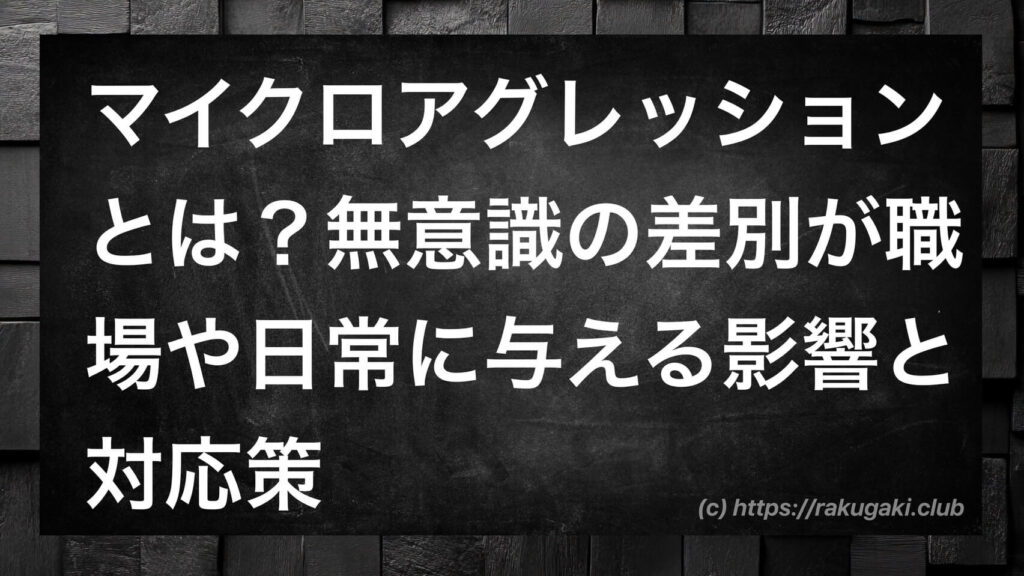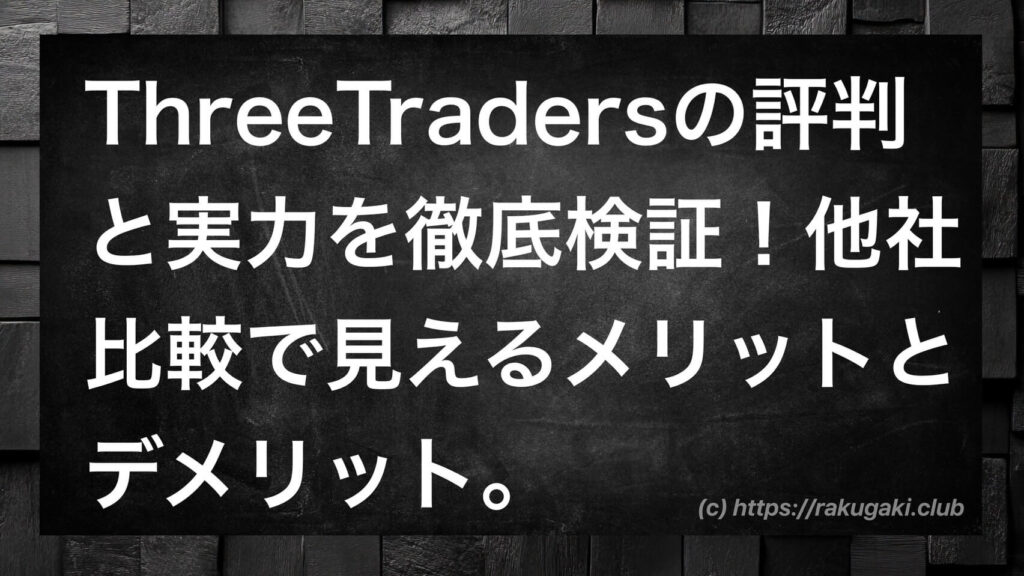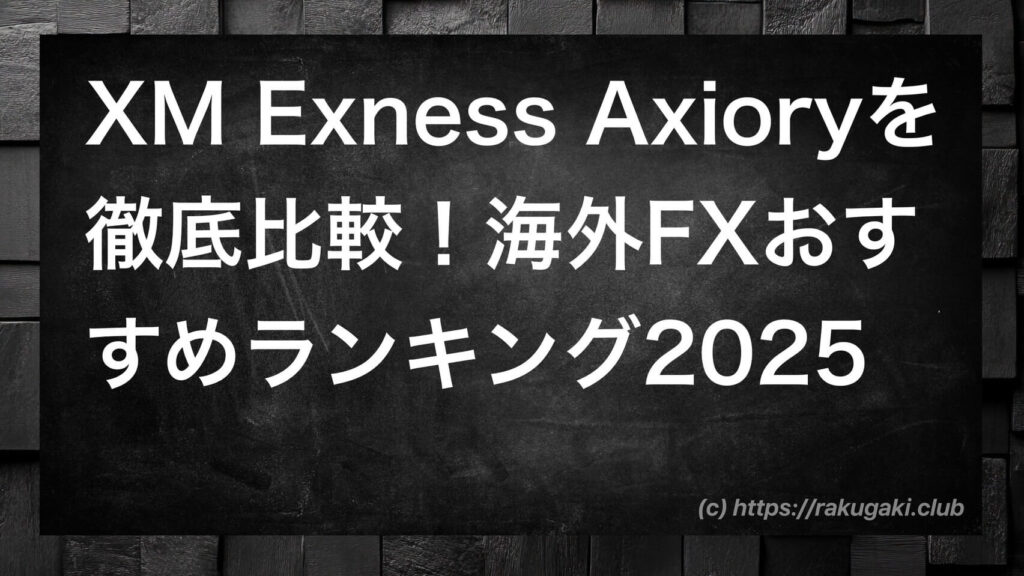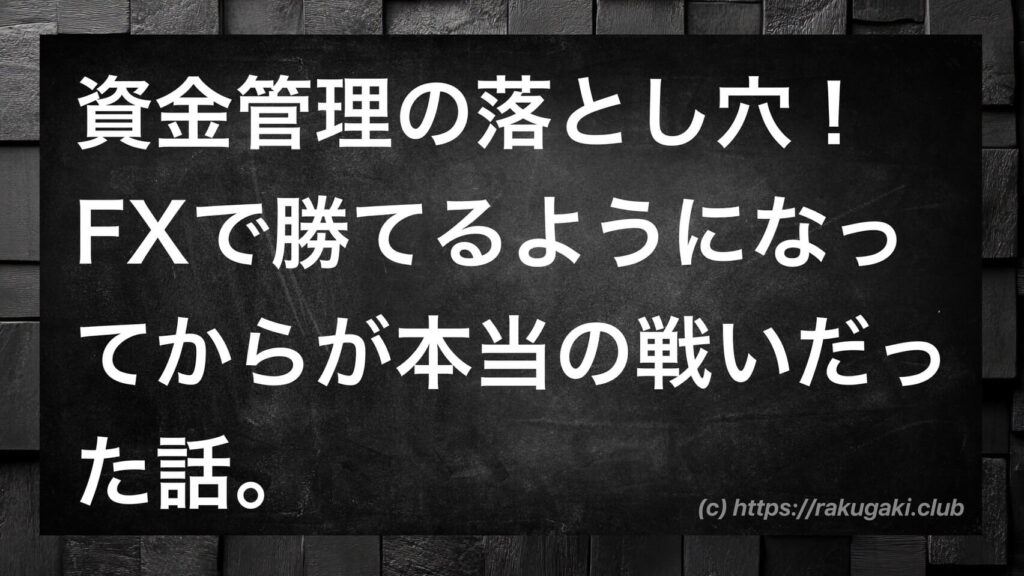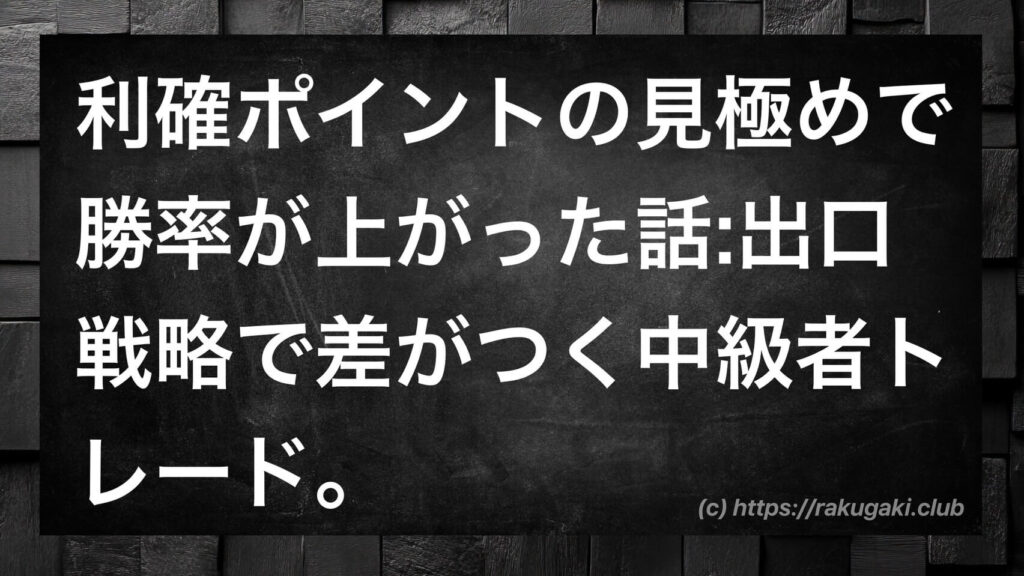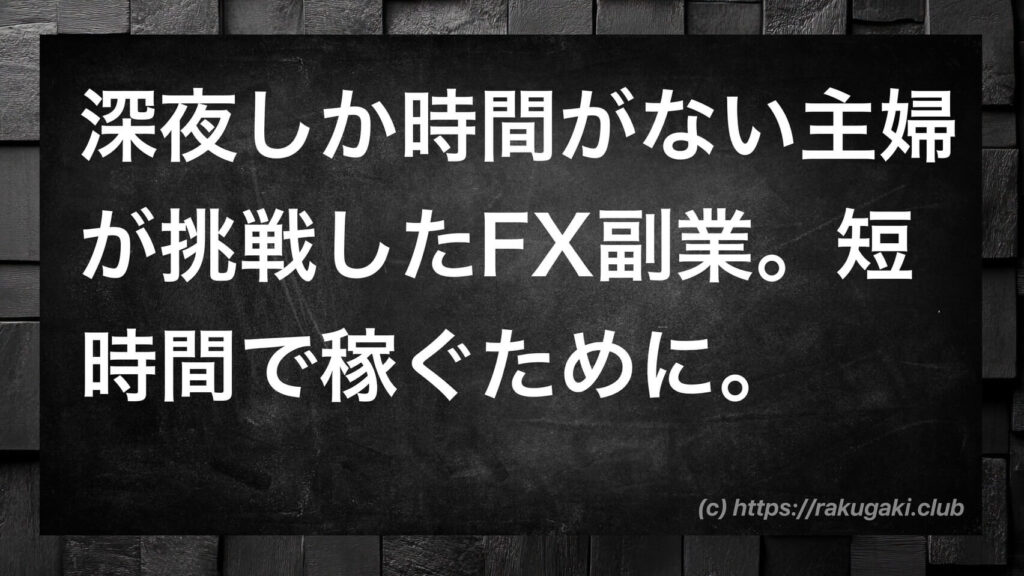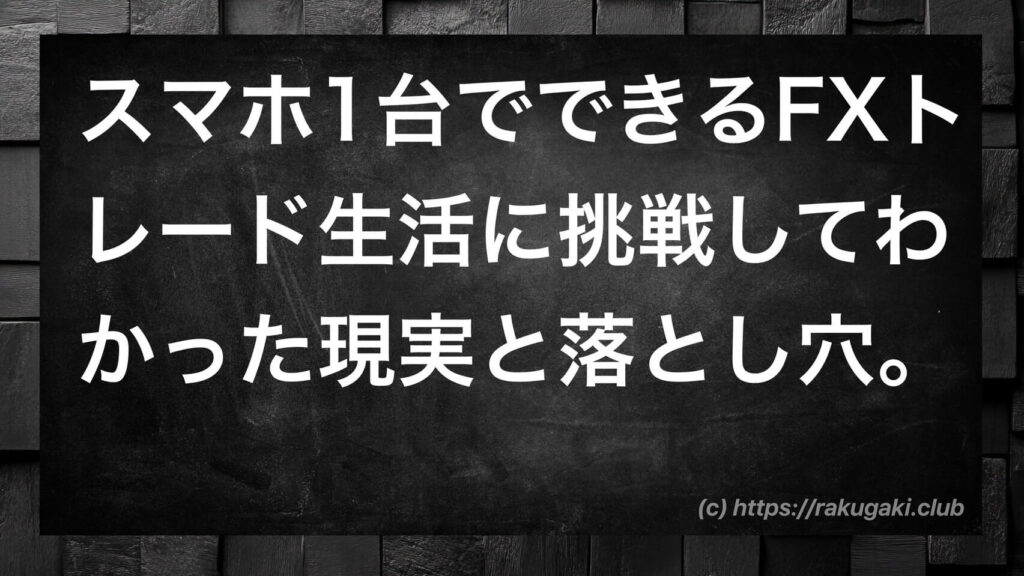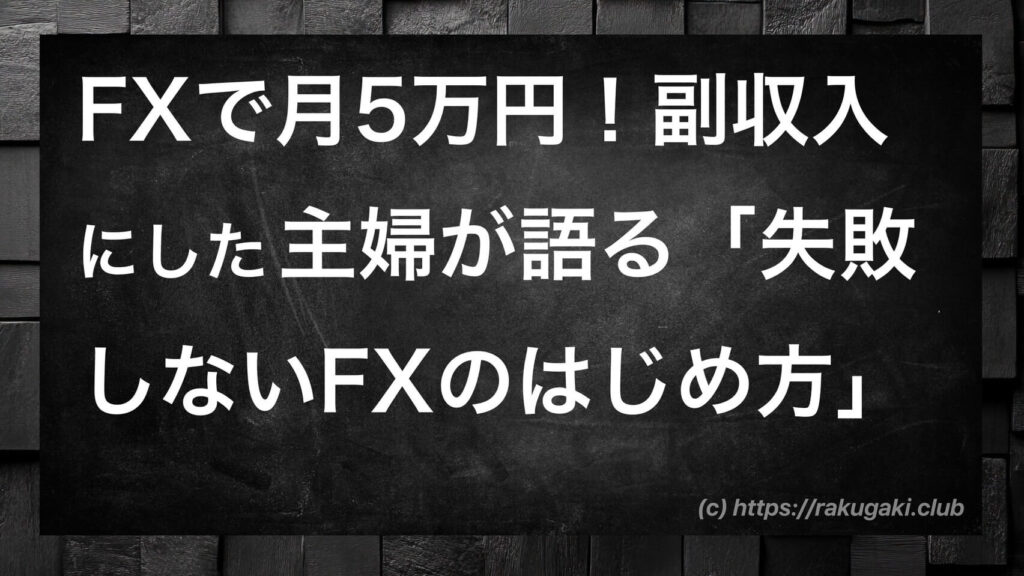マイクロアグレッションという言葉を知る前に、私は疲れていた
「なんか今日も、また言われたな」から始まる違和感
職場で、何度目かわからない“その一言”を聞いた帰り道、私はヘトヘトだった。
同僚のAさんが笑いながら放った言葉は、いつもと変わらない軽口だった。
「またその服?ほんと地味なの好きだよねー」
「どうせ彼氏いないでしょ?寂しそうだもんね」
「その程度で疲れたって、体力なさすぎじゃない?」
笑って返すのが“お約束”になっていた。言い返すと「冗談じゃん」と返されるのも“テンプレ”だった。
でもその夜、ふと気づいた。最近、仕事が終わると疲労感が尋常じゃない。身体というより、気持ちのほうがだ。
「いちいち気にする私が変なのか」と悩む日々
私が働くのは、社員30人程度の中小企業。事務職で、基本的には穏やかな人が多い職場だ。
だけど、なぜか最近、居心地が悪い。
原因が明確なわけじゃない。
毎日怒鳴られているわけでも、露骨な嫌がらせがあるわけでもない。
でも、言葉の端々に引っかかるものがあって、それが蓄積していく。
「そんなの気にしすぎだよ」
「悪気はないでしょ」
「それくらいスルーしなよ」
誰かに相談しても、決まってこの反応。
むしろ、自分が小さなことに目くじらを立てている“面倒な人”なのではないかという疑念が、心を締めつけていった。
それは「ハラスメント」じゃないと思っていた
上司も見て見ぬふり。「本人に言えば?」で片づけられる現実
一度だけ、上司に軽く相談したことがある。
「Aさんの言い方がちょっと気になるんですけど…」と。
返ってきたのは、
「うーん、Aさんってああいう言い方するよね。あんまり気にしなくていいんじゃない?」
「本人に言えば?悪気ないと思うけどなあ」
という“あしらい”だった。
たしかに、Aさんは他の人にも似たようなことを言っている。私だけが対象じゃない。
でも、ターゲットを絞っているかどうかは、本質じゃない。
私は、この「言われる側の苦しさ」が理解されないこと自体に、さらに傷ついた。
無意識の差別、という言葉に初めて触れた日
「マイクロアグレッション」という概念との出会い
転機は、ある休日に何気なく読んだネット記事だった。
タイトルは「あなたの“つもり”が誰かを傷つけているかもしれない〜マイクロアグレッションとは〜」
その記事には、こうあった。
マイクロアグレッションとは、意図的ではないが、繰り返されることで少しずつ人を傷つける言動。
言葉の暴力や差別的な態度が、本人の自覚なく日常化している状態を指す。
読みながら、私はページを閉じることができなかった。
今まで言われてきたこと、笑って流してきた言葉の数々が、頭の中でよみがえる。
「それって、“私が”おかしいんじゃなくて、“環境が”おかしかったのかも?」
ようやく、その視点にたどり着けた瞬間だった。
「私のせいじゃなかった」と認識するまでにかかった時間
自己否定から脱するための一歩
この“言葉”を知ったことが、自分を責める習慣を断ち切る第一歩だった。
それまでの私は、「こんなことで落ち込む私が悪い」「もっと強くならなきゃ」と思い続けていた。
でも、マイクロアグレッションという視点を知ってからは、
“誰にでも起こり得る構造的な問題”として捉えられるようになった。
これは、決して私の“心が弱いから”ではない。
社会や職場に無意識のハラスメントが染み込んでいるという現実に、ようやく目を向けることができた。
どこまでが“冗談”で、どこからが“ハラスメント”なのか
線引きのヒントは「主観」ではなく「影響」にある
マイクロアグレッションの厄介な点は、「言った側に悪意がない」こと。
そのため、指摘しても「そんなつもりじゃなかった」で終わってしまう。
でも、“つもり”ではなく、“結果”が問題なのだと、ようやく理解できた。
- 受けた側がどう感じたか
- その言葉が積み重なってどれだけ心を削ったか
ハラスメントかどうかの線引きは、そこにある。
この視点を持てたことで、ようやく私は「自分を守る言葉」を持てたのだと思う。
“悪気ないんだけど”の積み重ねが壊したもの
「褒めてるつもりだった」と言われても、全然うれしくなかった
ある日の昼休み。Aさんが、私の服を見て笑いながら言った。
「最近ちょっと垢抜けた?……いや、前がちょっとヤバかったもんね〜」
その場にいた同僚たちは、軽く笑って流した。
私も、慌てて笑ったふりをしたけれど、心のなかはぐちゃぐちゃだった。
帰宅後、その日のやりとりを何度も思い返してしまった。
「褒められたってこと?」
「それとも遠回しにけなされた?」
「私が気にしすぎ?」
自分でも分からなくなってしまっていた。
Aさんの発言には、毎回“冗談”という免罪符がついていた。
それを真に受けると「ノリが悪い」「感じ悪い」「空気が読めない」と思われるリスクがある。
その恐怖が、私をずっと沈黙させていた。
「そんなことで?」と思われる小さな言葉が、一番しんどい
別の日。業務中に少し疲れて、深くため息をついた私にAさんが言った。
「大げさだな〜。子どもでももっと頑張るよ?」
この一言に、ガツンと心を殴られたような気がした。
Aさんは明るく笑っていたし、その場も特に重くはならなかった。
でも、私にはその言葉が「あなたはダメな大人」という烙印に思えた。
周囲も「またAさん言ってるわ」くらいの反応で、特に問題視しない。
こうして、問題は問題として扱われず、“ただのノリ”として放置されていく。
そして私だけが、帰宅後に泣いていた。
同じように傷ついていた人が、社内にもいた
相談したくても、話せる人がいなかった理由
ずっと、「私だけが繊細すぎるんだろうな」と思っていた。
でもある日、後輩のBさん(女性)が休憩室でぼそっとつぶやいた。
「Aさんって、ほんと、言い方キツくないですか……?」
その瞬間、心のなかで何かが崩れた。
「え? そう思ってるの、私だけじゃなかったんだ……」
それまで私は、「周囲は何も感じていないんだ」と思い込んでいた。
でも実際には、みんな“気づかないふり”をしていただけだった。
Bさんが言うには、別の先輩社員もAさんの言動に悩んでいたという。
だけど、誰も面と向かって指摘したり、上司に相談したりはしていなかった。
理由は単純だった。
「面倒くさい人」と思われるのが怖いからだ。
沈黙が“許容”になってしまうという恐ろしさ
このとき、私は初めて「声を上げないことの危うさ」に気づいた。
たとえ意図せずとも、沈黙は“同意”と受け取られてしまう。
それが、加害側の「悪気はなかった」という免罪符をさらに強化してしまう。
私は決意した。
このまま我慢し続けていても、きっと何も変わらない。
でも、もし“私だけじゃない”と気づけたのなら、声を上げる意味はあるかもしれない。
そう思ったのが、変化のきっかけだった。
小さな“違和感”が積み重なるとき、人は黙っていられなくなる
「それ、ちょっとやめてほしいんです」と伝えた日
ある日、業務中にまたAさんからの軽口が飛んできた。
「また疲れてんの?ほんと要領悪いよね〜。まぁ真面目なのはいいことだけど〜」
このとき、私は思わず言ってしまった。
「Aさん、すみません、それちょっと……正直あまりうれしくないです」
一瞬、空気が止まった。
Aさんは目を丸くして、「え?冗談なのに。そんなつもりなかったけど」と困ったように笑った。
そして、その場にいた他の同僚たちも、少し微妙な顔をした。
誰も何も言わなかったけれど、たしかに“何か”が変わった空気があった。
それがいい変化かどうかは、その時点ではわからなかったけれど、
私は自分のために初めて「NO」を口に出せたことに、ほんの少しの達成感を感じていた。
最初に変わったのは、同僚の“目線”だった
翌日から、明らかに周囲の空気が違った。
Aさんは、私に対して明らかに距離を取るようになった。
だがそれ以上に気になったのは、周囲の同僚たちの反応だった。
ランチの時間、いつも一緒に食べていた同僚のCさんが声をかけてくれた。
「昨日のこと、よく言ったね。私もああいう言い方、ずっと苦手だった」
別の同僚もこっそりLINEで「私も我慢してた」と送ってきた。
その時気づいた。
私が声をあげたことは、周囲にとっても“きっかけ”になっていたんだと。
ハラスメントは“意図”より“影響”で判断すべき
「冗談」は、誰かの沈黙の上に成り立っていることを知った
Aさんの言動が職場の空気を壊していたということは、実は多くの人がうすうす感じていた。
でも、それが明るいノリやキャラの一部として認識されていたため、誰も止めようとはしなかった。
つまり、沈黙が“許可”になっていたのだ。
Aさんは悪意があったわけではない。
むしろ、場を盛り上げよう、楽しくしようという気持ちすらあったかもしれない。
でも、それによって誰かが笑えなくなっていたとしたら?
それはもう「冗談」ではなく、「攻撃」になってしまう。
“ハラスメントは、受けた側がどう感じたかで決まる”
それは一見すると主観的すぎるようで、実はとても大事な視点だ。
マイクロアグレッションが見えにくいのは、まさにこの“意図と影響のギャップ”があるからだ。
私たちは、“悪気ない”言葉にもっと敏感であっていい
「悪気ないんだけど」が枕詞になるとき、それは「言われても文句を言うなよ」というサインにもなる。
そんな空気を、無意識に受け入れてしまっていたことを私は深く反省した。
そして、それを許容してしまっていた自分にも、
何も言えなかったこれまでの自分にも、ようやく「仕方なかった」と言ってあげられた。
マイクロアグレッションは、誰もが加害者にも被害者にもなりうる。
だからこそ、私たちは普段の言葉や振る舞いを、
もう一歩だけ丁寧に見つめ直す必要があるのだと思う。
声を上げたあとの“余波”と、職場全体の変化の兆し
直属の上司が「悪気はなかったんだろ」と口にしたとき
数日後、私とAさん、そして直属の上司であるD課長を交えた面談が行われた。
理由は、Aさんが「人間関係がギクシャクしている」と相談したためだった。
D課長は穏やかに話し始めた。
「Aさんの発言で、気になる点があったと聞いています。でもね、Aさんは悪気はなかったと思うんだよね。あの人、ちょっと無神経なところはあるけどさ…」
その瞬間、私は頭が真っ白になりかけた。
「また“悪気がなかった”で片づけられるの?」
せっかく勇気を出して声を上げたのに、「受け取った側の気にしすぎ」と見なされる構図はあまりにも古く、苦しかった。
けれど、今度の私は違った。
「たとえ悪気がなかったとしても、私はあの発言で深く傷つきました。これまでにも何度もあって、心が持たなかったんです」
そう伝えると、課長は少しだけ黙り込んだ。
「そうか……」とつぶやいたあと、ようやく言った。
「じゃあ、一度部署内で“職場のコミュニケーション”について見直してみよう」
その言葉に、小さな希望の種が芽を出すのを感じた。
全体ミーティングでの「マイクロアグレッション」の共有
翌週の朝礼で、課長が全員の前で話し出した。
「最近、職場のコミュニケーションについて見直す必要があると感じています。“マイクロアグレッション”という言葉を知っていますか?」
誰もが一瞬キョトンとした。
「たとえば“冗談のつもり”で言った言葉が、誰かを傷つけていることがある。“悪気ないんだけど”で始まる一言も、時にハラスメントと受け取られるかもしれない。そういう小さなすれ違いをなくしていきたいと思っています」
課長の話は、説教じみてもおらず、誰かを責めるものでもなかった。
むしろ、「みんなで一緒に考え直していこう」というトーンだった。
その姿勢が、職場の空気を少し変えた。
Aさんの変化と、私が感じた“距離感の再構築”
Aさんは、その後も気まずそうではあったけれど、あからさまな態度は取らなかった。
むしろ、少し距離を取ったうえでの、丁寧な関わり方をするようになっていた。
たとえば、以前なら軽口で済ませていた場面でも、
「これ言っていいことかわからないけど、もし気に障ったら教えてね」
と前置きを入れてくるようになった。
それは、私にとっては“本音で話せる関係”ではなかったけれど、
“無神経さで傷つけられる恐怖”が減ったという意味で、大きな変化だった。
私は、Aさんと距離を置くことを選んだ。
でも、それは対立ではなく、互いの“安全距離”を見つけるという意味だった。
この時、私はようやく「ハラスメントへの対処」は“告発”だけでなく“環境調整”という方法もあると知ったのだった。
“意識すること”から始まる、静かな職場改革
「誰かを笑わせる」より、「誰も傷つけない」を優先する空気
全体朝礼でマイクロアグレッションという言葉が紹介されて以降、
職場には目に見えない“間”や“選び直し”の瞬間が増えた。
たとえば、誰かが何かを言いかけて、途中で言葉を止める。
そのあとに「……いや、ごめん、ちょっと言い方考えるわ」と訂正する姿が出てきた。
最初はぎこちなかったが、それでも誰かが“ブレーキをかける”姿勢を見せることで、
まわりも少しずつ、「傷つけない言葉」を意識し始めたのだと思う。
以前のように「盛り上げ役」として無遠慮なジョークを飛ばしていたAさんも、
今ではむしろ、「それ言い過ぎじゃない?」と他の人にブレーキをかける側に回っていた。
変わったのは言葉だけではなかった。
“配慮することはダサい”という空気が、“配慮できるのが大人”という空気に変わった。
上司が発した一言で、空気が決定的に変わった
ある日、別の課のリーダーが、業務に関する些細なミスをした部下に向かって言った。
「これ、またやっちゃった?○○さん、天然だもんな〜」
その場にいたメンバーは笑っていたが、笑っていなかったのがD課長だった。
「それ、冗談かもしれないけど……言われた側はどう感じたかな?」
その場の空気がすっと引き締まった。
D課長は続けた。
「“意図”が冗談でも、“影響”がマイナスなら見直すべきだと思う。
自分が気づけなかった言い方は、素直に修正していけたらいいと思います」
それをきっかけに、管理職層の会話にも“配慮”がしっかりと根づくようになった。
マネジメント層が本気で変わろうとしている――その姿勢は、職場全体に静かに波及していった。
私自身が「過去の自分と同じ悩み」を抱える後輩に出会った
しばらくして入社してきた新入社員のEさん(女性)が、ふとした雑談の中で言った。
「この職場、なんか居心地いいんです。前の会社では“自分の話題にされないか”って常に気を張ってました」
私はその言葉を聞いて、なんとも言えない気持ちになった。
“居心地がいい”と感じる空間は、偶然ではない。
きっと、それはたくさんの「意識的な選択」と「言い直し」の積み重ねでつくられていた。
自分が感じた“違和感”に向き合ったこと。
声を上げたこと。
話し合いを繰り返したこと。
すべてが、この空気につながっていたのだと感じた。
小さな発言が、誰かの心をえぐることもあれば
小さな行動が、職場の文化を変える第一歩になることもある。
「たかが一言」と見過ごさない感覚こそが、
これからの職場に必要な“当たり前”になると私は信じている。
無自覚なハラスメントに気づくためにできる、具体的な3つの対処法
1. 「その言葉、本当に必要?」と一呼吸置く習慣をもつ
マイクロアグレッションの厄介さは、“日常の一部”として繰り返される点にあります。
悪意がなくても、頻繁に同じような発言をされることで、相手の心は静かに削られていきます。
まず実践できるのは、自分の発言に一呼吸置くこと。
- 「相手の背景を知らずに決めつけていないか」
- 「言わなくてもいい一言ではないか」
この“間”を持つだけで、無意識の加害を防ぐ第一歩になります。
特に「悪気はないけど」「冗談で言ってるだけ」といった前置きは、
ハラスメントのサインになりやすいので注意が必要です。
2. “受け手基準”で見直すことが、組織を強くする
職場で「ハラスメントかどうか」の判断基準に迷うケースは多くあります。
そのときに重要なのが、“加害者の意図”ではなく“受け手の影響”で考える視点です。
たとえば、
- 冗談のつもりで言ったことが、相手にとって傷つく内容だった
- 気軽なつもりの言い回しが、上下関係の強調になっていた
など、“ズレ”が起きた時点で、リカバリーが必要になります。
この視点を全社的に持つことができれば、
単なるコンプライアンス対策ではなく、“心理的安全性”の高い組織へと育っていきます。
3. マイクロアグレッションに気づいたときの対処フレーズを持っておく
突然ハラスメント的な発言を受けたとき、咄嗟に反応できず後悔する人も多いものです。
そうならないためには、あらかじめ“使えるフレーズ”をいくつか持っておくと効果的です。
たとえば:
- 「それ、どういう意図で言ってますか?」
- 「今の言葉、ちょっとひっかかりました」
- 「その話題、私には不快に感じることがあります」
このように、相手を攻撃せず、でも距離感を示す言い回しを準備しておくことで、
“沈黙を選ばない自分”を守る手段になります。
また、上司や人事など、信頼できる第三者に記録ベースで相談することも大切です。
「証拠やログ」が残ることで、組織側の対応が変わるケースも多くあります。
小さな違和感に“フタをしない”ために
マイクロアグレッションは、被害が“明確な線”ではなく、“じわじわとした侵食”で進むからこそ対処が遅れがちです。
- 「これくらいで騒いだら面倒に思われるかも」
- 「空気を悪くしたくないし、私が我慢すれば」
――そうやって“気づいていたのに何もしなかった”経験が、
結果的に職場全体の沈黙や無関心を生んでしまうこともあります。
小さな違和感を共有する文化。
咄嗟の一言を見直す感覚。
そして、声を上げた人を孤立させない仕組み。
これらの積み重ねが、「働きやすい職場」をつくる本質です。
「冗談のつもりだった」が通用しない時代に、
私たちは“言葉の責任”と、職場における“信頼の距離感”を、もう一度見直す必要があります。