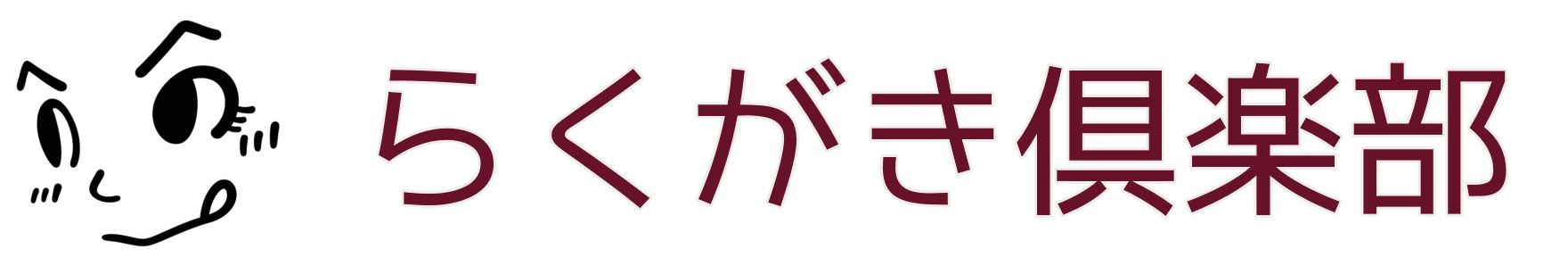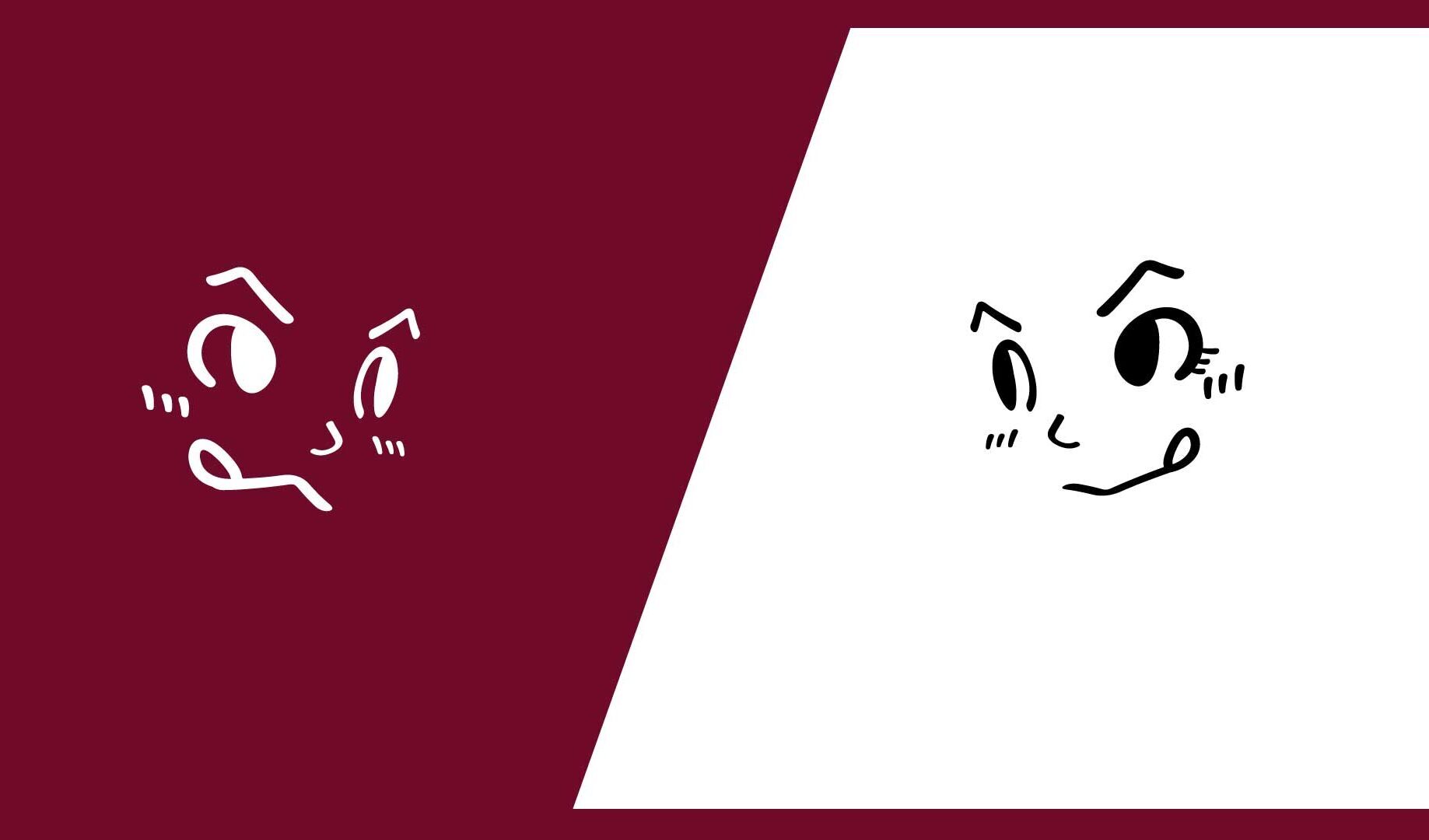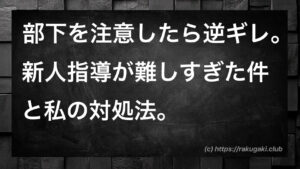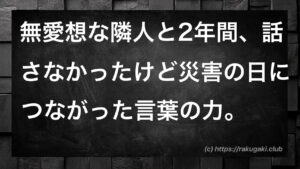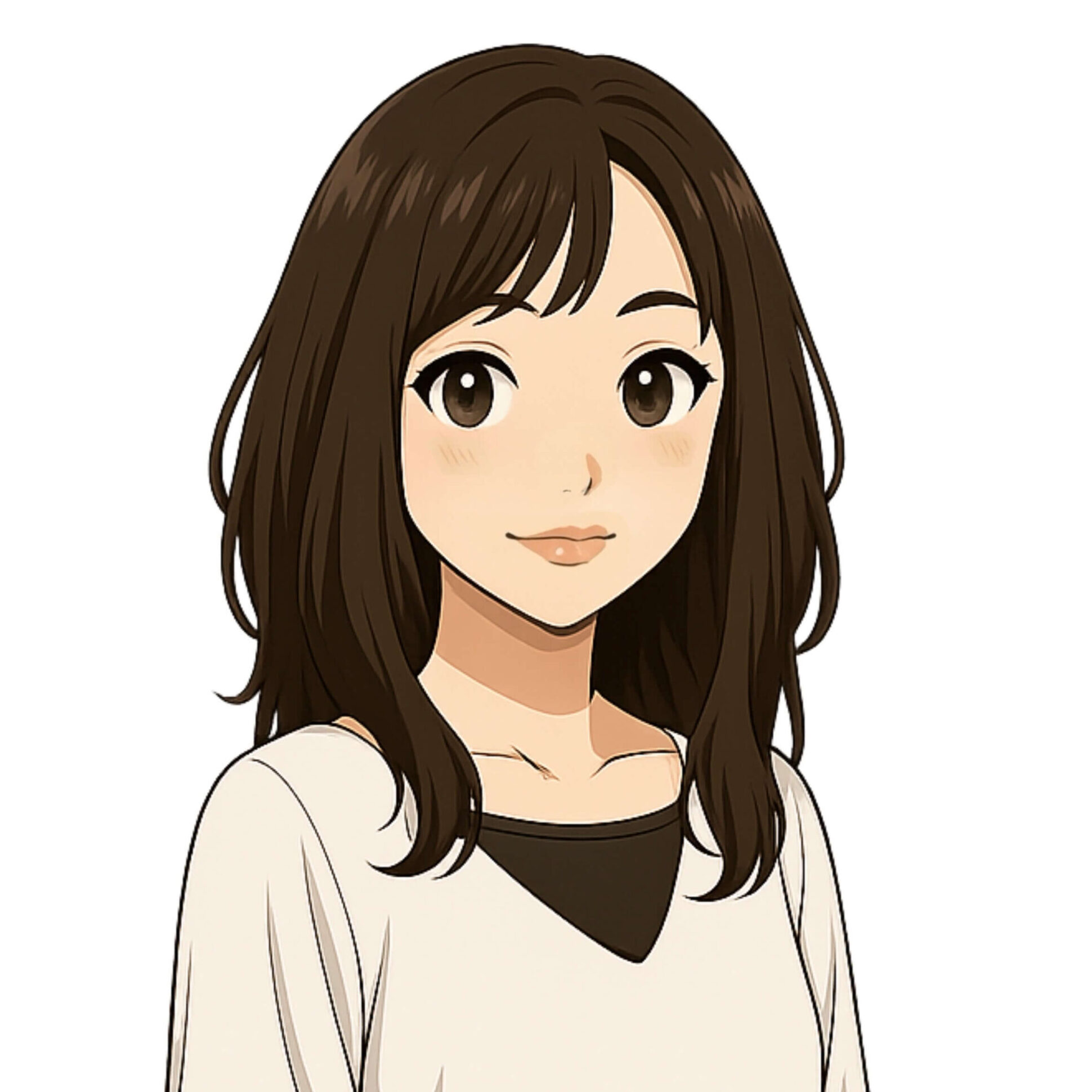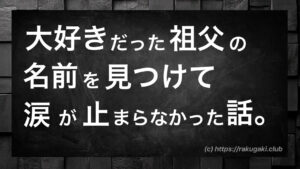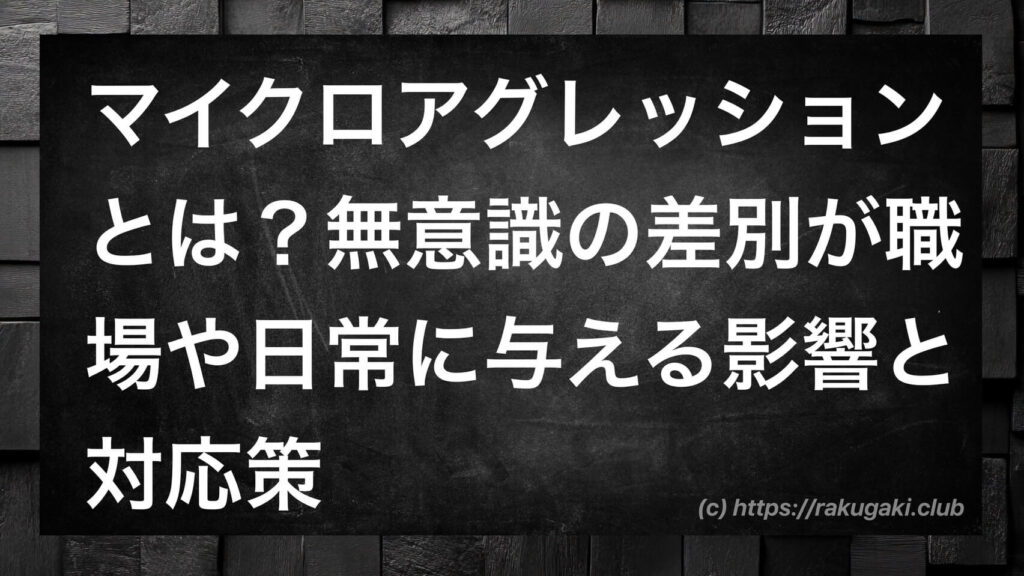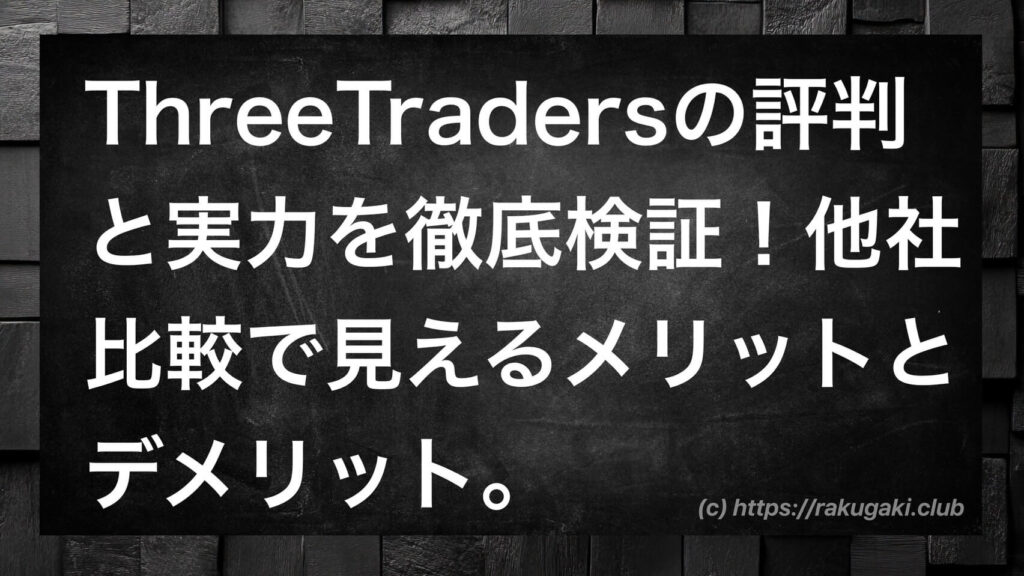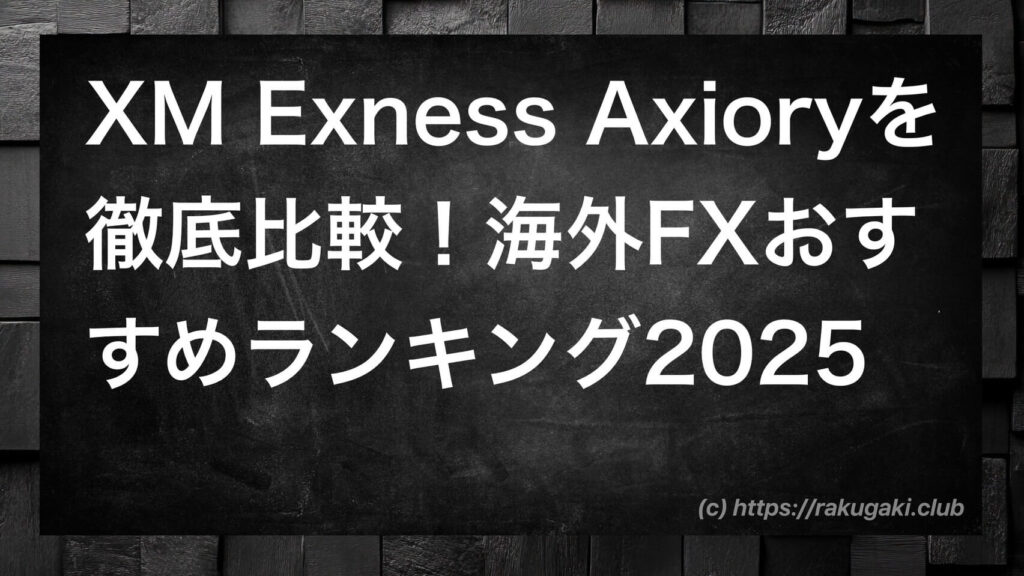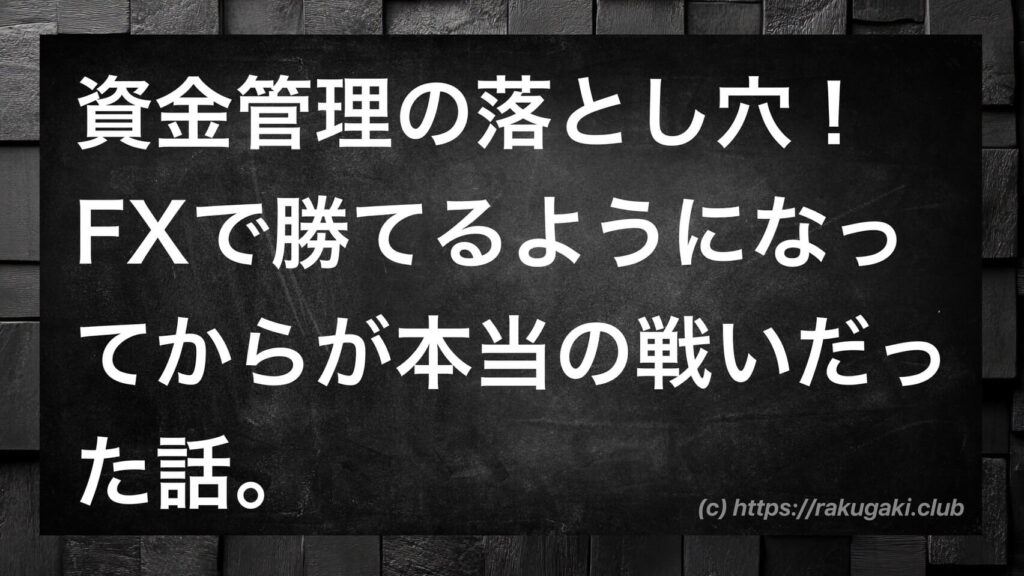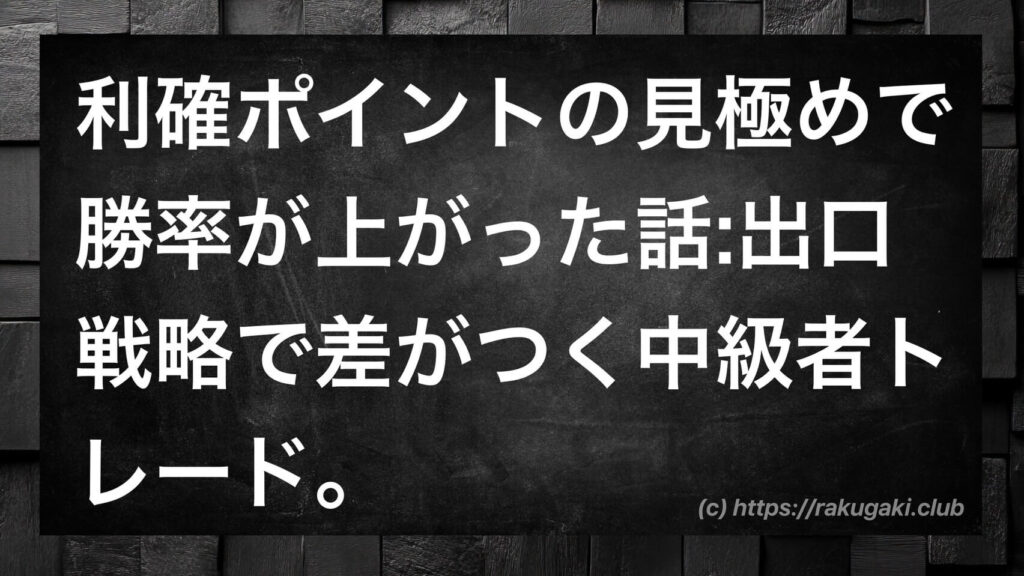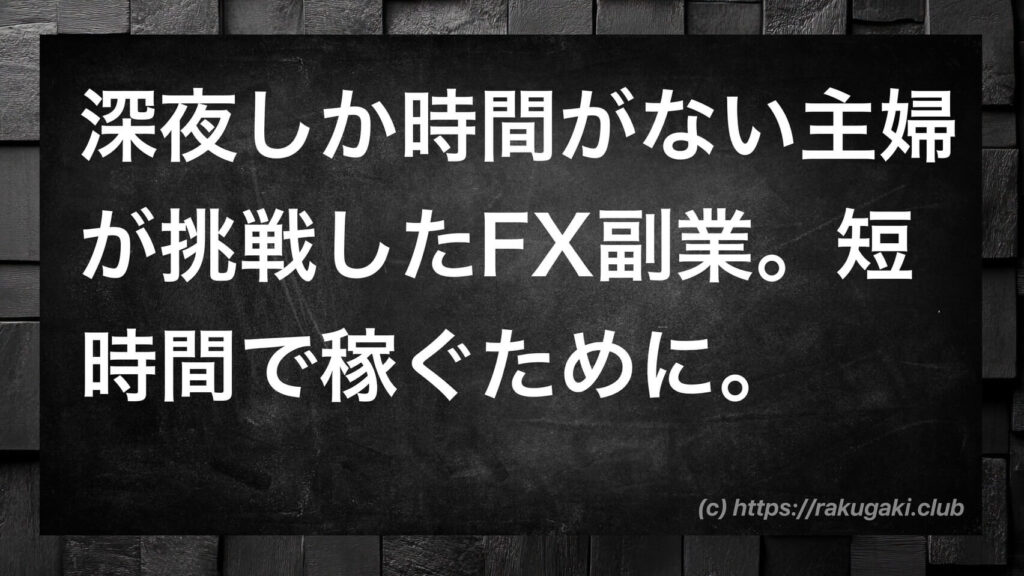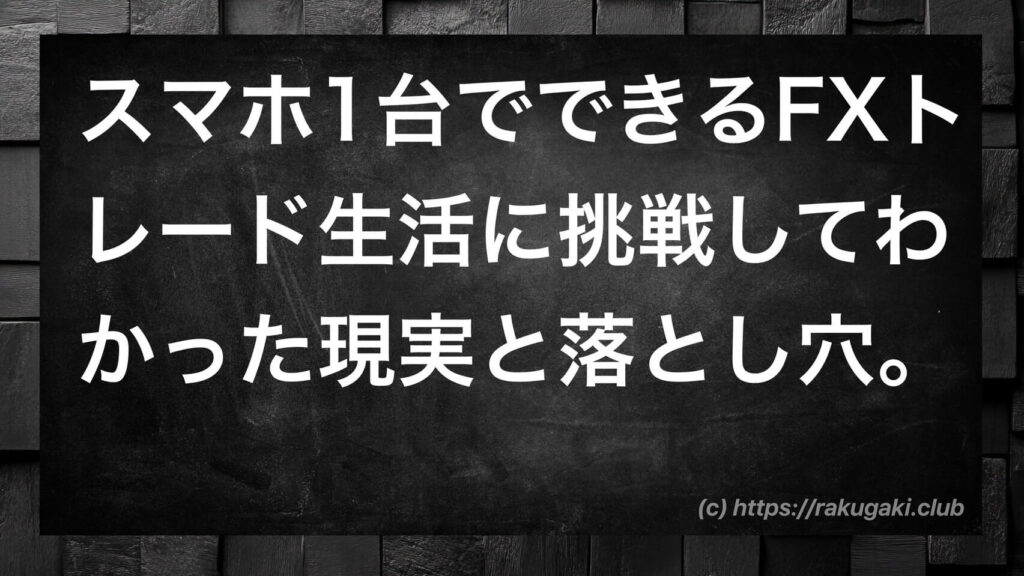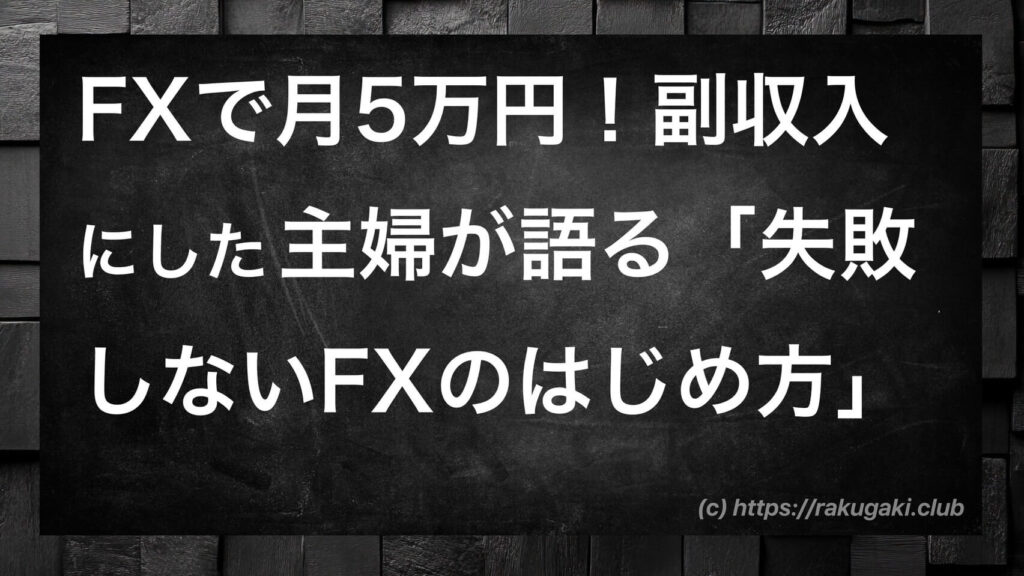赤ちゃんとの外出は“覚悟”が必要だった
子連れで出かけるというだけで、朝から気が重かった
息子が生後8ヶ月を過ぎ、離乳食にも慣れてきた頃。
少しずつ外出の練習を始めようと、私は何度目かの「子連れおでかけ計画」に挑戦していた。
この日は、産後はじめて友人と再会する予定だった。場所は都内のカフェ。時間は午前10時。
朝の混雑を避けて出発するつもりが、準備の途中で息子が盛大にうんちをしてくれて、あっという間に予定は狂ってしまった。
「なんでこのタイミングで…!」と嘆いても仕方ない。
おむつを替え、着替えさせ、ミルクを用意し、持ち物チェックをして…気づけばもう家を出る予定の時刻はとっくに過ぎていた。
電車に乗るだけで神経をすり減らす日々
ベビーカーは混雑時には迷惑になると思い、抱っこ紐で出発した。
玄関で「行ってきます」と深呼吸し、決意を固める。
ただ電車に乗って移動するだけなのに、それが大仕事に感じる。
エレベーターの位置、乗り換えの時間、ベンチの有無、トイレの場所。
すべての行動が「赤ちゃんが泣いたときにどう対応するか」で左右される。
静かな車内、険しい視線、遠慮がちな移動。私はいつも「小さくなる訓練」をしていた。
この日も駅に着いた瞬間、人の波に飲み込まれそうになった。
通勤ラッシュのピークは過ぎていたが、ホームにはビジネスバッグを持った人たちがぎっしり。
私は何度も何度も「すみません」と心の中で唱えながら、電車に乗り込んだ。
一駅ごとに増える乗客、そしてプレッシャー
電車の中は混雑していたが、なんとかドア付近のスペースに滑り込めた。
息子は最初、きょとんとした表情で周囲を見渡していたが、ほどなくして不安げな顔に変わった。
きゅうっと私の服を握り、小さく「えーん」と泣き出す。
このくらいの泣き声なら大丈夫、大丈夫…と自分に言い聞かせる。
だが車内はどんどん混み合ってくる。一駅、また一駅と人が増え、私たちは押しつぶされそうになっていた。
肩が当たる、カバンが揺れる。息子もその空気を感じたのか、泣き声が徐々に大きくなっていく。
周囲の目線が気になる。
見ていないふりをしている人もいるが、明らかに舌打ちをした男性もいた。
「うるさい」とはっきり聞こえる声ではないけれど、「そう思ってるんだろうな」という空気はひしひしと伝わってくる。
抱っこ紐の中で暴れる息子、滲む汗と後悔
電車が揺れるたびに、息子は泣きながら体をよじらせる。
抱っこ紐の中で暴れる赤ちゃんを押さえながら、私は必死であやした。
小声で歌を歌ったり、頬をつんつんしたり、おしゃぶりを口に含ませてみたり。
けれど、息子はますます泣き止まない。
私の額には汗がにじみ、頭の中はぐるぐるしていた。
「こんなに泣かせてまで出かけなければよかった」
「やっぱり赤ちゃん連れで電車なんて無理だった」
「迷惑になってる、申し訳ない…」
降りようかと思った。だけど、次の駅はホームが狭い駅。ベビーカーがない今、すぐに降りてベンチに逃げることもできない。
一瞬でも静かになれば…そう願ったけれど、息子の泣き声は止まらなかった。
限界に近づく中、誰も助けてくれない現実
周囲の大人たちは、ほぼ全員がスマホに視線を落としていた。
私の存在など最初からいなかったかのように、誰も目を合わせない。
誰かが声をかけてくれることもない。
譲ってくれる人もいない。
「がんばってね」と励ましてくれる人もいない。
私は、自分がすごく迷惑な存在に思えた。
誰かが助けてくれたら、どれだけ気が楽になるだろう…そんなことを考えている自分も、弱くて情けなかった。
けれど、私はまだこのとき、ある“出会い”が待っていることを知らなかった。
それが、この日を忘れられない日に変えるとは思ってもいなかった。
誰かが声をかけてくれることなんて、期待していなかった
見て見ぬふりをされる痛み
次の停車駅で少しだけ乗客が降りた。
けれど、すぐにまた人が乗ってきて、状況は変わらなかった。
息子は相変わらず泣き続け、私は抱っこ紐の中でじっと彼を支えながら、目を閉じた。
視線が痛かった。
直接何か言われたわけではないけれど、誰もこちらを見ようとしないその“無関心”が、逆に刺さった。
誰も目を合わせてくれない。誰も助けてくれない。
それが一番辛かった。
電車の揺れで赤ちゃんがバウンドするたびに、私はバランスを崩しそうになった。
息子の体温がどんどん上がっているのが分かった。泣き疲れと暑さ、そして周囲の視線に、私も限界が近づいていた。
「あの、すみません」その一言が、こわかった
そのとき、斜め前に立っていたスーツ姿の男性が、小さくこちらに手を伸ばしてきた。
「……あの、すみません」
え?と一瞬、体が硬直した。
まさか、注意されるのか?
「うるさい」とか、「電車降りてください」とか言われるのか?
覚悟を決めて顔を上げた。
すると、男性は目線を合わせるでもなく、小声でこう言った。
「席、代わりましょうか」
なんと返していいか分からなかった。
私は最初、何を言われているのか理解できなかった。
男性の後方にあったのは、優先席のひとつ。そこには男性の荷物が置かれていた。
おそらく、誰もいなかったタイミングで自分の席として確保していたのだろう。
私は、思わず「ありがとうございます」と頭を下げた。
座れることよりも、その“声をかけてもらえたこと”が何よりも嬉しかった。
まるで水を与えられた砂漠の民のように、私の心がじんわりと満たされていった。
息子も静かになった「安心」の空気
席に座り、抱っこの体勢を整え直すと、息子は急に泣き止んだ。
さっきまで暴れていたのが嘘のように、私の胸に顔をうずめて、ぐずりながらも静かになっていく。
「え、いま静かになるの?」と苦笑しながらも、私はその静寂にほっとした。
そして、私自身がようやく呼吸できるようになった。
車内の空気も、なんとなく柔らかくなった気がした。
向かいに座っていた女性が、小さく頷いて微笑んでくれた。
誰かのその“ちょっとした表情”や“仕草”が、どれだけ支えになるか。
「大丈夫だよ」と言ってもらえた気がした。
ほんの一瞬のやさしさが、こんなにも力になるんだと思った。
「助けてもらったことを、ちゃんと覚えておこう」
私はずっと、「迷惑をかけてはいけない」と思い込んでいた。
赤ちゃんが泣くことすら「申し訳ないこと」として、自分を責めていた。
でも、あの男性のように、誰かが声をかけてくれる世界もちゃんとあるんだと知った。
そして、あの一言がどれだけ救いになるのかを、私はこの身で体験した。
だからこそ、「自分も、そんな一言をかけられる人になりたい」と思った。
誰かが困っていたら、見て見ぬふりをするんじゃなくて、そっと「大丈夫ですか」と声をかけられる人に。
きっと、声をかけるほうも勇気がいる。
だけど、かけられた側は、その一言で人生が変わるほどのインパクトを受ける。
それは、あの日の私が証明している。
「自分がされてうれしかったこと」を、今度は私がやる番だ
同じように困っていたママに出会った日
あの日から数週間後。
私は再び電車で外出する用事があり、同じように抱っこ紐で息子と移動していた。
少しずつ外出にも慣れてきてはいたが、やはり電車に乗るのは緊張する。
そんなとき、乗り換えのホームで、見覚えのある光景を目にした。
赤ちゃんを抱えた若い女性が、改札を出る手前で泣き止まない子を必死であやしていた。
彼女の顔には、あの日の私と同じような疲れと焦りがにじんでいた。
通り過ぎる人々は、特に気に留める様子もなく彼女の横を通り過ぎていく。
私は思わず足を止め、ゆっくりと声をかけた。
「よかったら…改札まで荷物だけでも持ちますよ」
女性は驚いた顔をした後、ふっと表情を緩めて「すみません、ありがとうございます」と頭を下げてくれた。
赤ちゃんを抱っこしながら、重そうなトートバッグとベビーカーを手に持っていた彼女の荷物を少しだけ持って、一緒に改札を抜けた。
その短い時間の中で、私たちは自然と会話を交わした。
「何ヶ月ですか?」
「うちもその頃、毎日泣きっぱなしで大変でした」
「わかります、ほんとに…」
それだけで、彼女の顔色が少し明るくなった。
その姿を見て、私は確信した。
「声をかけるだけで、こんなにも救われるんだ」と。
“見て見ぬふり”が当たり前になる社会で
電車や駅で、困っている人を見かけることはよくある。
でも、「何かあったのかな」と思いつつも、つい見て見ぬふりをしてしまうのが日常になっている。
理由はさまざまだ。
・声をかけてトラブルになりたくない
・逆に迷惑がられたらどうしよう
・自分も余裕がない
その気持ちも痛いほど分かる。私もそうだった。
けれど、「何もしないこと」が“正解”のようにされてしまうのは、やっぱり少し違うと思うようになった。
誰かが困っていたとき、ほんの一言で空気が変わる。
「席、代わりましょうか」
「荷物、持ちましょうか」
「大丈夫ですか?」
その一言を投げかけられるかどうかが、社会の空気を作っていくんだと実感した。
「やさしさは連鎖する」ことを身をもって知った
声をかけてくれたスーツ姿の男性は、あの日私に席を譲ってくれたあと、特に何も語らずに電車を降りていった。
名前も知らない、顔も忘れてしまいそうなほど短い接点だった。
でも、その人がくれたやさしさは、確実に私の中に残り、行動のきっかけになった。
人からもらったやさしさは、次の誰かに渡していける。
「助けてもらった」という体験が、「自分も助けたい」という気持ちに変わる。
そしてそれが、また別の誰かを救う。
これはきれいごとではなく、私自身の中に起きた“変化”だった。
赤ちゃん連れの外出は、今でも簡単なものではない。
でも、「一人じゃない」と思えるだけで、少しだけ肩の力が抜けるようになった。
SNSでは流れてこない“リアルなやさしさ”の存在
最近は、SNSで「子連れに冷たくされた」「こんなに酷いことを言われた」といった投稿がよく目に入る。
もちろん、そういう現実もあると思う。私自身、心ない態度に傷ついた経験もある。
けれど、そればかりが“世の中のすべて”ではない。
静かにやさしく寄り添ってくれる人たちも、実はたくさんいる。
その存在は目立たないけれど、確かにそこにいる。
「見てる人はちゃんと見てる」
「黙っていても、感じてくれてる人がいる」
そんなふうに思えるだけで、世界が少しやさしく見えてくる。
だから、私はこの話をこうして書いておきたいと思った。
SNSでは拡散されない“いい話”も、ちゃんと伝えていきたいから。
誰かの“たった一言”が、社会全体の空気を変える力を持っている
「気づいてもらえること」だけでも、支えになる
育児中の外出は、特に赤ちゃんを連れていると、体力的にも精神的にもとても負担が大きいものです。
泣き止まない赤ちゃんをあやしながら満員電車に乗る——この状況がどれほど過酷かは、経験してみないとなかなか想像できないかもしれません。
でもそんななかで、たった一言の「席、代わりましょうか」が、どれだけ大きな支えになるか。
この体験を通じて私は、やさしさには“手段”よりも“気づき”と“意志”が重要なのだと気づかされました。
私たちは、すべてを解決するスーパーマンにはなれません。
でも、「見ているよ」「気づいてるよ」と伝えるだけで、誰かの心を軽くすることはできるのです。
「何もしない」はリスク回避ではなく、“機会の放棄”かもしれない
困っている人を見かけたとき、「何もしない」という選択肢を選ぶ人が多いのは、ある意味では仕方のないことです。
自分が声をかけることでトラブルになったり、迷惑がられるリスクを考えるのは、当然の感覚です。
しかし、私が強く感じたのは、「声をかけなかったこと」に対する後悔は、じわじわと残るということです。
逆に、声をかけて相手に感謝されたときのあの感覚は、忘れられないほど温かいものになります。
これは決して“勇気を持とう”という話ではありません。
選択肢の一つとして、「ほんの少し手を差し伸べる」という行動があることを知っておくだけでもいい。
そしてその行動が、社会全体の空気をやわらかくしていく土壌になっていくのだと思います。
小さなやさしさが“社会的インフラ”になる日常へ
公共交通機関や街中で、困っている人が困ったままでいるのが“当たり前”な空気は、少しずつ変えていくべきです。
それは法制度やインフラの整備だけでなく、私たち一人ひとりの“態度”によっても十分変化していけます。
今回のような一言のやさしさ——
それが、困っている人にとっては“命綱”のようなものになる場面もあるのです。
もちろん、すべての人が即座に行動できるわけではありません。
でも、「あの日、誰かが自分にしてくれたこと」を覚えておくだけでいい。
その記憶が、次のやさしさを生む源泉になります。
やさしさは、制度ではなく“文化”です。
文化は、一人ひとりの行動で育まれます。
そしてその文化が、誰かの生活を守り、未来の自分自身を助ける可能性さえあるのです。