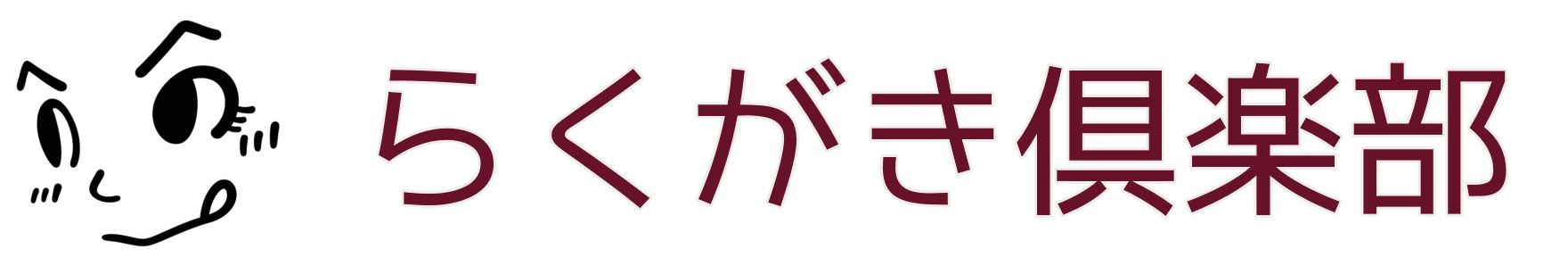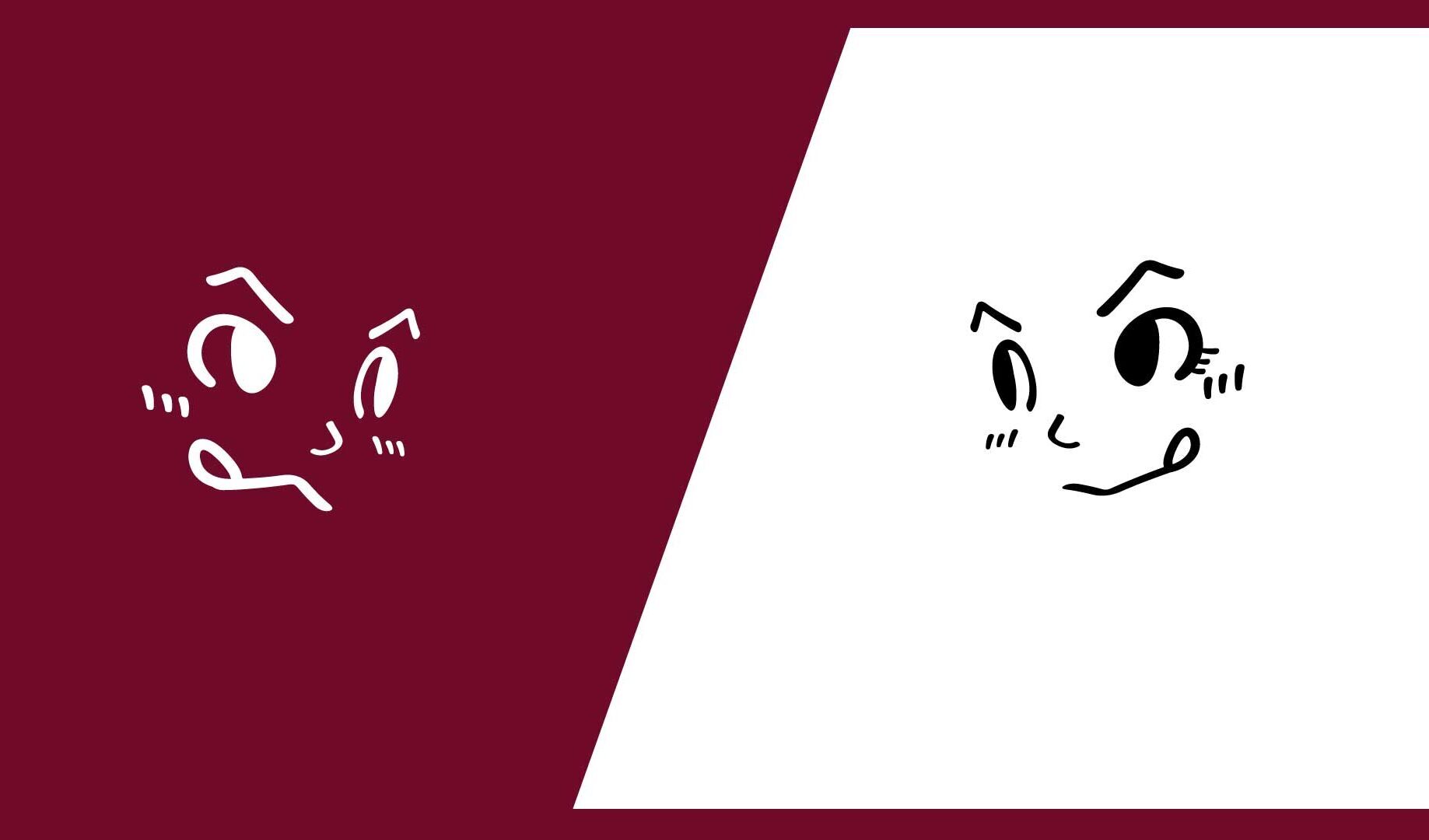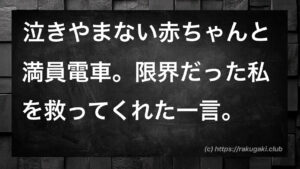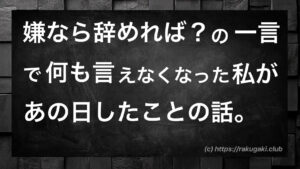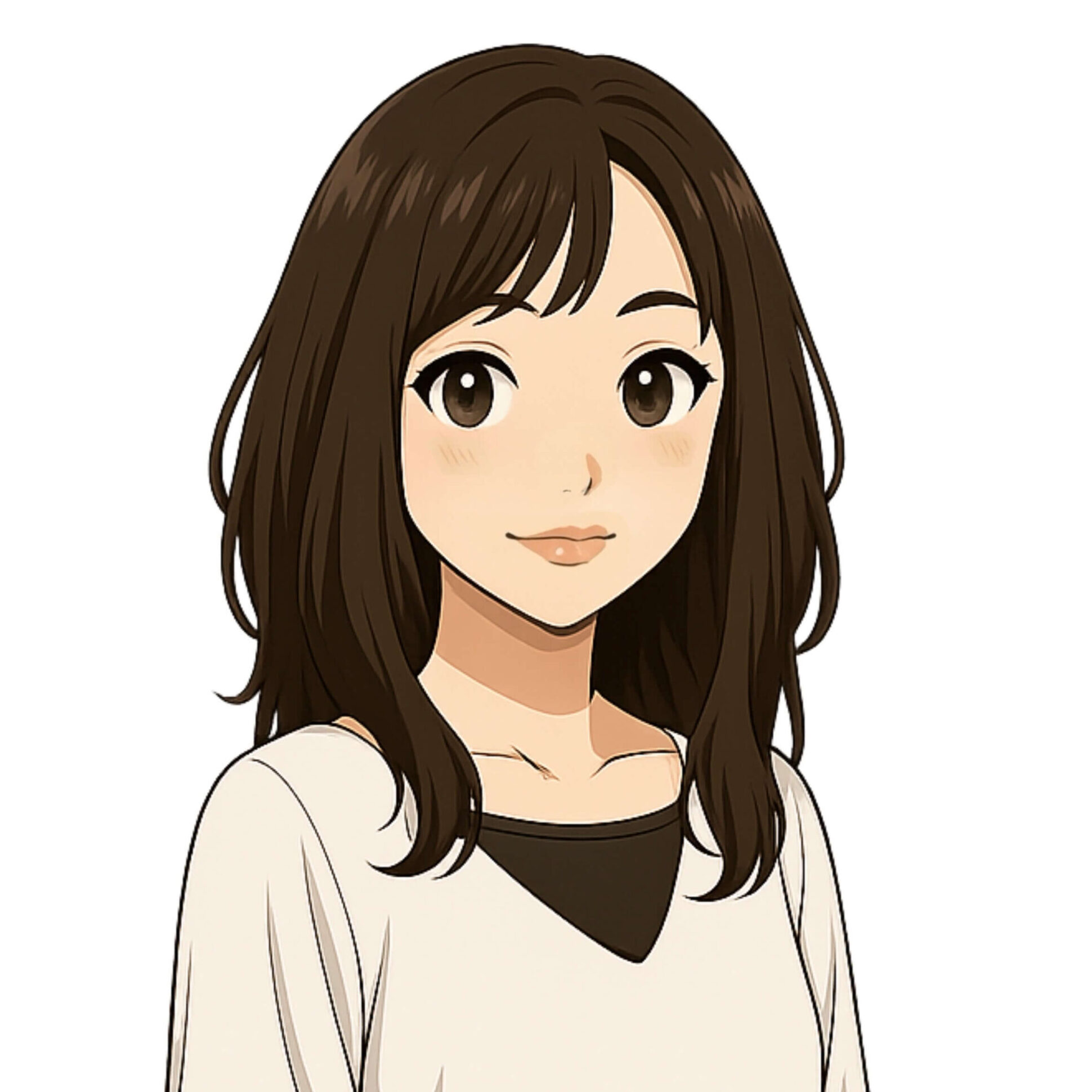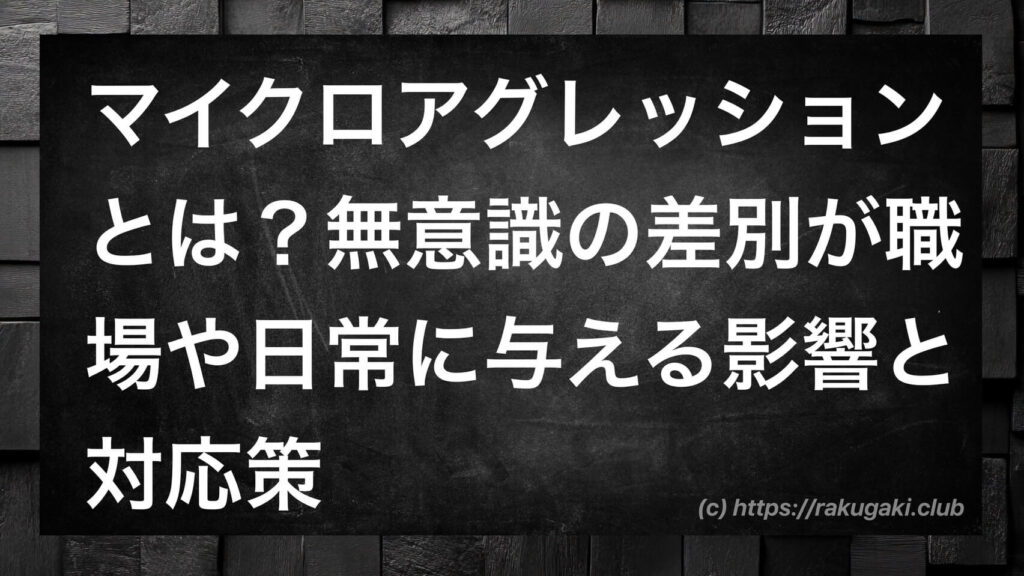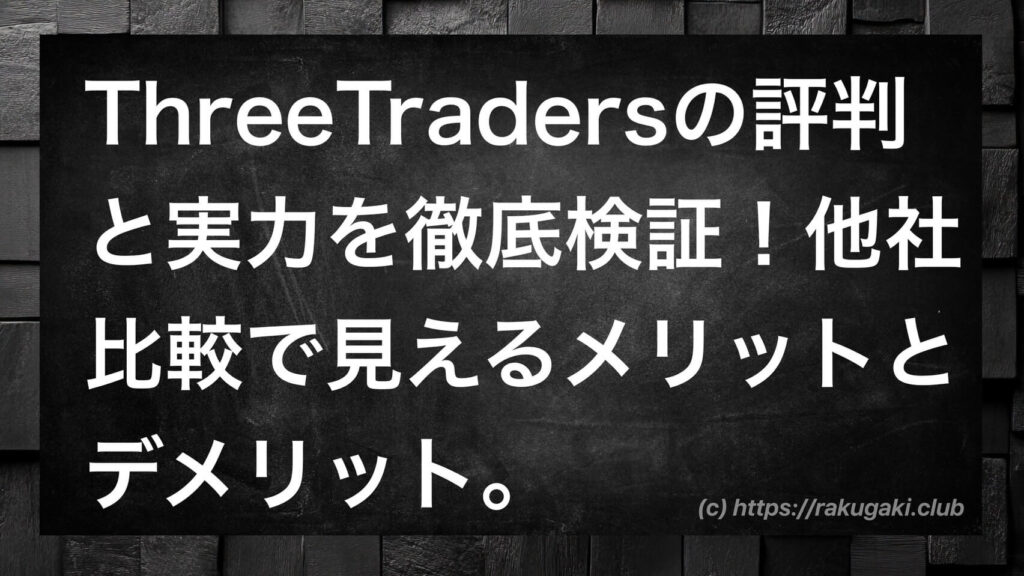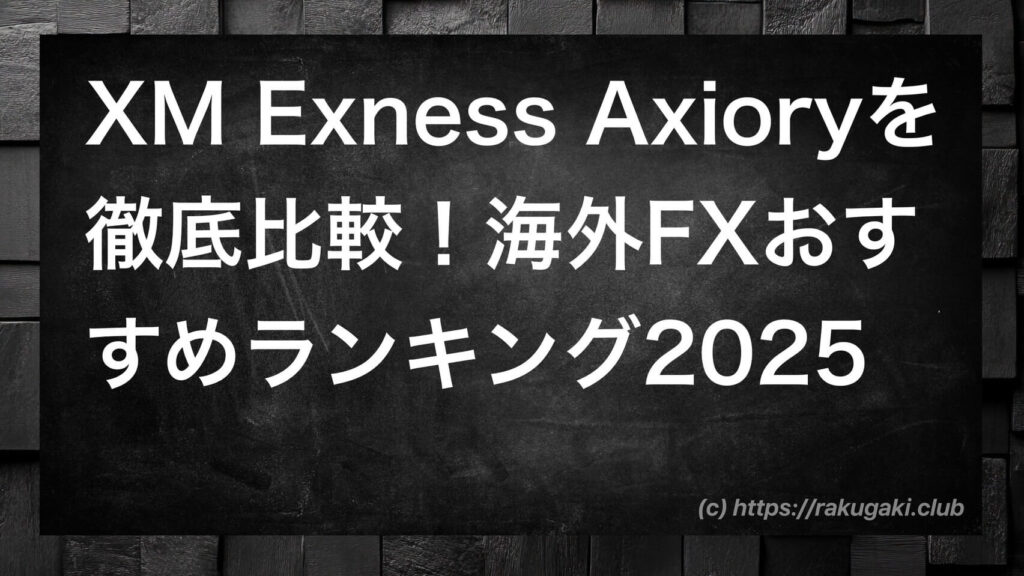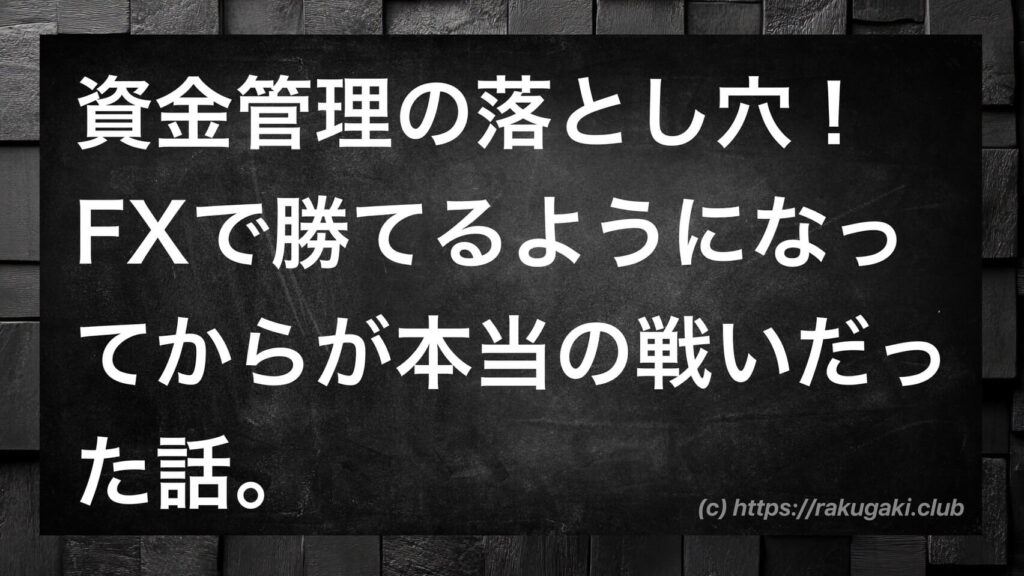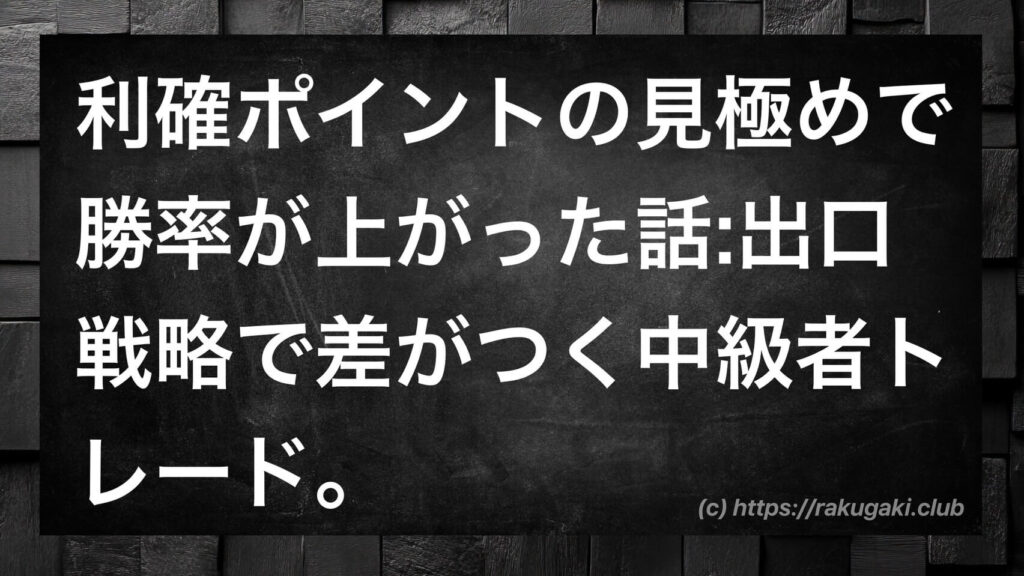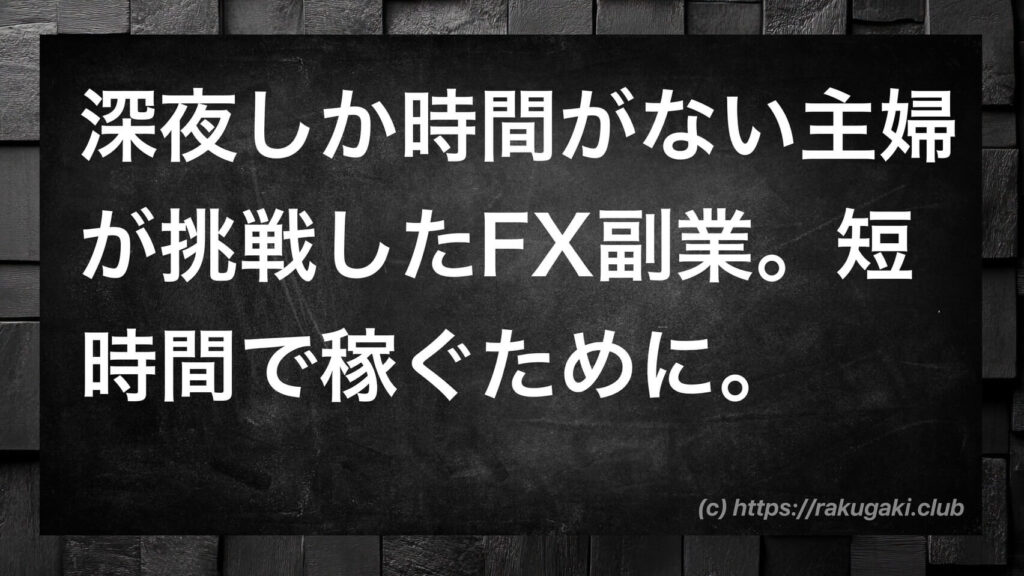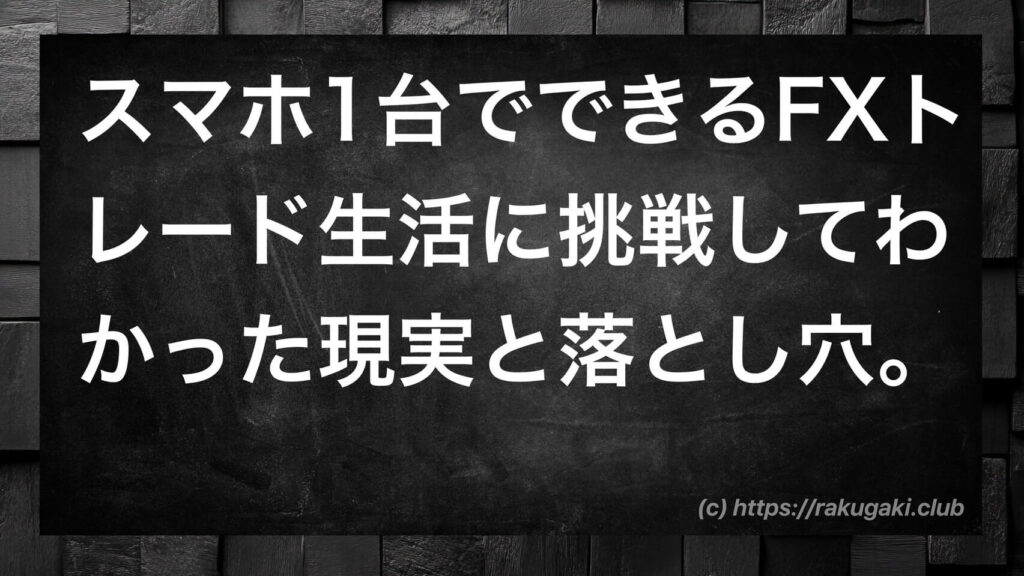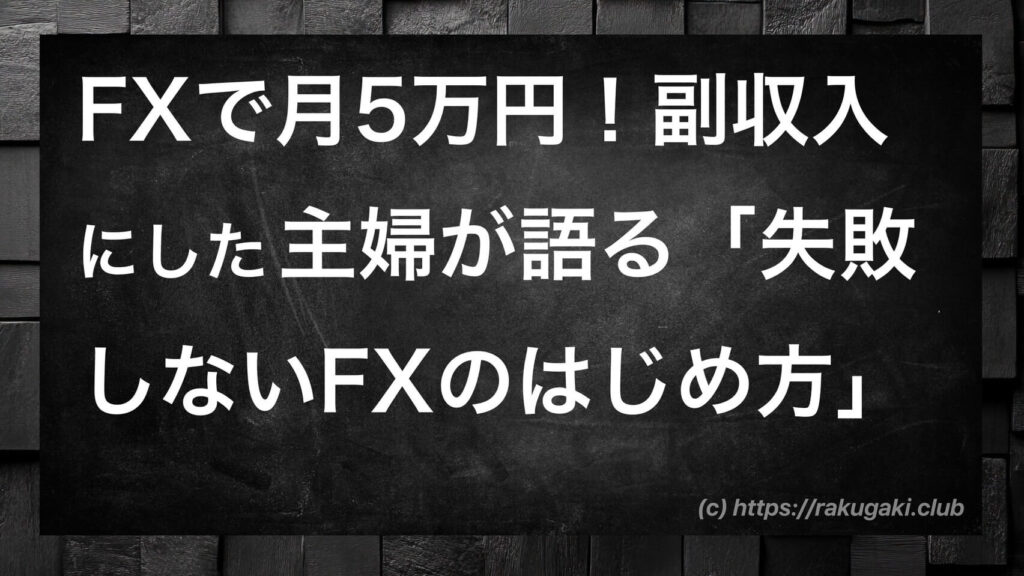無愛想な隣人と2年話さなかったけど、災害の日につながった言葉の力
ご近所との関係を築かないまま、日常に埋もれていた日々
「ただいまー」 エントランスの自動ドアが閉まる音と同時に、誰にも届かないただの独り言がマンションのエレベーターホールに響いた。会社から帰宅して、エレベーターで6階へ。降りた先の廊下は静かで、誰にも会わないことのほうが多い。
このマンションに引っ越してきてから、もうすぐ2年。築浅で、オートロック付き。駅から徒歩5分で、宅配ボックス完備。間取りも申し分なく、インテリアも整えた。でも、たったひとつだけ、いまだに「馴染めていない」と感じていたのが、近隣住民との関係だった。
といっても、トラブルがあるわけではない。騒音もないし、ゴミ出しのマナーも良い。管理人さんも親切。けれど、「人の気配がない」という感覚が、どこかしら心細さを生んでいた。
特に、隣室。うちの部屋と壁を挟んでいる「Tさん宅」は、郵便受けの名札で辛うじて名字が分かる程度で、姿を見たことは一度もなかった。引越しの挨拶に伺ったときも不在で、それっきり。
「顔を合わせても挨拶しない」なんていうことはないけど、そもそも顔を合わせる機会がない。そうこうしているうちに、こちらから声をかけるタイミングも失われていった。
最近では、廊下の奥からドアの開閉音が聞こえたら、無意識に足を止めるようになっていた。鉢合わせにならないように。気まずくならないように。——それが一番、気まずいことだと分かってはいるのに。
他人を避けるように生きる癖
振り返ってみると、子どもの頃から、人付き合いに得意意識はなかった。仲の良い友達はいるけれど、グループの中心にはいないタイプ。大学生になって一人暮らしを始めてからも、近所付き合いの記憶はほとんどない。
社会人になってからは、職場と自宅を往復するだけの毎日。職場では最低限のコミュニケーションが求められるけれど、帰宅すれば自分だけの世界に戻れる。それが心地よくもあり、逃げにもなっていた。
「わざわざ近所の人と仲良くなる必要なんて、ないよね」 そう思っていた。誰かとトラブルを起こさなければいい。迷惑をかけなければ、干渉されなければ、それで十分だと。
それが、間違いだと思い知らされたのは、忘れもしない“あの日”だった。
それはある日、突然やってきた
その日は平日だったけれど、私はたまたま在宅勤務の日だった。前日夜から続く雨のせいか、空気がどんよりと重たかった。朝8時20分。カーテンの隙間から差し込む光が、一瞬フッと消えた。
——直後。
地面の底から突き上げるような衝撃がきた。 「地震……?」 そう思う間もなく、部屋が激しく揺れ始めた。ガタガタという家具の震える音。棚から落ちる小物。床に転がるペン立て。テレビが軋み、窓ガラスがミシミシと鳴る。
いつもなら、1分もすれば収まる揺れが、今回は長かった。しかも、途中で一度、さらに強く突き上げられるような“第二波”がきた。
揺れが収まったあと、部屋を見渡すと、テーブルの上は散乱。キッチンの棚が開いて、調味料が床に落ちていた。スマホを掴んでニュースを確認すると、震源は都内直下型。震度5強。数年ぶりの大規模地震だった。
すぐに確認したのは電気と水道。部屋の電気は点かず、Wi-Fiもダウン。水も出ない。オートロックの共用扉が機能せず、非常用扉が開放されたという通知だけがスマホに届いた。
初めて実感する、“自宅の孤立”
「一人って、こういうことか」
エレベーターは止まり、階段を使って様子を見に行くにも、外はまだ危険が残る。TVも映らない。窓を開けると、同じ階のどこかで誰かがドアを開け閉めしている音だけが聞こえる。
私は、完全に情報を絶たれたまま、自宅で“閉じ込められた”。
非常用の水はあるが、量は少ない。食料も数日分はあるが、冷蔵庫が止まっている。何より不安なのは、「もしこれ以上悪化したら」という状況を、誰とも共有できないことだった。
——そのとき。
コン、と軽くドアをノックする音がした。 私は身構えた。こんなときに誰? 配達? まさか避難誘導? ドアを少しだけ開けると、そこには意外な人物が立っていた。
そう、2年間一度も話したことのない、隣のTさんだった。
ご近所との距離が、想像以上に不安を増幅させた
一人暮らしが「自由」から「孤独」に変わった日
あの日、地震が起きた瞬間、最初に頭に浮かんだのは「家具の転倒防止してたっけ?」でも「避難所の場所はどこだっけ?」でもなかった。
真っ先に湧いてきたのは、「この部屋で、誰にも気づかれずに倒れていたらどうしよう」という、孤立への恐怖だった。
私は都内の比較的新しいマンションで一人暮らしをしている。2年前に引っ越してきた当初は、オートロックと宅配ボックス付き、周囲の音も聞こえない静かな環境が気に入っていた。だれにも干渉されない、理想の生活空間。
でもその“快適さ”が、災害というイレギュラーな出来事に直面したとき、逆に自分を苦しめることになるとは思ってもいなかった。
エレベーターは止まり、水道もガスも使えない。電気も通らない状態で、部屋の中に閉じ込められたような感覚。スマートフォンの充電は40%を切り、外との連絡も心もとない。
自分が今どんな状況にあるのか、マンションの他の住人たちは無事なのか、誰一人わからない。
廊下に出ても人の気配はなく、各戸のドアは固く閉じられていた。管理人もいない。エントランスはオートロックのまま。何か起きても助けを求める先が見えない。
避けていた「声かけ」を、初めてしてみようと思った
ここで初めて、私は「誰かに声をかけてみようか」と思った。
もし、この建物の誰かと顔見知りになっていれば。挨拶を交わす関係だけでもあれば。
今この瞬間に、「大丈夫?」と声をかけ合える安心感があったのではないかと、自分のこれまでの在り方を反省するような気持ちになった。
でもそれと同時に、「いまさら声をかけるなんて、変に思われるだろうか」「突然チャイムを鳴らして、不審がられたらどうしよう」そんな気持ちが、足をすくませた。
人に頼ることも、関係を築くことも、日頃からの積み重ねだ。
非常時だけ助けを求めようとするのは、あまりにも都合が良すぎる——。
そんな自責の念がこみあげてきて、結局、誰にも声をかけられなかった。
私は、誰もいないような静かな部屋で、ひとり水の備蓄量を確認し、残った食材で何食分しのげるかを計算した。
情報が不足した状態では、判断も行動も鈍る。防災リュックの中身も見直してみたが、懐中電灯の電池が切れていた。
「このまま夜になったらどうしよう」
そんな不安が、少しずつ現実味を帯びてきた。
本当に必要だったのは「備え」より「つながり」だった
食料も、電池も、水も大事。でも、いちばん必要だったのは、誰かとつながっているという“安心感”だった。
被災時に誰かがそばにいて、「大丈夫?」と声をかけてくれる。それだけで、気持ちの余裕が全然違うということを、私は痛感した。
結局その日の午後、停電と断水は続いたまま。私の部屋のドアは閉じたまま、周囲の住人の姿も見えなかった。
でも、心のなかでは「次に誰かと会ったとき、ちゃんと挨拶しよう」と思っていた。
この体験を無駄にせず、今後の自分の生活を少しでも変えていこうと、そんな決意のようなものが芽生え始めていた。
そして、そんな思いが芽生えた翌日——隣の部屋から、初めての「声」が聞こえてくるのだった。
無愛想だった隣人との、最初で最後じゃなかった言葉
はじめての「こんにちは」は、想像よりもあたたかかった
次の日の朝、廊下に出てみると、隣の部屋のドアが少しだけ開いていた。
中から誰かの気配がして、なんとなくこっちをうかがっているような空気が伝わってくる。だけど私からは何も言えなかった。
前の日、自分は結局、誰にも声をかけられなかったくせに、今になって急に話しかけようとする自分がどこかずるい気もしていた。
でも、勇気はほんの一言でいい。「おはようございます」って、声を出せばよかったのだ。
「おはようございます」と私が言うと、数秒の間のあと、向こうからも小さく「……おはようございます」と返ってきた。
それは、たった五音のやりとりだったけれど、心の中に灯がともるような感覚だった。
このマンションに2年も住んでいて、初めて隣人と交わした挨拶。もっと早く、こういうやりとりができていたら、昨日の夜のあの不安も、もう少し違っていたかもしれない。
思えば、隣人の男性は、無愛想というより「接点がなかった」だけだったのかもしれない。こちらが「話しかけない人」だと判断されていたから、向こうもあえて関わってこなかっただけで。
最初の印象やすれ違いの雰囲気だけで、人を「無愛想」と決めつけていた自分が、少し恥ずかしくなった。
その日は結局、停電と断水が続いたままだった。
しかし、朝にかわした挨拶がきっかけになり、私は少しだけ、廊下で顔を合わせる人に話しかけられるようになった。
「昨日、うちの水は出ませんでしたけど、そちらはどうでした?」とか、「懐中電灯、貸しましょうか?」とか、ほんの短いやりとり。
でもその短いやりとりの積み重ねが、昨日の自分には想像もできなかった安心感を生んでいた。
「助けてもらった」ではなく「助け合えた」と思えた日
災害2日目の夕方、マンションの1階にある掲示板に、手書きのメモが貼られていた。
「水が少し出る部屋があります。困ってる方は○○号室までどうぞ」と書いてあった。○○号室の部屋番号は、なんとあの無愛想な隣人のものだった。
まさかと思いつつ、恐る恐る訪ねてみると、あの男性が玄関先に出てきて、「バケツ、持ってきてくれれば入れてあげますよ」と普通に言ってくれた。
その姿は、思っていたよりもずっと柔らかく、なんなら優しさすら感じる顔だった。
私は持っていた小さな給水バッグに水を入れてもらい、「本当にありがとうございます」と頭を下げた。
すると彼は「昨日、あなたが挨拶してくれたからです」と、ぽつりと一言。
たったそれだけだったけど、胸がじんわりと熱くなった。
「助けてもらった」というより、「助け合えた」と思える感覚。
その感覚は、他の住人とも連鎖しはじめていて、非常階段に段ボールを並べてちょっとした情報共有スペースのようなものが自然とできあがっていた。
「水が出た」「コンビニ営業してた」「トイレ貸してくれる施設があった」などの書き込みが並び、まるで小さな掲示板のようだった。
災害がつないだ「ご近所」という存在のありがたさ
災害は、日常を強制的に壊してしまうけれど、それによって壊れたのは“孤立の壁”だったのかもしれない。
これまで、誰とも関わらずに生活することが「楽」だと思っていたけれど、それは「楽」ではなく「不安定」だったと気づかされた。
ご近所づきあいは、別に毎日会話する関係でなくていい。
ただ、「もしものときに、お互いを気にかけ合える存在」であるだけで、これほどまでに安心感があるとは思わなかった。
私自身、防災グッズをそろえることばかりに気を取られていたけれど、本当に必要なのは、“つながり”という見えない備えだった。
2日後、ライフラインが徐々に復旧し、日常が戻ってくると、住人たちはまた静かにそれぞれの生活へ戻っていった。
だけど、挨拶を交わすようになった人たちとは、その後もたびたび廊下で言葉を交わすようになった。
あの「無愛想な隣人」とも、今ではすれ違えば「お疲れさまです」と互いに声をかけるようになっている。
笑い合うほど仲良くなるわけじゃない。でも、それでいい。
きっかけをくれたのは、あの日の挨拶。そして、そのあとの「ありがとう」という言葉だった。
ご近所づきあいが“防災の盲点”だったと気づいた話
“物”だけ備えても、本当の安心にはならなかった
私は災害対策として、飲料水、乾電池、モバイルバッテリー、カセットコンロ、保存食など、かなりの量の「防災グッズ」を準備していたつもりでした。
でも、いざ被災すると、それらが揃っていることよりも、「ひと声かけられる相手がいること」のほうが、心の安定に大きく影響しました。
例えば、停電で不安だったとき、隣人が声をかけてくれただけで、怖さが半減しました。
断水で水を求めて廊下に出たとき、情報をくれた住人がいたから混乱せずに済みました。
つまり、どれだけ物資を備えていても、それだけでは“孤独”という最大の不安には勝てなかったのです。
これまで私は、「災害対策=物理的な備え」と信じていました。
けれど、本当に役立ったのは「人との関係」という、目に見えない備えでした。
そしてその備えは、何か特別なことをしなくても、普段からのちょっとした挨拶や気づかいで育てていけるものだと気づきました。
「誰とも話さない暮らし」が、リスクになることもある
災害時、独り暮らしで情報を得られず困っている人が多くいました。
特に高齢者や、ネットに不慣れな住人は、マンションの非常放送の意味を取り違えていたり、避難所の場所を知らなかったりといった状況がありました。
一方で、近所に“話せる人”がいた住人たちは、自然と情報共有ができていました。
廊下で顔を合わせたついでに「○○で水くめるらしいよ」「このあたりは停電復旧したって」といった会話が生まれていたのです。
これは災害時に限らず、体調を崩したとき、事件があったときなど、日常のちょっとした“困りごと”にも通じます。
「誰にも頼れない環境」に自分を置いてしまうと、いざというとき動けなくなります。
その意味でも、「関係性の断絶」は、意識しないうちに自分の生活に“リスク”を抱えているのだと実感しました。
防災の一歩は、「こんにちは」と声をかけることから始まる
記事をここまで読んでくれた方の中には、「ご近所づきあい、ちょっと苦手…」という方も多いと思います。
私もずっとそうでしたし、今も積極的に誰かと関わっているわけではありません。
ただ、あの災害の日に「おはようございます」と声をかけただけで、世界が変わりました。
たったそれだけのことで、水をもらえたり、情報を教えてもらえたり、自分も他人に声をかけられるようになったのです。
だから、何も大きなことを始める必要はありません。
次に廊下で隣人とすれ違ったとき、軽く会釈してみるだけでもいい。
「こんにちは」と言ってみるだけで、防災対策がひとつ進んだと考えてみてください。
備蓄も大切。モバイルバッテリーも大切。
でも、一番の安心は「誰かに気づいてもらえる環境」を持っていること。
それは、コンビニでもホームセンターでも買えない、日常の中でしか育てられない“安心”です。
災害は、いつ起こるかわかりません。
だからこそ、普段から「挨拶」というシンプルな行動を、備えのひとつにしておくといいと思います。