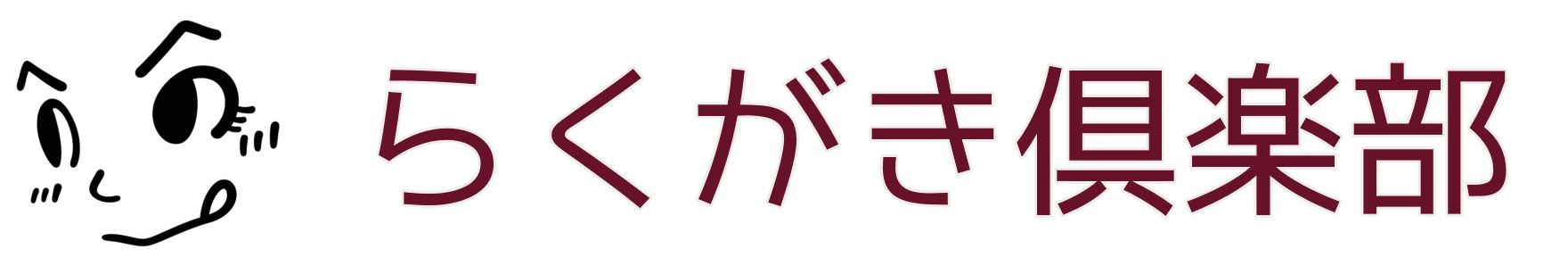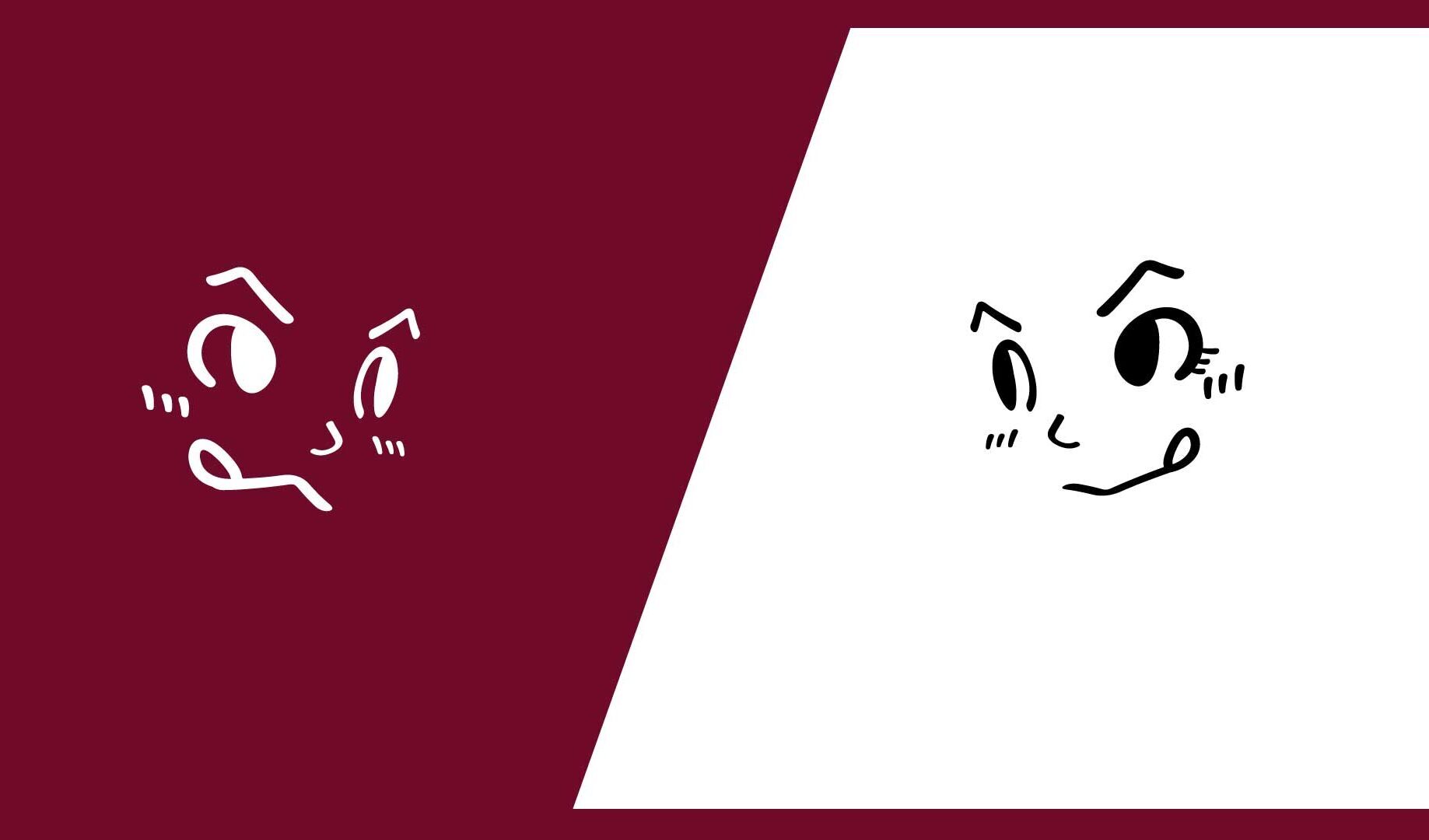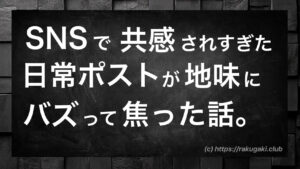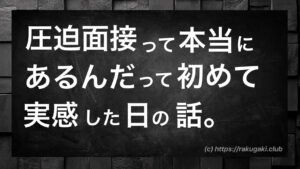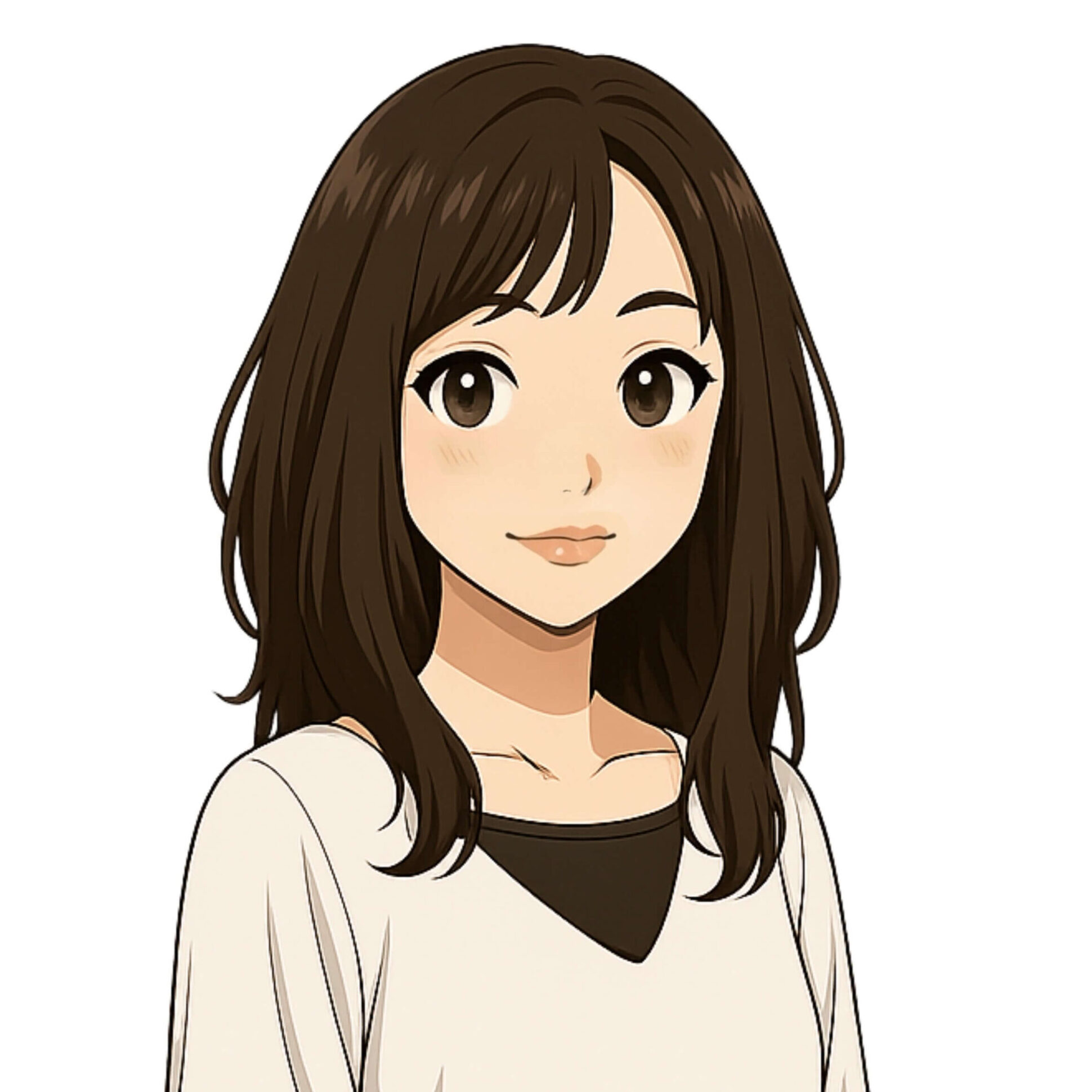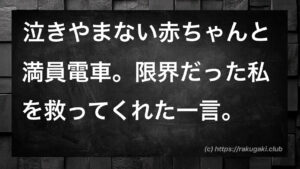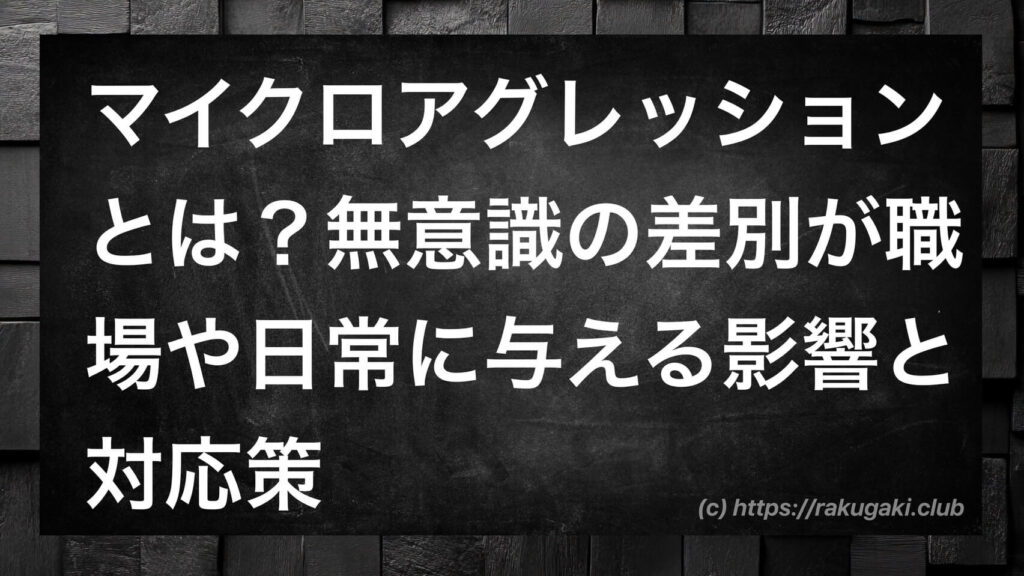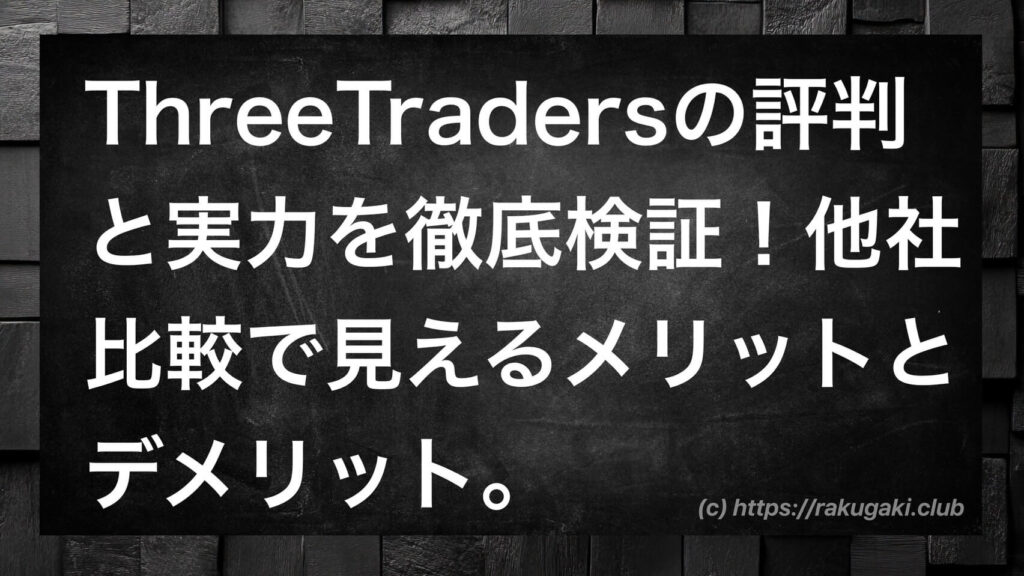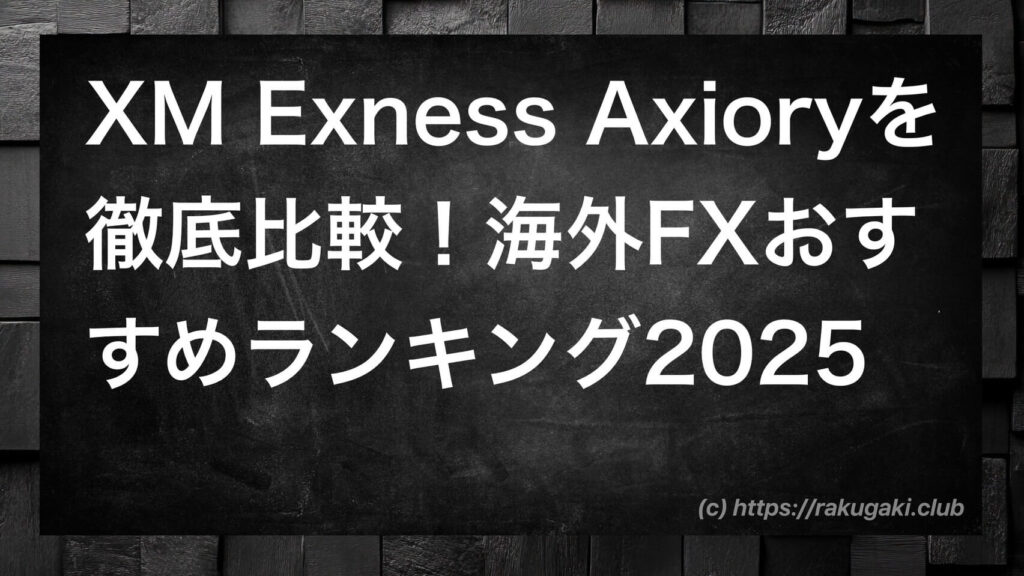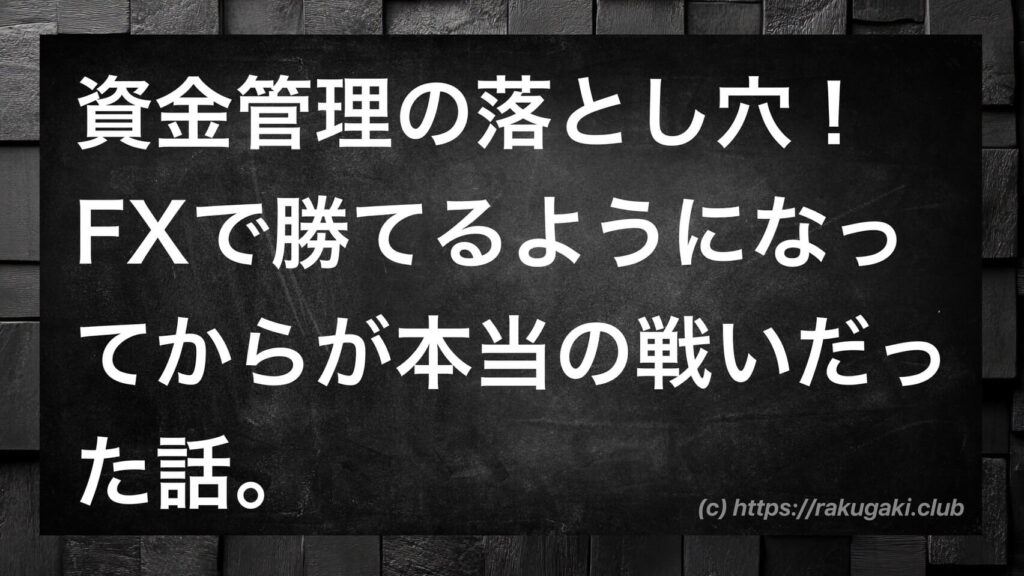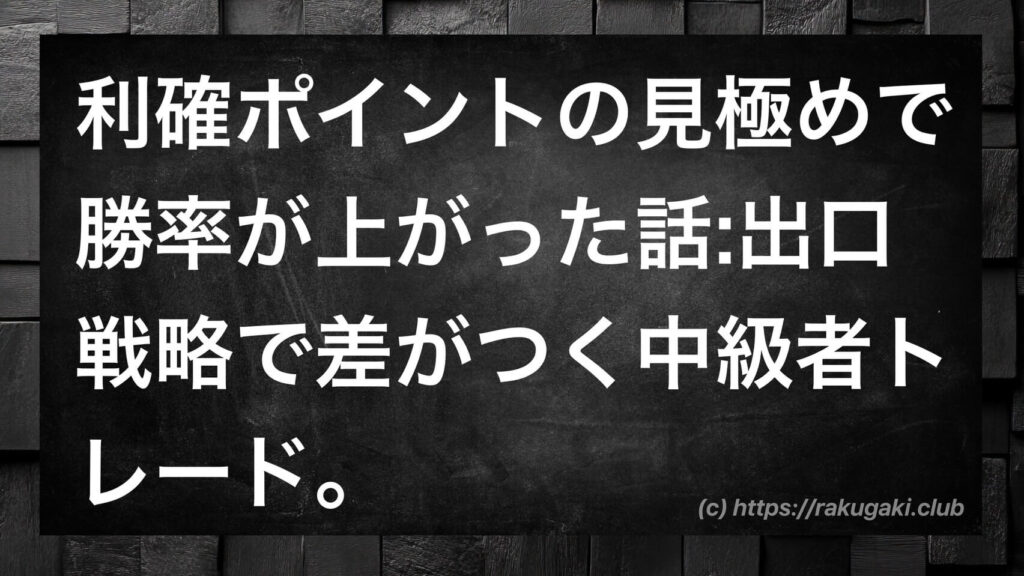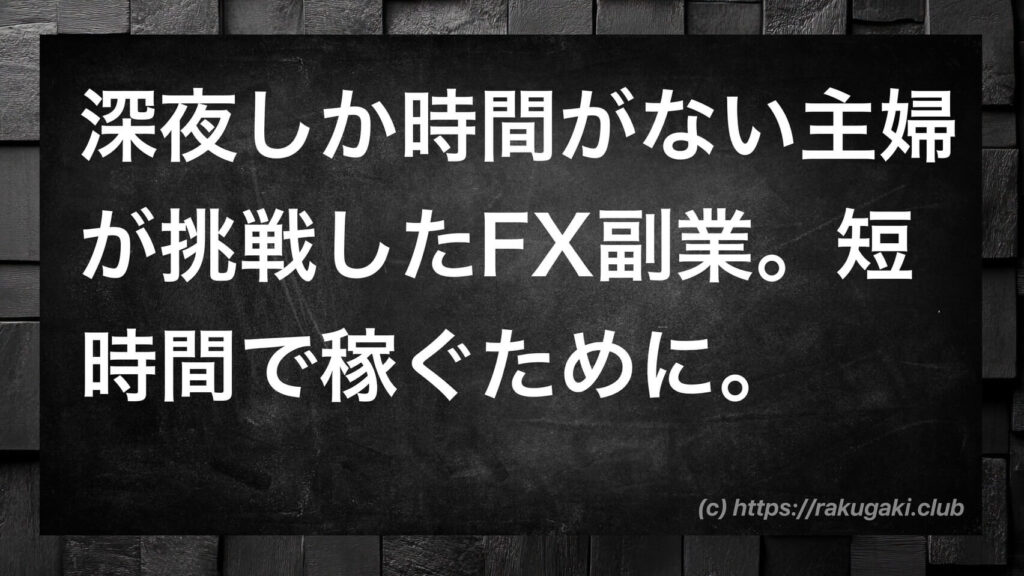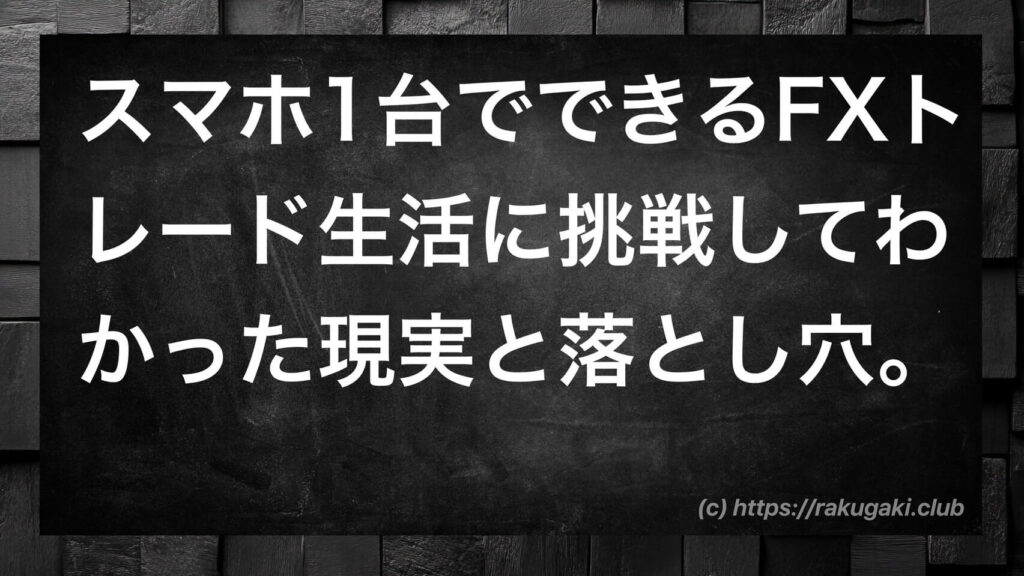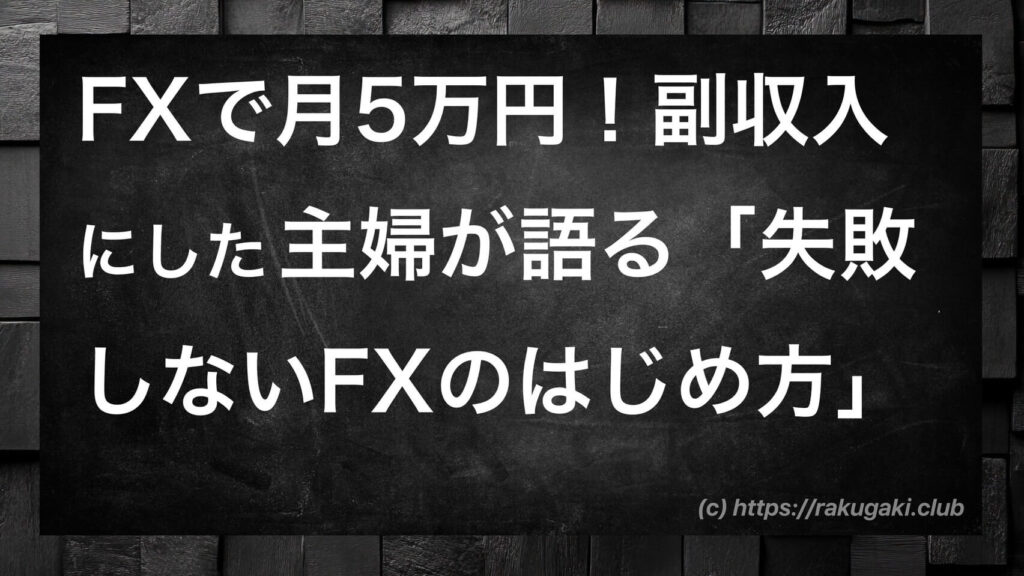なにげない検索が、遠い記憶の扉を開けた
検索窓にふと浮かんだ、あの名前
その日、私はなんとなく気持ちがざわついていた。
特別な出来事があったわけじゃない。天気は晴れ、仕事は定時で終わり、コンビニで買ったパスタは普通に美味しかった。
でもなぜか、心の中にすき間風が吹いているような感覚があって、帰宅後もずっと落ち着かなかった。
お風呂から上がって、濡れた髪のままベッドに寝転びながら、私はX(旧Twitter)の検索窓をなんとなく開いた。
そこで、ふと思いついた。
「じいちゃんの名前、入れてみたら何か出てくるのかな」
“今井伊作”。
東北の小さな農村出身の、物静かで口数の少なかった、私の祖父の名前だ。
数年前に亡くなったとき、葬儀の席で親族から「昔は村の青年団で有名だった」と聞いて、びっくりした記憶がある。
それくらい、普段は多くを語らない人だった。
まさか出てこないだろうな、と思いつつ、検索をかける。
ヒットしたのは、たった数件のポスト。
そのうちのひとつに、私は息を呑んだ。
ポスト主は“誰かの孫”じゃなかった
ポストの日付は、2日前。
投稿主の名前は「@shun_soba」、アイコンは十割そばの写真。
そのポストにはこう書かれていた。
「子どもの頃に遊んでもらった今井伊作さんのこと、ふと思い出した。
寡黙だけどやさしい人だった。雪かき手伝うと、りんご1個くれたなあ。
もう会えないけど、今も私の“理想の大人”のひとりです。」
胸の奥に、何かがずしんと響いた。
“遊んでもらった”という表現。
この人は、親族ではない。
でも、私の祖父のことを、私以上に“思い出せる人”なのかもしれない。
思わず投稿者のプロフィールを開いた。
東北在住、年齢はたぶん私より上。
ツイート内容から察するに、地域で活動してる人っぽい。
祖父のことが、“他人の記憶”としてインターネットに存在していることに、言葉が出なかった。
“伊作”という名前は、そう多くない
今井伊作という名前は、あまり見かけない。
名前に「作(さく)」がつくのは、東北の古い世代に多いと聞いたことがある。
うちの祖父の世代なら、同姓同名はほとんどいないだろう。
しかも、“雪かき”と“りんご”――
まさしく祖父の村そのものだった。
子どもの頃、冬に祖父の家に行くと、どこからかりんごを出してきてくれた。
決してお菓子ではなく、りんご。
ストーブの上でじわっと温められた、甘くて柔らかい、あの味を私は今でも覚えている。
「たぶん、じいちゃんのことだ…」
私はスマホを置き、しばらく天井を見上げたまま動けなかった。
“残されていた記憶”に触れる不思議さ
その投稿を読んでから、私は祖父のことをいくつも思い出した。
たとえば、縁側で種をほじくっていたスイカ。
味噌汁の豆腐がやたらでかくて、子どもの口には入らなかった話。
朝早く起きて、まだ暗いうちから畑に行く背中。
祖父が亡くなってから、どこかにしまい込んでいた記憶たちが、SNSという意外なところから引っ張り出されていく。
あの投稿は、タイムラインを流れる“たった140字のつぶやき”だったはずなのに、
それが私の中では、1,000字以上の思い出を呼び起こすきっかけになっていた。
誰かの“何気ない投稿”が、私にとっての宝物だった
SNSには、くだらないことや、愚痴や、日常の記録がたくさん流れている。
たいていはすぐに流れていってしまう。
でも、“あの投稿”は違った。
そこには、私の知らない祖父がいた。
私が記憶の中で閉じ込めていた“伊作じいちゃん”ではなく、
“誰かにとって、ちゃんと記憶に残る大人”としての、祖父の姿だった。
画面越しの言葉に、私は自然と涙がにじんだ。
まさか、こんな形でまた祖父に“会える”なんて思わなかった。
イッチちゃんの決意:投稿主に、話しかけてみようか
夜が深まるにつれ、私はスマホを握ったまま何度も迷っていた。
このまま心の中で「ありがとう」と思うだけでもいい。
でも、もしかしたら、直接聞けることがあるかもしれない。
祖父がどんなふうに見られていたのか。
どんな子どもたちに囲まれていたのか。
私は“孫”としてしか知らない祖父の姿を、
“他人”の視点から知ってみたくなった。
思い切って、投稿主のDMを開く。
そして、こう打ち込んだ。
「突然のご連絡すみません。
ポストされていた“今井伊作さん”は、おそらく私の祖父です。
投稿、拝見して涙が出ました。
もし差し支えなければ、祖父のことを、少しだけ聞かせていただけませんか?」
送信ボタンを押すと、心臓がドクンと鳴った。
返事が来るかはわからない。
でも、伝えられてよかった。
そう思ってスマホを伏せた。
知らなかった“じいちゃん”が、ポストの中にいた
DMの返信は、意外にもすぐに届いた
メッセージを送ってから半日後、通知がピロンと鳴った。
件名は「@shun_soba さんからのメッセージ」。
恐る恐る開くと、こんな一文が並んでいた。
「お孫さんだったのですね。
本当にびっくりしました。
伊作さんには、子どもの頃とてもお世話になりました。
お時間があれば、私の知っている伊作さんのお話をさせてください。」
目の前がふわっと明るくなった気がした。
SNSは、こういう奇跡をたまに運んでくれる。
イッチちゃん(私)は、ありがとうの気持ちを伝えながら、彼の言葉を受け取る準備を始めた。
“しゅんさん”という投稿主のこと
DMの文面は穏やかで、言葉遣いにもあたたかさがあった。
「しゅんさん」と名乗ったその人は、今は40代後半。
現在は同じ東北地方で地元のそば屋を営んでいて、ポストのアイコンもそのお店の名物らしい。
「昔、伊作さんの家のすぐ近くに住んでいて、
よく遊びに行ってたんです。
冬は雪かき、夏は畑の雑草取りを“手伝ってるつもり”で邪魔してました(笑)」
思わず笑ってしまった。
祖父はあまり“他人を招き入れる”タイプではなかったはず。
私の知ってる伊作じいちゃんは、どちらかといえば静かで、無口で、
何かを話すより黙って作業する人だったから。
だからこそ、“遊びに行ける存在だった”というのが意外だった。
祖父の家で過ごした“他人の夏”の記憶
「伊作さんの家、覚えてますよ。
広い縁側があって、夏になると麦茶が冷えてるやかんが置かれてて。
私ら子どもは勝手に冷蔵庫からコップを取り出して飲んでたんです。
もちろん“許されてる”って知ってたから(笑)」
あの家の冷蔵庫に、そんな使われ方があったなんて。
私が知っているのは、親族だけが集まるお盆や年末年始の雰囲気。
でも、地元の子どもたちにとっては、
祖父の家が「地域の秘密基地」みたいな存在だったのかもしれない。
畑で怒られて、でも怒られてなかった話
「一度だけ、本気で怒られた…ような気がした日があります。
畑で遊んでて、まだ育ちかけのとうもろこしを勝手に折っちゃって。
伊作さん、無言でそれ拾って、
そのまま火を焚いて、焼きとうもろこしにしてくれたんですよ。
何も言わずに。
それで“これは来週に食べるやつだった”って、ぼそっと言ってて」
「あれ、怒られてたんですかね(笑)」
私は笑いながら、ふと目頭が熱くなるのを感じた。
それ、じいちゃんだわ…と思った。
何かを失っても、誰かのせいにしない人だった。
あくまで静かに、自分の中で処理して、
そのうえで“場”を守ってくれる大人。
たしかに、私も似たような記憶がある。
壊したおもちゃを直してくれたこと、
転んでも黙って膝に貼ってくれた絆創膏のこと。
そうか。
あれは、私だけに向けられていたやさしさじゃなかったんだ。
“自分の知らない祖父”に出会う不思議な感覚
しゅんさんとのやりとりは、思いのほか続いた。
2通、3通と重ねるごとに、祖父の記憶が少しずつ色づいていく。
そして、私がふと聞いた。
「祖父って、話すの苦手な人じゃなかったですか?」
「そうですね。たしかに口数は少なかったかもしれません。
でも、言葉じゃなくて“すること”で伝える人だったと思います」
それを聞いて、私は大きくうなずいた。
言葉でほめたり、抱きしめたりはしない。
でも、早朝に私の自転車のパンクを直してくれてたり、
私が好きな味噌ラーメンだけを買い置きしてくれてたり。
あの人は、行動でしか感情を表せない人だった。
家族から聞いても出てこなかった話たち
不思議なことに、しゅんさんが語る祖父の姿は、
私の家族が話す“おじいちゃん”とはまた少し違っていた。
家族から聞いたことのないエピソードが次々に出てきて、
まるで祖父がもう一度別の角度から照らされているようだった。
「伊作さんね、町の祭りで一度だけ太鼓叩いてたんですよ」
「実はかなり昔、“村の雪合戦大会”で3年連続優勝してたらしいです」
「あと、近所の猫たちにめっちゃ好かれてました」
え、なにそれ。知らない、知らなすぎる。
でもどれも、聞けば聞くほど“らしい”気がしてくる。
SNSで“記憶”と“記録”が交差する場所
SNSって、どこか“いま”の世界ばかりが溢れてると思ってた。
トレンド、速報、つぶやき、炎上、バズ――
全部、スピードの世界のものだと。
でも、こうして過去のことを、たったひとつの投稿から辿っていけるなんて。
たった140文字が、私の記憶の奥深くに届いて、
しかも他人の言葉が“知らない祖父”を連れてきてくれるなんて。
SNSって、こんなにやさしい場所にもなれるんだな。
あの人が“誰かの中”に生きていたということ
いつの間にか、話し相手は“じいちゃんの話し相手”になっていた
しゅんさんとのDMは、その後も穏やかに続いた。
文字のやりとりなのに、まるでストーブの前で湯気の立つ湯呑みを挟んで、昔話を聞かせてもらっているような、そんなあたたかい感覚。
私が“孫”として知っている祖父と、
しゅんさんが“近所の少年”として覚えている祖父。
その二つの記憶が、ゆっくり重なっていく。
「そういえば、伊作さんの畑には、妙に細長いナスがありましたよね」
「うちの母が“あれは種が違う”って不思議がってました」
ああ、それ、わかる。
祖父が育てていたナスは、確かにちょっと細くて、味が濃かった。
「売ってるのとは違う」とよく言っていたけど、それが種の違いだったなんて、私は知らなかった。
“記憶”って、他人が補完してくれるものなのかもしれない
祖父のことをもっと知りたかったのに、生きているうちには聞けなかった。
それは、どこかで「聞いても話してくれないだろう」と思っていたから。
でも、本当は自分が知ろうとしていなかっただけなのかもしれない。
「伊作さんは、たまに“私の祖父のこと”を話してくれてました。
“昔はこの土地、牛で耕したもんだ”って。
それがすごくリアルで、子どもながらに“時間の厚み”を感じた記憶があります」
そんな話、聞いたことなかった。
でも祖父は、自分のことより“昔の人の話”をするタイプだったから、なるほどと思った。
「祖父のことを誰かが覚えていてくれる」
それって、思っていた以上に心がほどける出来事だった。
記録に残らない“普通の人の記憶”が、SNSに浮かぶ奇跡
祖父は、何か賞をもらった人でも、歴史に名を残した人でもない。
ただ、村の片隅で、農作業をして、家族を養って、
静かに、実直に生きていた“普通の人”だった。
それでも、しゅんさんのように“記憶のなかに大切にしまってくれている人”がいて、
その記憶がたまたま、SNSの投稿という形で表に出てきてくれた。
こんなことってあるんだ。
しかも、それを“見つけられた”のは、偶然なんかじゃなく、
“何かが導いた”とすら思えてくる。
小さなエピソードに滲む、祖父のやさしさ
「そういえば、伊作さんは、村の草刈りのときも最後まで残って片付けしてました。
誰も見てなかったのに、黙々と。
それがすごくかっこよかったんです」
私はその話を読みながら、涙が止まらなかった。
“誰も見てないのにやる”って、いちばん難しい。
そして、いちばん尊い。
そういう背中を、私は一緒に暮らしていた間にも、きっと見ていたのに、
当時は気づけなかったんだと思う。
家族でも知らなかった、もうひとつの“名前”
しゅんさんとのやりとりの中で、こんな一節があった。
「伊作さんのこと、近所の人は“いっさく先生”って呼んでましたよ」
私は思わず画面を二度見した。
「先生!?」
祖父が先生…? そんな話、聞いたことない。
「たぶん、正式な先生じゃなくて、
農業のこととか、土地の知識を教えてくれてたから、
子どもたちが勝手にそう呼び始めたんだと思います」
なんということ。
うちの家族の中でも、“伊作=寡黙なおじいちゃん”という印象しかなかったのに、
地域では“先生”と呼ばれていたなんて。
名前は同じなのに、まったく別の“物語”がそこに存在していた。
言葉が残らなかった分、行動が語ってくれたんだね
祖父は手紙も日記も残していない。
スマホもパソコンも持っていなかったし、当然SNSなんて縁もなかった。
でも、しゅんさんの言葉を通して思ったのは、
「言葉が残らない人生だったけど、“人の記憶”としてはちゃんと生きていた」ということ。
誰かの中に残る行動、やさしさ、背中、習慣。
それが、SNSというデジタルな世界にふわっと浮かんできたとき、
まるで祖父が、もう一度私の前に現れてくれたような気がした。
“会いたい”がかなわないからこそ、心が震える
もし、祖父が今も生きていたら、
この投稿を見せて「知ってた?」って聞けたのに。
しゅんさんの話を共有して、笑い合えたのに。
そう思うと少し切なくて、
でも、“今の私”がこの記憶に触れられてよかったと、心から思った。
あのとき、ふと名前を検索しようと思わなかったら、
この奇跡にはきっと出会えなかった。
SNSはときに騒がしく、過激で、疲れる場所だけど――
こうやって、静かに心を動かす何かも、確かにそこにあるんだな。
“思い出の中の祖父”が、今の私に教えてくれたこと
過去の話を聞きながら、自分の中の記憶も塗り替わっていく
しゅんさんとのDMのやりとりは、数日間続いた。
どのエピソードも、どこか懐かしくて、でも私の知らない祖父ばかりだった。
それが不思議と、寂しくはなくて、むしろ嬉しかった。
「伊作さんは、よく“やれることは、やれるうちにやれ”って言ってましたよ」
「言葉少ないけど、芯のある人だったと思います」
それを読んだとき、私の脳裏に浮かんだのは――
高校時代、進路で迷っていた私に対して、祖父がぽつりと言った一言だった。
「やりてぇことがあるなら、手ぇ動かせ」
当時は「昭和だな〜」なんて軽く流してしまっていたけど、
あれって、しゅんさんが聞いた“やれるうちにやれ”と根っこが同じじゃないか。
じいちゃんの言葉は、回りくどくなかった。
でも、それは決して無関心じゃなくて、不器用な“応援”だったんだなって、今さら気づいた。
“誰かの目を通した記憶”が、自分の祖父像を整えていく
祖父のことをこんなに真剣に考えたのは、いつ以来だろう。
亡くなったときですら、正直どこか現実味がなかった。
田舎に帰るたびに座っていたこたつ。
同じ味しかしない味噌汁。
そこにあることが当たり前で、いなくなる想像すらしたことがなかった。
でも、他人の目線で語られる祖父の記憶を聞いていくうちに、
「自分が知っていたのは、ほんの一部分だったんだ」と思い知らされる。
人は、誰かの中に何通りもの“顔”を持っている。
私にとっての祖父、母にとっての父、近所の子にとっての“先生”。
どれも間違いじゃなくて、どれも正解。
そして、その中に“イッチちゃんの祖父”がいる。
それが、なんだか誇らしかった。
SNSは“記憶をつなぐ場所”にもなれるんだ
私は正直、SNSはどこか信用できない場所だと思っていた。
言葉が切り取られたり、炎上したり、誤解されたり――
だからこそ“本音”を出す場所ではない、という感覚が強かった。
でも今回、何気ない一件の投稿が、
こんなにも豊かに“記憶のバトン”を渡してくれるなんて思わなかった。
SNSって、単なる発信の場じゃない。
誰かの記憶が浮かび上がる“共有のアルバム”みたいなものなのかもしれない。
誰かが覚えていることが、
誰かにとっての宝物になる。
それが、静かに、優しく、ちゃんと伝わっていくこともあるんだ。
祖父の名前を“もう一度ポストする”ことにした理由
しゅんさんとのやりとりを経て、私はある決断をした。
自分のアカウントで、祖父の名前を出してポストしてみようと思ったのだ。
いつもなら、家族のことを出すのはためらっていた。
とくに亡くなった人について語るのは、
なんだか“感傷的すぎる”と思われそうで恥ずかしかった。
でも今回は違った。
「この人のことを知ってた人、他にもいたらうれしいな」
「うちの祖父のことなんです。誰かの記憶に残ってるなら、聞いてみたいです」
そう思えたのは、
“祖父を思い出す”ことが、
“自分のルーツを受け取る”ことに他ならないと気づいたから。
だから私は投稿した。
「大好きだった祖父の名前を、ふと思い出して検索したら、
見知らぬ人の記憶の中に、ちゃんと生きていてくれた。
SNSって、こういう奇跡もあるんだな。伊作じいちゃん、私、あなたのこともっと知りたかったよ。」
バズらなかった。でも、それでよかった
この投稿は、バズらなかった。
いいねも数十件、リプもほんの数通。
だけど、その中には――
「私も祖父の名前で検索したことあります」
「こういう話、もっと聞きたいです」
「あなたの言葉、沁みました」
そんなふうに、静かに届いた言葉があった。
しゅんさんも、その投稿に返信してくれていた。
「伊作さん、きっと照れながら読んでますよ」
それを見て、私はひとりでくすっと笑った。
思い出すことは、生きてること
人は、思い出すことで“もう一度誰かと出会える”んだと思う。
記憶の中にしかいない人が、ふとしたきっかけで現れて、
また新しい気持ちをくれる。
私は、あの夜“伊作”という名前を検索したことで、
亡くなった祖父に、もう一度“はじめまして”を言えた気がした。
そして何より――
“私は、この人の孫なんだ”と、静かに誇らしく思えた。
祖父が教えてくれた“生き方”が、今の私を支えている
“伊作さんは、今もそこにいる気がします”
投稿から数日後、再びしゅんさんからメッセージが届いた。
そこには、ひとつの短い言葉が綴られていた。
「不思議ですね。
こうして伊作さんのことを話していたら、
今もそこにいるような気がしてきました」
それを読んだとき、私は涙がこぼれた。
画面越しの言葉なのに、心の深いところにまっすぐ届いて、
まるで本当に、祖父の姿が浮かんできたようだった。
たぶん、今もどこかで畑を耕していて、
よくわからないスマホの使い方にちょっと首をかしげながら、
私たちのやりとりを、笑って見ているんじゃないかって。
“やさしさ”をひとつずつ、受け継いでいくということ
祖父は、たぶん自分が誰かの記憶に残っているなんて考えもしなかったと思う。
ましてや、自分の名前がSNSで語られるなんて、想像すらしてなかったはずだ。
でも、確かに残っていた。
雪かきを手伝った子どもたち。
冷蔵庫の麦茶を勝手に飲んでいた近所の少年たち。
畑でとうもろこしを焼いてもらった記憶。
言葉ではなく、行動で伝えられた“やさしさ”の記録。
しゅんさんだけじゃない。
リプライの中にも、「たぶん同じ人です」という人がひとりだけいて、
祖父に手伝ってもらったという、古い木造倉庫の話を書いてくれていた。
名もなき日々のなかに、
祖父は静かに“誰かの役に立つこと”を選び続けていたんだと思う。
祖父の背中が、私の今の選択を支えてくれる
仕事で悩んだとき、
人間関係に疲れたとき、
「もう全部手放したい」と思ったとき。
私は祖父の姿を思い出すようになった。
たとえば、誰も見ていないところで草を刈る姿。
誰かの失敗を叱ることなく拾い直す姿。
“なにか言う”より先に“なにかする”姿勢。
そして、今の私も――
誰かの記憶に残るような生き方ができたらいいなと思うようになった。
派手なことはできなくてもいい。
特別じゃなくてもいい。
でも、そっとそばにいられるような、そんな人でありたい。
「話せなかったこと」が、話されていく嬉しさ
祖父が生きていた頃、私はあまり話せなかった。
なんとなく照れくさくて、
何を話していいか分からなくて、
会話らしい会話をした記憶が、ほとんどない。
でも今、私はこうして、
たくさんの“祖父のこと”を語っている。
SNSで、DMで、リプライで、心の中で。
不思議な話だけど、
亡くなってからの方が、祖父とちゃんと“話せている”ような気がする。
そしてその会話は、誰かと共有されることで、
新しい意味を持ち始めている。
祖父の名前が“タグ”になった日
Xでの私の投稿に、いくつかの人がこう返信してくれていた。
「“伊作さん”っていい名前ですね」
「うちの祖父も似た感じの人でした」
「“伊作さん”で検索して、泣きました」
そのとき思った。
祖父の名前が、“誰かの記憶に触れるタグ”みたいになっている。
それは、どこかうれしくて、
でもやっぱり少しさみしくて、
だけど――とてもあたたかかった。
たぶん、祖父のことを検索してくれた人たちの中にも、
“自分の大切な人”を思い出した人がいたのだろう。
その連鎖が、SNSの静かな奇跡だと思った。
「今、ここにいなくても」つながっている感覚
家にあった、祖父が最後まで使っていた湯呑みを取り出してみた。
縁が少し欠けていて、
底にはうっすらと茶渋が残っていた。
もうこの湯呑みを使う人はいない。
でも、私はそのカップを見つめながら、心の中で言葉をかけた。
「じいちゃん、見てた? 私、あなたの話をたくさん聞いたよ」
返事はないけど、返事がいらない感覚ってある。
そこに“いる”と思えること。
それが、いちばんの支えになるときがある。
SNSが“思い出の扉”になることもあると知った日
私はこれからも、
何気ないときにSNSで“名前”を検索するかもしれない。
大切だった誰かの名前、
昔の恩師の名前、
ふと浮かんだ友人の名前。
そこに何もなかったとしてもいい。
でも、もし見つかったとしたら――
それはまぎれもない“心の記録”だ。
祖父の名前が、それを教えてくれた。
“名を残す”って、記念碑や本に載ることだけじゃない。
誰かの言葉の中で生きている。
それが、たったひとつの投稿で伝わることもある。
静かに繋がる記憶と想いの先で、“わたし”は生きている
心にそっと、ひとつぶの温かい灯がともるように
何か大きなことが起きたわけじゃない。
ドラマチックな展開も、感動的な奇跡もなかった。
でも、私はあの日から、少しだけ世界の見え方が変わった気がする。
スマホの画面に浮かんだ、たった140字のつぶやき。
あの投稿が、祖父の記憶の扉を開け、
その記憶が私のなかに、あらたな輪郭を与えてくれた。
「思い出すこと」は、「出会い直すこと」だった。
もう会えないと思っていた祖父と、
SNSを通して、私はもう一度会えた。
“知らなかった”ことが、こんなにあたたかく胸を打つとは思わなかった
しゅんさんとのやりとりのなかで、何度も驚かされた。
祖父が“いっさく先生”と呼ばれていたこと。
畑のとうもろこしを焼いていたこと。
誰にも見られていなくても、村の片隅で黙々と働いていたこと。
私にとっては“無口なおじいちゃん”でしかなかった人が、
他の誰かのなかでは、ちゃんと「ひとりの人間」として生きていた。
それを“知る”ことが、こんなにも嬉しいなんて。
今では、祖父の記憶は“私ひとりのもの”ではなくなった。
しゅんさんの記憶と、SNSを通して繋がってくれた人たちの想いと。
みんなの中に、少しずつ残っている。
そして、それがとても心強い。
“大好きだった”と、声に出して言えるようになった日
昔の私は、感情を人に見せるのが苦手だった。
とくに「大切な人を大切だと思っていること」を、
言葉にするのがどうしても恥ずかしかった。
でも、SNSで「大好きだった祖父のこと」とポストして、
たくさんの“知らない誰か”がそれを読んでくれて、
温かい言葉を返してくれて――
私はようやく、言えるようになった。
「私、伊作じいちゃんのこと、本当に大好きだったんだ」って。
何かを語るのに、時間がかかってもいい。
想いを抱えたままでもいい。
でも、それが“今”ようやく言葉になったなら、
それはもう十分すぎるほどの奇跡だと思う。
誰かの記憶に生きることの、静かな尊さ
今井伊作。
ひとつの名前が、たしかに存在していた。
何十年も前に生まれ、
何年か前に亡くなった、ひとりの農村の男。
どこにでもいるような人。
どこにも記録されていない人。
だけど――誰かの中では、生き続けている人。
そして、その“生きた証”が、
こうしてSNSの中に、そっと浮かび上がってくれた。
それは、決して軽いことじゃない。
むしろ、とても重くて、ありがたくて、尊いことだ。
祖父がくれた“生き方のヒント”が、私の中に残っている
何も言わずに黙って手を動かすこと。
誰にも見られていなくても、自分のやるべきことをやること。
誰かを直接ほめなくても、背中で伝えること。
そして、決して“自分語り”をしないこと。
SNSは“語る場所”だけれど、
祖父の姿勢は、私に“語らないことの強さ”を教えてくれた。
私も、すこしずつでいいから、
そんなふうに生きていけたらと思う。
言葉を発信しながら、
でもそれに囚われすぎず、
地に足をつけて、黙って続けることを、忘れずに。
最後に――きっと、あの人は笑っている
「伊作じいちゃん、名前で呼ばれてバズってるよ」
そんなこと言ったら、きっとあの人は、
「なんだそれは」って眉をしかめると思う。
でもそのあと、少しだけ、口元がゆるむ気がする。
あの、ふわっとした照れ笑いを思い出す。
わたしは、そんな祖父の姿を想像しながら、
心の中で、もう一度つぶやいた。
「じいちゃん、ありがとう」
「今もずっと、大好きだよ」