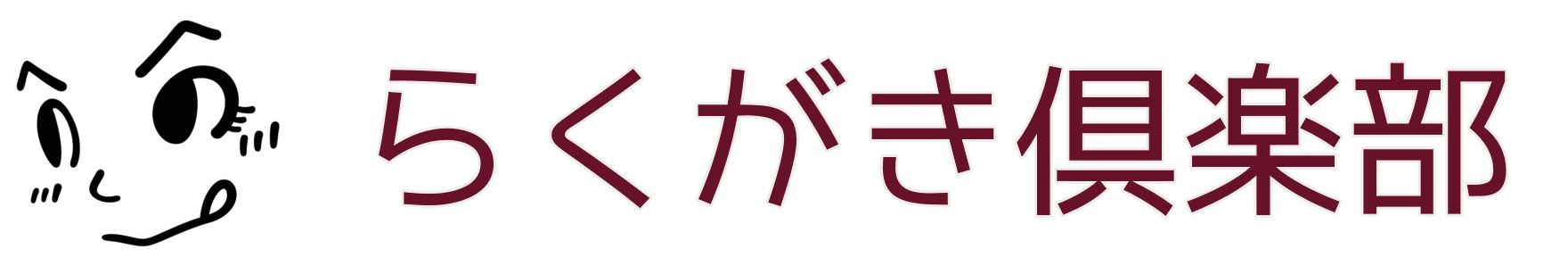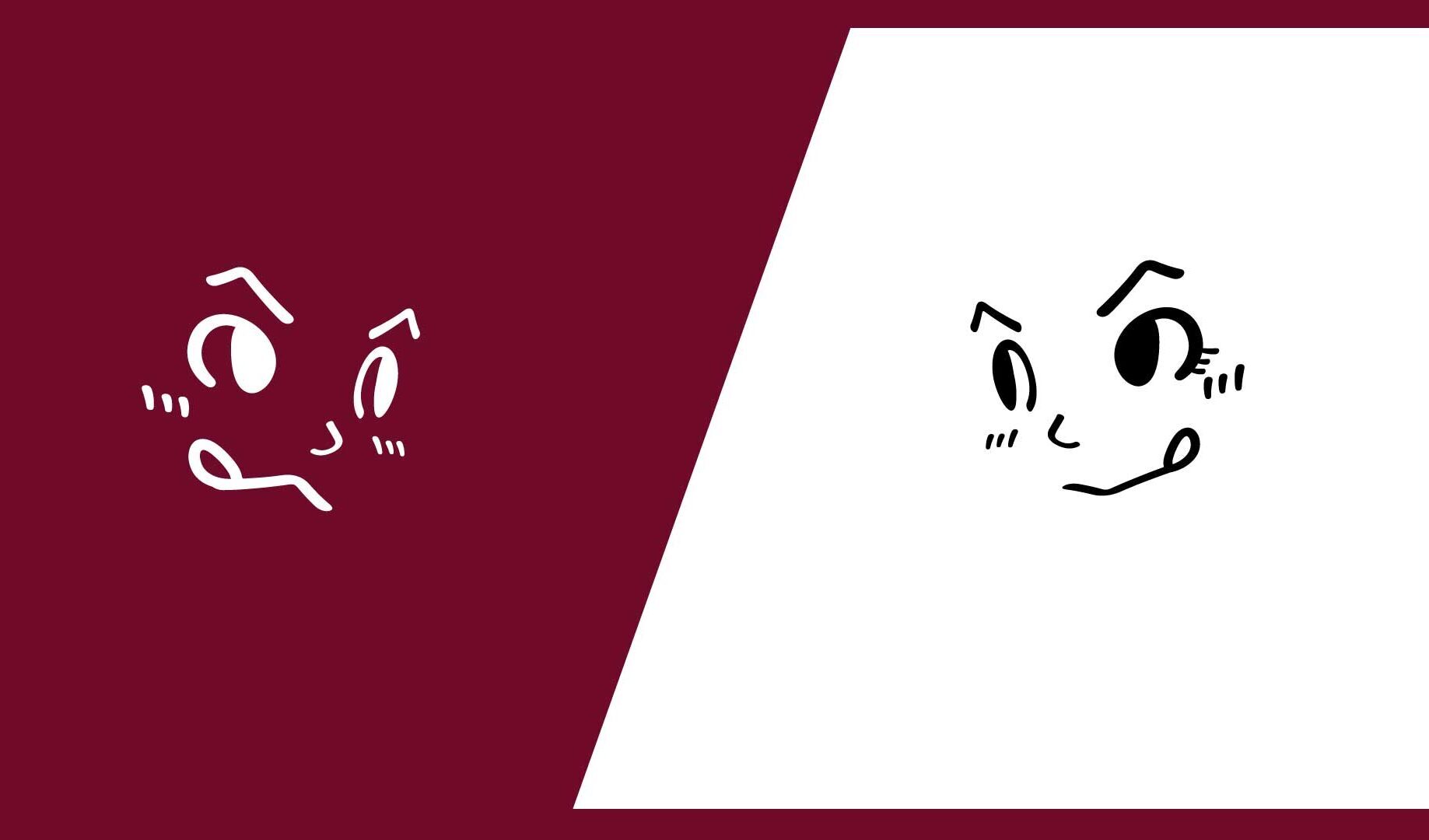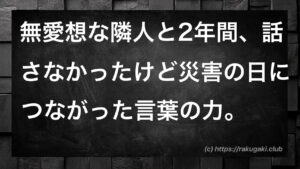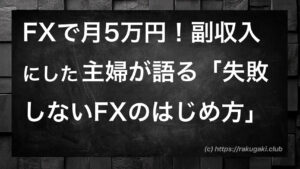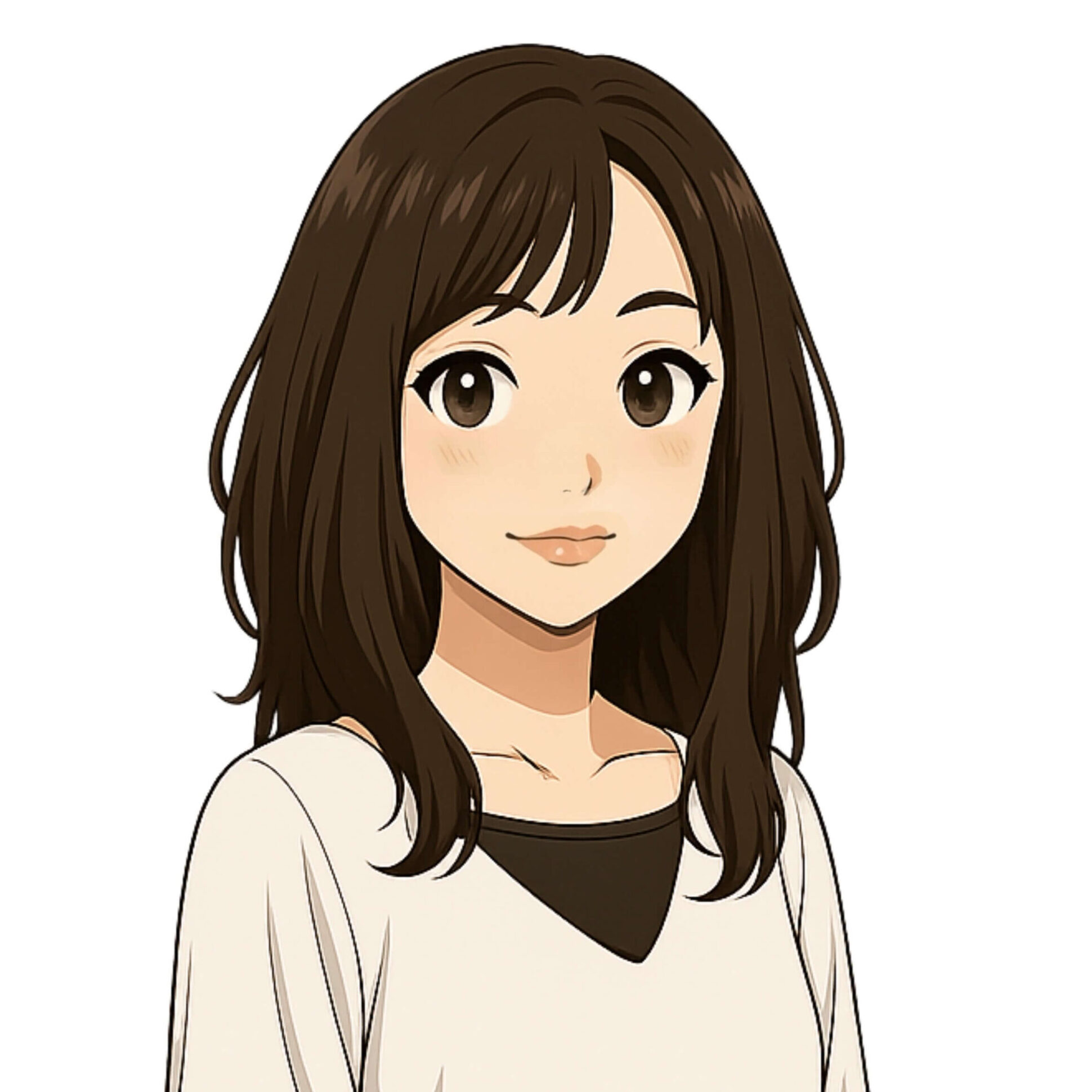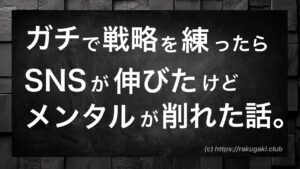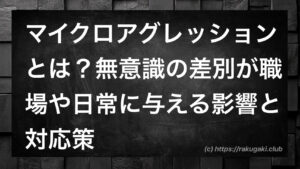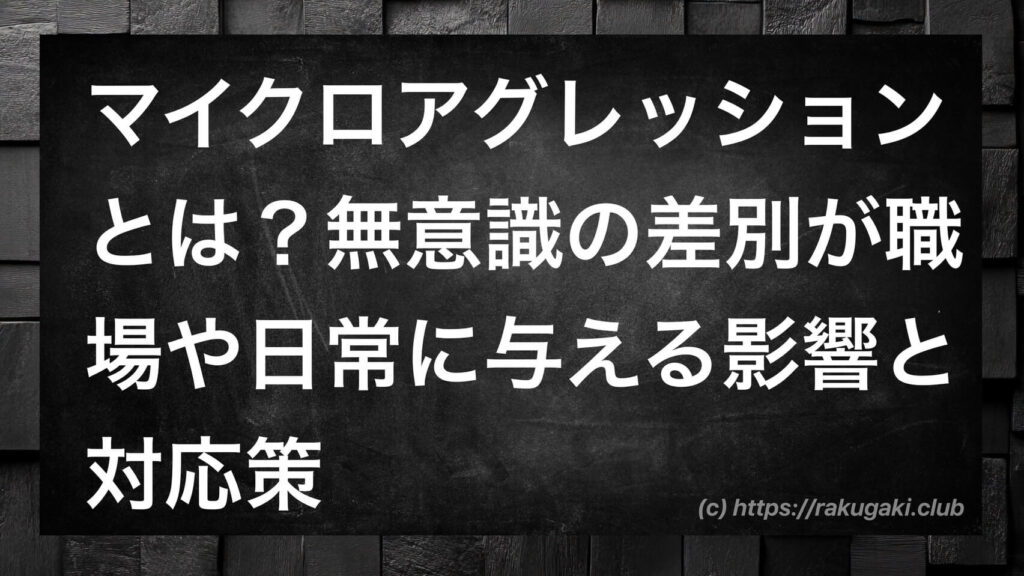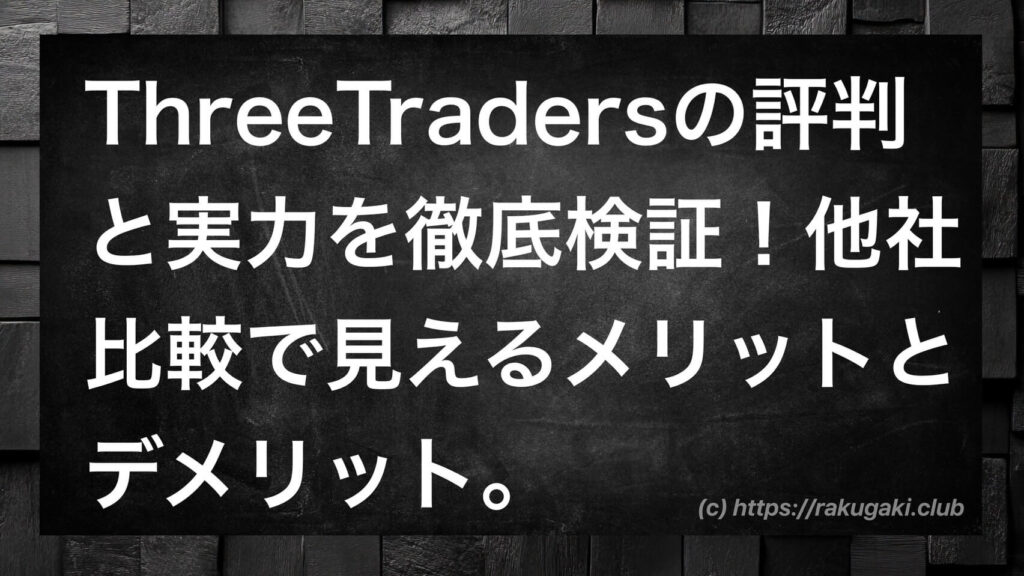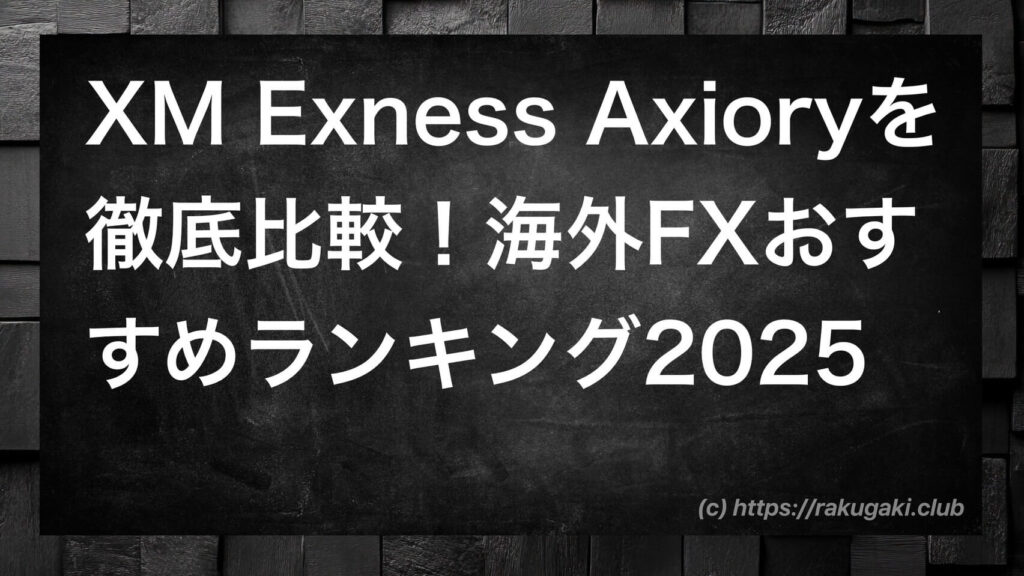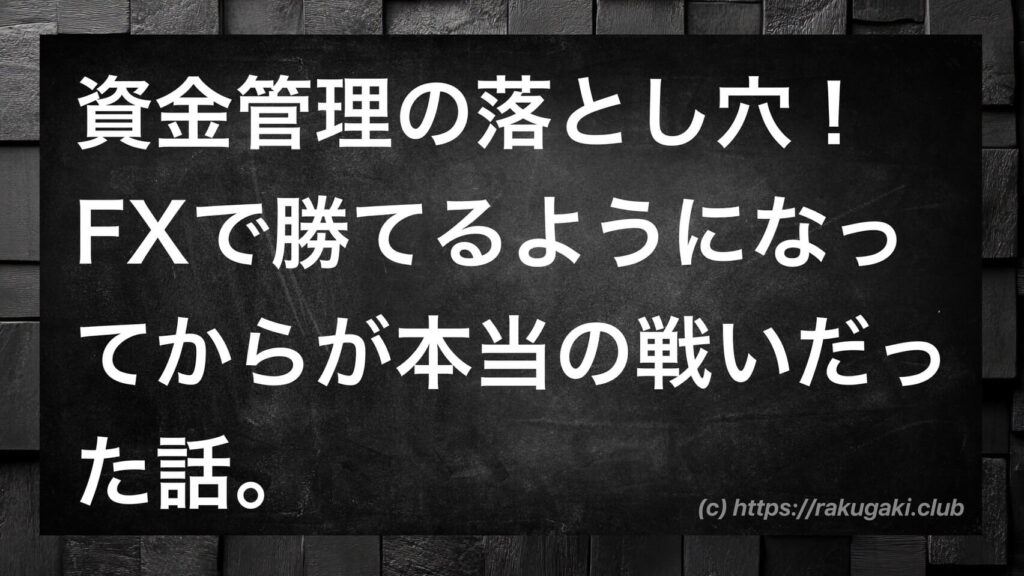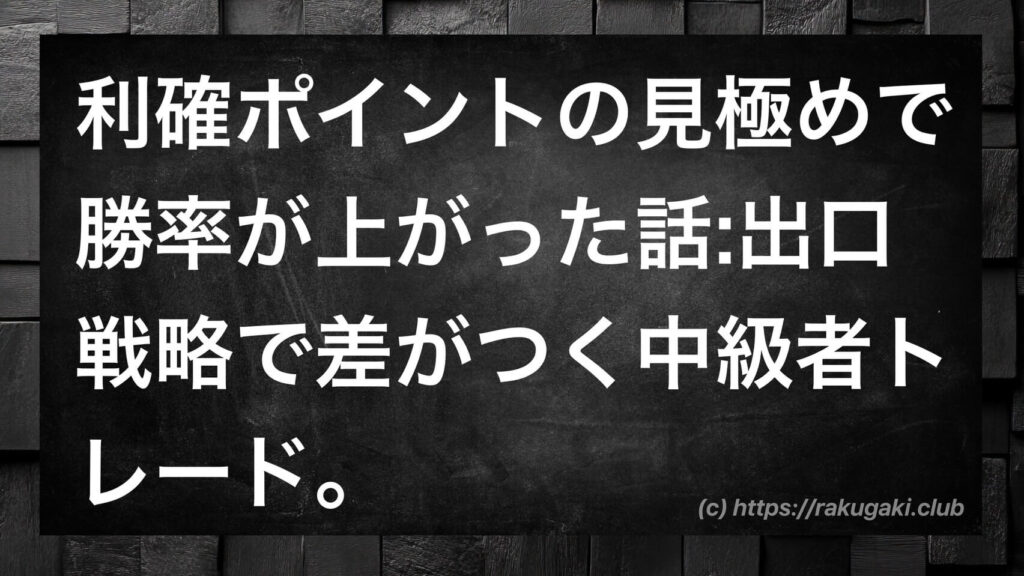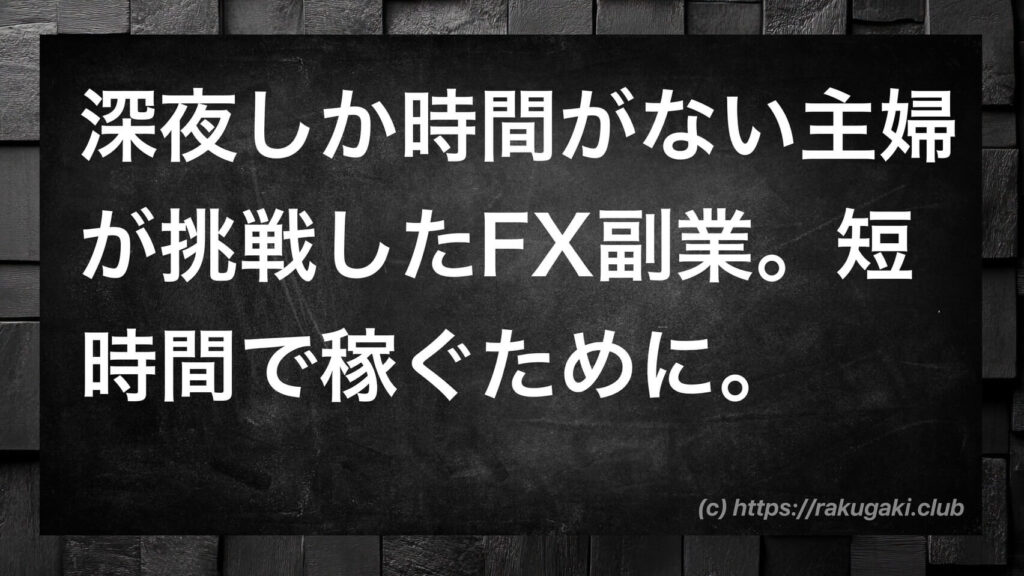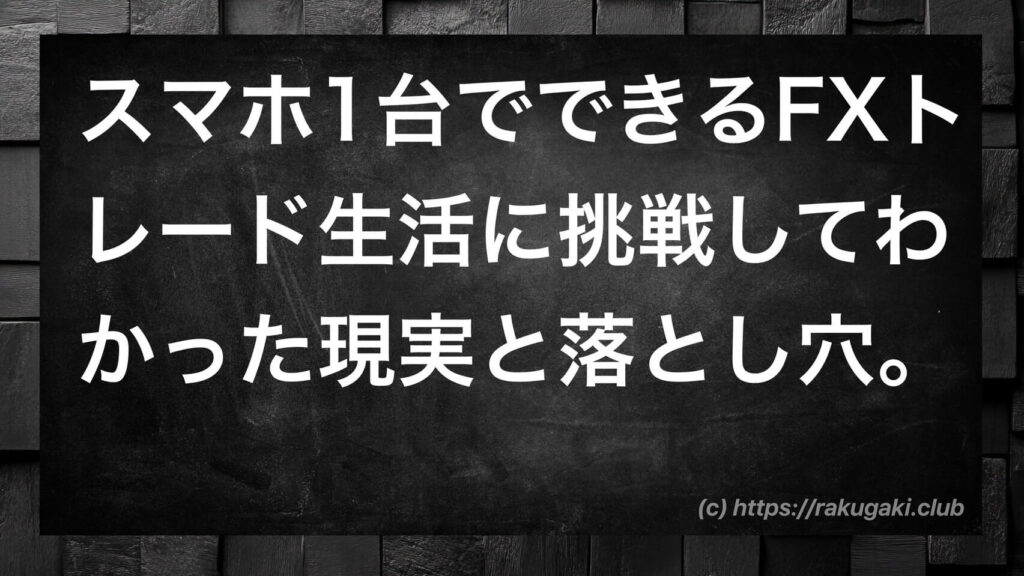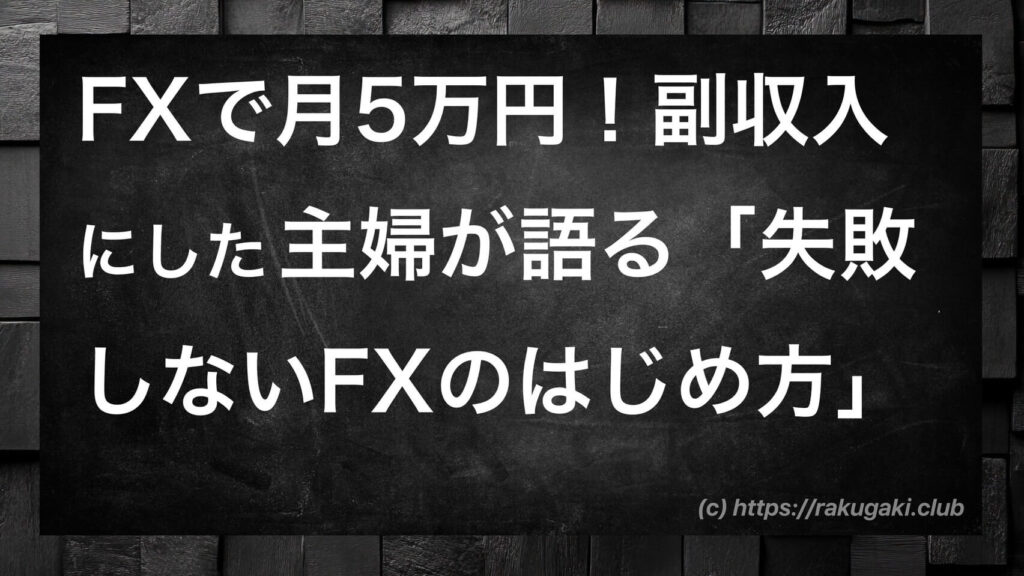“冗談でしょ?”で片づけられた言葉が、私を黙らせた。
職場における“ハラスメント”という言葉は、今では多くの人が耳にしたことがあるはずです。
しかし、その実態は、必ずしも怒鳴り声や露骨な嫌がらせではありません。
時には「冗談だよ」「そんなつもりじゃなかった」という“軽い一言”が、人の心を深く傷つけ、長く尾を引くこともあります。
この話は、私が「嫌なら辞めれば?」というたった一言で声を上げるのをやめてしまった、あの日のことから始まります。
表面上は穏やかな空気の中で、誰にも気づかれないまま、少しずつ自分らしさを失っていった体験を、今あらためて振り返ります。
その言葉を言われたのは、ほんの雑談の延長だった
「○○さんって、ちょっと愚痴っぽくない?」
そんな言葉が聞こえたのは、私が給湯室から出た瞬間だった。
耳に入ってきたその会話の主が、自分の上司と同僚であることを確認するのに、数秒もかからなかった。
職場の空気は表面上、穏やかだった。大声を張り上げる人もいなければ、あからさまに誰かをいじめるような行動も見受けられない。
ただ、何かを「言い出すこと」が許されない。そんな目に見えないルールのようなものが、職場全体を支配していた。
私は、入社して3年目。事務職として一般企業に勤める、ごく普通のOLだった。業務内容に不満はなかったが、徐々に感じるようになったのは、理不尽な指示や感情的な物言い、何より「相談しても改善されない」という無力感だった。
そんな中で、ある出来事が起きた。きっかけは、業務負担の偏りに対して上司に相談したことだった。
「嫌なら辞めれば?」の破壊力
そのときの上司の言葉が、タイトルにもなっている「嫌なら辞めれば?」だった。
言い方は、軽い冗談のようだった。
だが、私の心には、その一言が釘のように刺さった。
たしかに私は、言った。
「最近、業務の割り振りが偏っていませんか?」と。
しかし返ってきたのは、「あんまり言うと嫌われるよ」→「ま、嫌なら辞めればいいしね(笑)」という流れだった。
瞬間、空気が凍ったように感じた。
笑いながら冗談として言ったつもりかもしれない。
だが私は、「ここでは声を上げることすら否定されるんだ」と直感した。
それ以降、職場の人に業務上の相談をすることも、率直に意見を言うこともなくなった。
黙って受け入れるか、自分の中で処理するか。そんな選択肢しか与えられていないような感覚に陥った。
「正論ハラスメント」の正体とは何か
のちに知った言葉に、「正論ハラスメント」や「マイクロアグレッション」がある。
正論ハラスメントとは、言っている内容自体は間違っていなくても、それを武器にして相手の意見や感情を封じ込める行為だ。
まさに私が受けた「嫌なら辞めれば?」という言葉は、これに該当する。
「業務がきつい」と言えば、「じゃあ他の人も同じだから」「もっと忙しい人もいるよ」と返される。
「それ、私だけがやるんですか?」と聞けば、「みんなもやってる」「成長のチャンスだよ」と返ってくる。
相手は穏やかに、理屈で応じてくる。
けれど、そこには“話し合う姿勢”がなく、“従わせるための正論”が並ぶだけだった。
私はその日を境に、口数が極端に減った。
どんな小さな違和感も、誰にも言わず、メモ帳にだけ書き残すようになった。
言えなくなる職場で、何が壊れていくのか
声を上げることができない環境では、まず自己肯定感が削られていく。
「私が間違っているのかもしれない」
「こんなことで不満を言う自分が悪いのかもしれない」
「他の人は平気そうにやってるのに」――。
気づけば、「辞める」という選択肢を現実的に考えるようになっていた。
でも同時に、どこかで「私が折れなければいけないのか?」という反発心も湧いてきていた。
黙ることが、職場の平和なのか。
意見を言わないことが、大人の対応なのか。
そうして、私は小さく自分の中で「今の状態はおかしい」と思い続けていた。
初めて気づいた「笑えない冗談」の正体
「軽口」に見えて、軽くなかった言葉
直属の上司である佐藤課長(仮名)は、一見するとフランクで明るい人物だった。
声が大きく、飲み会では中心にいるタイプで、「お前、最近色気づいたな〜」「彼氏できたのか?」などの“軽口”を、男性社員にも女性社員にも飛ばしていた。部署内ではそれが「佐藤課長のノリ」として扱われ、誰も本気で受け取っていないように見えた。
だが、私にとっては、少しずつ居心地の悪さが積み重なっていた。
たとえば、髪型を変えたときに「それ、男ウケ狙い?」と笑われたり、昼食を一緒にとっただけの男性同僚とのことを「社内恋愛じゃん」とからかわれたり。笑ってごまかすのがルールのようになっていた。
周囲は笑っていたけれど、私自身はまったく笑えていなかった。
ただ、当時の私は「自分が気にしすぎなのかも」と思い込むことで、やり過ごそうとしていた。
声をあげたくても、「面倒な人」になりたくなかった
ある日、取引先からの接待で、私が同行することになったときのこと。
打ち合わせ後、佐藤課長は皆の前で「〇〇さん(取引先)が『君みたいな若い子が来てくれて嬉しいってよ〜』ってさ。俺のチョイス正解でしょ?」と冗談交じりに言った。その場は笑いが起きたが、私は顔がこわばるのを隠せなかった。
帰社後、こっそり先輩に「ちょっとあれ、不快だったんですけど…」と漏らすと、返ってきたのは「まあまあ、あの人のいつもの冗談だし。気にしたら負けだよ」という言葉だった。
「気にしたら負け」
その言葉は、ハラスメントを“自分の心の弱さ”にすり替えてしまう。
私はそこで、口を閉ざすことを選んだ。
何かを言えば「被害者意識が強い」「空気を読めない人」扱いされるかもしれない――そう思うと、職場での立ち位置や評価が気になって仕方がなかった。
正論ハラスメントが、相談を封じていく
そして決定的だったのが、ある飲み会の席での一言。
課長がまたもや「最近、なんか不機嫌じゃない?」と話を振ってきた。私は「ちょっと忙しいだけです」とやんわりかわそうとしたのだが、「まぁ嫌なら辞めれば? 会社なんて他にもあるでしょ?」と軽く言い放たれた。
その瞬間、心がざわついた。
“冗談”という形で放たれたその一言は、「お前の感じ方なんて知らない」「不満があるなら出て行け」と言われたように感じた。
そして、「ここでは何を言ってもムダなんだ」と諦めが生まれた。
このとき、私は気づいた。
“嫌なら辞めれば?”という正論めいた一言が、相談や報告を封じ込める力を持っていることを。
見えない傷が積み重なる職場で、私は自分を見失っていった
毎日の「ちょっとしたこと」が、心をすり減らしていく
あの日から、私は自分が職場の“雑音”のような存在に思えてならなかった。
何を言われても「冗談」として受け流され、真面目に返しても「空気読めない」と思われる。言い返せば反抗的、黙っていれば都合のいい相手。
どんな選択をしても、自分が悪者になってしまうような感覚。
たとえば資料を作っても、課長は「女の子らしいデザインだね〜」と一言添えてくる。
それは褒め言葉なのか、嫌味なのか、判断もできない。
「ありがとう」と笑って受け取るべきなのか、「それ、どういう意味ですか?」と聞くべきなのか――毎回、答えのない選択肢に直面していた。
積み重なる“些細な違和感”が、気づけば私の働く気力を奪っていった。
「傷ついた」と言える環境がなかった
同じ部署にいる先輩女性も、表面上はうまく課長とやり取りしていた。
その姿を見て、「自分が未熟なのかも」「あの人は乗り切れているのに」と、ますます声をあげられなくなった。
職場のグループチャットでは、課長の冗談に皆が笑いのリアクションを送る。
私は既読をつけるだけで精一杯だった。
ある日、休憩室でその先輩に勇気を出して聞いてみた。
「…あの、課長の冗談って、気になりませんか?」
すると彼女は、苦笑しながら「まぁ、私も最初は戸惑ったけど…もう慣れたよ。波風立てても損するしね」と言った。
その一言で、「ここには本音を言える場所がない」と確信してしまった。
“慣れ”や“流す”ことが大人の対応。
それが、この職場での処世術だった。
メンタルの揺らぎが、仕事のミスへとつながっていく
次第に私は、集中力を欠くようになっていった。
会議中も、課長の何気ない言葉に神経をとがらせてしまい、話が頭に入ってこない。
雑務の手順を忘れたり、納期を勘違いしたり――それまでになかったミスが増えていった。
上司からの「最近、どうしたの?」という言葉にも、本当の理由を答えられなかった。
「すみません、気をつけます」とだけ答える日々。
でも内心では、「あなたのせいで」と叫びたかった。
言葉にすれば楽になるはずなのに、それを言えない空気が、さらに私を苦しめていた。
マイクロアグレッションは気づかれにくい“鈍器”だった
後から知った言葉だが、「マイクロアグレッション」という概念は、この体験そのものだった。
露骨な攻撃ではないけれど、日常的に繰り返される小さな“刺し言葉”。
それが積み重なることで、確実に人を傷つけ、追い詰めていく。
誰かに「それはセクハラだよ」と言われるようなものではないからこそ、深く刺さる。
加害者も、被害者も、その構造に気づかないまま進行する。
その“鈍さ”こそが、マイクロアグレッションの厄介なところだった。
私はそれに、確実に蝕まれていた。
勇気を出して伝えた言葉が、職場に起きた小さな“揺れ”を生んだ
自分のためではなく「これからの誰かのために」
ある金曜日の昼下がり、私はついに会社の「社内相談窓口」のチャットフォームにアクセスした。
そこには、「匿名での相談も可能です」と、ひとこと添えられていた。
匿名――
それは私にとって、心の鍵をひとつ外してくれる言葉だった。
直接、課長に訴えたいわけではない。
ただ、この“空気”が当たり前になっていることが、どうしても怖かった。
そして、「次に誰かが同じ思いをしてしまう前に」何か一歩を踏み出したかった。
相談フォームに綴った内容は、客観的な事実だけに絞った。
課長の発言の内容、タイミング、それによってどう感じたか――
すべて主観を排除して、事実として記述した。
送信ボタンを押した瞬間、心臓の鼓動が耳の奥に響いた。
“これで変わるわけじゃない”
そんな気持ちが大半だった。
でも、“何も言わなければ、何も変わらない”
その事実に、私はようやく向き合うことができた。
「全社研修」という形で返ってきた答え
週が明けて数日後、人事部から「全社対象のコンプライアンス研修」の案内が届いた。
内容は「マイクロアグレッションと職場のコミュニケーション」と記載されていた。
誰かが私の声を受け止めてくれたのかもしれない――そう思った。
でも同時に、「これで終わったわけじゃない」とも感じていた。
研修はオンラインで、講師は外部の専門家だった。
「悪気がないから許される」「本人が笑っていたから問題ない」
そうした“自己免責”の構造が、なぜ人を傷つけるのかを、実例とともに丁寧に解説してくれた。
特に印象に残ったのは、講師が言ったこの言葉だった。
「マイクロアグレッションとは、“相手を見下す意図はなかった”という自己正当化が、無自覚なまま人の尊厳を傷つける現象です」
私は画面越しに、涙が出そうになった。
ようやく、自分が感じてきた違和感に、名前がついた気がした。
課長の“変化”は突然には訪れなかった
研修後、すぐに課長の言動が劇的に変わったわけではない。
最初の数日は、相変わらず「〜ちゃん」「女の子っぽいね」といった言葉が飛び交っていた。
でも、明らかに“視線”は違っていた。
私の顔色をうかがうように、発言のあとに一瞬の間が生まれる。
そして少しずつ、私ではなく他のメンバーに対しても「名前+さん付け」で呼ぶ機会が増えていった。
私だけでなく、職場全体の“空気”が、少しずつ変わっていった。
その変化は、もしかしたら“研修による一時的な効果”なのかもしれない。
でも、その「一時的な揺れ」がなければ、変化の芽も生まれなかった。
人の価値観は、すぐには変わらない。
でも、“何かが違うかもしれない”という気づきを与えることは、できる。
それが、私があの日フォームに書いた言葉の、最初の成果だった。
「気づいてもらう」ことが、対話の第一歩になる
ある日、帰り際に課長が「お疲れさま、〇〇さん」と私の名字を初めて“さん付け”で呼んだ。
それまでの「〇〇ちゃん」とは明らかに異なる響きに、私は一瞬、言葉を失った。
それが“演技”だったとしてもよかった。
“誰かに言われたから”だったとしてもよかった。
大事なのは、「自分の言葉が、相手に届く可能性がある」と知れたことだった。
無意識の加害、無意識の被害――
その両方が、沈黙のまま繰り返されるのではなく、
言葉によって“見える化”され、対話のきっかけとなる。
「伝える」ことは怖いけれど、それでも伝えなければ何も変わらない。
私はそれを、あの日初めて知った。
マイクロアグレッションに気づいた職場が変わるまでのプロセスと学び
見えづらい加害と被害の構造を、構造として理解する必要性
今回の体験を通じて、最も強く感じたのは「ハラスメントとは明確な悪意だけで成り立つものではない」という事実だった。
マイクロアグレッションはその最たる例であり、本人が“悪気なく”口にしたひと言や態度が、継続的に相手の自尊心を傷つける。
この構造は、当事者ではない第三者からは特に見えづらく、「大げさに受け取りすぎでは?」「気にしすぎじゃないか」という反応を生みやすい。
しかし、問題の本質は「受け手の感受性」ではなく、「構造的な繰り返し」にある。
つまり、“毎回少しだけ違和感がある”“本人に言っても改善されない”という継続性・放置性こそが、被害者の心をすり減らしていく。
だからこそ、マイクロアグレッションは個人の資質の問題ではなく、職場の風土・コミュニケーションの型として見直すべき課題である。
これを「なんとなく嫌だった」「なんかモヤモヤした」ではなく、職場環境改善の対象として数値化・言語化していく取り組みが必要とされている。
企業が取るべき“予防”と“検知”のアクション
企業の人事部門、特にコンプライアンスやダイバーシティを担当する部門が注力すべきは、「問題が顕在化してから対応する」のではなく、
問題が“まだ声になっていない段階”で検知できる仕組みを持つことだ。
以下のような対策が、実行可能かつ有効とされている:
- 定期的な無記名アンケート(社内の雰囲気・言動に関する自由記述を含む)
- マイクロアグレッション事例を含む研修の定期開催
- 社内チャットでの即時・匿名報告システムの整備
- “指摘されたときの対応”についての上司向けマニュアルの整備
また、加害者とされる側へのアプローチとしても、「謝罪を強要する」のではなく、
「再発しないための行動」を共に設計することが建設的である。
多くの企業が「ハラスメント研修をしている」と口にするが、その内容が“パワハラ”や“セクハラ”の定義にとどまっている場合、
マイクロアグレッションのような“グレーゾーンの圧”を見逃す温床となりかねない。
つまり、明文化できない違和感を、どう組織として捉えるかが次のフェーズに求められている。
誰もが“加害者”にも“被害者”にもなりうる職場で必要なこと
マイクロアグレッションは、「意図しない差別」「無意識の偏見」が根底にある。
つまり、完璧に防ぐことは難しい。
だからこそ、「誰もが“加害者になってしまう可能性”を持っている」ことを前提とし、
**そのときにどう向き合い、どう修正できるかの“姿勢”**が問われる。
本記事の事例で登場した課長のように、本人が“気づかされる”経験を経て変化するケースは、決してレアではない。
問題は「気づく機会がなければ変わりようがない」ことにある。
だからこそ、“被害”を受けた側が声を上げるリスクを少しでも下げるために、
- 匿名性の担保
- 社内文化としての対話の推奨
- 見過ごしにくいルール整備
が必要であり、それらは被害者の“勇気”に依存しない持続的な仕組みとして設計されなければならない。
本記事は「誰かの苦しみを“冗談”にせず、見過ごさない職場」に向けた一つの記録だ。
たった一人の声が、組織の気づきを呼び、変化の連鎖が始まることがある。
その可能性を信じて、制度と対話の両輪で、“誰も泣き寝入りしない環境づくり”が求められている。