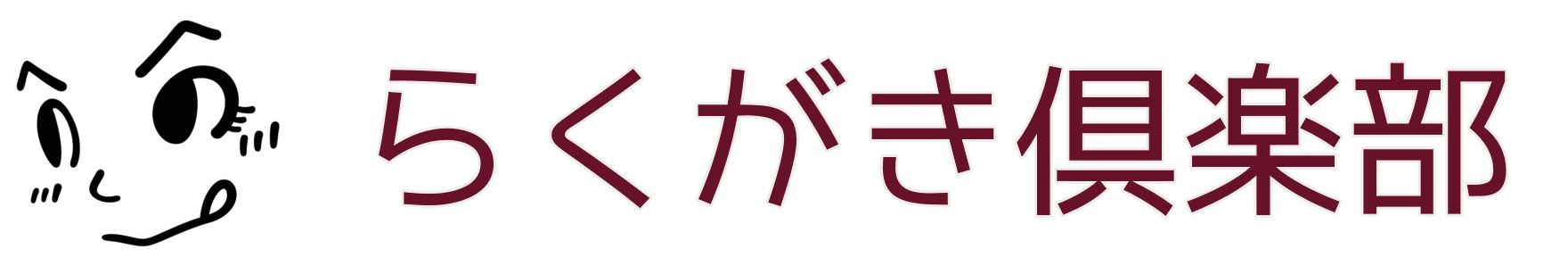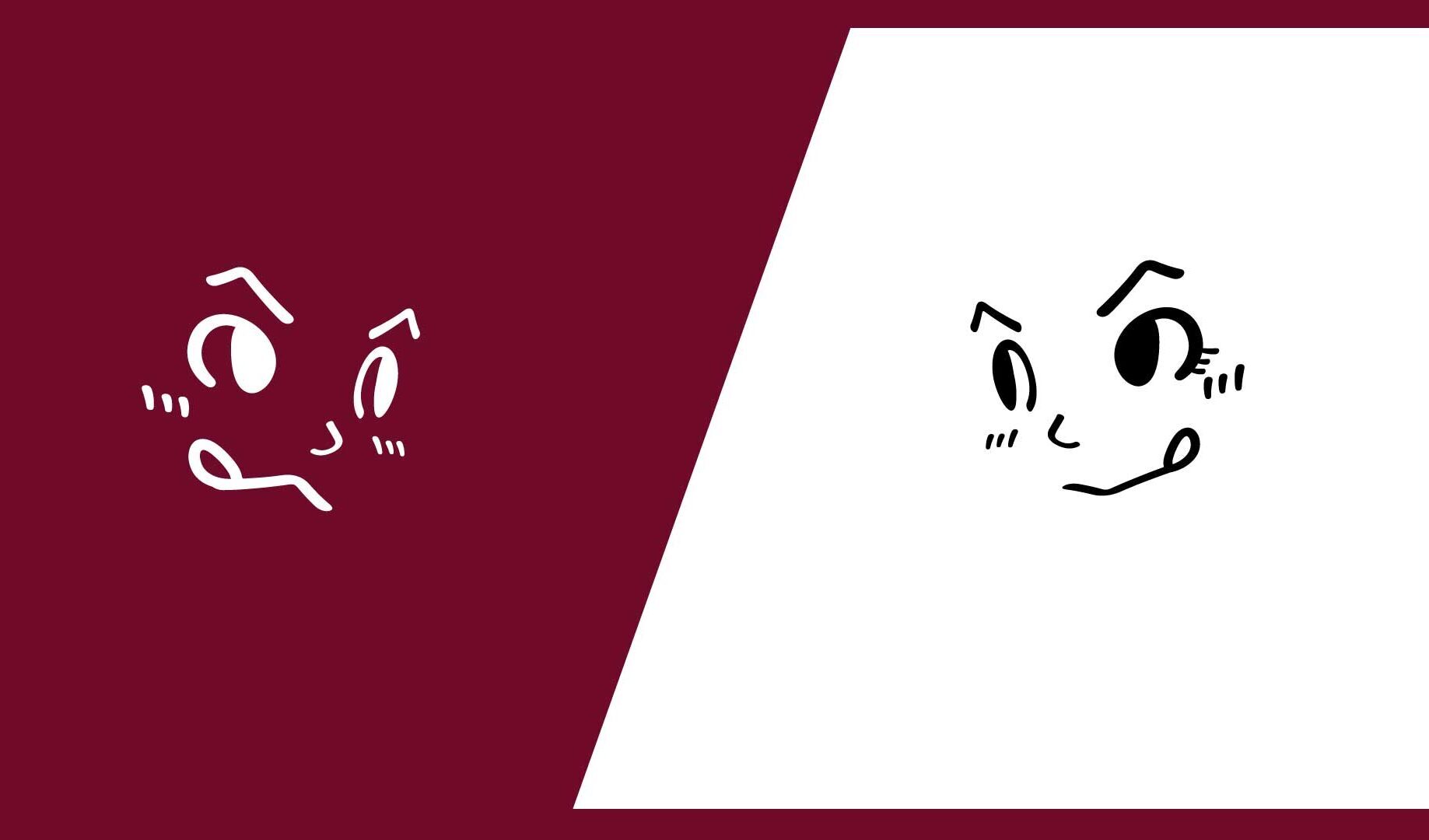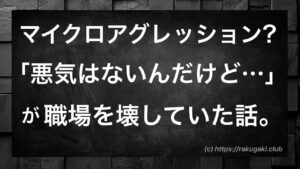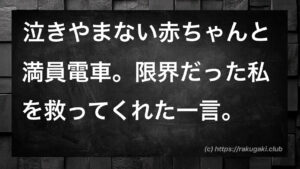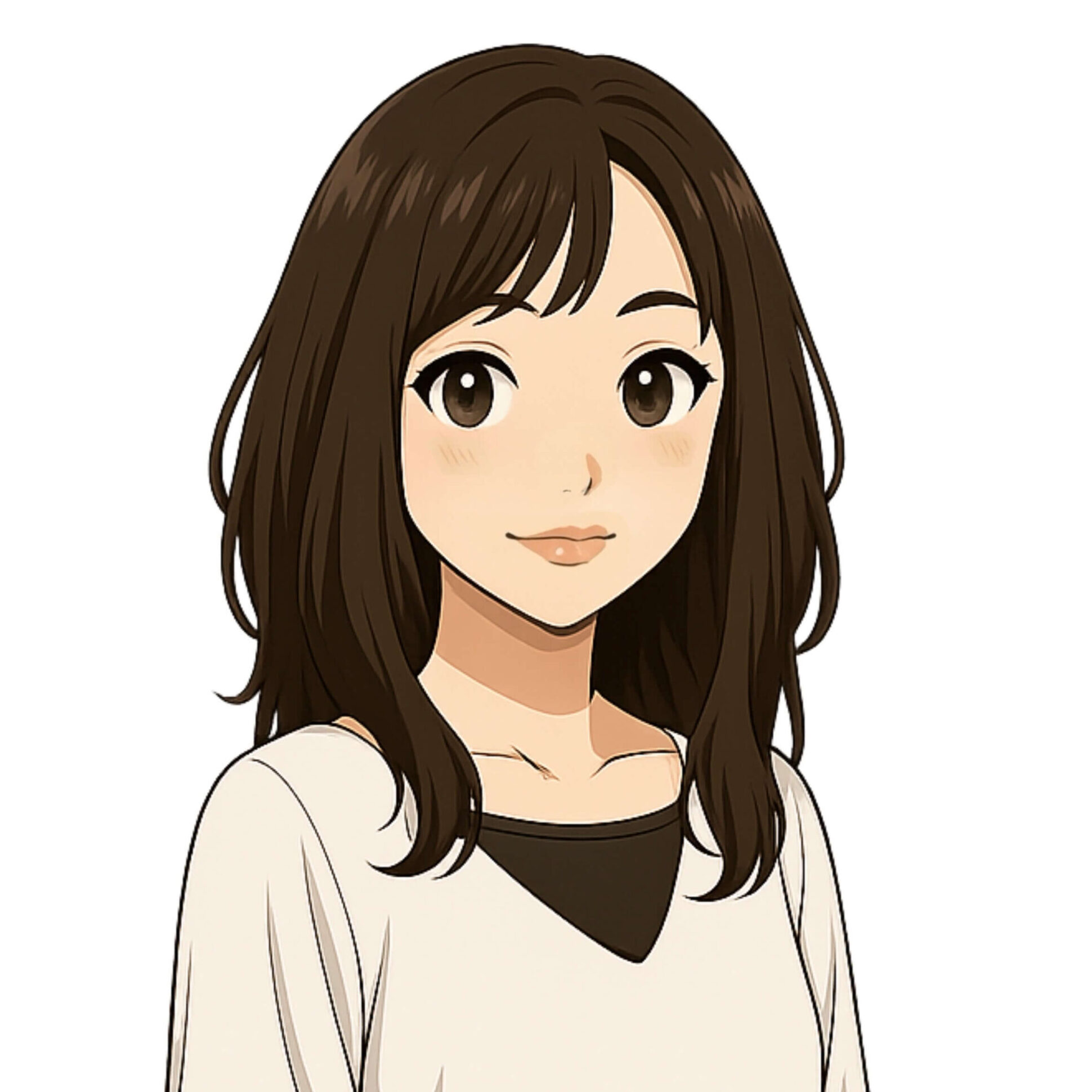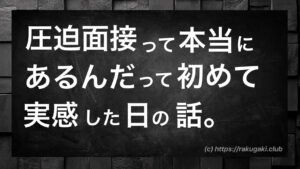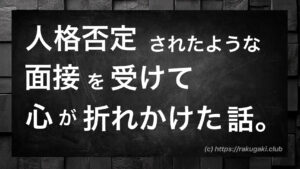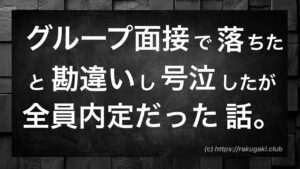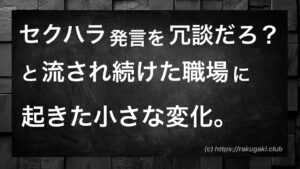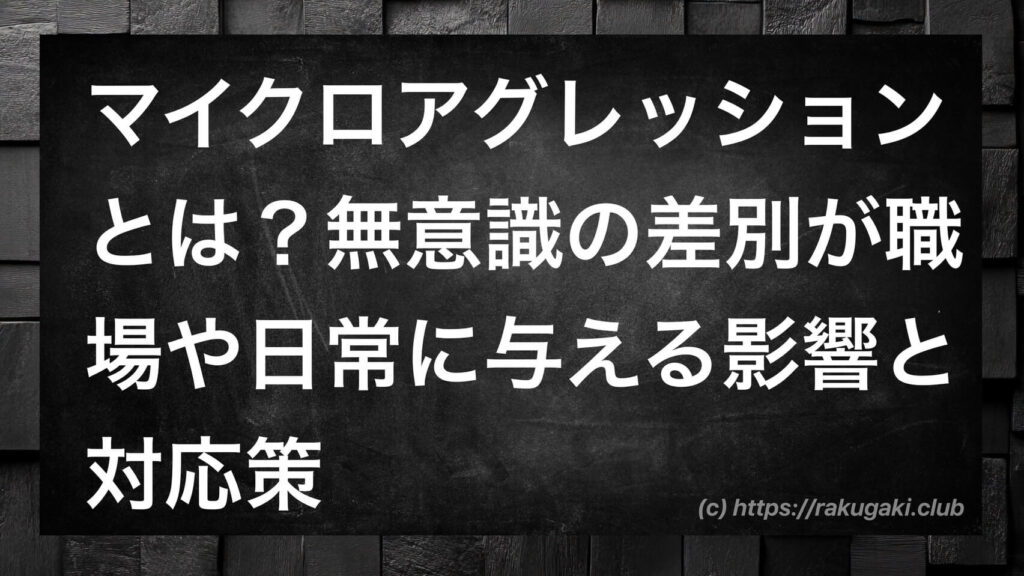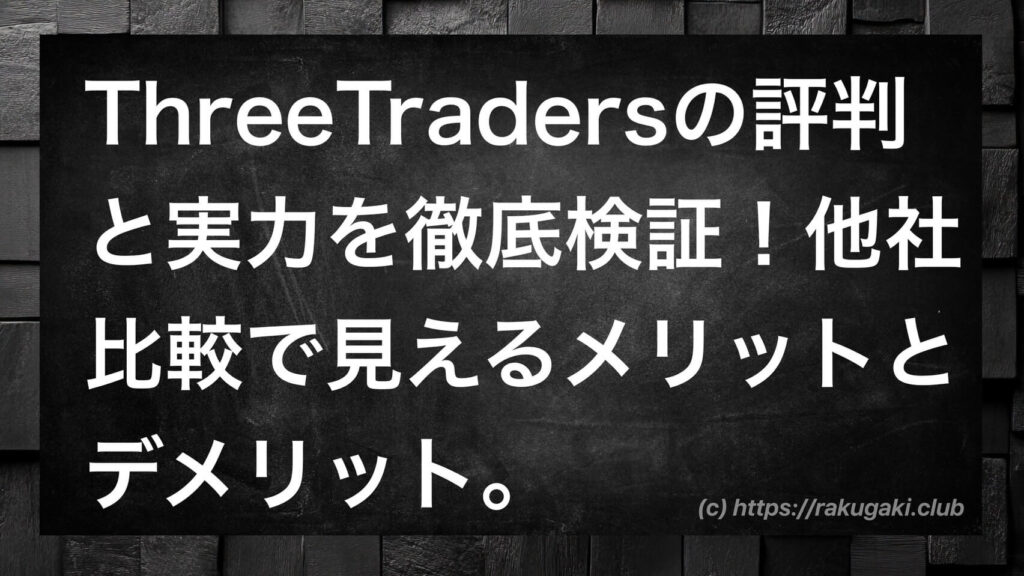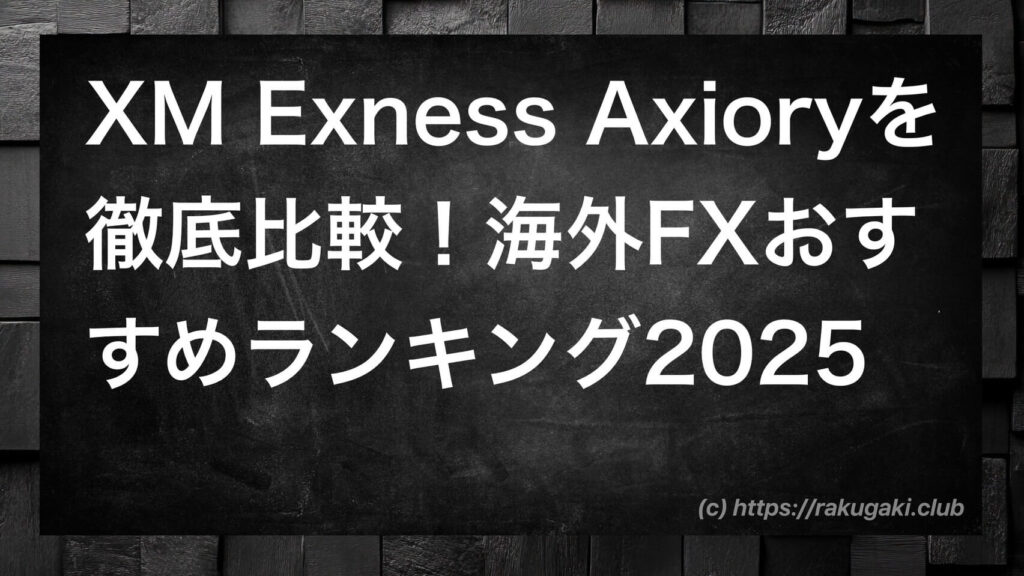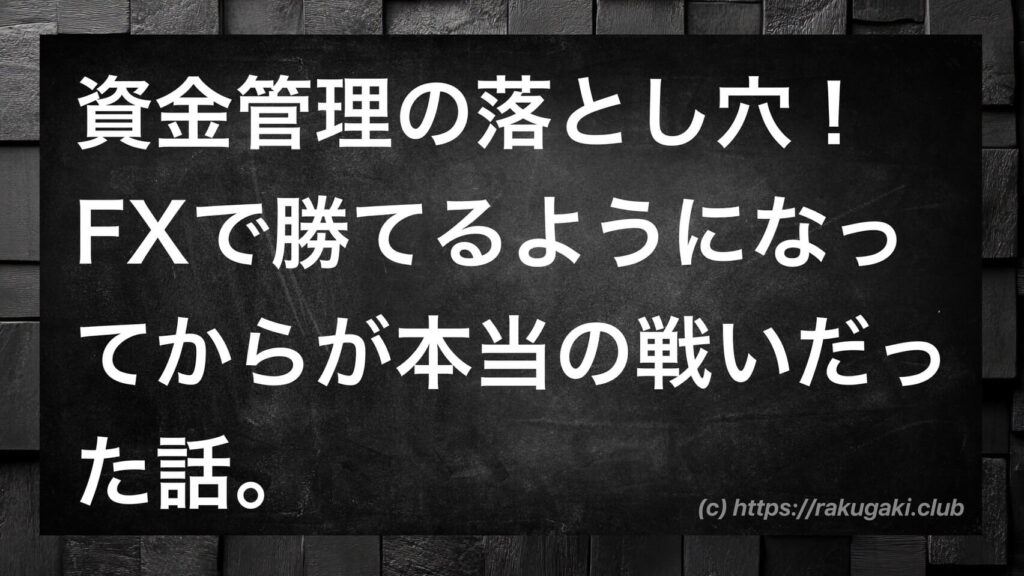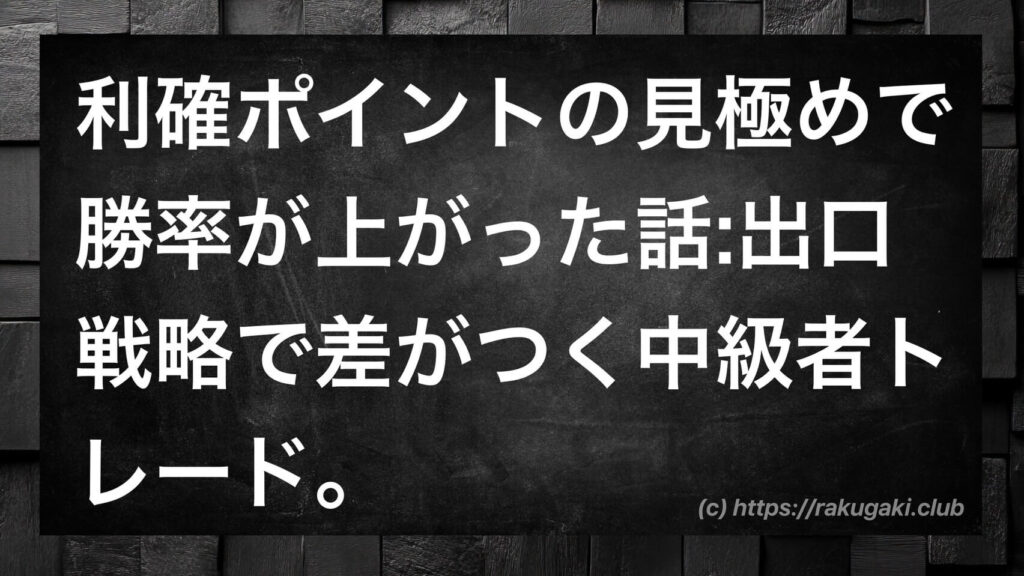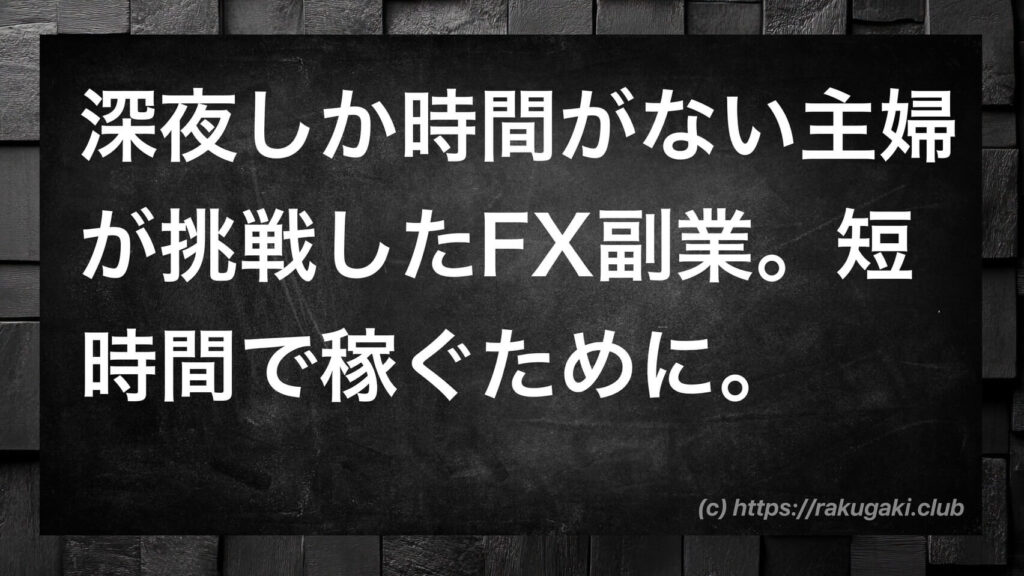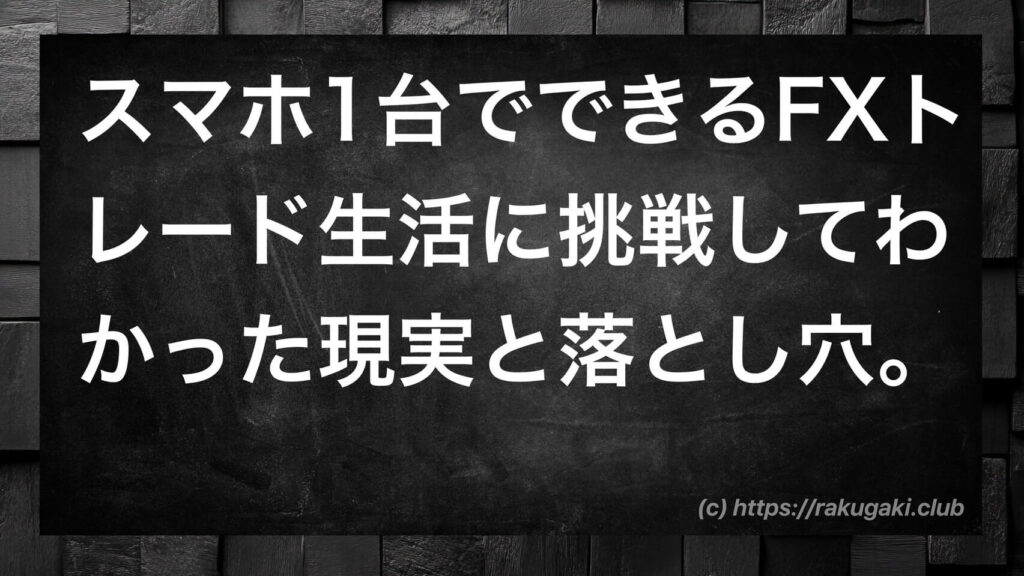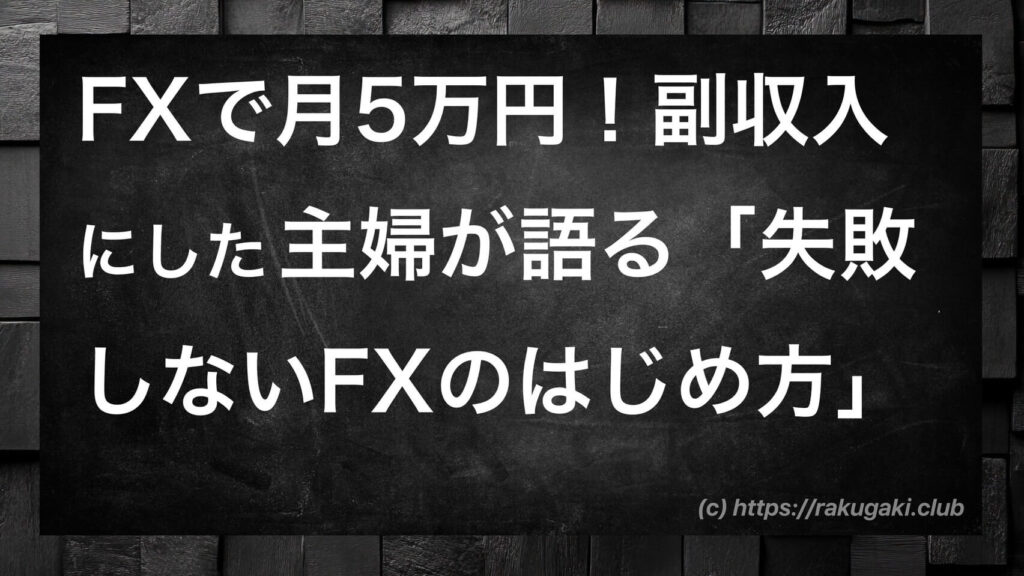新人指導のはずが、「ハラスメント呼ばわり」されてしまった
「ちょっとした指摘」がまさかの通報されちゃった
それは、いつもの朝礼が終わった直後だった。
部署内で私が指導役として見ていた新人のHさん(22歳・新卒)が、突然、上司の課長に付き添われながら私の席にやってきた。
そして、信じられない言葉を口にした。
「〇〇さんの言動で、精神的に強いストレスを受けたと感じています」
……正直、最初は何のことか分からなかった。
私は普段から部下を怒鳴ったり、感情的に詰めたりはしないタイプだ。
Hさんにも、業務ミスがあった際にはやや厳しく指導したことはあるが、それはあくまで“業務上の確認と是正”のつもりだった。
だが、Hさんは明らかに動揺していて、目もうつろだった。
課長からも「一旦、指導スタイルを見直してもらえないか」と告げられ、私はただただ言葉を失った。
思い返してみた「注意の瞬間」
事の発端は、おそらく前週のこと。
Hさんが取引先に送った請求書の送信ミスが発覚した。
その内容は金額の桁が一つ間違っており、先方に誤った請求がいってしまっていた。
私は慌てて先方に電話して謝罪し、訂正書類を即日送付。
一件落着したように見えたが、その後、Hさんには以下のように声をかけた。
「Hさん、請求書の作成は最終確認までしっかり見ないとダメだよ。今回は私が気づいたからよかったけど、金額のミスは信頼に関わるから。次は注意してね」
これだけの話だった。
「大声で怒鳴った」わけでも、「人格を否定した」わけでもない。
だが、Hさんにとってはそれが強い“プレッシャー”だったのかもしれない。
指導者側の常識と、新人世代のギャップ
私は40代半ば。いわゆる「厳しくされて育ってきた世代」だ。
「仕事で怒られるのは当たり前」
「失敗は責任を持って次に活かせ」
「新人は、まずメモを取って覚えろ」
こうした“社会人の基本”を、若い頃は当然のように受け入れてきた。
実際、そうやって鍛えられた経験が、いまの自分の土台になっていると思っている。
だが、HさんたちのようなZ世代と呼ばれる若者たちは、「怒られる」「注意される」という経験そのものに過敏だ。
指摘の仕方がフラットであっても、「攻撃された」と受け取る人もいる。
もちろん全員ではない。
だが、「厳しさ=愛」だった時代の価値観が、いまでは通用しないことも多い。
このギャップこそが、指導とハラスメントの境界を曖昧にし、
指導する側を“加害者”にしてしまうのだ。
相談先がないという“孤独”
Hさんとの一件のあと、私は数日間、会社に行くのが憂鬱だった。
上司に詳しい状況を話しても、「最近は難しいからね」と苦笑いで済まされる。
同僚に軽く相談しても、「俺も似たようなことあったよ、気にすんな」で終わる。
誰も「自分が責められる側になった」状況について、真剣には捉えていないように思えた。
——私は何か間違ったことをしたのだろうか?
——それとも、いまの世の中が変わっただけなのか?
——でも、言わなきゃまた同じミスをするのでは?
そんな葛藤をひとり抱え続けるうちに、「指導すること自体が怖い」と感じるようになっていた。
それでも“言うべきことは言わなければ”と思った理由
社内で指導係に抜擢されたとき、私は強く責任を感じていた。
「後輩を守るのは、自分しかいない」
「自分が仕事の基礎を教えなきゃ、誰がやるんだ」
そんな気持ちで、メモの取り方からメールの文面、電話対応の作法まで細かく教えてきた。
もちろん、時には厳しいことも言った。
だが、それは“意地悪”ではなく、“育てるため”だった。
だからこそ、Hさんからの申し出と「ハラスメント」という言葉に、私は深く傷ついたのだと思う。
それでも──私は指導をやめなかった。
なぜなら、「言わなかったことで後悔する未来」の方が怖かったから。
後輩の成長の機会を奪い、職場に不安が残ることの方が、はるかに大きな問題になると考えたからだ。
この出来事は、私の働き方、教え方、伝え方をすべて見直すきっかけになった。
「正しく伝える」とはどういうことか?
「言葉で人を動かす」とはどういうことか?
そして、「誤解されない指導」とは何を意味するのか?
次のセクションでは、私が実際にとった行動、社内で起きた変化、そしてHさんとの再接点についてお伝えしていく。
指導か?ハラスメントか?迷いながらも伝えた“その先”で
上司への相談と、社内での方針確認
Hさんからの「精神的ストレスを感じた」という申し出を受け、私は自分なりに動き出した。
最初に行ったのは、直属の上司である課長との1対1の面談の場を設けてもらうことだった。
私はこれまでのやりとりをすべて振り返りながら、
・注意の内容は業務ミスに対するものであること
・声を荒らげたことも、否定的な人格攻撃もなかったこと
・むしろ指導として必要なやりとりだったという認識であること
を冷静に伝えた。
課長は「〇〇さんの意図はわかる」と言いつつも、今の会社が推進する「ハラスメント防止ガイドライン」に照らし合わせると、
「受け取る側がどう感じたかを重視する姿勢に変わってきている」と話した。
つまり、言った側の“意図”よりも、受け取った側の“感情”のほうが重視される。
その瞬間、私は納得と戸惑いがないまぜになった。
確かに、職場の安全性や多様性を尊重する流れとしては当然だと思う。
しかし一方で、それは“指導ができない職場”にもつながりかねないと危機感を覚えた。
ハラスメント研修の中に見えた“ヒント”
後日、偶然にも社内で「職場のハラスメント対策」研修が開催された。
全社員対象であり、パワハラ・セクハラ・マタハラなどの定義と事例が共有された。
その中で、私がとくに心に留まったのが「マイクロアグレッション」という言葉だった。
これは、無意識の偏見や些細な発言・行動が、相手にとってストレスや屈辱となることを指す。
たとえば、
- 「このくらい、普通にできるよね?」
- 「やる気ある?」
- 「若いんだから吸収早いでしょ」
など、悪意なく発せられた一言でも、相手の自己肯定感を削ってしまう可能性があるという。
——ああ、自分も無意識にこういう言い方をしてしまっていたかもしれない。
そう思った瞬間、私はようやく“自分ごと”としてHさんの感じた苦しさを想像できた。
それは「自分は悪くない」と思い込もうとしていた心の姿勢に対する、最初の崩れでもあった。
再度Hさんに向き合う決意
ある程度冷却期間をおいてから、私は上司の同席を得てHさんとの面談を希望した。
一方的に弁明するつもりはなかった。むしろ、何が辛かったのかを素直に聞きたかった。
Hさんは少し戸惑いながらも、こう話してくれた。
「〇〇さんの言っていることは正論だと分かっていました。でも、いつも“できてない”って見られているようで、呼吸が浅くなるんです」
その言葉を聞いて、ようやく腑に落ちた。
私は“論理”で伝えていたが、Hさんは“感情”で受け取っていたのだ。
私は“全体像”で注意していたが、Hさんは“一言一句”に傷ついていたのだ。
だから私は、こう答えた。
「ごめんね。ちゃんと伝えたいと思っていたけど、伝え方に無神経だった。これからは、できたことにも目を向けて、言葉を選んで伝えていくようにするね」
Hさんは軽くうなずいていた。
和解というほど劇的な場面ではなかったけれど、“指導”が“対話”に変わった瞬間だったと思う。
言葉を変えれば、職場の空気も変わる
その後、私は指導方法を大きく見直した。
以下は、私が実際に取り入れた具体的な方法だ。
- 1:ポジティブフィードバックを必ず入れる
指摘の前に「良かった点」を一言でも添える。例:「昨日の対応、とても丁寧だったね。その上で…」 - 2:業務ミスは“事実ベース”で伝える
「こういうことが起きたよね。それについて確認したいんだけど…」という伝え方に変更。 - 3:質問形式で気づきを促す
「この場合、何が原因だったと思う?」と尋ねてから、一緒に振り返る。 - 4:伝えるタイミングを調整する
全体が慌ただしい時間帯ではなく、少し落ち着いた場面で静かに話す。
この4つだけでも、職場の雰囲気は大きく変わった。
「注意された」という感覚が薄れ、「学びとして受け取れた」という声が出てきた。
指導者に求められる“スキルのアップデート”
ここで気づいたのは、私自身が“古い指導法”をアップデートできていなかったという事実だ。
・上から目線で言ってしまう
・焦りや苛立ちが口調に出てしまう
・「自分の若いころは…」と比較してしまう
これらは意図せずとも、新人にとっては「圧」になり、信頼を失う要因となる。
一方で、今の時代には“共感ベース”のコミュニケーションが求められている。
正論より、対話。経験談より、対等な立場での共有。
それが、指導における“信頼関係のベース”になると実感した。
次のセクションでは、この経験を通じて見えてきた「上司や組織が果たすべき役割」や、
「もしあなたが同じ状況に直面したらどう対応すべきか」について、より実践的に深掘りしていきます。
「誤解されたくない」と思うほど、誤解は深まっていった
自分の“正しさ”にすがる危うさ
Hさんから「注意の仕方がきつい」「精神的につらい」と言われたあの日から、私は数日間、自分の中で整理がつかない感情を抱えていた。
確かに、厳しいことを言った自覚はある。でも、業務を滞りなく進めるために必要なことで、決して怒鳴ったり、叱責したりしたわけではない。
むしろ私は、「丁寧に伝えたはず」とすら思っていた。
でも、それは“私の基準”での話だったのだ。
「自分は正しいことを言った」と思えば思うほど、「なぜ通じなかったのか?」という疑問ばかりが大きくなり、Hさんに対する苛立ちも湧いてくる。
その感情をもってしまうことに対して、自己嫌悪もあった。
——あれは本当に“指導”だったのだろうか?
——ただの“正論押しつけ”になっていなかったか?
そんな問いが頭のなかをぐるぐると回る。
“伝えたこと”と“伝わったこと”のギャップは、こんなにも深いのかと痛感した瞬間だった。
Hさんとのすれ違いの本質は「安心感の欠如」だった
ある日の帰り道、ふと自分のメモ帳を見返していたら、
新人だった頃の自分が書いた「先輩に言われてショックだった言葉メモ」が出てきた。
- 「まだ分かんないの?これ何度目?」
- 「ちょっと常識なさすぎるんじゃない?」
- 「自分で考えて動いてよ」
——これ、自分が今Hさんに言ってた言葉と、似てないか?
ぞっとした。
当時、私が感じたのは「怖い」「相談しづらい」「私はダメな人間なんだ」という自己否定だった。
そう、Hさんも、同じような“安心感の欠如”を感じていたのではないか。
それは“正しさ”とはまったく別の次元の話だった。
私は、相手の視点や心の状態に無頓着なまま、
「伝え方」ではなく「伝えた内容」にばかり意識を向けていたのだ。
自分の「無意識バイアス」に向き合うということ
その後、社内のオンライン研修で「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」について学ぶ機会があった。
- 「このくらい分かるでしょ?」と思ってしまう認知
- 「自分は怒っていないから問題ない」と思い込む態度
- 「昔はもっと厳しかった」と過去基準を押しつける発想
こういった“無意識の当たり前”が、知らず知らずのうちに職場の空気を重くし、指導を受ける側の心を圧迫していく。
Hさんのことだけではなく、今までの新人たちに対しても、自分がどんな無意識バイアスを持っていたかを振り返った。
そして気づいたのは、「私は善意のつもりでも、相手がそう感じるとは限らない」という当たり前の事実だった。
社内における“指導の場づくり”を変えていく
私は一連の経験を経て、チーム内の指導体制にも働きかけを行った。
1:新人向けアンケートの実施
業務面だけでなく、「メンタル面の不安」や「質問しづらさ」についても自由に書ける匿名アンケートを実施。
これにより、表には出てこなかった“職場の空気”に関する意見や感情が少しずつ見えてきた。
2:フィードバック文化の導入
上司が部下にだけでなく、部下から上司にも「フィードバック」できる場をつくった。
これは心理的安全性の確保に役立ち、指導者側の自省にもつながった。
3:ロールプレイ研修の試験導入
「言い方によって受け取り方がどう変わるか」を学ぶロールプレイ研修を、小規模チーム単位で実施。
“気づかぬハラスメント”に対する理解が深まり、職場全体のコミュニケーションが少しずつ滑らかになっていった。
それでも、100%伝わることはない
Hさんとは、数ヶ月後にようやく「今の指導はすごく分かりやすかった」と言ってもらえる日が来た。
それでも私は、過去の失敗を忘れないようにしている。
なぜなら、どれだけ気をつけても、100%相手に正しく伝わることなんてないと知ってしまったからだ。
でも、それを怖がって黙ってしまうのではなく、
「どうすれば誤解されにくいか」
「どうすれば傷つけずに伝えられるか」
を考え続けることが、これからの“指導”には必要なのだと思う。
「叱る」より「支える」へ
私は今、「叱る人」ではなく「支える人」になりたいと思っている。
その方がチームの成長が早いし、何より働く一人ひとりが「ここにいていいんだ」と思える職場の空気になる。
そして、指導者である自分自身もまた、メンバーから支えられていることを実感できるようになる。
誰かを育てることは、自分を育て直すことでもある——
それは、Hさんとの一件が教えてくれた最大の教訓だった。
「伝えたつもり」では済まされない、指導者としての責任
「正論」が通用しない現実と向き合う
指導というのは、正しいことを言えば通じる——
そう思っていた頃の私は、まるで“伝えること”にしか意識が向いていなかった。
だが現実には、「正論」でさえも拒絶されることがある。
ある日、Hさんがミスを繰り返していた報告書のフォーマット。
私は時間を取ってマンツーマンで説明し、
「なぜその順番で入力すべきか」「なぜその文言が重要なのか」を丁寧に伝えた。
その日のうちに改善が見られ、「よかった」と思ったのも束の間。
数日後、また同じミスが繰り返されていた。
理由を聞くと、「言われた通りにやったけど、やっぱりしっくりこなかったから、前のやり方に戻した」とのこと。
私は内心、呆れた。
「言われた通りにやってダメなら相談すべきだろう」
「それが社会人の常識じゃないのか?」
でも、その“常識”は、自分が勝手に信じてきたルールだったと気づくのに、少し時間がかかった。
指導の目的は「納得」ではなく「定着」
指導者として、自分の役割は何か?
それは、“納得”させることでも、“理解”させることでもない。
ましてや、“言い負かす”ことでもない。
最終的な目的は、「業務として定着させること」であり、
言葉のやり取り以上に、「行動が変わる」ことがゴールなのだ。
そのために必要なのは、
- 一度で伝わらないことを前提に構えること
- 同じ説明を“伝え方を変えて”繰り返すこと
- 「伝わっていないかもしれない」を受け入れること
つまり、“伝えたつもり”を手放す勇気が、指導者には不可欠なのだと知った。
一人では抱えない。「報連相」のあり方も見直した
Hさんとの関係は、少しずつ改善しつつも、どこか緊張感をはらんでいた。
私の伝え方に敏感に反応することもあれば、
逆に「放っておかれている」と感じる場面もあったらしく、チームリーダーとしての立ち位置に悩むことが多くなっていた。
そんなとき、上司が「報告はチームで共有して、指導内容も記録しておこう」と提案してくれた。
その日から、指導した内容・タイミング・相手の反応を簡潔に記録し、
他の教育係とも共有するようにした。
すると、それまで“私とHさんだけ”だった関係性が、
チームとしての支援構造に変わっていった。
「指導=個人間のやり取り」ではなく、
「指導=職場全体で支えるプロセス」になっていったのだ。
部署内で起きた「逆ギレ事件」の再来
ある日、別の新人スタッフが「○○さんに怒鳴られました」とチームチャットで投稿した。
当のAさんはまったく怒鳴っておらず、トーンをやや強めにしただけだったという。
そのやり取りを見ていたメンバーの一人が呟いた。
「もう、“怒鳴った”かどうかじゃないんだよね。“怒鳴られたと感じた”かどうかなんだよ」
まさにそれが、私がHさんとの間で体験した「ハラスメントと感じた側のリアル」だった。
誰かにとっては普通の指導も、
他の誰かにとっては「攻撃的」「人格否定」と受け取られる。
この“温度差”を埋めるには、
- 周囲との情報共有
- 指導プロセスの見える化
- 「気になることは話していい」という空気作り
といった、“組織としての土台”が不可欠だ。
心をすり減らさない「距離感」の大切さ
指導に真面目に向き合おうとすればするほど、傷つくこともある。
- 伝え方を反省しても、相手には響かない
- 自分なりに努力しても、報われないと感じる
- 相手のためを思ったのに、「怖い」と言われる
こんなことが続けば、誰だって心が折れる。
私も、もう二度と新人担当をやりたくないと思ったことがある。
でも、そこで気づいたのは、「相手の成長を“自分の責任”にしない」ことの大切さだった。
成長は本人のものであり、
指導者はあくまで“きっかけ”を与える立場だ。
そのために、適切な距離を取り、
相手に干渉しすぎず、自分も疲弊しない関わり方を選ぶようにしていった。
ハラスメントのグレーゾーンに立たされる人へ
パワハラ、マイクロアグレッション、無意識のバイアス——
私たちが気づかぬうちに加害者になり得るこの時代。
だからこそ、「伝える技術」や「感情の調整力」は、
職場における“専門スキル”としてもっと認識されるべきだと思う。
もし、今、誰かとの関係に悩んでいるなら、
まずは「自分の正しさ」から少し離れてみてほしい。
「なぜ伝わらない?」の前に、
「どうしたら伝えやすい空気になる?」を考えることで、
あなたの指導力はきっと変わる。
上司から部下へ。伝え方より支え方を整える組織へ
パワハラと言われないために「何を変えるべきか」
「伝えたのに伝わらなかった」
「正しい指導が“ハラスメント”と誤解された」
こうした状況を、個人の反省や努力だけで解決するのは難しい。
むしろ、現場に求められるのは“個人任せ”ではなく、指導の設計そのものを見直す仕組みづくりである。
たとえば、以下のような対策が現場で機能しやすい。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指導履歴の記録 | 指導日時・内容・相手の反応を簡単に残す(ExcelやNotion等) |
| 指導方針の可視化 | チーム内で「共通の言い回し」や「対応の順序」を統一 |
| 感情のトーンガイド | 「強めに言うときの目安」「静かに伝えるべき事項」をあらかじめ定義 |
| 上司・第三者との連携 | 一対一ではなく、観察・フォロー可能な第三者を含むようにする |
| 定期的なフォロー面談 | フィードバックを受ける場を新人にも指導者にも提供する |
これらを実施すれば、「感情的に言った/言われた」といった曖昧な指摘ではなく、
行動ベースでの改善と対話ができるようになる。
「パワハラをしない」より「パワハラと受け取られない」環境づくり
現代の職場で求められるのは、「意図がなければOK」という時代からの脱却である。
つまり、“加害の意図”がなくても、受け手が不快であれば、それはハラスメントになる。
この考え方に基づき、以下のような点を意識して設計するとよい。
1. 主観のズレを埋める視点
- 「自分は怒っていない」は通用しない
- 「相手がどう感じたか」を都度確認する姿勢が大切
2. “口頭注意”より“構造化された対話”
- 「改善してね」だけでなく、「なにを」「なぜ」「どうやって」を文書化
- 対話型マネジメントの導入(チャットログの活用など)
3. 「指導者育成」が人材開発の要になる
- 新人研修だけでなく、「中堅への指導法研修」を制度化
- ハラスメント事例をケーススタディ化し、予防学習へ活用
「気づく」「認める」「共有する」のサイクルを
個人レベルでできることもある。
- 自分が使っている言葉に、攻撃的なニュアンスが含まれていないか
- 相手の立場や感受性を無視したコミュニケーションになっていないか
- 気づいた違和感を「なかったこと」にせず、小さく共有していくか
特に最後の「共有」こそ、ハラスメントを未然に防ぐ最大の防波堤である。
「気のせいかも」と思う程度の違和感ほど、最初に声をあげづらい。
だからこそ、チームで“違和感を歓迎する土壌”を育てる必要がある。
指導とハラスメントの境界線を曖昧にしないために
「正しさ」だけでは、人は動かない。
「善意」だけでも、人を傷つけることがある。
だからこそ、私たちは**“伝える側の責任”を持ちながらも、“相手が受け取りやすい環境”を整える努力**が求められる。
それは決して、「言いたいことを言えなくなる」ことではない。
むしろ、「どうすればちゃんと伝わるのか」を工夫し、
「何をサポートすれば定着するか」を考えることこそが、真の指導力であり、
これからの組織に必要なコミュニケーション文化なのだと実感している。