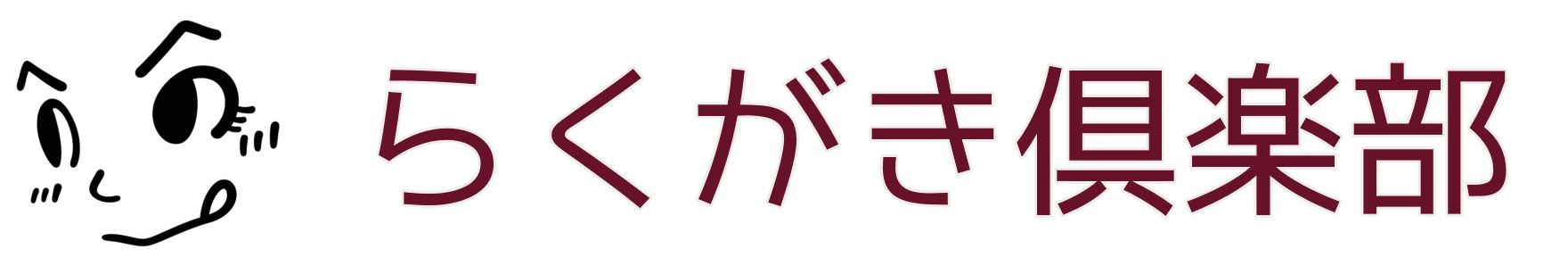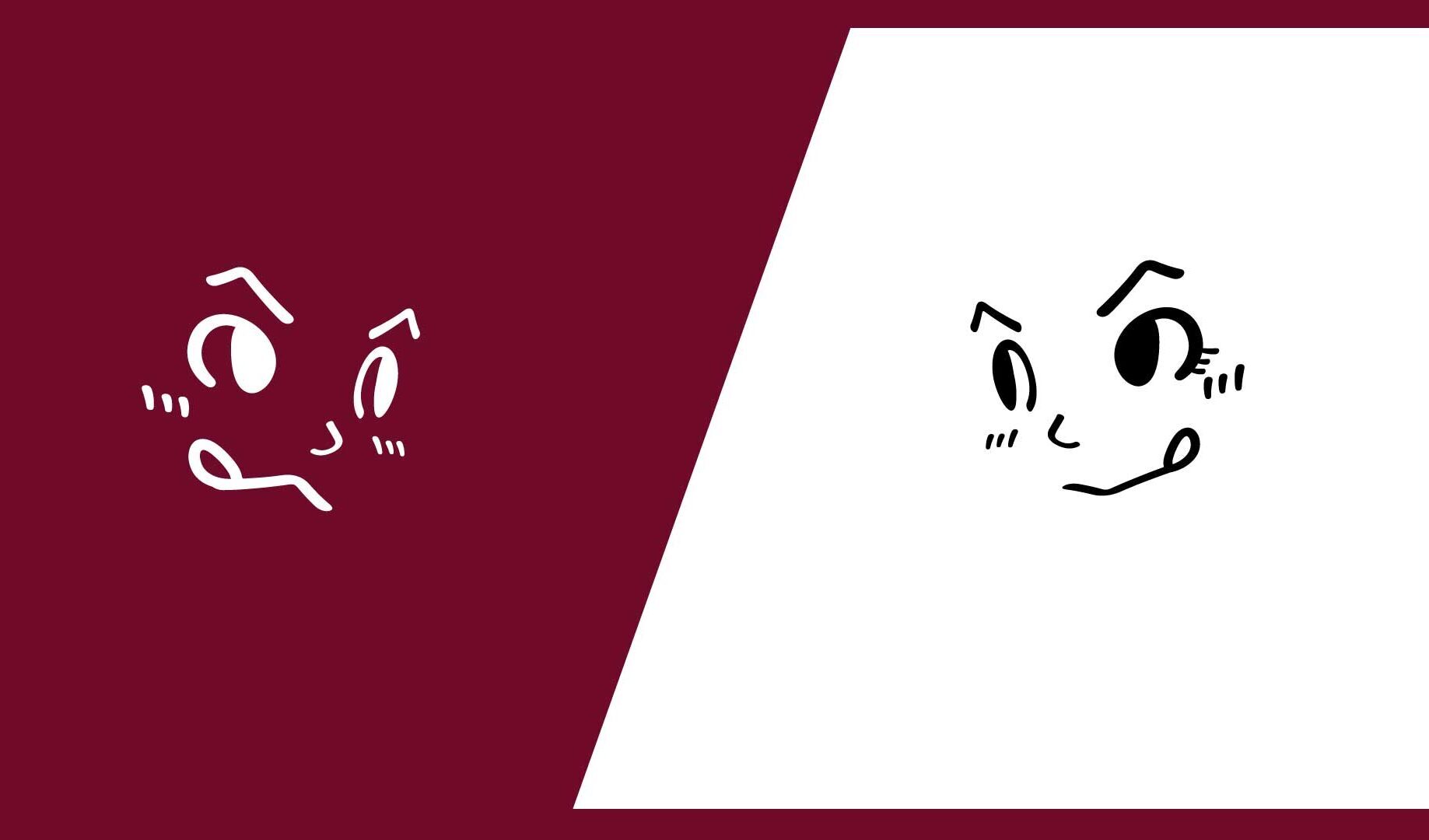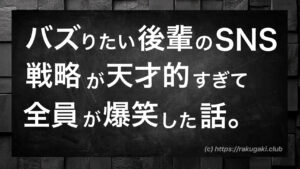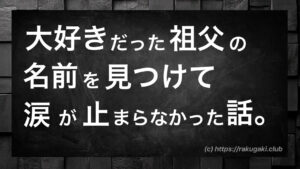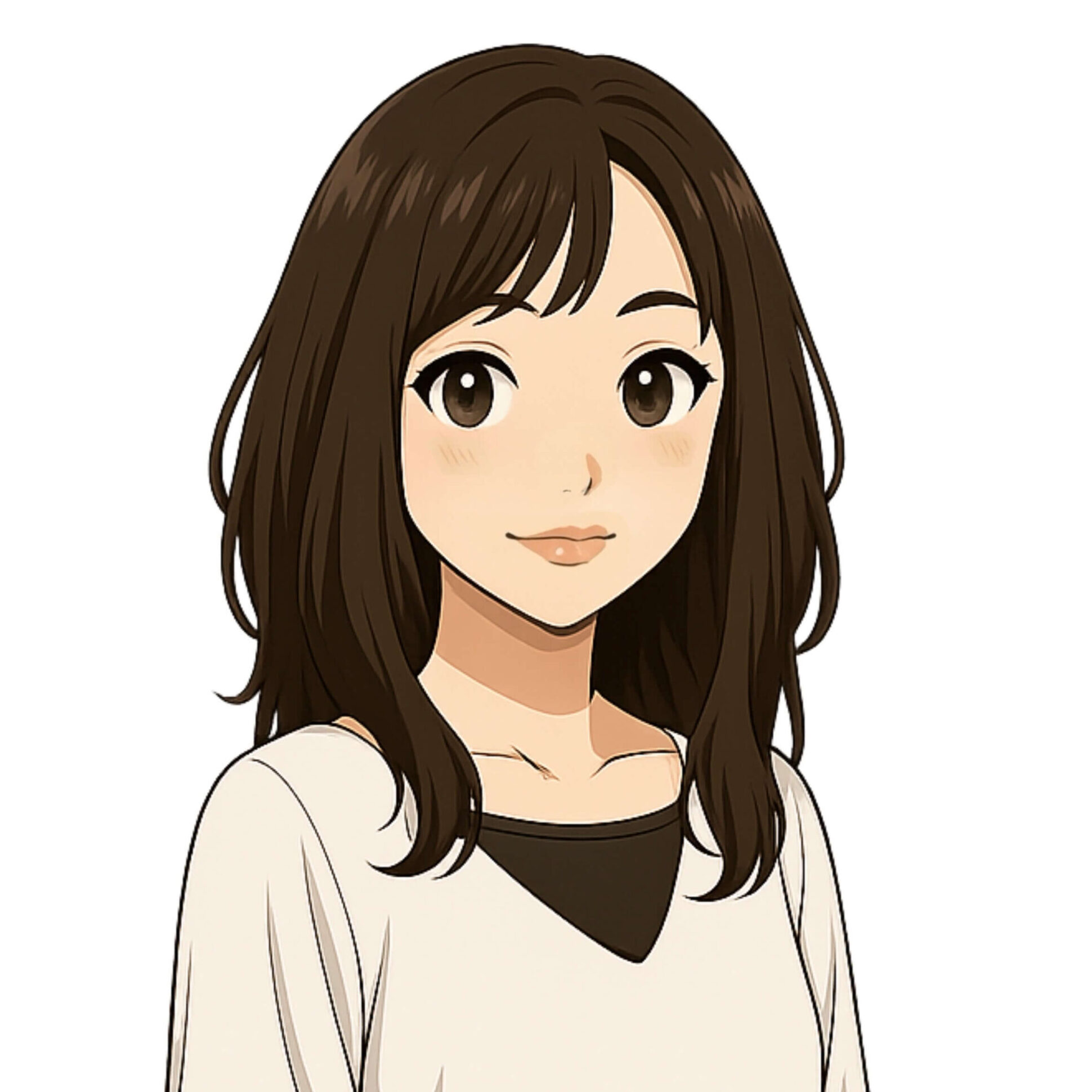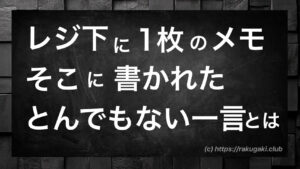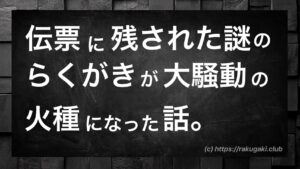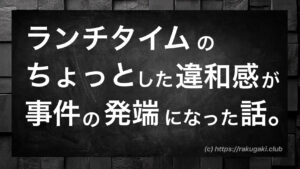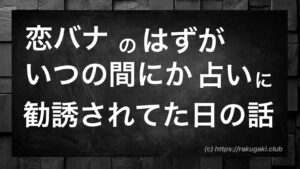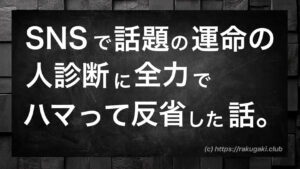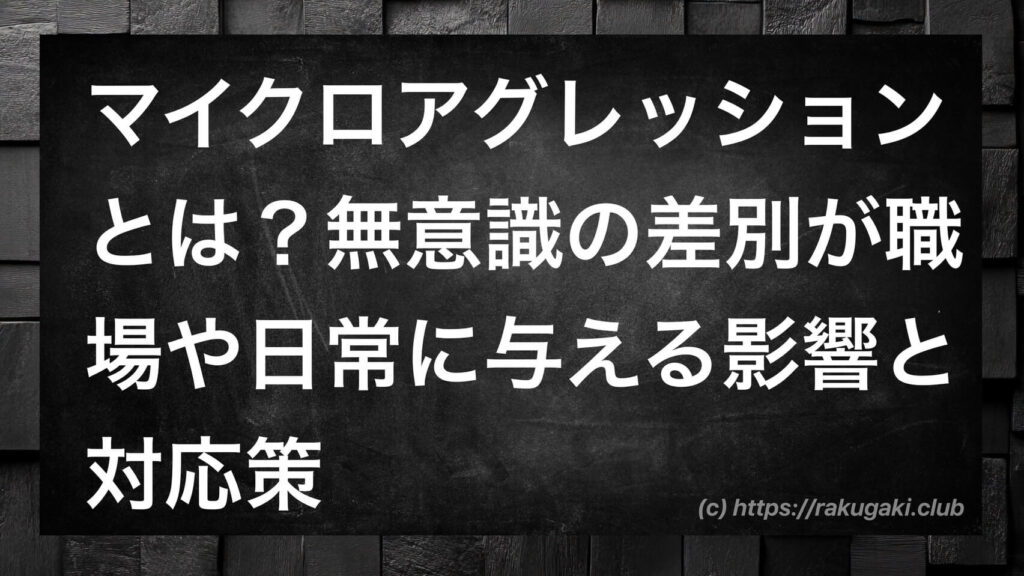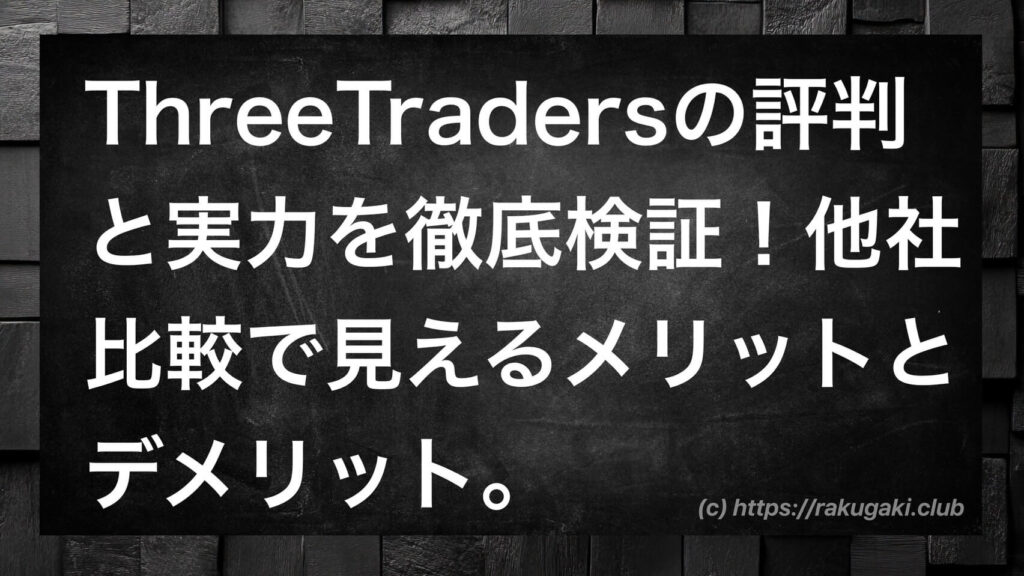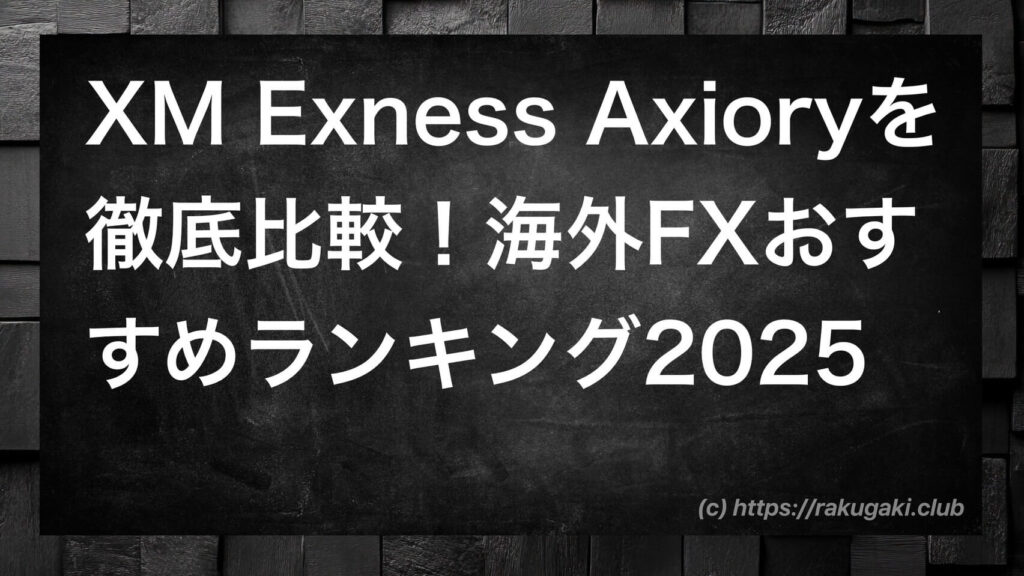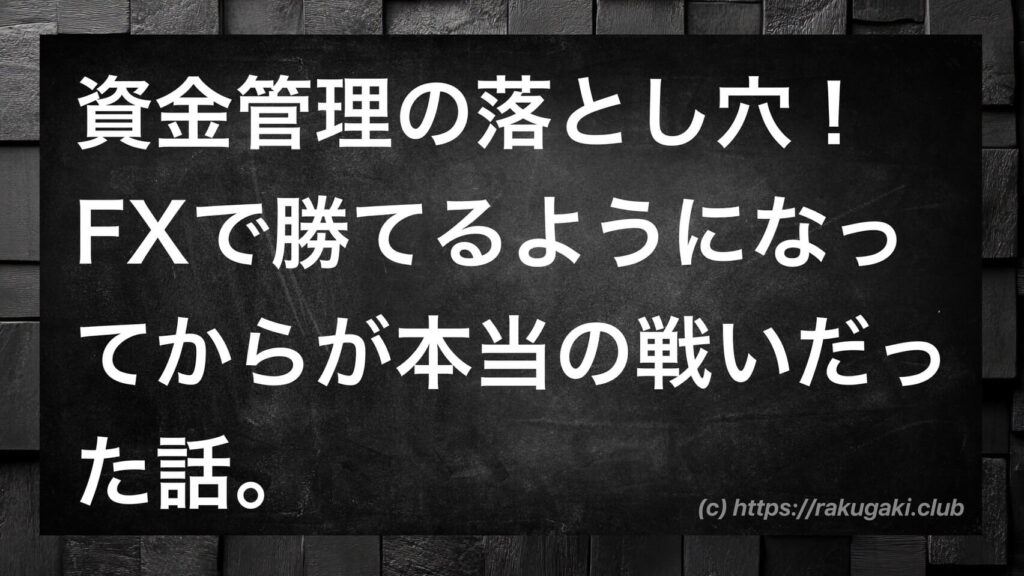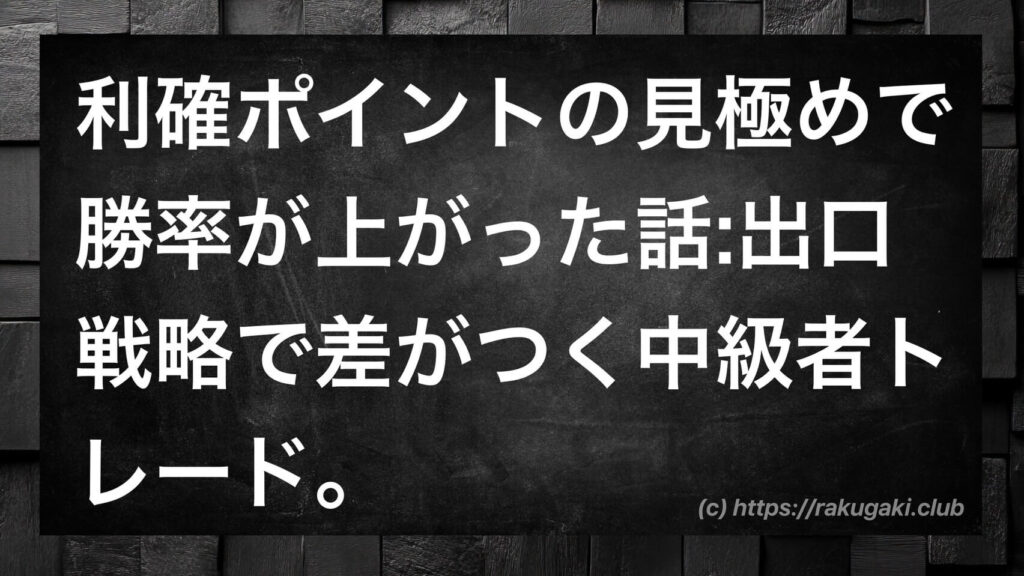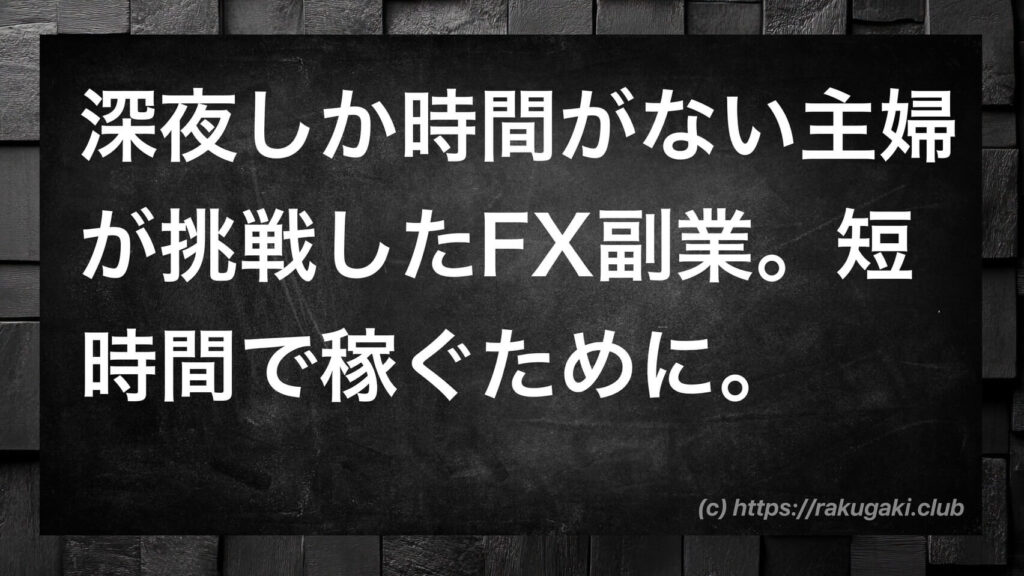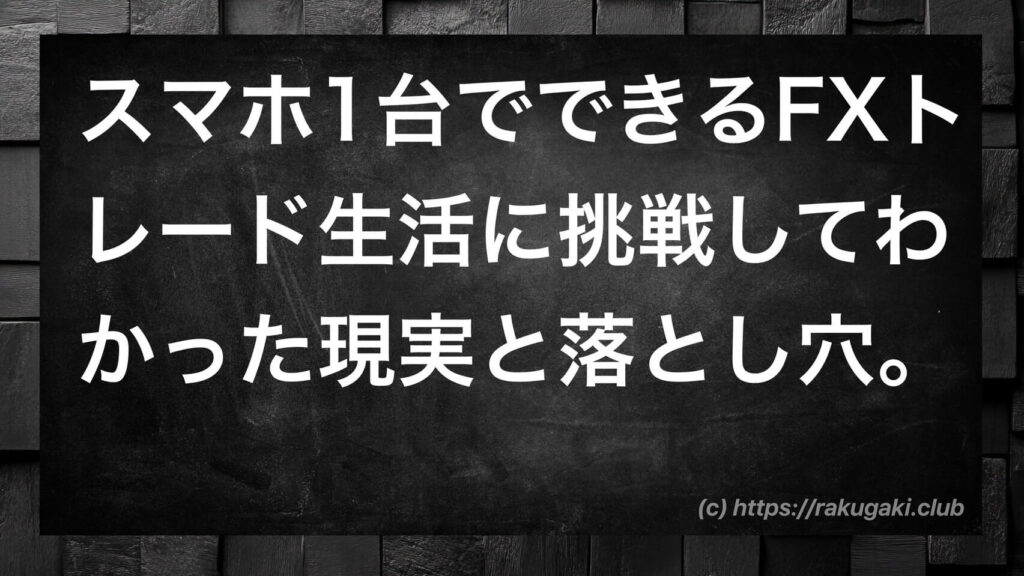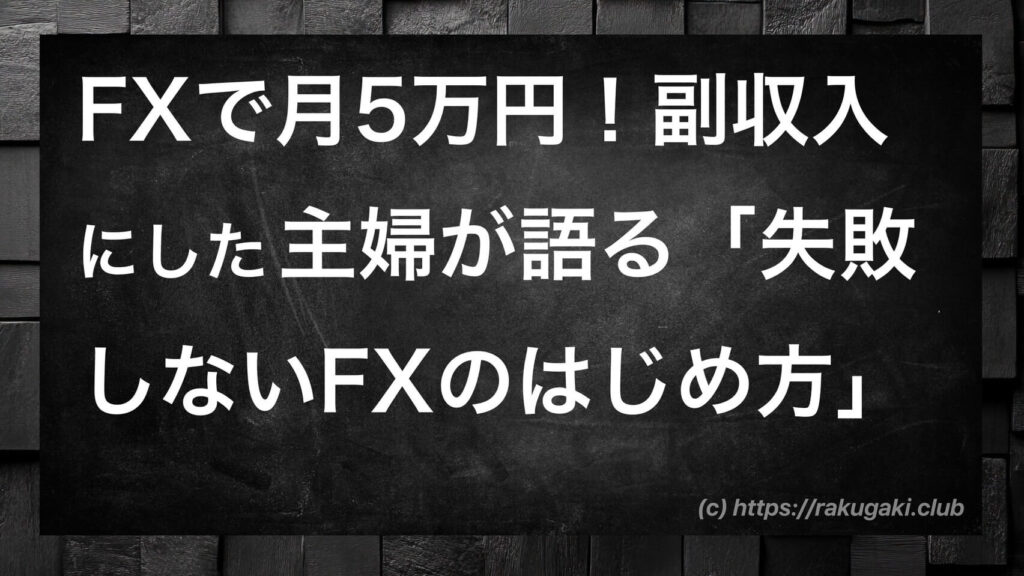通勤電車の中で起きた、ちょっとした奇跡
無言の戦場で起きた小さな出来事
朝の通勤電車って、なんであんなに無言の戦場みたいな空気が漂ってるんだろう。
人と目が合わないように気をつけつつ、ギリギリ座れるかどうかの椅子取りゲームに挑みながら、スマホのニュースを読むふりをして現実逃避する。それが、都心で働くOLの朝の風物詩だ。
その日も、私はいつも通りのテンションで、山手線の車両に滑り込んだ。ちょっと寝坊してしまったせいで、空いてる席はなし。吊革にもつかまれず、ドア近くの微妙なスペースに体をねじ込むように立った。隣には、保育園児くらいの小さな子どもとお母さん。子どもは小さなリュックを背負っていて、指先でママのコートの裾を握っていた。
目が合わないように…と思っていたのに、不思議なもので、ふとしたタイミングでその子と目が合ってしまった。するとその子は、まるで知り合いにでも会ったかのように、にっこり笑って、小さく手を振ってきた。
やられた。
朝のぼんやりした脳みそに、その一瞬の笑顔がじわっと沁みてきて、なんだか救われた気分になってしまった。「ああ…今日も頑張るか」って、自然と思えたのが自分でも驚きだった。
私もマスクの下でそっと笑って、小さく手を振り返す。
そしたら、その子が照れたようにママの背中に顔を隠して、くすくす笑った。
それを見たママが「ごめんなさい、朝から騒がしくて」と小さく会釈してきたので、「全然、大丈夫です」って感じでこちらも会釈を返した。
そのやりとりは、ほんの30秒くらいの出来事だったと思う。でも、妙に心に残った。
「今日の朝、見知らぬ子どもに手を振られて、ちょっと泣きそうになった。通勤の満員電車で、誰かと“あたたかい気持ち”を分け合えたの、いつぶりだろう」
私は、その気持ちのまま、会社のデスクに着くなり、X(旧Twitter)を開いてポストした。
本当にただの感情のメモみたいなもので、フォロワーもそんなにいないし、いつもなら数いいねつくかどうかの裏アカ的存在。なのに…。
“共感”は静かに広がっていく
午前11時
メールチェックを終えて、ふとスマホを見ると通知がピコンピコンと鳴り止まない。
「ん?」
開いてみると、投稿に100件以上のいいねがついていた。
「えっ? なんで?」
そこから、地味に、でも確実に、通知が止まらなくなった。
午後1時:お昼休み
ランチの時間になり、同僚と一緒にカフェテリアへ向かう途中も、私はスマホの通知に釘付けだった。
「どうしたの、ずっとスマホ見てるね?」
「いや…朝の通勤中のこと、何気なくポストしたら、バズりそうな勢いで…」
「バズりそうって、どれくらい?」
「いま、2,000いいねくらい…」
「それはバズってるって言うんだよ!」
同僚の一言で、自分のポストが思った以上の広がりを見せてることにようやく気づく。
しかも、リプ欄を見てみると、「わかる」「似たようなことあった」「朝の電車って、ほんと殺伐としてるよね」など、共感系のコメントがずらりと並んでいた。
職場に波及する“裏アカの顔”
午後3時:上司からの一言
「◯◯さん(←私の名前)、SNS詳しいんだって?」
なぜか、営業部の課長がニヤニヤしながら話しかけてきた。
「えっ!? な、なんでですか…?」
「いや〜、△△さん(←社内のちょっと情報通な人)が“◯◯さんのポストが今バズってるらしい”って言っててさ」
背筋が凍った。
どうして職場の人が、私のアカウント知ってるの…?
しかもあれって、裏アカ寄りで、たまに仕事の愚痴も書いてたのに…。
「…どうして知ってるんですか?」と聞いたら、「いや、俺の後輩が偶然見つけて、“この人、もしかして◯◯さんじゃね?”ってなってさ〜」と軽く言われた。
うそでしょ。
その日の夕方、ポストは8,000いいねを超えていた。
拡散されるにつれて、私のアカウントにもどんどん新しい人が押し寄せ、フォローされ、DMが飛んでくる。
「素敵なお話ですね!」
「朝から癒やされました!」
「あなたの言葉のセンスが好きです」
──どれもありがたいけど、急に増えたフォロワー数が恐怖でもあった。
たった一言の日常ポストで、こんなことになるなんて。
今までは、SNSってちょっとした「心の吐き出し口」くらいに思ってた。
でも今、私は、予期せぬ共感の渦に巻き込まれている。
バズったポストが、じわじわ私の日常を侵食してくる
「いい話」をしたつもりだったのに
ポストが広まり出してから、私は毎日「通知」との戦いになった。
スマホの通知欄が、ひとつの投稿だけで埋め尽くされる。リプライ、引用、フォロー、DM…通知オフにすればいい話なのだけど、「もう誰も反応してないかな…」と確認せずにはいられない。軽く依存っぽくなっていたのかもしれない。
でも、たったひとつ、明確に困っていたことがあった。
「どこまでが“共感”で、どこからが“監視”なんだろう…?」
私のアカウントは、完全に顔出ししてるわけじゃないし、本名でもない。けれど、職場で「この人かも」と特定されたように、過去ポストやちょっとした口癖で、じわじわと“私”が浮かび上がっていく。
「見てます」から始まるプレッシャー
最初に怖さを感じたのは、知らないアカウントからのDMだった。
「あなたの他のポストも読んでます。心に沁みました。」
その文面自体は優しいし、悪気はないのだと思う。でも「他のポスト」って…?
その日から、自分の過去のつぶやきが急に恥ずかしくなった。
なんでもない日曜日のつぶやき、会社の愚痴、買い物で失敗した話。
過去の自分が無防備に言葉を放っていた場所が、今では全方位からの視線にさらされている。
突然の“バズられた側”との接触
そんな中、信じられないDMが届いた。
「おそらく、うちの子と私のことだと思います。朝、ありがとうございました。」
私は心臓が止まりかけた。
投稿内には誰の名前も、場所も、時間帯も書いていなかった。なのに、「あの朝のこと」とわかったらしい。
「私たちも、素敵な出会いだったと思っています。子どもも、あれ以来“朝の電車、また乗りたい”って言っています」
涙が出そうになった。
たしかに私は、相手にとっても“記憶に残る出来事”だったのかもしれない。
だけど同時に、「ああ、やっぱり“人のこと”を勝手にポストしてたんだな…」という反省の気持ちも強くなった。
共感の押し売りと、誰のものでもない感情
いい話のはずだった。
誰かに元気をあげたかったわけじゃなく、自分の気持ちを整理するために書いたものだった。
でも、バズったポストは、いつしか私の手を離れて“みんなのもの”になっていく。
コメント欄には、「こういう大人が増えるといい」「世の中捨てたもんじゃない」「朝の電車、たしかに地獄」などの共感が並び、それはそれでありがたい。
だけど中には、「こういうの、子どもを利用してバズるってやつ?」といった皮肉コメントも出てきて、私は何もしてないのに責められてるような気持ちになった。
職場の空気がちょっとだけ変わっていく
バズの影響は、思わぬところに波及した。
会社の同僚が、さりげなく「昨日のポスト、またバズってたね」と言うようになり、ランチで「SNSって怖くない?」という話題が上がることが増えた。
ある日、別部署の後輩が言った。
「◯◯さんって、SNSでちゃんと“人を動かす言葉”使えるの、すごいです。尊敬します!」
それは、うれしいようで、うれしくない言葉だった。
私は「動かす」とか「狙って」なんて考えてなかった。ただ書いただけ。思ったことを素直に。
けれど、SNSは勝手に“読み手”を選ぶ。そして、受け取り方も選べない。
そのズレが、じわじわと自分の中にプレッシャーとなって蓄積されていく。
「今日も何か書かなきゃ」になっていく日々
不思議なことに、ポストがバズったあと、私は「何か言葉を発信しなきゃ」と思うようになった。
“書かなきゃ”という焦燥感と、“でも怖い”という不安の板挟み。
Xを開いては、何も書かずに閉じる。開いて、書いて、消す。
そんなことを繰り返しているうちに、頭の中はいつもSNSのことでいっぱいになっていった。
匿名の世界なのに、見られているという実感
ある日の夜、ふと気になって「自分のアカウント名」で検索をかけてみた。
そこには、知らない人たちが「この人のポスト、なんかクセになる」とか「感情表現がちょっと盛ってる気がする」とか、好き勝手に書いていた。
“バズ”って、フォロワー数とか通知の数だけじゃなくて、“他人の解釈に晒される回数”のことでもあるんだなと知った。
いいことだけを受け取れたらどれだけ楽か。
でも実際は、称賛と同じくらいの数だけ、ざらっとした違和感や、“観察”されているような目線が混じってくる。
静かに、でも確実に「自分」が変わっていく
あの朝の、子どもの笑顔に救われた自分は、もっと素直だった気がする。
誰の目を意識するでもなく、ただその瞬間に感じたことを、自分の言葉で書き残した。
それが、数日たった今では、“何を書くか”の前に“誰がどう受け取るか”ばかりを考えてしまっている。
SNSは、心のメモ帳でありたい。
けれど、誰かに見られることで、いつしか“見せる前提”の文章になってしまう。
それが、こんなにもしんどいなんて、思ってもみなかった。
“わたし”の輪郭がSNSで勝手に形作られていく
“キャラ付け”される恐怖
あるとき、タイムラインに自分のアカウントが引用されたポストが流れてきた。
「この人、いつも共感系のポストしてる。なんか“癒し系OL”って感じ」
私はそこで手を止めた。
…癒し系? 私が?
たしかに、あの朝のポストは穏やかだったかもしれない。でも、私の過去ポストを全部見てたらわかるはずだ。生理前でイライラしてるときに「満員電車の中で肘当ててくる人、全員宇宙に飛ばしたい」とか書いてたし、仕事でやらかした日に「この世でいちばん無能な会社員ランキング2位に入賞した」って泣きながらポストした日もある。
それなのに、「癒し系OL」という肩書きがいつの間にか私についていた。
それは、ちょっとした“キャラ設定”のようでもあり、私の言葉が自分の意図しない形で“商品化”されていく感覚に近かった。
フォロー数と自由の反比例
フォロワーはどんどん増えていく。
300人くらいだったのが、2,000人、3,000人と膨れ上がり、通知欄が常ににぎやかになる。
でもその分、「書けないこと」が増えていく。
仕事の話も、愚痴も、恋愛のことも、プライベートな感情も、誰に見られてるかわからない状況では出せなくなる。
それに、共感を得ていた文体から外れることが、妙に怖くなっていた。
「前みたいな、あったかい話じゃないのね」
「なんか最近、雰囲気変わった?」
そう言われるのが怖くて、“自分らしさ”がどんどん狭まっていく。
SNSの向こうにいる“見えない読者”を、常に想像しながら言葉を並べる日々。
そのうち、私はひとつのことに気づく。
「私、“いい人”っぽくあらねば、と思ってるんじゃないか?」
誰かの期待に応えようとするうちに、私のポストは私の言葉ではなくなっていた。
もう一人の“わたし”が、私を追い詰める
「らしさ」って、SNSではとても強い武器になる。
でもそれが、日常にまで影響してくると話は別だ。
ある朝、職場のトイレで、同僚がこんな会話をしていたのを聞いてしまった。
「◯◯さんって、Twitterでバズったっていうあの人でしょ?」
「あの癒し系の? わかる~、でもたまにポスト盛ってるよね」
完全に盗み聞きだけど、聞こえてしまったその声が耳から離れなかった。
“盛ってる”。
言葉ひとつで、真実が変わる世界。
私は別に脚色したつもりもなかったけど、感情をこめた言葉が“演出”だと受け取られることもある。
そしてその解釈が、“わたし”というキャラクターを勝手に書き換えていく。
DMという名の“会話ではない会話”
フォロワーが増えるにつれ、DMの数も増えていった。
最初は応援メッセージだったけど、そのうち「今度こういうテーマで書いてほしい」とか「あなたの経験談で救われたから、これも語って」みたいな“依頼”が届くようになった。
中には、とても長文の人生相談もあった。
「私も朝の電車が辛くて、でもあなたのポストを見て少し救われたんです。もっとそういう言葉をください」
気持ちは嬉しい。
でも私は、誰かを救うために書いたわけじゃなかった。
次第に、私のポストには「癒しを期待する目線」がどんどん重ねられていった。
その目線は、やさしいけど、重たかった。
SNSの“顔”と現実の“顔”のズレ
ある日、仲の良い同僚がランチ中にぽつりとこう言った。
「SNSのあなたって、なんか“いい意味で違う人”みたいだよね」
私は「へぇ、どう違う?」と聞いた。
すると彼女は少し考えてから言った。
「うーん…なんか、現実の◯◯さんよりちょっと丁寧で、穏やかで、やさしい。“よりよい◯◯さん”って感じ?」
その言葉が、喉の奥につっかえるような感じがして、私はそれ以上何も言えなかった。
SNSの中の私が、私を追い越して、勝手に“理想化されたわたし”として走り出している。
誰も悪くない。
でも、どこか置き去りにされている気がした。
「書けない」ことが、こんなにも苦しいなんて
SNSのアカウントを閉じようか――。
そんな考えが浮かぶようになったのは、フォロワーが5,000人を超えた頃だった。
ポストするたびに「これは共感されるか?」を考え、
リプライをもらうたびに「この人は本当に私を見てるのか?」と疑い、
RTの数で一喜一憂する。
書きたいのに、書けない。
書いても、怖い。
そんなループの中で、私は疲弊していた。
それなのに、Xを開いてしまう。
通知をチェックしてしまう。
何か言葉を打っては、消す。
あの日の子どもがくれた“手を振る”という行為
ふと思い出すのは、あの朝、子どもがくれた笑顔と、小さな手のひらだった。
言葉はなかった。
でもあの一瞬が、どれだけ私を救ったか。
SNSに言葉を綴るのも、もしかしたら“手を振る”みたいな行為なのかもしれない。
誰かと直接つながるわけじゃないけど、どこかでふわっと心が通う。
それで十分だったはずだ。
でも今の私は、“手を振る”どころか、“振り方”ばかり気にしている。
私は、私の言葉を取り戻したい
もう一度、素直に、自分の気持ちを書ける場所にしたい。
“いい人”とか“癒し系”とか、そういうラベルをはがして、
ただの私としてポストできるように。
それができなければ、アカウントを閉じてもいいと思った。
でも、やめる前に一度だけ。
“正直な今”を、そのままポストしてみよう。
そう思って、私はスマホを手に取った。
“正直な今”をポストしてみたら、もっとバズった件について
「もう疲れました」のポスト
深夜0時過ぎ。
ベッドに入ってからも、スマホをいじる指は止まらなかった。
Xを開いて、閉じて、また開いて。
フォロワー数は6,400。通知は1,000件以上たまっていて、DMの未読も60件を超えている。
…これってもう、私の手に負える範囲じゃないよね。
それなのに、なぜか「何か言葉を残さなきゃ」と思ってしまう。
これで最後かもしれない。
そんな気持ちを抱えながら、私はスマホのメモ帳に言葉を打ち込んだ。
「最近、何をつぶやいても“誰かに見られてる”って思うようになってしまいました。
誰かを癒したいとか、共感してほしいとか、そんな立派なこと考えてたわけじゃないのに。
ただのひとりの社会人の、朝の通勤の出来事を書いただけだったのに。
こんなに“いい人”じゃないし、うまく言葉も出ないし、
本当はちょっと、疲れてしまいました。」
編集ボタンを押したあと、しばらく投稿するか迷って、深呼吸してからポストボタンを押した。
画面に「送信されました」と表示されたとき、肩から何かがすとんと落ちた気がした。
数時間で通知が“それ以上”の状態になる
朝、目覚ましより先にスマホのバイブで目が覚めた。
開いてみて絶句した。
いいね数:1.8万
リポスト数:4.2万
引用数:8,500以上
えっ…?
前日の「癒し系通勤ポスト」どころの騒ぎじゃなかった。
私の“正直な弱音”ポストが、それを遥かに超える速度で広がっていた。
“共感ポスト”から“共感しすぎポスト”へ
リプ欄や引用はこんなコメントで溢れていた。
「わかる。共感されすぎると、怖くなるよね」
「“正直な人”が傷つくSNSなんて、もうやめたくなる」
「癒し系なんかじゃないって言うけど、こういう言葉こそ救われるよ」
あの夜、誰にも見せるつもりじゃなかったような本音が、
今また「新たな共感」の渦を巻き起こしていた。
この頃になると、私はもう通知を追いきれなかった。
ただ、画面越しに無数の声が飛んできて、
それらがまるで「わたしもいるよ」と手を挙げているように感じた。
自分の“居場所”がぼやけていく感覚
その日、会社では特に何も言われなかった。
でも、私の視線は妙に落ち着かず、同僚と目が合うたびに「バレてるかな?」と気になった。
ランチの時間、いつものメンバーで集まったとき、後輩の1人が小声で言った。
「あの…◯◯さんって、もしかして…このアカウントの人、ですよね?」
画面を見せられる前に、私は「うん」とだけ答えた。
認めるしかなかった。あまりにも広まっていたから。
「すごいです!昨日のポスト、泣きました」
「“疲れたって言っていい”って、あんなに優しく書けるのって、才能ですよ」
その言葉に、私は笑うしかなかった。
もう「ありがとう」すら言えなくなっていた。
“期待される正直さ”のジレンマ
翌日以降も、私はポストをしなかった。
でも、それでもフォロワー数は増え続けていた。
“正直な本音を語った人”。
“等身大の共感ポスト主”。
“弱音すら癒される存在”。
またしても、新しいラベルが、私の上に貼られていった。
本音を吐露しても、また期待される。
「疲れた」と言っても、「そう言ってくれてありがとう」と返される。
私は、どこまでいっても“誰かのための存在”になっていた。
しかも、自分がそう望んでしまった部分もある。
「誰かのために」と思って投稿したことは一度もないのに。
なのに、見返りを求めてないと言いながら、反応を待ってしまう自分がいた。
“私のことなのに、私が遠い”という矛盾
投稿したはずの言葉が、
気づけば自分の手から離れ、誰かに拾われ、誰かに解釈されて、
“他人にとっての物語”として生まれ変わっていく。
「癒された」
「涙が出た」
「優しい人でいてくれてありがとう」
そんな言葉に、私はどう応えればよかったんだろう。
嬉しいけど、怖い。
怖いけど、無視できない。
無視したら“いい人じゃなくなる”気がしてしまう。
SNSの中で、私は“私”であることが、どんどん難しくなっていった。
言葉に宿る“意図”と“期待”のすれ違い
ある日、引用で流れてきたひとつの言葉に、心がざわついた。
「この人、たぶん“いい人やめたいのにやめられない人”なんだと思う。ちょっと他人事じゃない」
たしかに、そのとおりかもしれない。
私は“やめたい”と言いつつ、“やめたくない”気持ちもどこかにあった。
共感されることに安心して、
誰かの言葉に支えられながら、
でも同時に、自分の中の“理想像”に縛られていた。
自分のことなのに、誰かの期待を先に考えてしまう。
本音なのに、本音であることに自信が持てなくなる。
それがSNSだった。
それが、バズのあとに待っていた世界だった。
“癒される言葉”じゃなく、“ありのまま”を
私はもう、誰かにとっての癒しの存在ではいられない。
もともとそんな人間じゃないし、
誰かを救えるほど、強くもないし、やさしくもない。
でも、それでも書きたいと思う。
やっぱり、言葉にすることが、私にとっては“手を振る”ことだから。
ポストの最後に、私はこう書いた。
「今は疲れてるけど、またちゃんと“何か”を感じたら書きます。
それが誰のためにもならなくても。
自分の言葉を、自分のままで書けるようになるまで、ちょっと休みますね。」
言葉を“誰のもの”として届けたいのか、という話
「少し休みます」ポストの、その後
「またちゃんと何かを感じたら書きます」
そうポストしたあと、私はXのアプリを一度スマホから消した。通知もDMも、検索も、何もかも。意外なほどあっさりできた。
アカウントは削除しなかった。
でも、“反応”を気にする生活を、一時的に手放すことにした。
数日後、スマホを開く回数がぐんと減っていることに気づいた。
代わりに、何年も放置していた本棚から文庫本を引っ張り出したり、
ずっと気になっていた近所のカフェに足を運んだり。
言葉を“書く”のではなく、“感じる”ことを優先し始めていた。
「共感の海」から岸に戻ってみてわかったこと
SNSの波の中にいたときは、いつも溺れている感じがしていた。
リツイートの波、いいねの波、DMの波。
どれもありがたかったけど、自分で自分を見失うほどには“他人”が多すぎた。
アプリを消した日から、私はようやく“泳ぐ”のをやめて、岸に立つことができた。
誰に届くか、より
誰に届いてほしいか、の方が大切かもしれない。
そんなふうに思えるようになったのは、SNSと一度距離を置いてみたからこそだった。
職場の人たちの変化と、静かな受け止め方
Xをやめてからの数日、職場の人たちは意外と何も言わなかった。
むしろ、妙な気を遣っているのか、あの話題に触れないようにしている気配があった。
ただ、ランチのとき、ひとりの先輩がふとこう言った。
「あのときのポスト、ほんと良かったよ。
“共感される”って、ほんとはしんどいことなんだなって、初めて気づいた」
驚いた。
その人はいつもSNSに興味がなさそうで、私のアカウントのこともあまり知らないと思っていた。
でもちゃんと“読んで”くれていたんだな、と思えたその瞬間、少しだけ胸があたたかくなった。
フォロワーじゃなくて、読んでくれる誰かへ
SNSをやっていると、つい「何人に届いたか」「どれだけ拡散されたか」に気持ちが向く。
でも、本当に大事なのは、“一人ひとりにちゃんと読まれること”なんじゃないか。
バズっていたあのとき、数字の裏にいる“人間”を、私はちゃんと想像できていなかった気がする。
数千のリツイートよりも、
「ありがとう、泣きました」とポツリとくれた1件のDMのほうが、
よっぽど私の心に残っている。
“言葉”を使うときに必要な覚悟
SNSって、発信もできるし、観察もできる場所だ。
誰かを元気づけたり、支えたりもできるけど、
そのぶん“消費される”リスクも常にある。
私はたまたま、それをちょっと強めに体験しただけ。
でもその経験があったから、今は思う。
「わたしの言葉は、わたしが届けたい誰かに向けて発したい」
拡散されるのが目的じゃなく、
誰かに“手紙”を書くような感覚で、また言葉を並べていけたらいいなと思う。
再開するかどうかを決めるのは、“期待”ではなく“感情”で
Xを再インストールする日が来るかどうか、まだわからない。
でも、書きたいと思えたときに、すっと言葉が出るような状態でいたい。
書かなくちゃじゃなく、
書きたいな、と思えたら、それが“再開の合図”なんだと思う。
フォロワーの数も、通知の数も、もう気にしない。
バズったらまた怖くなるかもしれないけど、
それでも、自分の言葉で、自分の速度で、また始められると信じたい。
あの日の“手を振ってくれた子”が、今もどこかにいるなら
もしもあの朝の電車で会った親子が、今もこのポストを読んでくれていたとしたら、
私はただ一言、伝えたい。
「ありがとう。あの朝、あなたの“にっこり”が、全部の始まりでした」
SNSがどんなに大きくなっても、
あの日の30秒が、私の原点であることに変わりはない。
バズったその先で、ようやく見つけた“わたしのSNS”
あの日々を経て、今の私はどうなったか
あれから、半年が経った。
Xのアカウントはまだある。フォロワーは少し減ったけど、それでも数千人はいる。
でも、今の私は、前ほど頻繁にはポストしていない。
たまに、ふと思いついたことを書く。
きれいな夕焼けを見た日、カフェで隣の席の会話にクスッとした日、
うっかりケチャップを白いシャツにこぼして落ち込んだ日。
どれも“共感されること”を目的としたわけじゃなく、
ただ、言葉にしておきたかった気持ちをそっと置いた、そんな感じだ。
いいねが3つでも、リプがゼロでも、
今はその静けさに救われている。
「バズ」とは、光でもあり影でもある
かつての私は、バズることで“見てもらえること”の快感を知った。
でも同時に、“見られること”の苦しさも思い知った。
SNSの世界では、一瞬で「誰か」になれる。
でもその「誰か」は、たいてい“自分ではない自分”だ。
演じてるつもりがなくても、期待に応えるうちに“キャラ”が生まれていく。
あの頃の私は、癒し系OLとしても、共感ポストの人としても、
いつしか“本物の自分”からどんどん遠ざかっていた。
「何を言うか」より「誰として言うか」
バズを経験して学んだのは、SNSの言葉は常に“文脈”に包まれているということ。
言葉だけを見てもらえることなんて、ほとんどない。
誰が言ったか、どんなキャラなのか、何者なのか。
人はつい、“キャラ”に反応する。
だからこそ、わたしは“誰かっぽい何者か”になる前に、
“わたしとしての言葉”を出す努力をしようと決めた。
「バズる文章」じゃなくて、
「誰にも届かなくても、自分の心に正直な文章」を。
SNSとの付き合い方に“正解”はないけれど
それでも、SNSをやめようとは思わなかった。
怖いこともあるし、しんどくなることもあるけれど、
ときどき誰かの言葉に救われたり、
思いがけないつながりが生まれたりする場所でもあるから。
大切なのは、“心地よい距離感”でいられること。
誰かに合わせすぎず、かといって自分だけの殻にこもりすぎず。
“言葉を差し出す”という行為が、自分を削りすぎないように。
そして、誰かの言葉を受け取るときも、過剰に抱え込まないように。
SNSはツール。
わたしの心の延長にある“ちょっとした出窓”くらいの感覚で、ちょうどいいのだと思う。
「あの朝の30秒」がくれたもの
最後に、やっぱり伝えたいのは――
すべてのきっかけになった、あの朝の子どもとお母さんのこと。
ほんの数秒、見知らぬ私に手を振ってくれたあの子。
くすくす笑いながらママの後ろに隠れた、その姿。
あの出来事がなかったら、
私はポストをしなかったし、
この一連の経験も、たぶんなかった。
あの子の笑顔が、
私の言葉を動かした。
そしてその言葉が、私自身を変える経験につながった。
共感は目的じゃなく、結果でいい
今ならはっきりわかる。
共感って、狙って得るものじゃない。
伝えたいと思ったことを素直に書いたとき、
たまたま誰かの心に“ふっ”と触れた結果が、共感になるんだ。
逆に言えば、
共感されなくても、それでいい。
それでも書きたかったなら、その言葉にはきっと意味がある。
SNSがどれだけ進化しても、
フォーマットが変わっても、
この感覚だけは、大切にしていたいと思う。
それでも、また私はポストする
しばらく投稿しなかったアカウントに、久しぶりのポストを打った。
「あのときの“おやすみなさい”から、だいぶ経ちました。
また、何かが心に浮かんだら、書いていこうと思います。
誰に届くかは、もうそんなに気にしません。
でも、どこかで誰かが読んでくれてたら、それだけで十分です。」
通知は、あまり鳴らなかった。
でも、それでよかった。
バズらない言葉も、
共感されない感情も、
全部ひっくるめて、“わたしのSNS”なのだから。