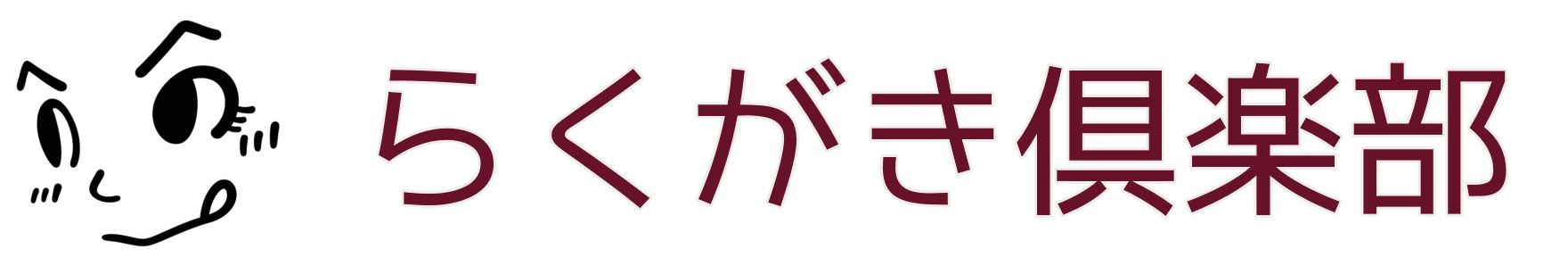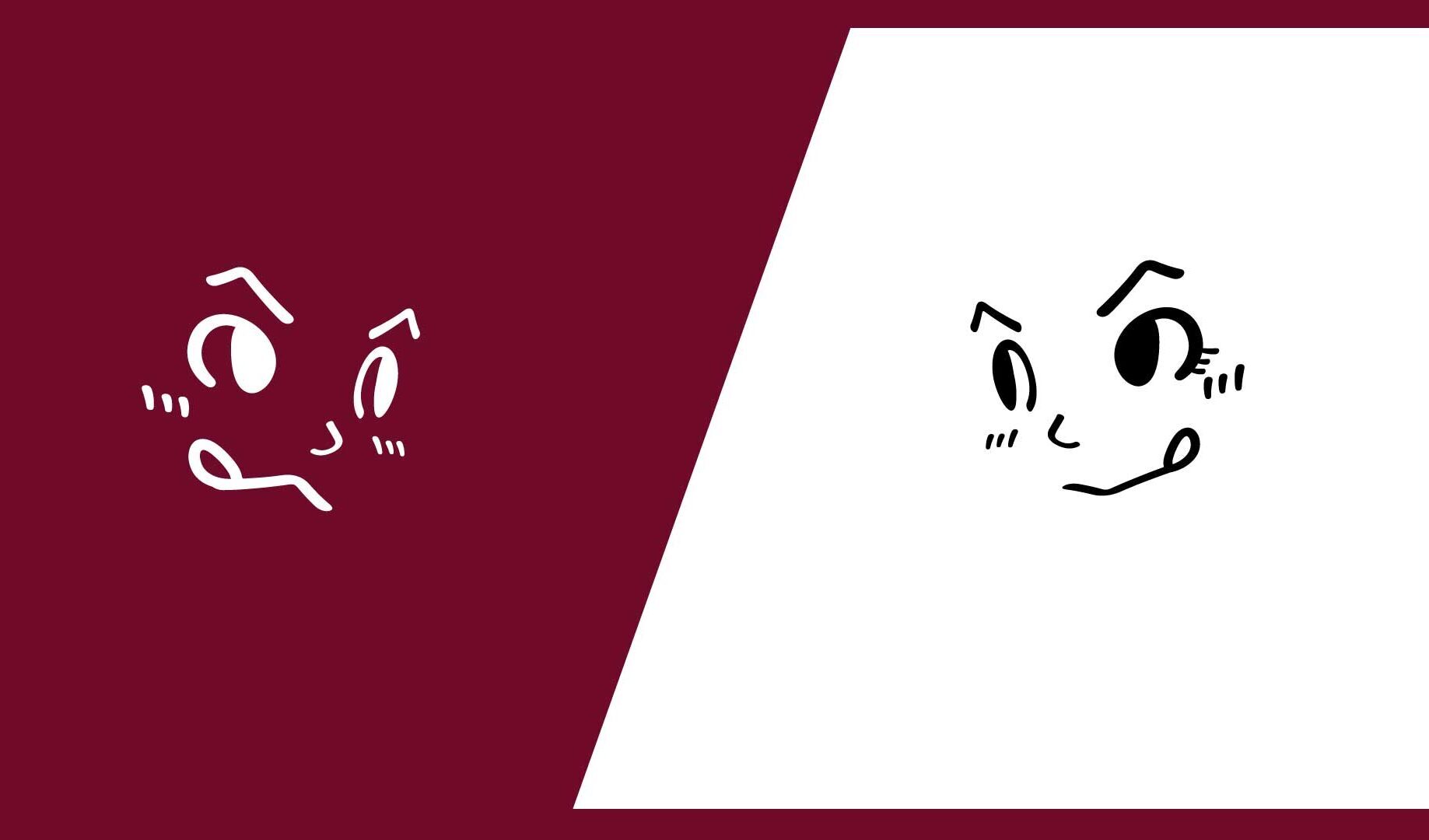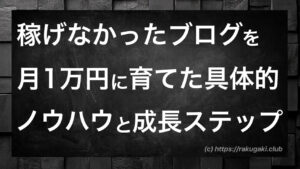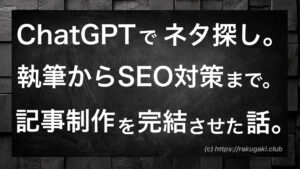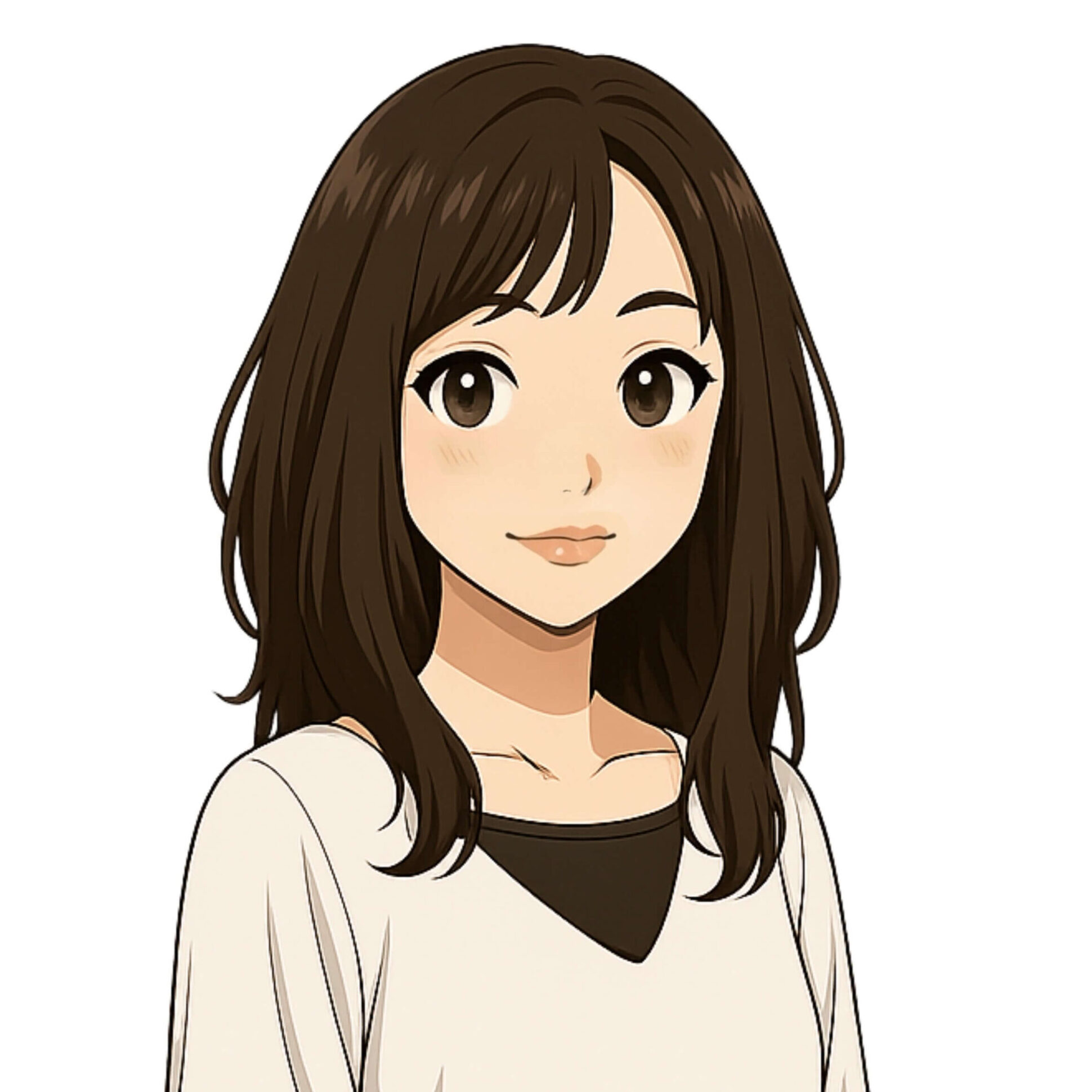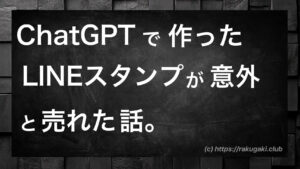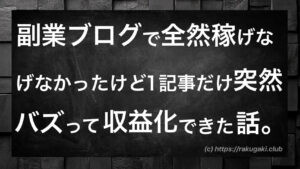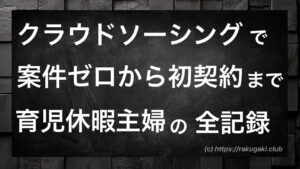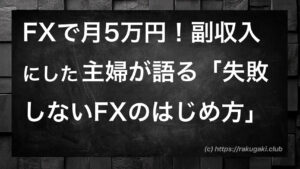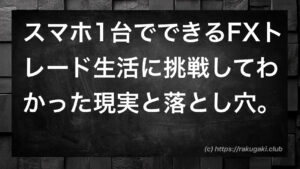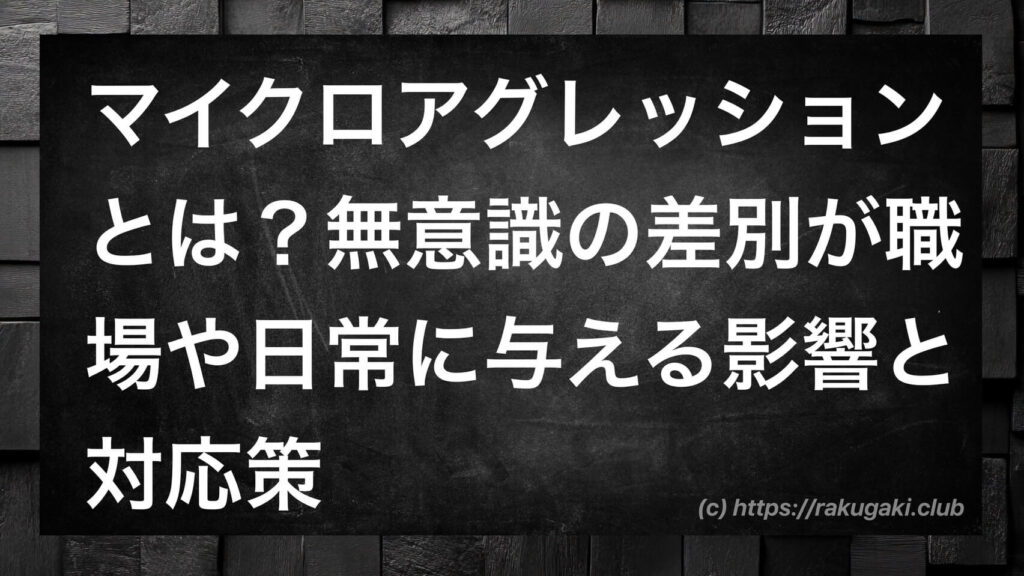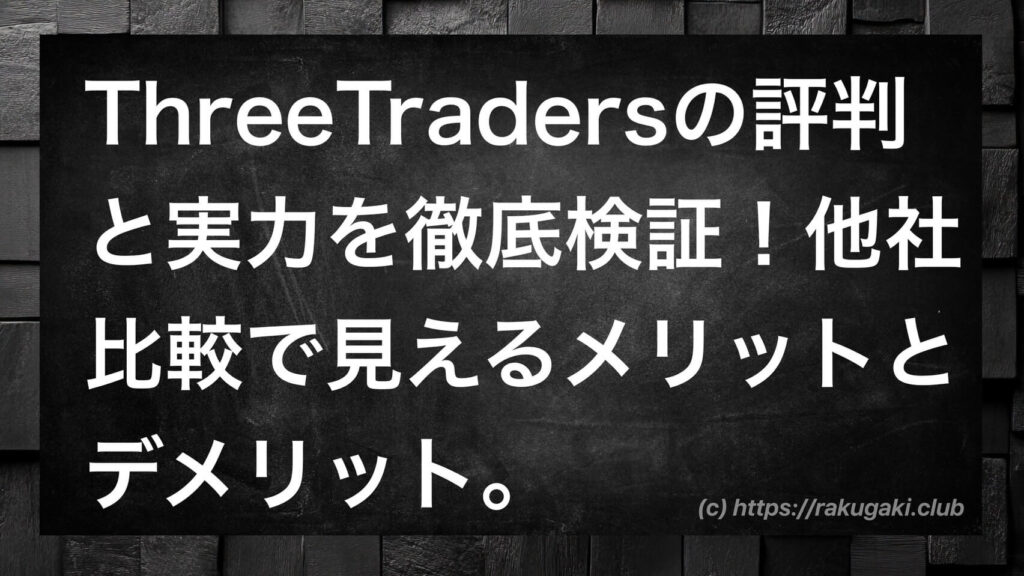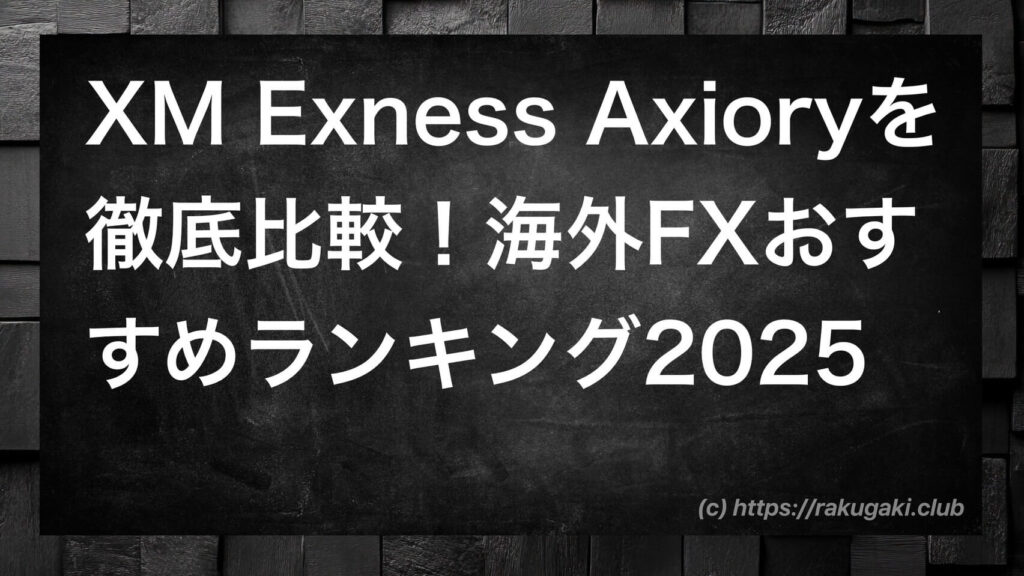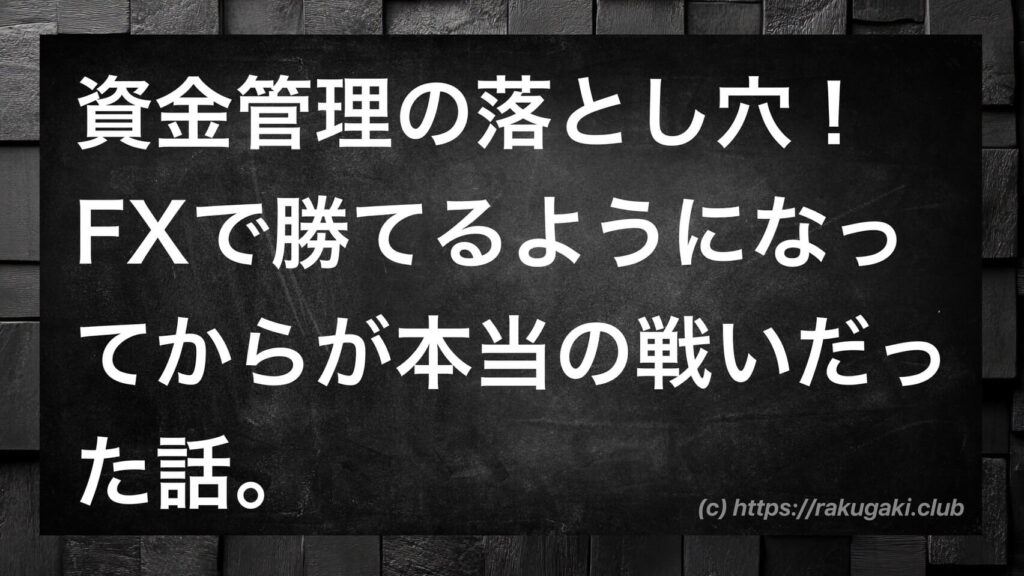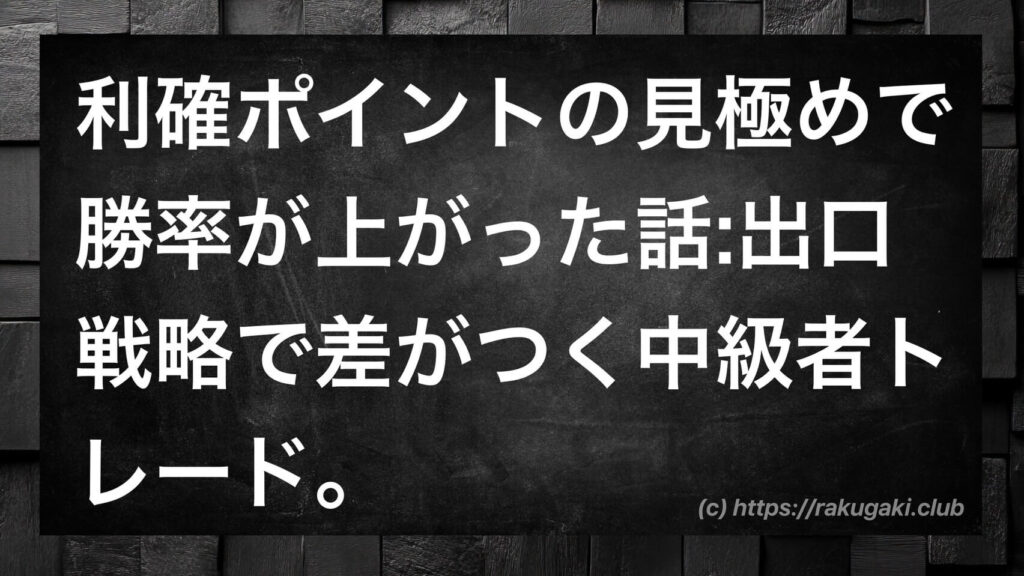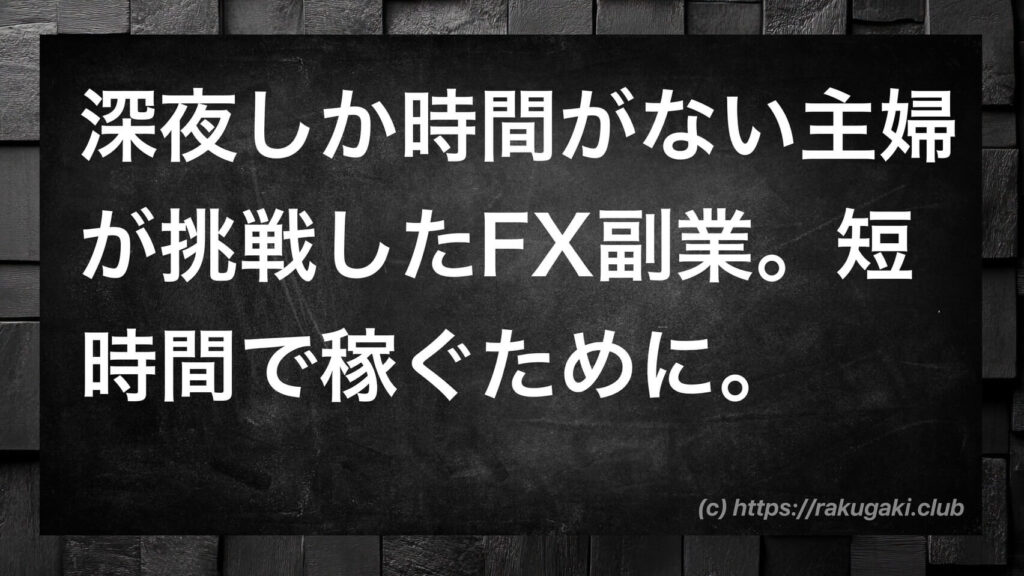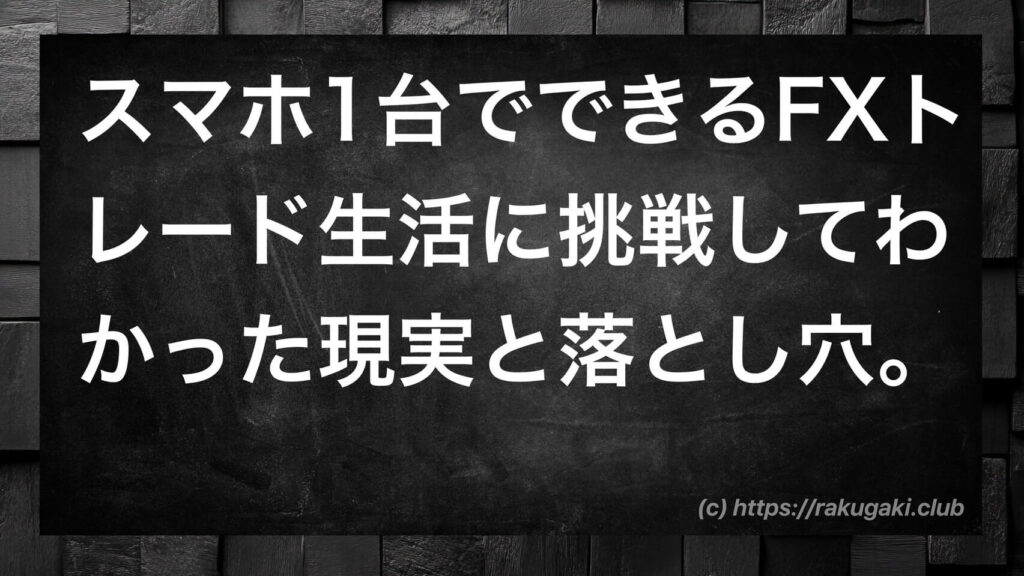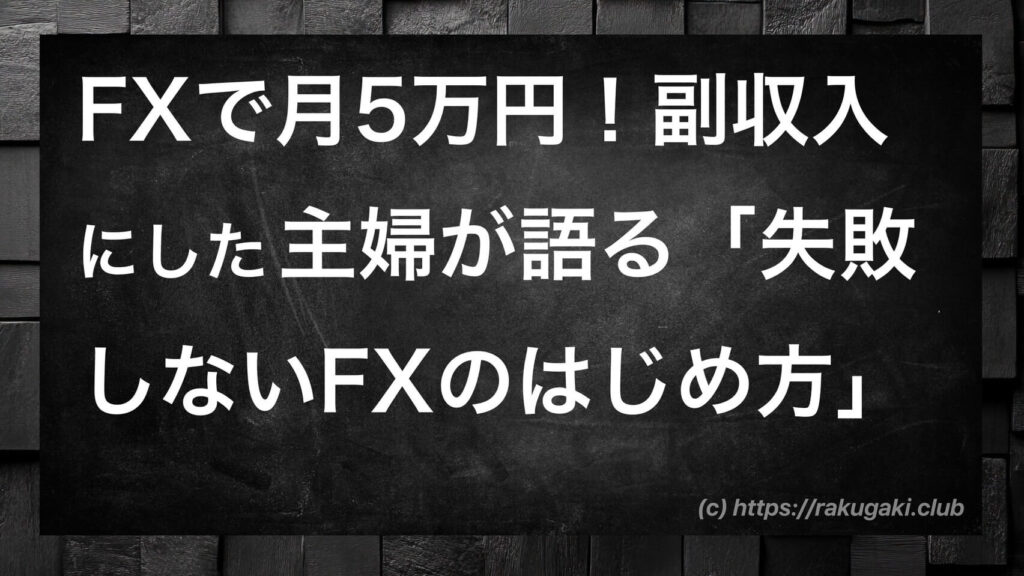noteで稼げると信じていた、あの頃の自分へ
「副業ならnoteがいいらしいよ」
そんな言葉をXで見かけたのがきっかけだった。
当時、私は社会人3年目。仕事も覚え、多少の余裕ができた頃。
副業に興味を持ち始めたばかりだった。
noteで稼いでいるという人たちのツイートはどれも眩しかった。
「月3万円」「1日で1万字売れた」など、文章で稼ぐ世界があることに興奮した。
ライティング経験もあるし、自分にもできそう——そう思っていた。
最初の記事、“気合い”だけで投稿してしまった
「まずは自分の体験を売ろう」と決めた。
選んだテーマは「副業初心者が月1万円を稼ぐまでの実録体験」。
価格は500円。表紙もCanvaで整えた。文章も推敲した。投稿直後は、少しだけ手応えを感じていた。
でも結果は「誰ひとり買わなかった」。
数日経っても、売上は0。
通知も感想もなければ、アクセス数も見えない。
「これはダメだったかも…」と不安がこみ上げた。
なぜ売れなかったのか、まるで見当がつかなかった
あのときの私は、根本的に2つのことを勘違いしていた。
- 良い記事を書けば勝手に売れると思っていた
- noteでも“読まれてから買われる”と信じていた
でもnoteは「買わないと読めない」世界。
つまり、読まれる前に買ってもらう理由が必要だった。
そして私は、その理由を一切提示していなかった。
SNSでの宣伝も、実は「告知」だけだった
記事を投稿した直後、私はXで宣伝もした。
フォロワー数は約800人。
「note出しました!」とURL付きでポストした。
でも、いいね1、リポスト0、売上0。現実は冷たかった。
今思えば、そこに“読者視点”は一切なかった。
どんな人向けなのか? 何を学べるのか? なぜ500円の価値があるのか?
そういった情報が、まったくなかったのだ。
noteで売れるには「記事の質」ではなく「売る設計」だった
ブログやSNSと違い、noteは購入前に中身が見えない。
だからこそ、タイトル・導線・信頼性がすべて。
特に重要だったのがこの3点:
- 何が得られるかが明確なタイトル
- 購入者の疑問に答える導線(SNS導入文)
- 書き手の実績・信頼性の提示
たとえ内容が良くても、売れる仕組みがなければ意味がなかった。
「noteが売れない」は才能の問題ではない
この経験から学んだことがある。
noteが売れない理由は、「才能がない」わけじゃない。
売るための構造を知らないまま出すから、売れないのだ。
この「構造」を理解したあと、私は再度noteにチャレンジした。
もちろん、次のnoteもすぐには売れなかった。
でも、「買ってもらうための仕組み」をひとつひとつ組み直していった。
その過程こそが、コンテンツ販売における本質だった。
売れなかったnoteを徹底分析してみた
売れなかったnoteを冷静に見直してみると、恥ずかしいくらい“売れない要素”のオンパレードだった。
タイトルが「ふんわり」していた
当時つけたタイトルは、「副業初心者が1万円稼ぐまでのリアル記録」。
自分としては「ありのままの体験を売る」ことに価値があると思っていた。
でも、いま振り返ればこのタイトルは以下の点で問題があった:
- ターゲットが曖昧(誰のための記事か不明)
- メリットが弱い(読み手に何が得られるかわからない)
- 目新しさがない(他にも似たような体験記事は多い)
タイトルは「内容を要約するもの」ではなく、「買いたくなるコピー」でなければならなかった。
導入文が「自己紹介」だった
noteの冒頭、私は「このnoteを書いた理由」と「自分のプロフィール」から始めていた。
でもそれは読者にとっては関係がない。
読み手が知りたいのは「自分にとってこのnoteが必要かどうか」。
正しくは、最初の数行で
- どんな悩みに答えるnoteなのか?
- どんな人に読んでほしいのか?
- 読んだあとにどんな変化があるのか?
を提示するべきだった。
導入文の設計をミスすると、それだけで購入ボタンは押されない。
「内容が濃い」だけでは売れない
私はnoteの中に、細かな実践記録や実際の数字をしっかり盛り込んだ。
でも、読まれないnoteにいくら情報を詰め込んでも、誰にも届かない。
問題は、「買う前に価値を伝える」プロセスが抜けていたことだった。
具体的に足りなかったのは:
- SNS上での「連続投稿による興味づけ」
- 実績や信頼性の積み上げ
- リピーターを生むコンテンツ設計
noteの販売は、記事単体ではなく「仕組み」で成り立っていると知った。
「安いから売れる」は幻想だった
値段は500円。最初は「安いから買ってもらえる」と思っていた。
でも実際には「500円ですら払う理由がない」記事だった。
価格設定で意識すべきなのは金額ではない。
- 価格に対して「損しない」と思わせること
- 「買わない理由をつぶす」説明をしていること
noteは「値段」よりも「納得感」で買われるのだと痛感した。
売れなかった理由をまとめると
- タイトルで“買う理由”を提示していない
- 導入文が読者目線になっていない
- コンテンツ販売の仕組みを作っていない
- SNSとの連動が弱く、関心を引けていない
- 「読まれる前提」で書いてしまった
これらの失敗は、note初心者が陥りがちなパターンそのものだった。
2本目のnoteで実践した“売るための仕組み”
1本目で売れなかった経験をもとに、「売れるnote」とは何かを徹底的に学び、試した。
その結果、2本目は数本売れるようになり、ようやくnote販売の基本構造が見えてきた。
誰のためのnoteかを、最初に決めた
1本目との一番の違いは「読者を明確にしたこと」だった。
具体的には:
- noteを書こうとしている副業初心者
- まだ実績がないが、最初の1本を形にしたい人
- 文章に自信がないけど、売れるnoteの構成を知りたい人
これらのターゲットを明確にし、「彼らの悩みに答える」という方針で全体を設計した。
タイトルに「欲しい成果」を明記した
2本目のタイトルはこうした:
「売れないnote」が「3本売れるnote」になった構成テンプレート
成果の数字を入れることで、信ぴょう性がアップ。
また、「構成テンプレート」という具体ワードを入れることで、読者のニーズに直結させた。
結果、SNSでも反応があり、クリック率・購入率ともに上がった。
読者の「導線」を意識した設計
2本目のnoteでは、note単体ではなく、以下の仕組みを意識した:
- 投稿前からX(旧Twitter)で関連記事を複数投稿
- noteの一部を抜粋・図解にして発信
- 購入者限定で“次の特典note”の割引を用意
つまり「買ったあとにも得がある」構造にすることで、購入ハードルを下げた。
本文は「構成+例+ひな形」のセット
前回はただの体験談。今回は以下の流れで構成した:
- 売れなかった時の構成例
- 売れたときの構成にどう改善したか
- 実際に使えるnote構成テンプレート
読み手が「自分にも使える」と思えるように、ひな形形式でまとめたのが功を奏した。
感情より、再現性を重視した
noteでの販売は「ストーリー」ではなく「再現性」が価値になる。
たとえば、「こう書けば売れる」の“根拠”を言語化するよう意識した:
- なぜその見出しにしたのか?
- どんな順番で内容を構成したのか?
- どこで「読む気を削がれる」のか?
これにより、「体験記」ではなく「ノウハウ」に変換できた。
販売後のフォローも丁寧にした
購入者に対しては以下のようなアクションも行った:
- お礼メッセージ
- 関連noteの無料クーポン提供
- 感想投稿へのリツイート
これにより「買ってよかった」と思ってもらえ、SNS上での自然な拡散も起きた。
「noteは甘くない」と気づいたからこそ学べたこと
noteに記事を出して、最初に突きつけられた現実。それは、
**「誰も買ってくれない」**という事実だった。
でも、この経験があったからこそ、私は「売るとは何か」を深く考えるようになった。
noteは「読み物」ではなく「商品」
一番大きな学びは、「noteはブログと違う」ということだった。
ブログは読者との“継続的な関係性”を築いていける場だが、
noteはそれ単体で「買う価値がある」と思わせなければならない。
つまり、noteは読み物である前に「商品」である。
そのためには、文章力よりも先に「商品設計力」が問われる。
noteは「セールスライティング」が9割
SNSで「役立つことを無料で発信していたら自然と売れる」なんて話もあるが、
実際は、売れるnoteはほぼ例外なく“売るための文章”で構成されている。
- タイトルで「得られる未来」を伝える
- 導入で「読み手の悩み」を代弁する
- 本文では「再現性」「具体例」「信ぴょう性」
- 最後に「行動を促すクロージング」
この型を知らずに書いた1本目は、「読まれて終わるnote」になっていた。
自分のnoteが「どのステージ」にあるかを把握する
失敗したあと、私はnote販売を「成長ステージ」で捉えるようにした。
- 書くことで満足しているステージ
- 書いたnoteを“届けたい相手”に見てもらうステージ
- 読まれたnoteが“買われる”ステージ
- 買われたnoteが“拡散される”ステージ
- noteから“別の価値”が生まれるステージ(例:相談、講座、DM)
最初の1本目は、完全に「①」で止まっていた。
今は「③〜④」の間にいる自覚がある。
自分がどこにいて、次に進むには何が足りないかを言語化することで、
noteというプラットフォームを攻略できる実感が生まれた。
コンテンツ販売の本質は「誰のどんな問題を解決するか」
これはnoteに限らず、stand.fmやBrain、Voicy、どのプラットフォームでも共通している。
“売れる”とは、解決されたい課題がそこにある、ということ。
だからこそ、
- 「誰に向けて書いているのか?」
- 「どんな悩みを持っている人か?」
- 「どんな未来を求めている人か?」
これを自分に問い続けられるかどうかが、コンテンツ販売の勝負所だった。
noteは、知識を売る場ではなく「変化」を売る場
最後に、私が一番大切にしている考え方をシェアしたい。
noteで売るべきは、情報や体験談ではなく、
**「これを読んだあとに、読者がどう変わるか」**である。
その視点が持てるようになってから、私のnoteは読まれ、買われ、時にはDMで感想が届くようになった。
売れるnoteを作るには、“伝えたいこと”ではなく、“相手が変われる導線”を描く必要がある。
それを学ぶ最初の1歩が、「全然売れなかったnote」だったのだ。
少しずつ売れたことで変わった「戦略」と「視点」
noteが1本も売れなかったあの日から数週間、
私はnoteの書き方を根本から見直した。
そして、3本目でようやく初めての“購入通知”が届いた。
その瞬間、「あ、ちゃんと届いたんだ」と胸が熱くなった。
最初に売れた記事は「体験+戦略」のハイブリッド型
初めて売れたnoteのテーマは、「副業ブログで最初にやるべき5つのこと」。
ポイントは、「自分のリアルな失敗」と「今のやり方」をセットで書いたことだった。
- 完全初心者だったときに何を間違えたか
- なぜ今はこうしているのか
- どうすれば読者も同じ失敗を回避できるか
この“振り返り+戦略型”が読者に刺さったのだと思う。
「バズ」ではなく「文脈のある発信」が売上につながる
売れた直後、私は浮かれて「バズるnoteの作り方」などを調べまくった。
でも、バズを狙う投稿ほど、数字は出るのに“購入”にはつながらなかった。
結局、買ってくれる人は「過去の自分と似た悩みを持つ人」。
そうした人に届くような文脈や流れをつくることの方が、
バズ狙いよりよっぽど大切だった。
SNSとnoteを「セット」で考えるようになった
それまでは、
- noteを書く
- 投稿リンクをSNSに貼る
- たまにリプで宣伝する
…という単発的な使い方だったが、
売れたあとからは「SNS→note」の導線設計を意識するようになった。
- Twitterでは日常的な悩みや学びを発信し、共感でフォローを増やす
- 固定ツイートにnoteリンクを設置
- フォロワーが増えるタイミングで再度note紹介
すると、数字は小さくても安定的にnoteが読まれるようになっていった。
売れるようになって初めて分かる「売れる前に必要なこと」
今になって思うのは、
noteで売れるようになっても「文章力」より大事なものがいくつもあるということ。
- リサーチ力(検索キーワード、ターゲット像の把握)
- 構成力(“答え”を最後に書かず、読み進めたくなる設計)
- CTAの作り方(購入後の行動まで意識した導線)
これらは、1人も買ってくれなかったnoteを出したからこそ気づけた。
noteが売れるようになると、副業の視界が一気に開けた
1本、2本と売れるようになってくると、以下のような変化が起きた:
- note収益が毎月3,000円→5,000円→1万円と徐々に伸びていく
- note読者からSNSでのDM相談が来る
- noteをきっかけに自分の他サービスへ誘導できるようになる
特にnoteは「売る場所」であると同時に「信頼構築の場」になる。
結果的に、副業としての柱のひとつになり得ると確信した。
noteで売れなかった理由と、これから始める人へのヒント
副業としてnoteに挑戦して、最初に直面した現実は「誰にも読まれず、誰にも買われない」という“ゼロの壁”でした。
でも、そこから売れるようになるまでに必要だったのは、意外にも「執筆スキル」よりも“販売戦略”と“読者視点”でした。
売れないnoteにありがちな3つの原因
noteが売れなかった頃の自分に、今だからこそ言えるのは次の3つの問題点です。
- ターゲット不明瞭
「誰に向けた記事か」が不明確だと、タイトルも内容も刺さらない。 - 導線がない
SNSとの連携がなければ、そもそも読まれるチャンスがない。 - 内容が独りよがり
「自分語り」で終わってしまい、読者が得るものがない。
これらを改善しただけで、販売数がじわじわと増えていきました。
売れるnoteをつくるための3ステップ
私が実践して効果を感じた具体的な改善ステップは以下のとおりです:
- 検索キーワードをもとに記事テーマを決める
「note 稼げない」「副業 始め方」などの実際に検索されている語句を参考に。 - 体験+ノウハウ型にする
体験談だけでは売れない。そこに“再現可能な要素”を必ずセットで加える。 - SNSとの連携を強化する
日常のポストとnoteを自然につなげて、“フォロワー”を“読者”に転換する流れをつくる。
「売れない」を分析できれば、noteは副業に向いている
noteの良さは、誰でも今すぐ書けて、ノーコストで始められる点です。
しかしその反面、「書けば売れる」というほど甘くない市場でもあります。
重要なのは、「売れなかった理由」を主観ではなくデータと行動から分析できるか。
- タイトルクリック率は?
- 読了率は?
- SNS経由か、検索流入か?
これらを少しずつ見ながら改善していけば、noteは副業として“育てる”ことができます。
まとめ:noteで失敗する人ほど、成長スピードが早い
noteで一度も売れなかった経験は、確かに苦いものでした。
でも、だからこそ「何が通用しないのか」「どう届ければいいのか」がリアルに理解できました。
最初からうまくいく人はいません。
売れない時期に何を考えて、どう改善するか。それが副業の成功を左右します。
これからnoteに挑戦する方は、最初の“ゼロ”にめげず、データと読者視点を武器にしてみてください。
「売れるかどうか」は運の要素もありますが、
「売れなかった理由を次に活かせるかどうか」は、完全に分析次第です。