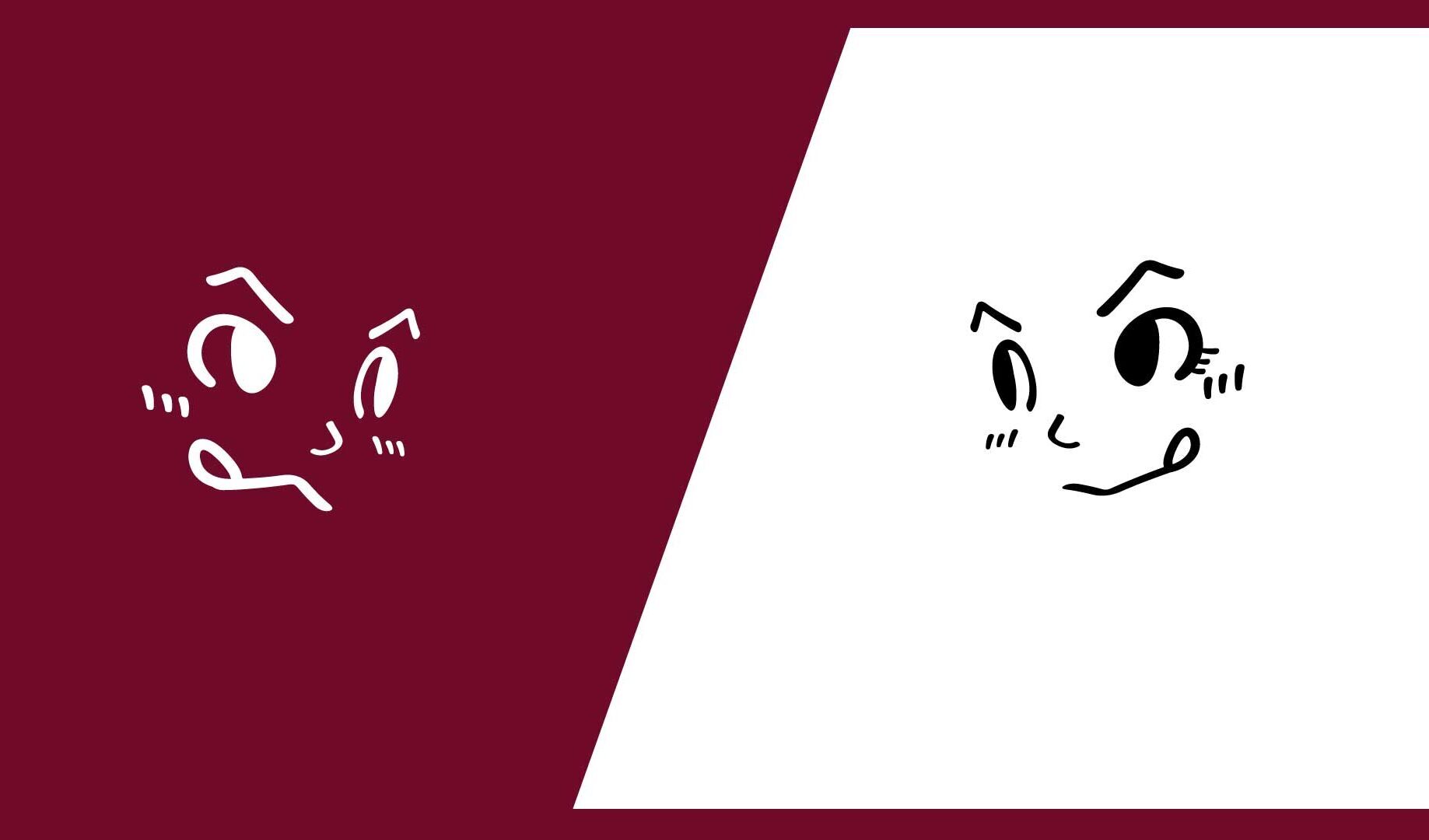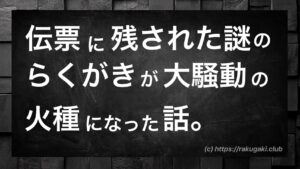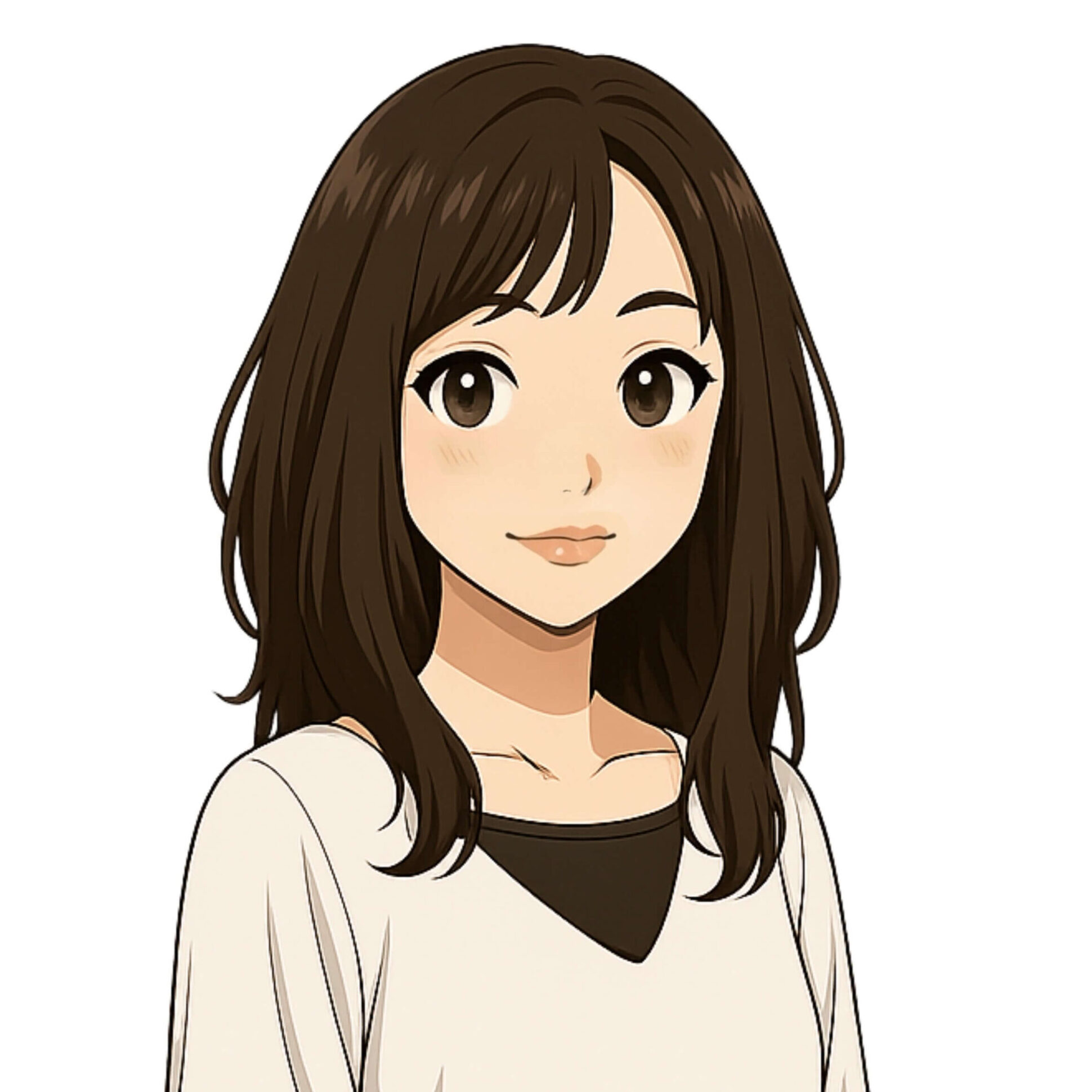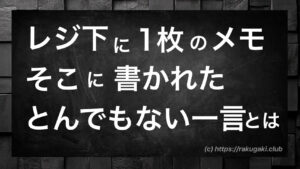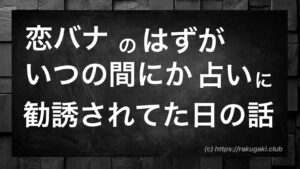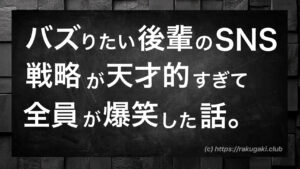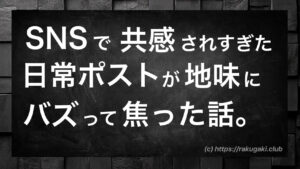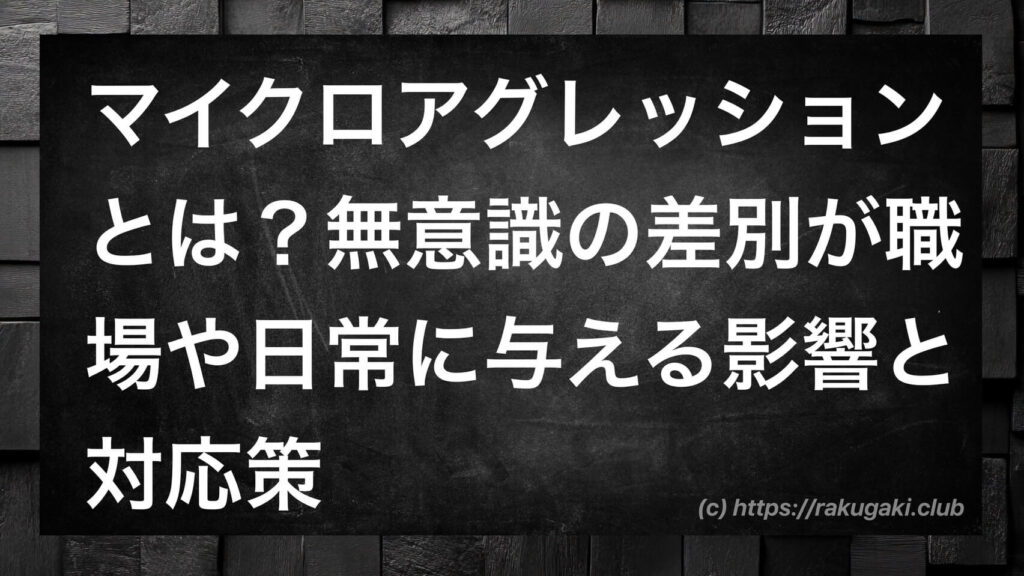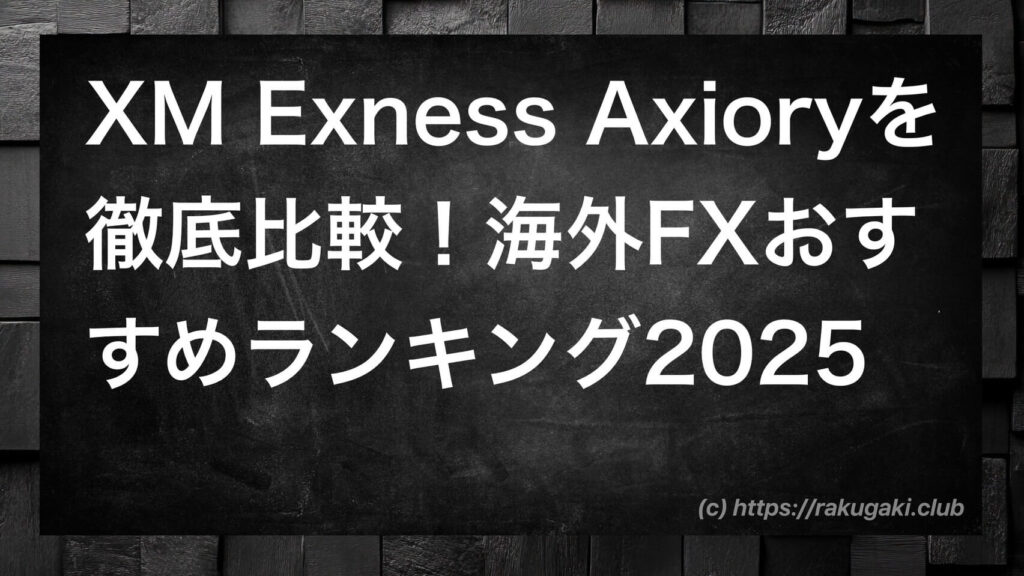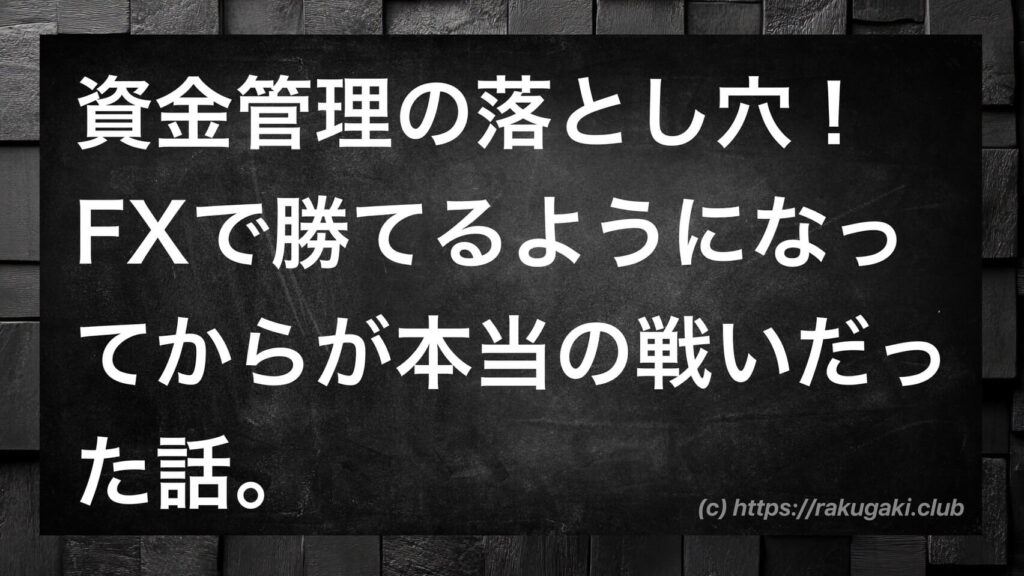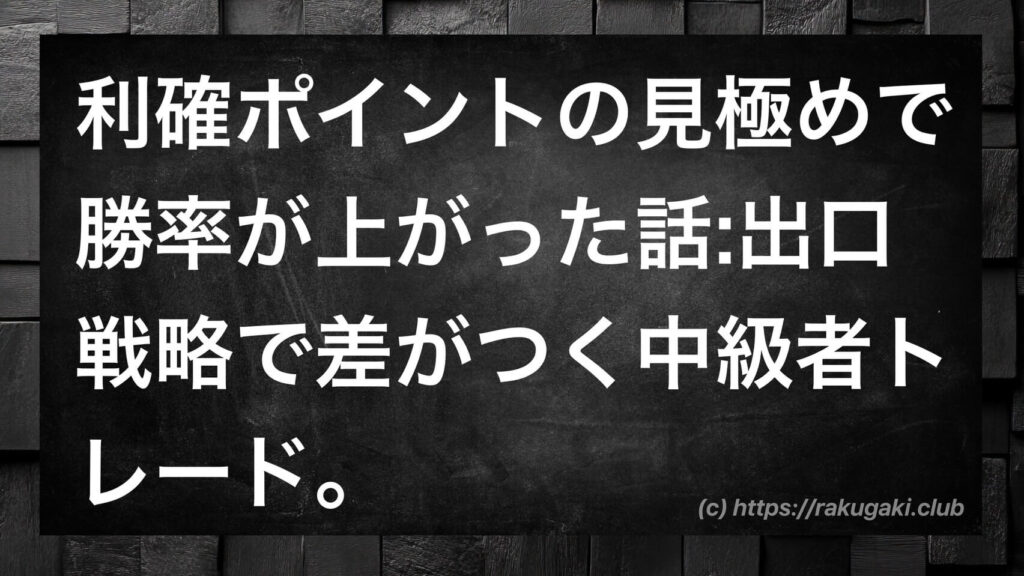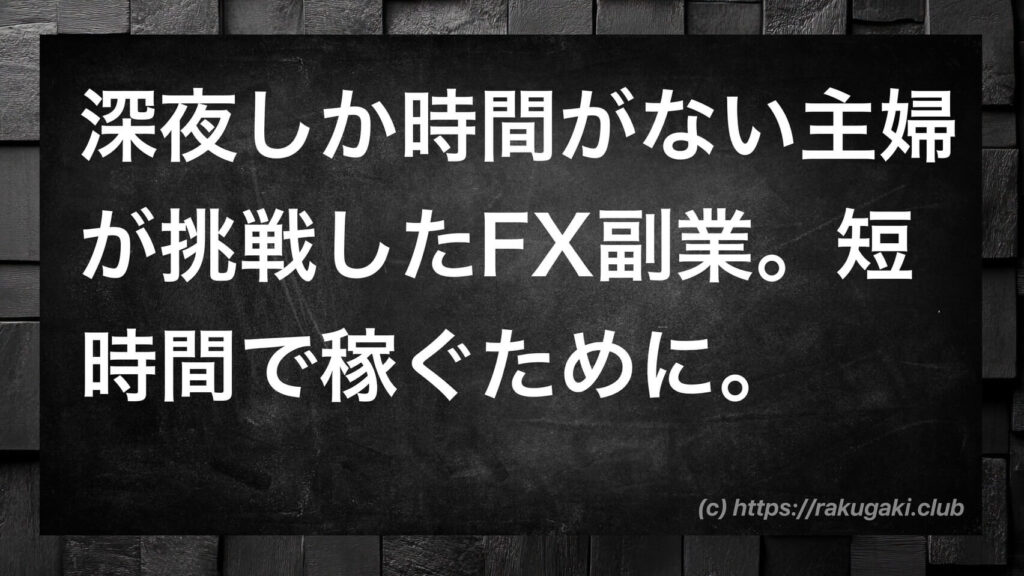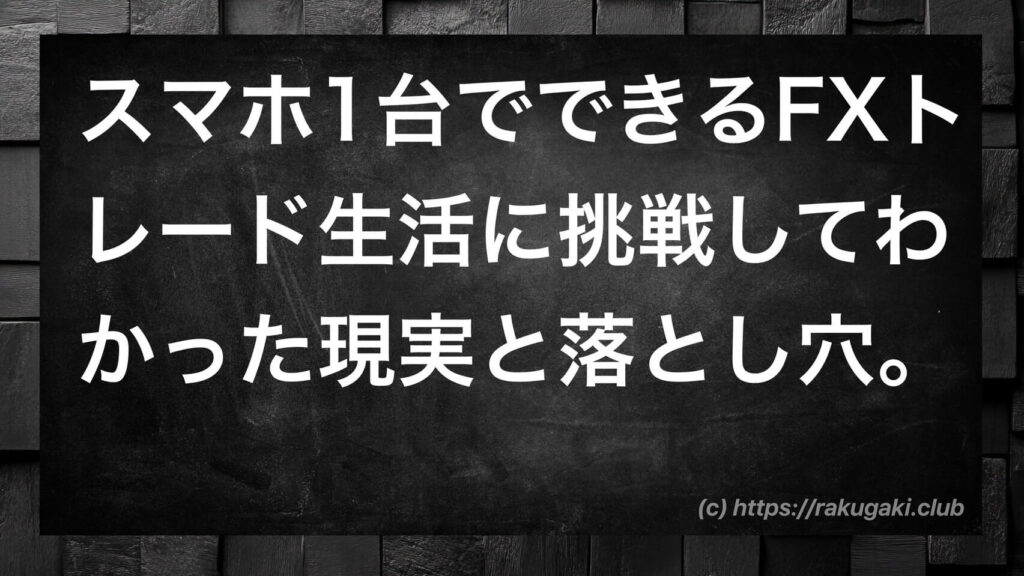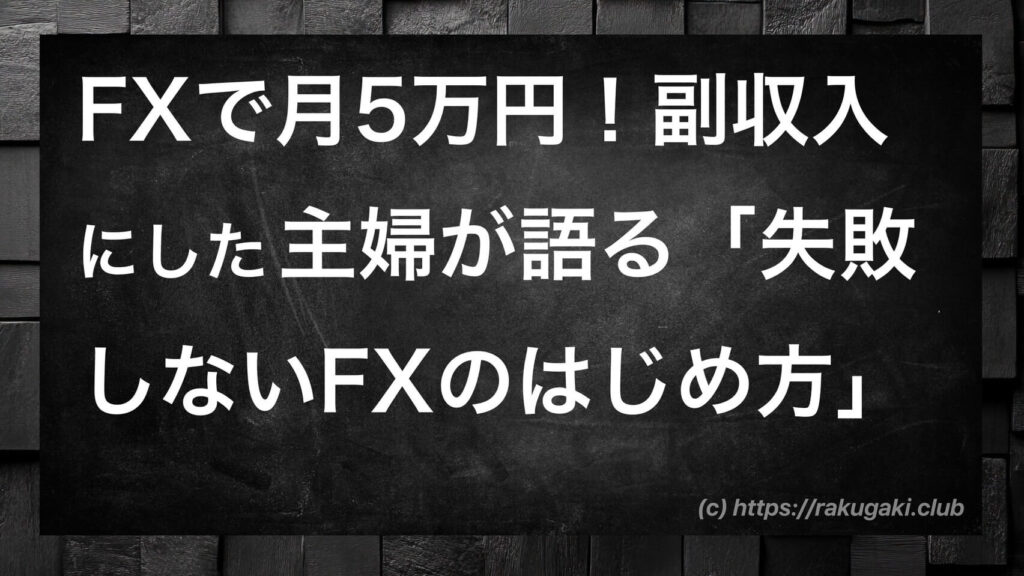ランチタイムの“ちょっとした違和感”が、事件の発端だった
「いらっしゃいませー!」
時計の針は、11時55分を少し過ぎたところ。
まさに“ランチタイム・ラッシュ”が始まろうとしていた。
イッチ――つまり俺は、いつものようにホール担当として動き回っていた。
テーブルを拭いて、お冷を出して、メニューを配って、
お客さんの呼び出しに対応して、次の案内の準備をして――。
「この時間帯は、まさに“戦場”だよな……」
思わず心の中でつぶやいたとき、案の定、さやかちゃんが厨房から叫んだ。
「イッチくーん! Bセット入りまーす!」
「了解です!」
素早く厨房のタブレットに注文を入力し、
手元のメモを確認しながら次のテーブルへと向かう。
お客さんはすでに注文を決めていたようで、笑顔で告げられた。
「日替わりランチとアイスコーヒー、お願いします」
「かしこまりました!」
この一連のやりとりも、すっかり体に染みついた“日常”。
注文を繰り返して復唱し、厨房に伝えて――それだけのこと。
……のはずだった。
“おしぼり”が一品としてカウントされている謎
その約10分後、事件の発端が、ひっそりと顔を出す。
「ねぇ、イッチくん」
あかねさんが、やや困惑した表情で呼び止めてきた。
「お客さんのテーブル、注文内容って“日替わりランチとアイスコーヒー”だよね?」
「はい、そうですけど……」
「伝票に“おしぼり(単品)”ってあるんだけど」
「……へ?」
思わず固まった。
「いやいや、そんなの入れた記憶ないですけど……」
「でも、厨房の端末には“おしぼり”って通ってたのよ。
しかも“1”って、しっかり数量まで」
「ちょ、ちょっと待ってください!俺そんなの……!」
タブレットの履歴を確認してみる。
そこには、確かに
・日替わりランチ……1
・アイスコーヒー……1
・おしぼり………………1
の文字。
「いやいやいや! “おしぼり”って!?」
「ねえ、それ、料理カテゴリに入ってるけど!?」
「……は?」
厨房の奥から、さやかちゃんの爆笑が聞こえる。
「誰!? “おしぼり”を一品料理にしたの!」
“おしぼり=メニュー化”疑惑、現場を騒がせる
騒ぎを聞きつけて、店長がひょこっと顔を出してきた。
「ん? なんか楽しそうだねー、なになに?」
「店長、これ見てください」
あかねさんがタブレットの画面を指差す。
「……おしぼり1? しかも料理扱い? なんだこれ(笑)」
「イッチくんが注文取ったんだけど、本人は入力した記憶がないらしくて」
「まさかの“おしぼり誤発注事件”ですね〜」
店長は軽く笑ったが、本人――俺としては笑えない。
「いや、本当に記憶にないんです……。
もしかしてどこか押し間違えて……? でも、“おしぼり”ってそもそも項目にあります?」
さやかちゃんが操作パネルを操作しながら言う。
「あるよ。“サイドメニュー”の最下部。なんか昔の設定で残ってるだけだけど」
「なんでそんなの残ってるんですか……!」
「え? たまに子どもが間違えて押すから、笑い取れるように残してある(笑)」
「笑いのためかよ!!!」
お客様のリアクションが“想像の斜め上”だった件
そんな混乱のさなか、肝心のお客様が呼び出しボタンを押した。
「……すみません、これ、頼んだ記憶がないんですけど」
テーブルには、なぜか“丁寧に折りたたまれたおしぼり”が
楊枝と一緒に皿に盛られて置かれていた。
完全に“前菜”扱い。
「……誠に申し訳ございません!!」
俺は全力で頭を下げた。
だが、お客さんは逆に笑っていた。
「いえいえ、面白かったです。これ、ネタにしていいですか?」
「どうぞご自由に!」
SNSに載せられたらどうしよう……という緊張を抱えながら、
それでもちょっと救われたような気がした。
事件は、まだ序章に過ぎなかった
休憩中、かなちゃんがカウンターでつぶやいた。
「でも、ほんとにイッチさんがミスしたんですかね……?」
「えっ?」
「だって、入力したのって何時ですか?
その時間、イッチさん、他の席で呼ばれてたと思うんですよ」
「……え、マジで?」
「伝票の履歴、誰が操作したか見られないんですかね?」
「さすがにそこまでは……」
「もしかして、ゴーストが……」
「やめろぉぉぉ!」
「それか……」
あかねさんが、ふっと意味深な顔で言った。
「店長がまた、やらかしたんじゃないの?」
――この予感は、後にとんでもない“真相”を暴き出すことになる。
“おしぼり一丁”が巻き起こした、職場ぐるみの笑撃
ランチタイムのピークがひと段落した午後1時半。
客足が少しずつ落ち着き始め、厨房からはホッとしたような息遣いが聞こえ始めた。
しかし、俺――イッチの心の中は、まだバタバタしていた。
(おしぼりって、誰が入力したんだ……)
思い返しても、自分で入力した記憶はない。
だけど、あのときは確かに俺が接客していて、伝票にも俺の名前が記録されていた。
店長も曖昧な反応だったし、かなちゃんは「本当に自分ですかね?」とぼんやり言っていたが、
確証はどこにもなかった。
それでも――。
「ま、失敗って、そういうもんだよね!」
ドン!と背中を叩かれ、我に返る。
ふり返ると、あかねさんがニヤリと笑っていた。
「おしぼり、めちゃくちゃウケてたじゃん。あの席のお客さん、爆笑してたし」
「……ええ、まあ、助かりました」
「“おしぼりアミューズ”って名前つけとけば、正式メニューにできるかもよ?」
「絶対注文こないですよそれ……」
思わず苦笑いしつつ、ちょっとだけ気持ちが軽くなる。
あかねさんのこういう切り替え力、ほんと見習いたい。
「おしぼりを、正式メニュー化しよう!」という冗談が暴走する
そんな中、さやかちゃんが裏から登場。
「ねえねえ、“おしぼりアート選手権”やろうよ!」
「……は?」
「ほら、折り方とかで勝負。バラとか鶴とか作ってさ。
最後に“芸術点”つけて誰が一番センスあるかってやつ!」
「なにそれ、昭和の喫茶店か!」
俺がツッコむ間もなく、かなちゃんがスマホを取り出して言う。
「TikTokで流行るかもしれませんよ、“おしぼりチャレンジ”」
「そっちに拡散されるのも困るって!」
でもなんだか、みんな楽しそうだった。
おしぼりミスが“ネタ”として店の空気を和ませている。
さやかちゃんが「おしぼりバーガー!」といって丸めたおしぼりをバンズに挟み始めた時点で、
俺は小さく吹き出してしまった。
店長の飄々ぶりと、“黒幕”説の再浮上
そのタイミングで、店長がバックヤードに入ってくる。
「なになに? なんか文化祭みたいな空気になってるけど」
「店長、実はですね……」
あかねさんが事情を簡潔に説明すると、店長は目を細めて言った。
「うーん……俺、入力したかなぁ……いやぁ、してないと思うけど……」
「その言い方、めっちゃ怪しいですって」
「でもほら、イッチくんが入力したって履歴には残ってたでしょ?」
「……いや、履歴って“最終操作した人”しか残らないですよね?」
かなちゃんが、ぽそっと鋭いことを言った。
「つまり、途中で店長が代わって入力したら……イッチさんの名前になるまえに上書きされるってことも」
「おい……マジか……」
店長は肩をすくめた。
「まあ、誰がやったかなんて、もうわかんないけどさ」
その言い方がまた“無責任の極地”みたいで、逆に笑えてきた。
「じゃあもう、店全体の総意ってことでいいですかね」
「そうしとこう!」
全員がうなずいて、なんとなく丸く収まった。
イッチ、モヤモヤの中に“温度”を感じはじめる
だけど、俺の中のモヤモヤは完全には晴れなかった。
(もし本当に自分のミスだったとしたら?)
(でも、記憶にないってことは、無意識にやっちゃってるのか……)
それを考えると、なんだか落ち込んでしまいそうになる。
そのとき――。
「イッチくん」
あかねさんが、ふとまじめな声で言った。
「仮にさ、本当にイッチくんがミスしてたとしても、
こうやって笑いに変えられるってすごいことだと思わない?」
「……そうですか?」
「うん。たとえば前に、別のバイト先で失敗したとき、
“ちゃんとしろよ!”ってマジギレされたことがあるんだよね。
でもさ、この店って、失敗しても誰かが笑い飛ばしてくれるじゃん?
それって、実はめちゃくちゃありがたいことだと思うんだよ」
「…………」
俺は、言葉を失った。
そうだ。確かに、怒鳴られたり、責められたりは一切なかった。
むしろ、笑ってくれて、ネタにしてくれて。
それどころか「おしぼりバーガー」まで生み出された。
(なんだこれ……最高の職場じゃん)
そう思ったとき、少しだけ心がほぐれた。
“チーム”としての空気が育ち始める瞬間
その日の営業が終わり、閉店準備をしていたときのこと。
かなちゃんが、業務用の伝票プリンタを眺めながら言った。
「ねえ、伝票って自動印刷されるとき、誰が触ったか履歴残るようになりませんかね?」
「それって……どこにログインしてたか、とか?」
「はい。もしくは、誰のアカウントで入力されたかっていう履歴管理とか」
「それ、ITに強い人が必要だな」
店長が笑っていたが、かなちゃんは真剣だった。
「でも、こういう“原因不明のミス”って、
ちゃんと追跡できるようにしておいた方がいいと思うんです。
誰かを責めるためじゃなくて、“安心して働くために”」
その言葉に、なぜか一同がシン……と静まり返った。
そしてあかねさんが、ぽつり。
「かなちゃん、いつの間にそんなこと言えるようになったの?」
「え、あ……いや、ただの思いつきです……///」
みんなが笑った。
俺も、笑った。
(失敗って、隠したり誤魔化したりするもんだと思ってたけど、
ここでは、ちゃんと“見てくれる人”がいるんだな)
そう思えた瞬間だった。
まさかの再発と、時を超える“おしぼりの呪い”
午後3時を過ぎた頃。
ランチタイムの喧騒がすっかり落ち着き、
店内はほんのり眠気が漂う“アイドルタイム”へと突入していた。
客席には2組だけ。
テーブルの片隅でパフェをシェアしている女子高生と、
ノートパソコンを開いて黙々と作業をしているサラリーマン風の男性。
俺――イッチは、バックヤードでレジ締めの準備を進めていた。
「さて、今日も無事に終わ……」
——ブーーーン……
「…………ん?」
レジ横の伝票プリンターが、唐突に動き出した。
紙がジジジ……と音を立てて出てくる。
この時間、新たなオーダーが入るはずもない。
そもそも俺しかバックヤードにいない。
それなのに、目の前には1枚の伝票。
【オーダー】
・おしぼり…………1
「……は?」
完全にフリーズした。
プリンターに目をやり、注文端末の画面を確認する。
誰も、何も、押していない。
「やっば……」
ぞわり、と背中を冷たいものが駆け抜けた。
“第二の事件”発生! バイトメンバー全員大騒ぎ
「イッチくん! なに、その顔!?」
あかねさんが休憩室から出てきて、伝票を見て吹き出した。
「ちょっ、また“おしぼり”!? 今度は何!?」
「……俺、何もしてません……」
「え、マジで!? 誰も操作してないのに出てきたの?」
「はい……完全に自動印刷です……」
「……呪いだわ」
呆れたように言い放って、あかねさんがかなちゃんを呼びに行った。
数秒後、さやかちゃんまで連れてきて、再び“おしぼり会議”が始まった。
「これ、もうさ、ほんとに“おしぼりの神”が宿ってるって!」
「もしくは……この店が“おしぼり”を奉納する神社だったとか?」
「いやその設定、急に江戸時代!」
全員が半笑いのまま軽くパニックになり、
厨房の端では、さやかちゃんが“呪い除け”と称しておしぼりを天井に投げていた。
「やめろ! 火災報知器に引っかかる!」
“封印された日誌”と、あかねさんの暴走
そのとき、あかねさんがバックヤードの棚から
やたら年季の入ったファイルを取り出してきた。
「これ……伝説の“バイト日誌”」
「そんなのあるんですか!?」
「あるのよ。初代バイトリーダーの頃から、代々引き継がれてるっていう……」
「もはや家宝やん!」
ホコリを払いながらページをめくるあかねさん。
中には、過去のバイトたちの走り書きのようなメモがたくさん並んでいた。
“レジが急に爆発音した(たぶん冷却ファン)”
“厨房でネコ目撃(未確認)”
“バイトの子がカフェオレで滑って転倒。しかも3連続”
と、やたらカオスな記録ばかり。
そんな中、1ページに大きく書かれた文字が目に飛び込んできた。
「おしぼりの呪い、再び」
「…………!?」
全員、息を飲んだ。
「え、何?“再び”ってことは前もあったの!?」
「こ、これは……」
かなちゃんが顔をしかめながら読み上げる。
“2ヶ月で7回、おしぼりだけの伝票が出た。
誰が押したかは不明。店長に報告したが、
『そういうこともあるよね〜』で片付けられた”
「いや、店長!!!」
全員、心の中でツッコんだ。
そのときの店長の反応が想像できて、全員でズコーーッとずっこける。
伝票ミスの正体が、ついに明らかに
ちょうどそのとき、当の店長がご帰還。
「お疲れさま〜、なんか盛り上がってる?」
「店長、“おしぼり事件”また起きました!」
「また? マジで? だれ、今度は幽霊?」
「自動でプリンタから“おしぼり1”の伝票出ました」
「ははは、またか〜」
「“またか”って、以前も?」
「うーん、あったねぇ。なんか設定がずっとバグってるんだよ、あれ」
「……直してないんですか?」
「いや、直し方がわかんないんだよ〜。
このシステム、導入したの俺じゃないし、マニュアルないし」
「なにそれ、ゆるっ!!」
完全に拍子抜けした。
イッチは思わず頭を抱える。
「俺、めちゃくちゃ反省してたんですけど……」
「それも含めていい経験だったでしょ?」
「店長、あのですね……」
さやかちゃんが小声でボソッ。
「たぶんそれ、パワハラ一歩手前……」
「えー、愛のスパルタだよ〜」
「うわぁ〜〜〜」
“笑えるミス”がもたらした“学び”と“つながり”
ドタバタとした一日を振り返りながら、
俺は静かなホールで一人、夕方の光を見つめていた。
結局、原因は“古い設定ミス”。
人為的なミスではなかったと判明したことに、心底ホッとした。
でも。
「……まあ、いいか」
仮に俺のミスだったとしても、
この店の空気が、仲間が、
それを笑いに変えてくれていた。
“完璧であること”よりも、
“失敗しても大丈夫と思えること”のほうが、
ずっとあたたかい。
その事実に気づけた今日は、
きっと俺のバイト人生にとっても、
ひとつの“進化”だったのかもしれない。
おしぼりが独り歩きする日――「幻の裏メニュー」の誕生
数日後――。
“おしぼり騒動”もすっかり過去の笑い話となり、
バイト先には、いつもと変わらない穏やかな空気が戻ってきていた。
俺――イッチも、ようやくミス疑惑から解放された安堵と、
あかねさんやさやかちゃんの妙なテンションに鍛えられたせいで、
どんな些細なトラブルも「まあ、ネタになるし」と受け流せるようになっていた。
しかし――この日の出来事は、そんな“成長した俺”をも打ち砕いた。
常連客のひと言が場を凍らせる
午後2時過ぎ。
ランチの波が過ぎ去ったあとの、静かな店内。
ひとりの常連さん――30代くらいの男性が、いつものカウンター席に座った。
「いらっしゃいませー! お久しぶりですね!」
俺が笑顔で声をかけると、その人もにっこり。
「この前の“おしぼり料理”、すごく面白かったよ。
今日も頼めるかな?」
「………………はい?」
固まる俺。
「えっと……“おしぼり料理”って、どちらのことでしょうか……?」
「ほら、前に“おしぼり一丁!”ってやってくれたやつ。
あれ、友達に話したら爆笑だったんだよ。SNSにも書いたら、けっこうウケたし」
……ちょっと待て。
それ、ほんとに“ネタ”として広まってんの?
「ちょ、ちょっと確認してきますね……!」
俺は逃げるように厨房へ。
「ちょ、あかねさん! おしぼり、メニュー化されてます!?!?」
「へ?」
「さっきの常連さん、“おしぼり料理頼みたい”って言ってきたんですけど!?」
「……えっ!? ちょ、ちょっと待って、笑う準備させて……!」
あかねさんが腹を抱えて笑い出した。
「ついに来たか……『おしぼり伝説』……!」
「いやいやいや、伝説になってたら困りますって!!」
SNSでまさかの“バズり”現象が発覚
この騒動のあと、さやかちゃんがスマホ片手に近づいてきた。
「イッチさん、“#おしぼり一丁”で検索してみてください」
「なにそれこわい」
恐る恐るTwitter(じゃなかった、今はX)を開いて検索してみると……
#おしぼり一丁
#謎の新メニュー
#爆笑レストラン体験記
大量のポストが表示された。
「居酒屋で“おしぼり一丁”って言ったらガチで伝票出てきたwww」
「しかも店員、めっちゃ真顔だったのに後ろで笑ってたw」
「これ新手のサービス?バズ狙い?(笑)」
「その後、“おしぼりバーガー”まで出てきてカオス」
「これが“日本の未来食”……!」
俺は頭を抱えた。
(やばい……これ、広まってる……!)
しかも、その中には動画を撮っていたお客さんもいたようで、
イッチ本人が映ってるクリップも発見された。
(マスクしてるけど……これ、完全に俺じゃん!)
店のロゴも、制服も、バッチリ映っている。
店長の“開き直り”と、スタッフたちの暴走
「これは……チャンスじゃないか?」
店長が例のごとく飄々とした顔で現れた。
「メニュー表に、“裏メニュー:おしぼり一丁(限定)”って書いてさ、
ワンドリンク制にして500円くらい取っても……」
「いやいやいやいやいやいや!!!」
俺とかなちゃんが全力で止めに入る。
「それ、完全に炎上案件になりますって……」
「SNSって、好意的なコメントだけじゃないですからね」
「でも、これを狙ってやったって思われたら逆にウケるんじゃない?」
「うちの店、そんな戦略的じゃないですから!!」
店長の“経営者ごっこ”にブレーキをかける一方で、
あかねさんとさやかちゃんはというと――
「イッチくん、これから“おしぼり係”ね!」
「“おしぼり仕込み”って必要ですかね!? 朝の仕込みに!」
「あ、そうだ。注文入ったとき用に“おしぼりトング”用意しとこう!」
「もはや芸人じゃないですか!!」
かなちゃんの冷静な分析が刺さる時間
その盛り上がりの中、かなちゃんが珍しく真面目なトーンで口を開いた。
「でも、これってすごいことですよね」
「なにが?」
「だって、たった一つの注文ミスが、
こうやって“バズ”につながるなんて、普通じゃありえません」
「……まあ、確かに」
「おしぼり伝票がバグって出ただけで、
一つの“物語”ができて、客にも共有されて、拡散されて。
気づいたら、“笑っていい思い出”になってる。
それって、SNSがある今だからこそ生まれる現象じゃないですか?」
「……うん。言われてみればそうだ」
「“拡散されること”って、時に怖いけど、
こうやってポジティブに働くこともあるんだなって思いました」
真顔で語るかなちゃんに、
さやかちゃんがぽそっとツッコミ。
「いつからそんなにクールキャラになったの……」
「もともとですけど……?」
「ええ〜!? 私の中で“ポンコツ癒し枠”だったのに!」
「それ誰にも伝わってませんから!!」
イッチ、“ネタの主役”になっていたことに驚く
俺はその日のバイトを終えて、スマホを開いた。
あの日の“おしぼり一丁”事件は、確かにミスだったかもしれない。
けれど、それが笑いに変わり、SNSでネタとして拡散され、
今ではお客さんとの会話のきっかけになっている。
(あのとき、落ち込んだままだったら、こうなってたかな……)
(みんなが笑ってくれたから、自分も笑えたんだよな)
伝票1枚のミスが、
“伝説”になって、
“話の種”になって、
そしてちょっとだけ、
“自分の存在”を肯定してくれた気がする。
それはたぶん――
とても貴重な体験だった。
バイトの“伝説”が街に染み出した日
「イッチくん、やばいよ」
ランチ直前、あかねさんが慌てた様子で厨房に駆け込んできた。
その手には、スマホ。そして真顔。
「何があったんですか?」
「今、カウンターの3人組、さっき“おしぼり一丁チャレンジ”って言って写真撮ってた」
「…………え?」
まさかと思ってホールを覗くと、
20代前半くらいの男性客3人が、伝票を片手にスマホを構えている。
一人が、“おしぼり”を両手で持ち上げ、カメラに向かってニヤリ。
別の一人は動画を撮っている様子。
「“映え”を狙ってますね……」
「やばいなこれ。ついに“チャレンジ系”になったか……」
SNSでバズる→ネタ化→模倣が生まれる。
バイトネタがひとり歩きして、“文化”になってしまう。
……これは、思ったより深刻かもしれない。
ネタが“お店の顔”になりかけている現実
あかねさんがぽつりとつぶやいた。
「たしかにさ、最初は笑える“ちょっとした事件”だったよ?
でも今や、“あの店=おしぼり一丁”って認識されつつあるよね」
「うん……それはもう、完全にそうだと思います」
「しかもさ、さっき来たお客さん、
“TikTokで見たので来ました〜”って言ってたよ。
で、注文する前に、“おしぼり出ますか?”って」
「……完全にネタスポット認定されてますね」
俺は少し、背筋が寒くなった。
笑って許された“おしぼり事件”が、
今や、店のイメージにまでなりつつある。
“発信される”ことは、諸刃の剣なのだ。
店長の“やっと”な決断と、あかねさんの暴走続行
そんななか、ついに店長が重い腰を上げた。
「やっぱ、正式にアナウンス出すか」
「えっ、今さら!?」
「いや、逆に今だからこそ。バズりすぎたら炎上も近いしさ。
“うちはネタOKの店じゃないですよ”って、軽く伝えとくべきだよね」
「まあ……正解ですけど……」
「ってことで、あかねさん、SNS担当よろしく!」
「えっ、マジで!?やったー!!」
異常なテンションでスマホを掲げるあかねさん。
「“#おしぼり一丁は都市伝説です”ってタグ作るね!」
「いやいやいや、煽ってる!煽ってるから!」
「じゃあ、“裏メニューではありません(震え声)”はどう?」
「なんで震えてる体なんですか!?やめて!!」
「じゃあ最後の手段……漫画化しようか」
「なんでそうなる!!」
完全に浮かれモードのあかねさん。
これ以上任せたら、“イッチの物語”がフィクションとして永遠にネットを彷徨う可能性がある。
店長、ほんとに人選ミスですって……。
“笑い”を扱うむずかしさを学んだ瞬間
その日の夕方、かなちゃんがバックヤードで小さくつぶやいた。
「……“笑ってもらう”って、ほんと、むずかしいですよね」
「ん? どういう意味?」
「イッチ先輩の“おしぼり事件”がウケたのは、
笑いの“温度”がちょうどよかったからだと思うんです」
「温度?」
「そう。“いじり”でもなく、“馬鹿にする”でもなく、
ただ“ほっこりしたミス”として消化された。
それって、偶然だけじゃなくて、イッチ先輩の対応や、
私たちの“雰囲気”が作った空気なんじゃないかなって」
俺は黙って聞いていた。
「だから、これ以上ネタが暴走したら、
“誰かを傷つける笑い”になってしまう可能性もあるんですよ」
「…………」
「だから店長の判断、ちょっと遅かったけど、ちゃんと抑えてくれてよかったです」
「……ほんとにな。ありがとう、かなちゃん」
かなちゃんの言葉は、
俺の胸にじんわりと染み込んでいった。
“失敗”がもたらす“つながり”と“発信”のちから
その夜、俺は家でひとりスマホを見つめながら考えていた。
最初は、“ただのミス”だった。
誰かに責められるかもしれない、
怒られるかもしれない、
自分が嫌になるかもしれない。
でも、
それを“笑い”に変えてくれる仲間がいて、
“面白がってくれる”お客さんがいて、
“優しさ”と“余白”で包んでくれる環境があった。
だから、俺は笑えた。
だから、みんなも笑ってくれた。
SNSで“バズる”ことが、すべていいことじゃない。
だけど、自分の“失敗”が誰かの“笑顔”につながったのだとしたら、
それはもう、失敗なんかじゃなかったのかもしれない。
「……うん。悪くなかった」
俺はそっとスマホを置いて、
明日も“おしぼり”を忘れず仕込もうと心に決めた。
いや、それはやめとこ。
“おしぼり一丁”は伝説になりました
数日後――。
店長から、「全員出勤の日にちょっとしたミーティングをしたい」とLINEが入り、
バイト仲間全員が揃うという珍しい日がやってきた。
開店準備の合間、バックヤードに集合した俺たちは、
少しだけソワソワしながら店長の言葉を待っていた。
「えー……お集まりいただき、ありがとうございます」
まるでスピーチでも始めるかのように立ち上がる店長。
「今日はですね……“おしぼり一丁事件”の顛末について、正式に振り返ろうと思いまして」
「え、そこまで正式にする必要あります?(笑)」
「いいじゃん、伝説なんだから!」
あかねさんがノリノリで笑う。
“伝説の始まり”を振り返る店長の語り
店長が、ホワイトボードに“事件の流れ”を書き始める。
- 謎の伝票「おしぼり一丁」が突然出現
- イッチが動揺しながらも、律儀におしぼりを提供
- ネタとして一部始終がスタッフに拡散
- SNSで拡散 → “#おしぼり一丁”爆誕
- 常連客が「幻の裏メニュー」だと勘違いして注文
- 新たな来客層出現 → “チャレンジ系”へ
- 店長、「これはまずい」とやっと対処
- あかねさん暴走(←重要)
「最後いらん!」
あかねさんがすかさずツッコミを入れ、笑いが起きる。
店長は少し真面目な顔で続けた。
「でも、改めて思うんだよね。
この“ミス”が、ここまで笑いになって、
お客さんにも伝わって、結果としていい雰囲気を作れた。
これって、すごいことなんじゃないかなって」
“缶バッジ”と“イッチの肖像”という暴挙
「あ、ちなみに……これ、作っちゃった!」
そう言って、あかねさんが取り出したのは――
“おしぼり一丁缶バッジ”。
まさかの公式(非公式)グッズである。
「なにこれ!? しかもこれ、俺じゃん!!」
「イッチくんが、伝票片手に困り顔してるイラストにしてみた☆」
「いやいや、勝手に似顔絵描かないで!?!」
「あとこれも」
彼女がもうひとつ取り出したのは、
“イッチラテ缶”。
「……なにそれ」
「缶の側面に、あの日のエピソードを漫画風に印刷したの!
バックヤード限定で販売するから!」
「売るの!? しかも“限定”ってどういう意味!?」
「バイト仲間だけで楽しむ“非流通系メモリアルアイテム”よ」
「いや、語感強いな!!」
店内に爆笑が響く。
“バイトって悪くない”と感じた一言
そのとき、普段はあまり大声を出さないさやかちゃんが、ふと口を開いた。
「……なんか、バイトって、
しんどい日もあるし、理不尽なこともあるし、
“もう来たくない”って思うときもあるけど」
「……うん」
「でも、こういうことがあるから、やっぱりやめられないよね」
静かに、でも確かに。
その言葉に、全員が“うん”とうなずいた。
「怒られるミスより、笑えるミスの方が、ずっと記憶に残るし」
「そうだね……ほんと、それはそう」
「イッチくん、今回主役だったからって、次も何かやらかしていいからね!」
「いや、二度と勘弁してください……!」
“失敗を笑える空気”が人を救う
俺は、そっと自分の手帳を開いた。
このバイトを始めたばかりの頃――
“ミスしないように”と、細かくルールをメモしていた。
「伝票は丁寧にチェックする」
「レジの打ち間違い注意」
「注文復唱を忘れない」
だけど、今回の“おしぼり一丁事件”では、
そのどれも役に立たなかった。
でも、その代わりに――
「ミスしても笑えばいい」
「笑ってもらえれば、救われる」
「“おしぼり”は毎回2本用意しておく(?)」
新たなメモが加わっていた。
俺はようやく、
“バイト”という場所が“仕事”以上のものを持っていることに気づいた。
それは、
人と人との関係のなかでしか得られない、笑いと安心。
かなちゃんの“最後の釘”が刺さる
そして、帰り際――。
かなちゃんがにこっと笑って俺に言った。
「でも……“おしぼり一丁”ってもう言っちゃダメですからね。
次は、何が来るか楽しみにしてますけど」
「うっ……ご、ごもっともです……」
その笑顔は、
ほんの少しだけ、“お姉さん”のようで――
ちょっとドキッとしたのは、秘密。
“伝説”は静かに、けれどしっかり刻まれていく
その日の営業が終わり、
ホワイトボードには、誰かがいたずらでこう書き残していた。
『おしぼり一丁』は伝説となりました。
そして……第2章は、もうすぐ始まる。
隣には、俺の似顔絵。
困り顔の。
……ああ、
このバイト、まだまだ何かが起きそうだな。
そう思いながら、
俺は、そっと店の電気を消した。