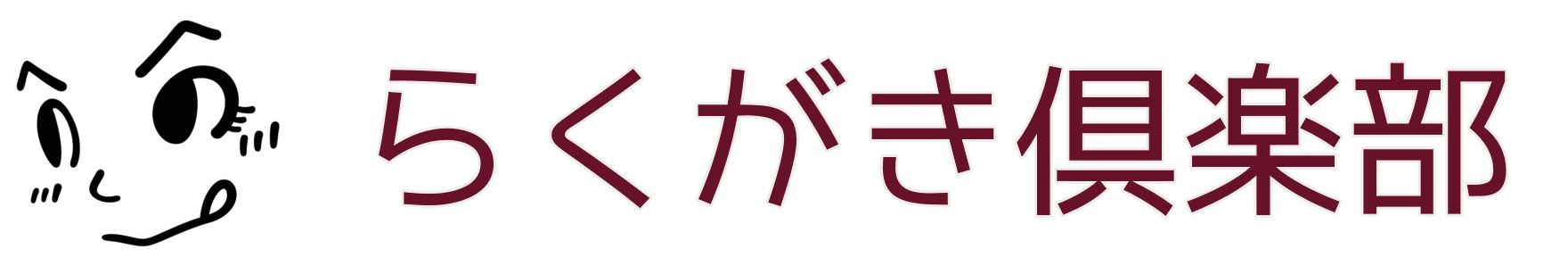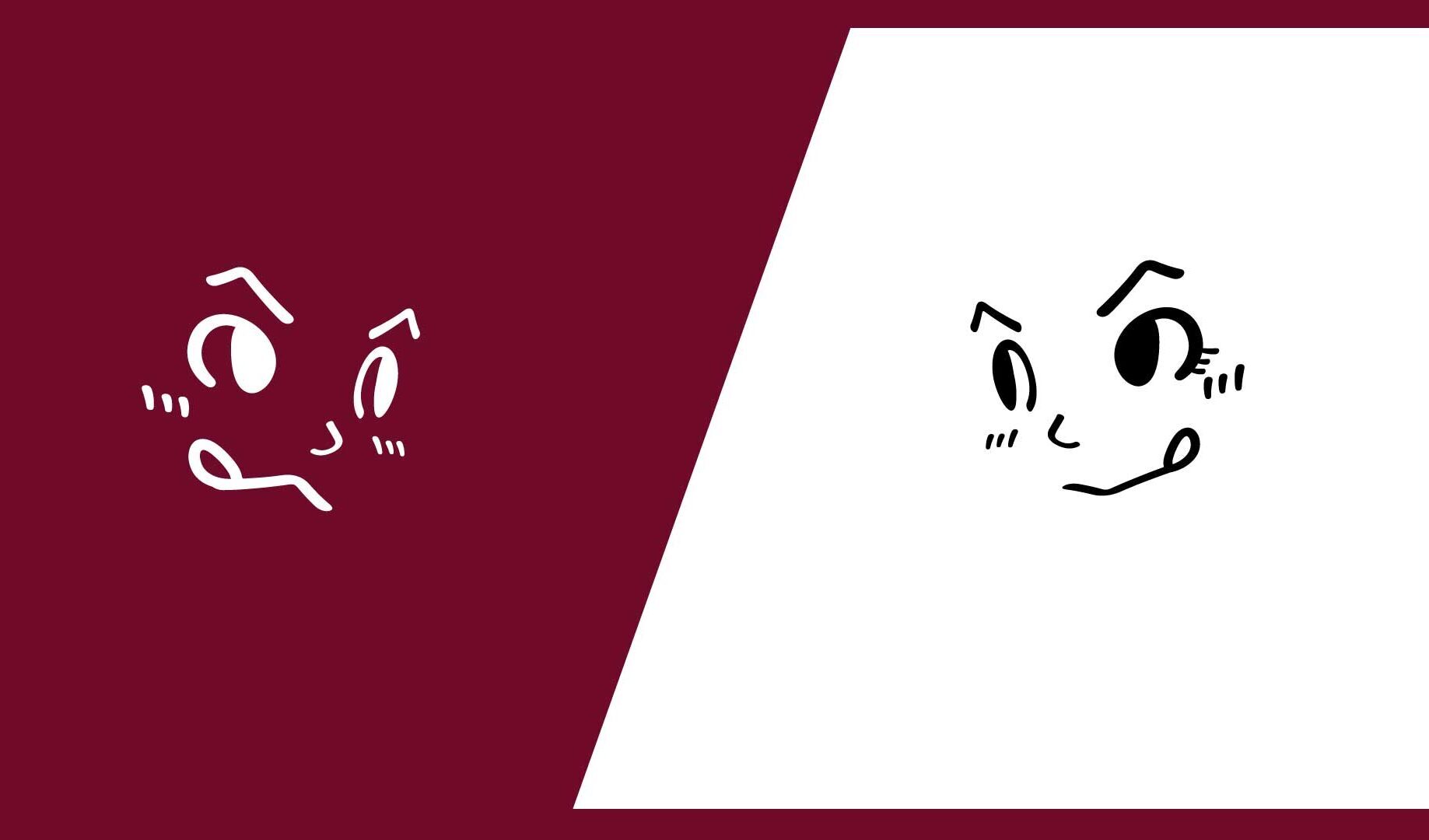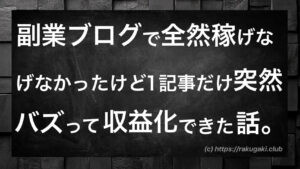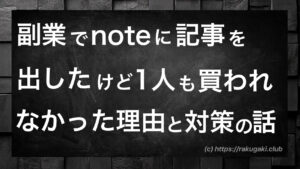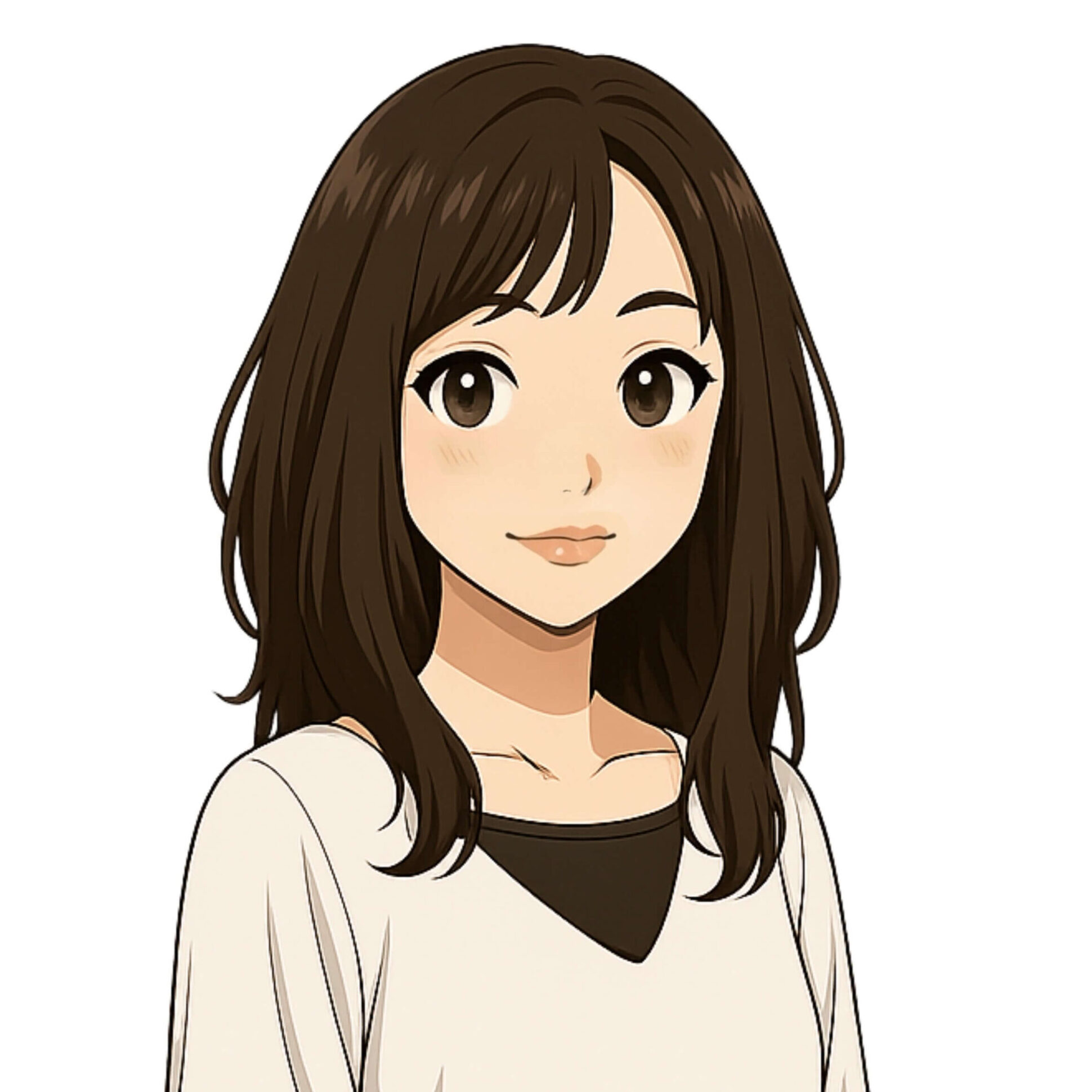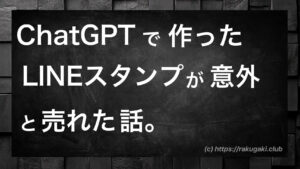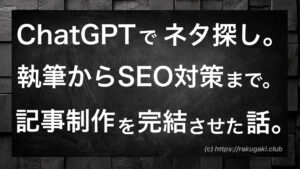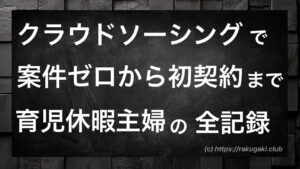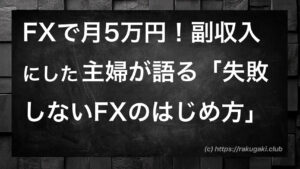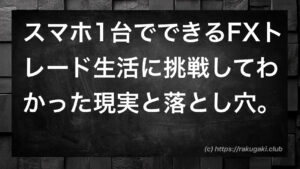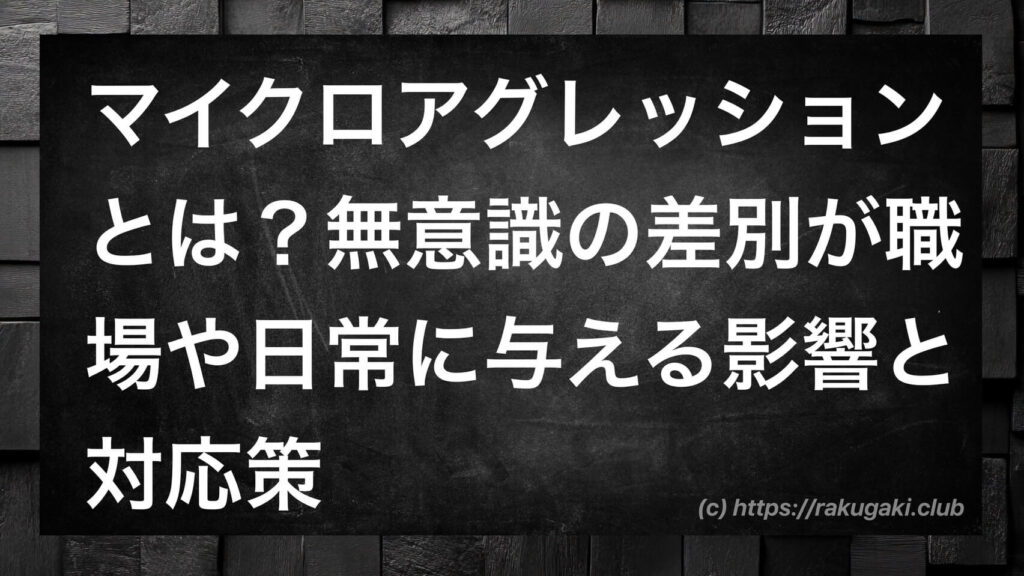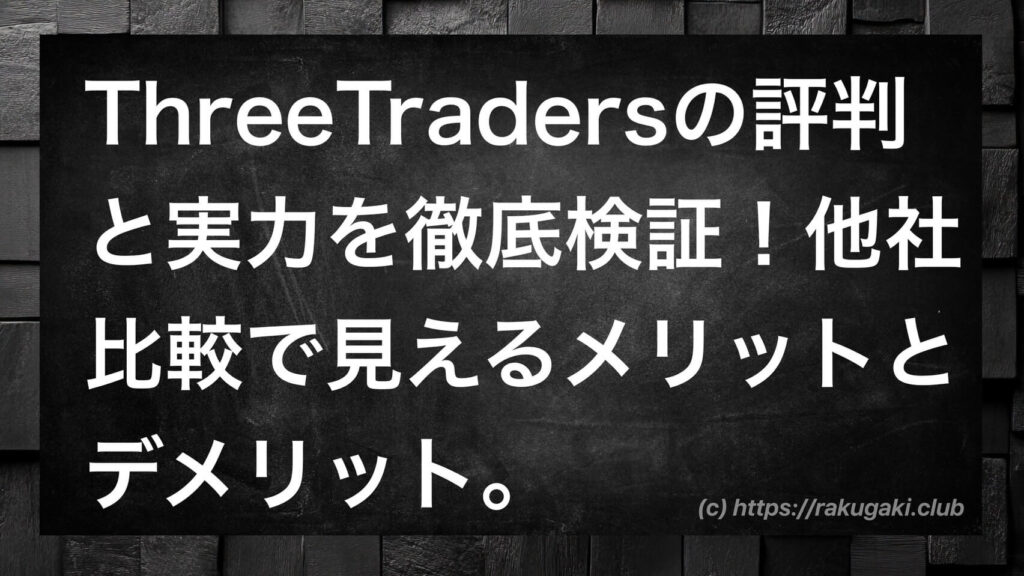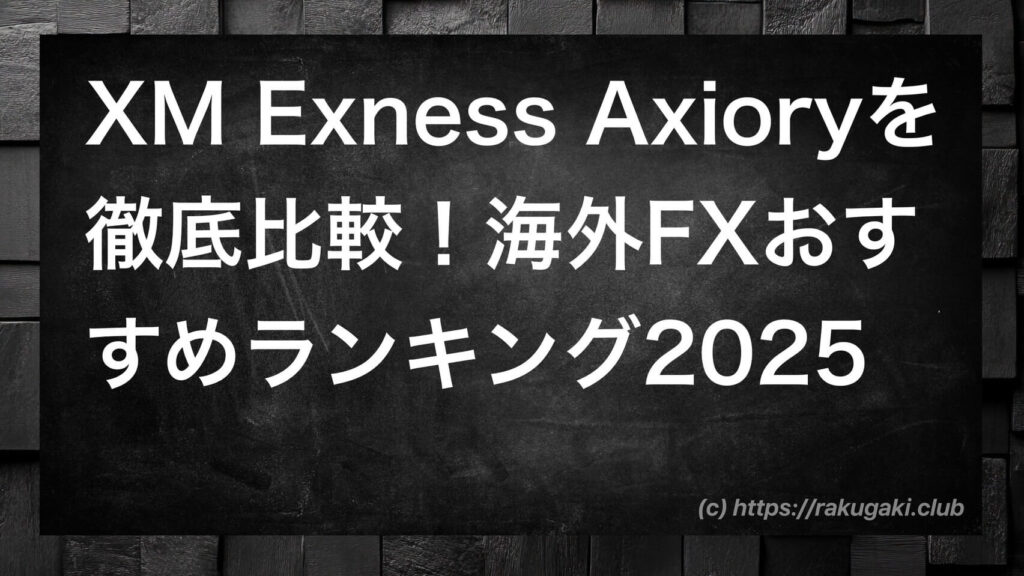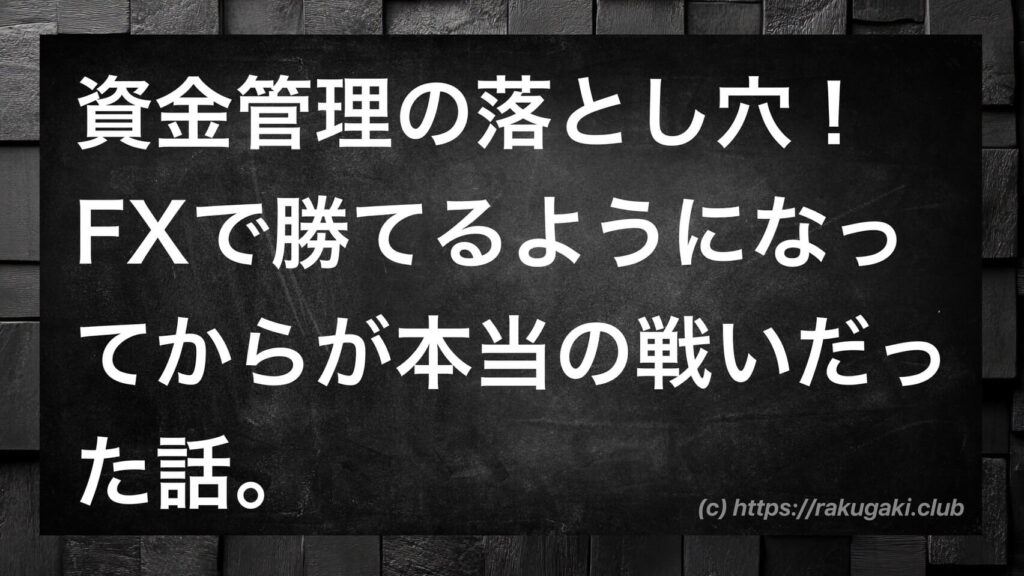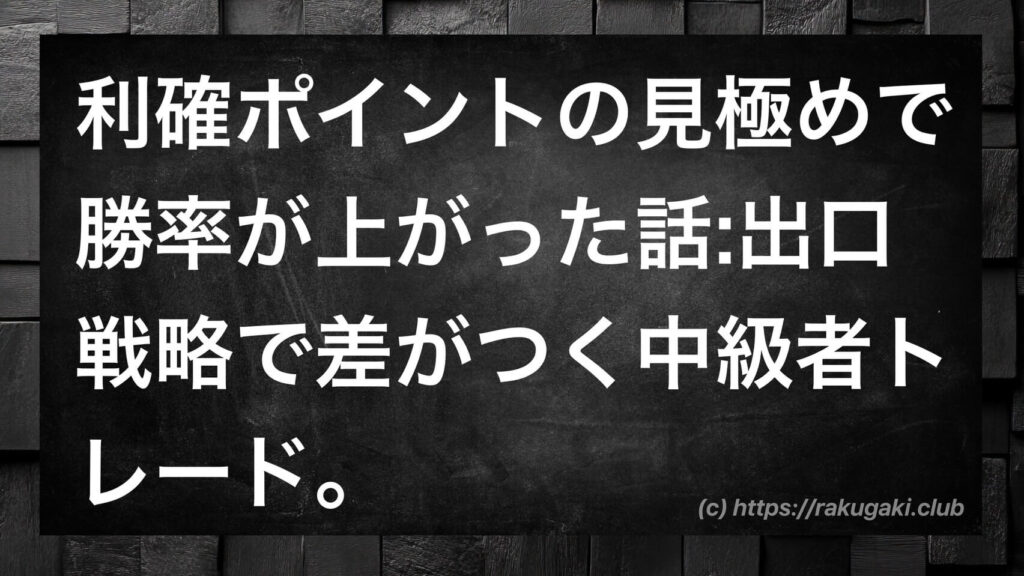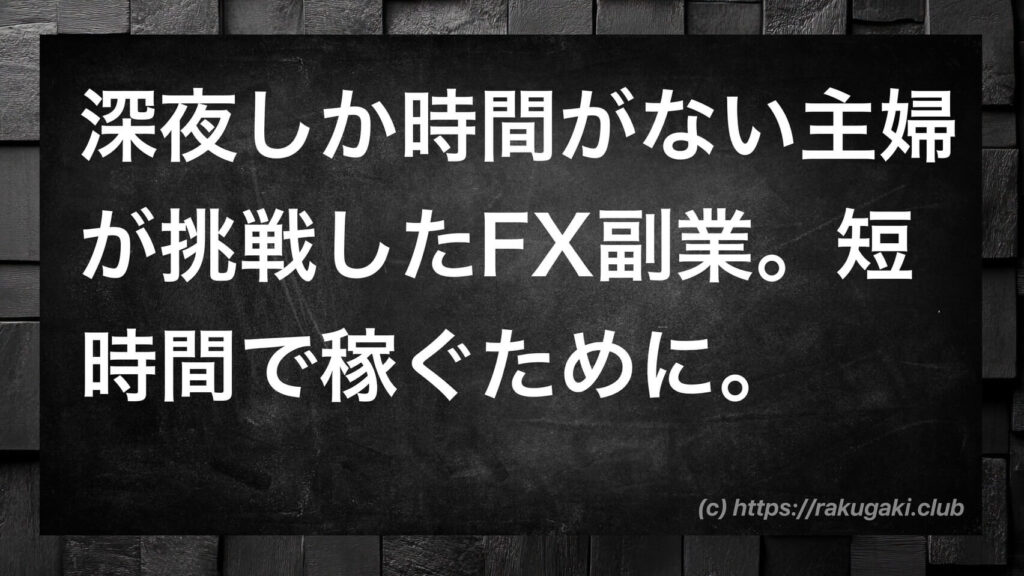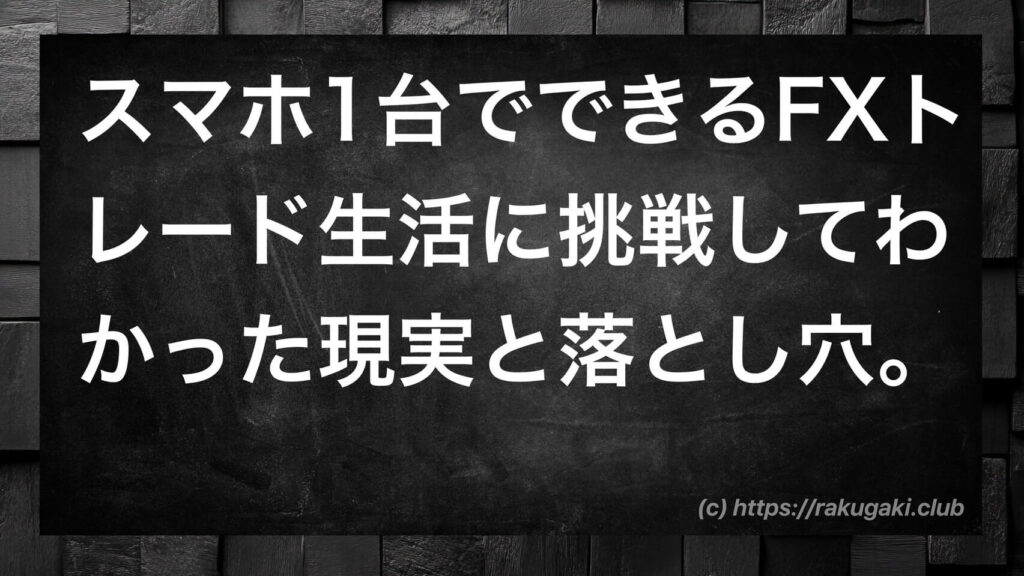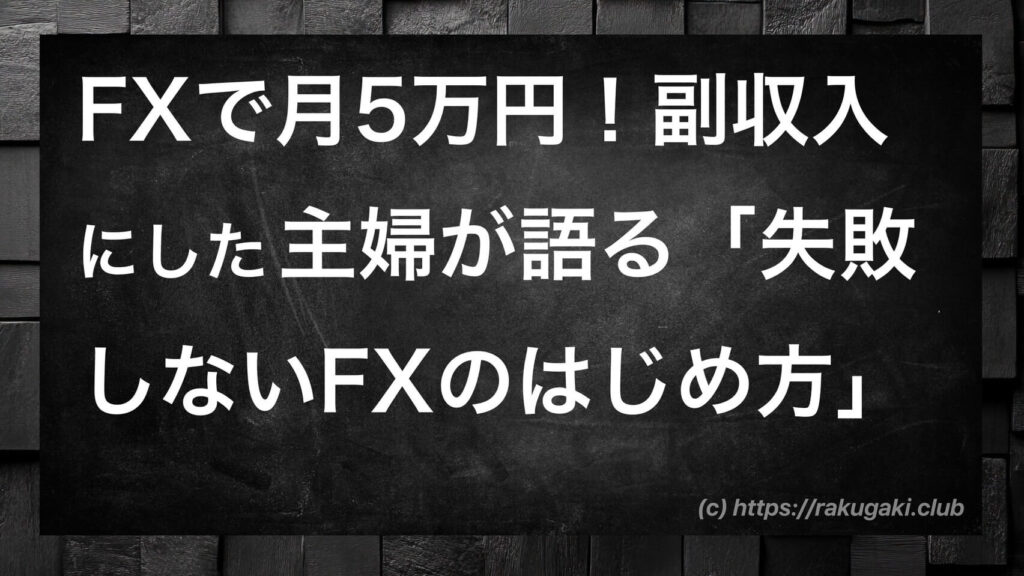1円も稼げなかった3年間、でもやめなかった理由」
副業ブームが加速していた数年前、会社の同僚が「ブログで副収入を得ている」と言っていたのがきっかけだった。
イッチくん(私)は、当時30歳を過ぎたばかり。会社員として安定した収入はあったけれど、将来に対する不安や、自分のスキルのなさにモヤモヤしていた時期だった。
「ブログなら、初期費用もかからないし、コツコツ型の自分に合ってるかも」
軽い気持ちでWordPressを立ち上げ、レンタルサーバーとドメインを契約。最初の数記事を書いたときの達成感は、今でも忘れられない。
しかし──
それから3年間、収益は「0円」。
正確にはアドセンスで数十円、Amazonアソシエイトで数円は発生していたけれど、月1万円どころか、振込可能額(8000円)すら一度も突破できなかった。
頑張ってるのに結果が出ない
毎週1記事更新を目標に、仕事終わりや休日にコツコツ執筆。
「SEOとは何か」「タイトルの付け方」「キーワードの選び方」もネットで独学した。
でも、どれだけ頑張っても検索順位は圏外、PVは月200〜300、収益は0円台のまま。
Twitterで「ブログ 月収10万円突破!」みたいな投稿を見るたび、自分だけが取り残されているような気がして、胸がぎゅっとなった。
でも、なぜかやめられなかった
稼げなかった理由はいくつもある。
- 書きたいことだけ書いていた
- 読者のニーズを調べていなかった
- タイトルがふわっとしていた
- カテゴリーや構造がバラバラだった
今になって振り返れば「当然稼げなかった」と思える要素がいくつもあるけど、当時の私は「正解」がわからなかった。
でも──
それでも、やめなかった。
「やっていて楽しい」が、唯一の原動力だった
アクセス数は少なかったけど、たまに届くコメントが嬉しかった。
「この記事、共感しました」
「初心者の私にもわかりやすかったです」
そんな反応があると、報酬がなくても「やっててよかった」と思えた。
お金にならなくても、「誰かの役に立った」と思える時間が確かにそこにあった。
本気で変わろうと思った“ある出来事”
そんな私に転機が訪れたのは、ブログ開設から3年後。
ある日、サーチコンソールで流入ワードを見ていたとき、あるキーワードで1位を取っている記事があることに気づいた。
しかも、その記事だけ、PVが他の10倍以上伸びていた。
「あれ? なんでこの記事だけ?」
そこから私は、ようやく「ちゃんと分析して改善する」ことを始めた。
「アクセスがある記事」と「ない記事」の違いに気づいた
そこから、Googleアナリティクスとサーチコンソールを何度も見返して、ある傾向に気づいた。
- アクセスが多い記事には、具体的なキーワードが入っている
- タイトルが読者の悩みを直球で表現している
- 記事構成が、読者の「検索意図」に沿っている
つまり、「検索ユーザーに向けて書いた記事」がちゃんと読まれていたということ。
この瞬間、「自分の書きたいこと」から「読者が知りたいこと」へ、価値の軸が移動した。
この1記事が、私の「ブログ観」を180度変えたのだった。
小さな成果が、“希望”になった
その月、初めてアドセンス収益が3桁になった。
「たった300円」かもしれない。
でも、私にとっては「ゼロじゃない収益」が何よりも大きかった。
「ここから伸ばせば、もしかしたら…」
そんなふうに思えた瞬間から、ブログへの向き合い方が変わっていく。
そして、次のステップへと踏み出すことになる──。
「当たった記事」を分解して、収益化の方程式を探した
ひとつだけ、なぜかアクセスが伸びた記事。
私は、その記事を徹底的に分解して分析することから始めた。
タイトルは、「検索そのまま」だった
その記事のタイトルは、今思えば本当にシンプルだった。
「ブログ 収益化 できない時に見直すべきこと」
つまり、「誰かが実際に検索しそうな言葉」をそのまま使っていた。
対して、他の記事のタイトルはどうだったかというと──
- 「ブログ初心者が3ヶ月で感じたリアルな壁」
- 「副業の挫折と小さな希望」
悪くはない。でも、ふわっとしていて、検索には引っかかりにくい。
このときはじめて、「記事タイトルは“文学”じゃなくて“検索窓の答え”でいいんだ」と理解した。
構成は「自分の話」じゃなく「相手の問題解決」だった
伸びた記事を見返してみると、意外なことに気づいた。
書き出しは「自分語り」じゃない。
「こんな悩み、ありませんか?」という、読み手への問いかけから始まっていた。
続く段落では、
- 原因の説明
- 解決ステップ
- 注意点
- 実体験の補足
と、まるで小さなノウハウ記事のような構成になっていた。
逆に、読まれてない記事の多くは、
「今日はこんなことがあって…」
「僕はこういう人間でして…」
と、自分の話が主軸になっていた。
誰のための記事か。ようやく気づいた
私は、気づいてしまった。
これまでの私のブログは、「自分が書きたいこと」を書いていたけど、「読者が知りたいこと」ではなかった。
- 自分の失敗談ばかりだった
- 結論がふわっとしていた
- ノウハウを具体的に伝えていなかった
一方、PVが伸びた記事は、
- 検索意図に沿っていた
- タイトルが明確だった
- 結論が最初から示されていた
つまり、「読者目線」で考えられていた。
私はようやく、**「個人ブログでも“設計”が必要なんだ」**と理解した。
「稼ぐブログ」は、“優しい営業マン”だった
ここで、ふと気づいたことがある。
自分のブログは、いわば24時間働く営業マンのような存在。
でも、いままでは読者の興味も聞かず、商品だけ押し付ける「押し売りマン」だった。
これじゃ、成果が出ないのも当然。
そこから私は、「優しい営業マン」のように読者の話を聞き、悩みを理解し、そっと提案するようなブログに変えようと決めた。
書き方・構成を全部変えた
次に書いた記事からは、以下のことを意識した。
- キーワードを決めてから構成を作る
- 結論を冒頭に置く(PREP法)
- 読者が行動しやすい導線をつくる
- 必要なら図解や箇条書きも入れる
また、過去の記事も少しずつリライトした。
とにかく、「“いい話”じゃなくて、“役立つ話”を書こう」と決めた。
成果は、ちゃんと数字に表れた
変更から1ヶ月。
1日あたりのPVが、20→70へ。
アドセンス収益も、月300円→1,200円に。
さらにAmazonアソシエイトでは、ブログ経由で小物ガジェットが売れ、数百円の成果報酬が入るようになった。
これは、一気にバズったわけではない。
でも、地味に、でも確実に右肩上がりになった。
一番大きかった変化は「書くのが楽しくなったこと」
数字が増えたこと以上に嬉しかったのは、「書くことへの手応え」が出てきたことだった。
「誰かがちゃんと読んでくれてる」
「検索からたどり着いてくれてる」
「“役に立った”と思ってくれてる」
これまでの3年間は、“誰にも届かないラジオ”をやってるような孤独感があった。
でもいまは、確かに“向こう側に誰かがいる”。
それが、書き続けるモチベーションになっていった。
1万円の壁を超えるためにやった“地味すぎる努力”
月1万円──
それは、ブロガー界隈で言えば「小さな成功」かもしれない。
でも、当時の私にとっては、とてつもなく大きなハードルだった。
PVを“伸ばす記事”と“支える記事”に分けた
まず私が始めたのは、記事の役割分担だった。
- 伸ばす記事:検索ボリュームがあるテーマで狙った集客用の記事
- 支える記事:内部リンクで導線を整えたり、成約率を上げるための記事
「人気記事を量産すればいい」と思っていた頃は、全記事にPVや収益を求めていた。
でもそうじゃない。
ひとつが人を集め、もうひとつが売上につなげる。
この組み合わせが「稼げるブログ」の基盤だと気づいた。
アフィリエイト案件の選び方を変えた
それまで私は、「単価が高いもの」を優先してアフィリエイトしていた。
でも、ぜんぜん売れない。
商品ページまで飛んでも、離脱率が高かった。
理由は明白で、自分のブログの読者層とマッチしていなかったから。
たとえば、
副業初心者向けの記事に、「法人向けクラウド会計ツール」なんて貼っても、誰も買わない。
そこからは、読者が「今」必要としていそうなものに絞って紹介するようにした。
たとえ単価が低くても、読者にとって有益であれば、ちゃんと売れる。
成果が出た導線は、意外と地味だった
結果的に一番売れたのは、
記事の途中に何気なく置いたリンクだった。
「このへんでつまずく人、多いですよね」
「自分はこれで解決しました」
という流れの中に、さりげなく1つのリンクを挿入。
ド派手なCTAや、ボタンデザインの主張じゃない。
“会話の延長”にあるリンクが、一番反応がよかった。
SNS流入は「補助」であって「主軸」ではないと気づく
当時はX(旧Twitter)やInstagramからもアクセスを得ようと、毎日投稿していた。
けれど、SNSの波は安定しない。
どんなにバズっても、次の日にはゼロに戻る。
一方、Google検索からの流入は、少しずつ、でも着実に積み上がっていった。
「SNSは発射台、検索は畑」
このイメージがようやく自分の中でしっくりきて、記事制作のリソースをSEOに寄せていくことを決断。
書きたいことは「書きたい記事」と「求められている記事」のハイブリッドに
やっぱり、ただのSEOライティングだけだと気が乗らないときもある。
だから私は、自分のモチベーションを保つために「半分ずつ」にした。
- 読者の検索意図を満たすことを最優先にしつつ
- その中に、自分の体験や感情も“味付け”として入れる
すると、数字も出て、自分も納得できる。
結果、「ちゃんと稼げて、ちゃんと好きな記事」になった。
月1万円に到達した日は、別にドラマチックじゃなかった
その日、なにかの通知が届いたわけじゃない。
ただ、Googleアドセンスやアフィリエイト報酬を集計して、
「お? 合計で1万円いってる」と気づいた。
でも、不思議と心が震えた。
あんなに遠かった1万円。
ずっと届かなかったあの金額に、ようやく指が触れた。
小さな成功が、“長く続ける力”になる
この1万円が、ブログですべてを稼げる証明ではない。
けれど、「継続すれば成果になるんだ」と思える体験だった。
そして何より──
- 自分で考えて
- 自分で設計して
- 自分の力で収益を生んだ
その感覚が、自分を変えてくれた。
続けること」と「伸ばすこと」は違うと気づいた日
月1万円に届いた──
ようやく「ブログで稼ぐ」という言葉に、ほんの少し手が届いた気がした。
でも、そこで終わりじゃなかった。いや、終われなかった。
「もっと伸ばしたい」と思ってしまったのだ。
続ければ結果が出る、という幻想
私は、“継続は力なり”という言葉をずっと信じていた。
実際、あきらめずに記事を書き続けた結果、月1万円には到達した。
でもそのあと、「継続しているだけ」では成長が止まる瞬間が来た。
アクセスが頭打ちになった。
収益も伸びない。
新記事を出しても、反応が薄い。
「あれ? 何かがおかしいぞ……」
“分析”という名の現実直視
そこで私は、アクセス解析と収益データを一度ちゃんと見直すことにした。
- どの記事がPVを取っているのか
- どこから流入しているのか
- どこで読者が離脱しているのか
- どの広告リンクがクリックされているのか
これまで「なんとなく」でやっていたブログを、
数字ベースで“診断”する視点に変えた。
すると、思っていたのとまったく違う現実が見えてきた。
売れてる記事と「書きたい記事」は一致していなかった
私が「このテーマならいけるはず」と思って書いた記事は、あまり読まれていなかった。
逆に、
「まぁ一応書いとくか……」くらいのノリで出した記事が、安定した検索流入を持っていた。
読者のニーズと、自分の期待値はズレていた。
そこから私は、「読まれる=価値がある」という事実を素直に受け入れることにした。
伸びる記事には“型”があった
データをもとに、PVや収益が伸びている記事をいくつか見比べた。
すると──
構成やキーワードの“型”が浮かび上がってきた。
- タイトルに数字が入っている
- 見出しに検索ワードを盛り込んでいる
- 回答を冒頭で簡潔に提示している
- 経験談はあくまで補足に留めている
「感情ベースで書く記事」と「検索に応える記事」は違う。
この切り替えが、私の中でようやくできた。
SEOを学びなおすという選択
もう一度、SEOの基礎を学びなおすことにした。
- ラッコキーワードでの検索意図分析
- サジェストキーワードの拾い上げ
- 共起語と見出し構成の整合性
- パッと読んで意味がわかる日本語
正直、当時は「こんなの、個人ブログに必要?」と思っていた。
でも、そうやって思考を止めていたからこそ、月1万円の壁を越えられなかったのだと痛感した。
伸ばすためには「他者目線」が必要だった
それまで私は、「自分が書きたいこと」「自分が知っていること」を中心に記事を作っていた。
でもそれって、自己完結のコンテンツなんだ。
読者が検索してたどり着く記事には、
- 問いに答える力
- “読みやすさ”という配慮
- “先回りする視点”
が必要だとわかった。
「書いた」ではなく、「読まれた」が正解。
収益化のための思い切った“断捨離”
そこから私は、過去記事の多くをリライト or 削除した。
- PVが取れていない
- 成約導線がない
- 内容が古い or ニーズとズレている
当時は「時間をかけて書いたものを消すなんて」と躊躇したけれど、
“資産”になる記事だけを残すという判断は正解だった。
このあたりから、PVも収益も、また少しずつ動き始めた。
次の壁を越える準備が、ようやく整ってきた気がしていた──
売る」ことに抵抗がなくなった日
ブログのアクセスがようやく安定してきた頃、私はひとつの疑問にぶつかった。
──「このアクセスを、どう“収益”に変えたらいい?」
読まれる記事が増えたのに、広告収入はそれほど伸びていなかった。
そこで私はようやく、避け続けていたテーマに手をつけた。
“売る”という行為への苦手意識
私はずっと「売ること」に苦手意識を持っていた。
- 商品紹介=ゴリ押しに見えるんじゃ?
- アフィリエイトリンクって信用される?
- 読者を騙すような気がする……
そんなふうに思っていた。
でも、考え方を変えた。
「売る」のではなく、「助ける」ように届けることができれば、それは悪いことじゃない。
商品選びを“自分目線”から“読者目線”に切り替えた
たとえば、過去記事で紹介していた「書籍」のリンク。
私が読んで良かったものを紹介していたけれど、実際にはそれほどクリックされていなかった。
一方、「読者の悩みに直接刺さる内容」に合わせて、
- 実用的なツール
- ブロガー向けのサービス
- 初心者でも使いやすい教材
などを**“悩み解決型”で提案した記事**は、コンバージョンが明らかに伸びた。
本当に売れる記事の“共通点”
分析を続けて気づいた「売れる記事の型」はこうだ。
- 読者が明確な悩みを持って訪れる
- 解決方法を提示する(体験ベース)
- 解決手段として“商品やサービス”を紹介
- メリット・デメリットを正直に書く
- 導線は丁寧に、押しつけずに置いておく
意外と、“売り込まない方が売れる”のだ。
自分が心から良いと思えるものだけを選ぶ
とはいえ、すべての商品を扱うようにはしなかった。
- 自分で使ったことのあるもの
- 誰かに安心してすすめられるもの
- ブログの読者層と相性のいいもの
こういう「自分の中で正直でいられる範囲」に限定した。
結果、成約率は高くないけど、リピーターや指名買いが出るようになった。
サイドバーや記事下CTAの改善
記事コンテンツだけでなく、ブログ全体の導線も見直した。
- サイドバーに「人気記事」ではなく「おすすめツール」を掲載
- 記事下に「まとめと次の一手」をセットで記載
- メルマガ登録やLINEリンクなどは一切使わず、1クリックだけに集中
このあたりから収益が“積み上がる”感覚が出てきた。
収益=信頼の積み重ね
最終的に思ったのは、収益は「信用の蓄積」なんだということ。
「この人がすすめてるなら、読んでみよう」
「紹介されてたツール、たしかに良かった」
「なんか読みやすくて信頼できるブログだな」
そんな読者のリアクションが、少しずつ増えていった。
収益は「数字」だけど、作るのは「人」
アクセス数も、収益額も、あくまで“結果”でしかない。
その裏側には、
- 必要とされる記事を考えた時間
- 表現の伝え方を悩んだ日々
- データとにらめっこした試行錯誤
そんな「人としての努力」があった。
ブログ収益化の正体は、誰かの役に立った証だったんだ。
「収益化」の正体は、戦略と継続の積み重ねだった
ブログで収益を上げるには、センスや才能よりも「再現可能なプロセス」の理解と実践が欠かせない。
思いつきで書いていた時期は稼げなかった。でも、読者のニーズを明確に捉えてからは、数字が変わった。
以下に、月1万円までの成長を支えた要素を整理しておく。
① キーワード設計と読者ニーズの一致
PVが増え始めたのは、「自分が書きたい記事」ではなく「読者が検索しそうな内容」に特化した頃からだった。
- 商標系KWと悩み解決系KWのバランス
- タイトルと導入文に「検索意図」を意識
- Googleサジェストとサーチコンソールで答え合わせ
自分視点のコンテンツはアクセスされにくい。
検索者に寄り添ったテーマ設計が、安定した流入を生む。
② 「読みやすい構成」と「伝わる導線」
文章力ではなく、“論理構造”で勝負した。
- 結論 → 理由 → 具体例 → 結論、の型を使う
- 各見出しに1テーマ
- 結末に「次の一手」を用意する
これにより読者の滞在時間が伸び、直帰率も改善。
記事の価値は「読了率」で決まる。
③ 「売る」ための仕組みは“文章の中”に組み込む
ただバナーを貼っても売れない。
「なぜそれを紹介するのか」をストーリーとロジックで説明することで、読者の納得度が上がった。
- 体験談型:使ってどうだったか、を主軸に
- 比較型:選ぶ基準と読者の状況を想定
- 導線:リンクは記事中に1〜2回に絞る
“売るための言葉”は、あくまで自然に馴染ませる。
それが信頼とCV率に直結する。
④ 収益化は“正直な情報発信”の先にある
読者は敏感だ。
嘘っぽい表現、過剰なアフィリエイト誘導、キラキラしすぎた成果報告――全部見透かされる。
だから私は、なるべく等身大で書いた。
稼げなかった時期も、回り道も、正直に記録してきた。
結果的に、読者と自分の信頼関係ができたことが、最大の資産だった。
ブログで月1万円を稼ぐのは「通過点」だが、価値ある実績
もちろん、1万円で生活はできない。
でも、「自分の力でお金を生んだ」経験値としては、何物にも代えがたい。
- 初収益の喜び
- 地道な積み重ねの成果
- ブログが“資産”になる感覚
これらは、SNSやトレンドでは得られなかった「持続的な力」だった。
ブログは、続けた人が勝つ。
そして、“勝ち方”は誰でも学べる。
私ができたのだから、きっとあなたもできる。
次はあなたの番だ。
ブログで月1万円を“積み上げる”、その最初の一歩は、今日からでも遅くない。